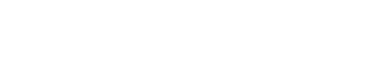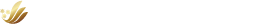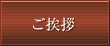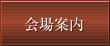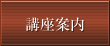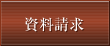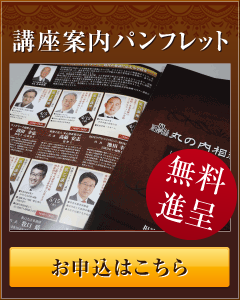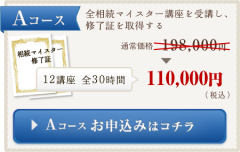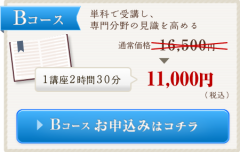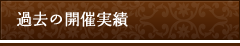参加者の声
相続マイスター講座18期 第1講座の感想

また、農地の納税猶予に関しては適用することにより、土地の評価が減額でき相続税が大幅に減額できる場合があると学んだため、適用の用件、可否について理解を深めることで実用に近づくことができ、お客様の節税に繋がると考えました。 I様


また、相続に関することにかかわるまでは知りませんでしたが、相続は日本経済を回しているということを教えていただき、とても大きな業務だということが分かったため、社内でもその大きな業務に携わっているという自覚をもって自分の業務を行っていきたいと思いました。 O様
月次監査部署配属になると相続に触れる機会が少ないですが、相続の知識は必須だと考えます。月次監査時にお客様と相続の話になることが多いため、活用していけたらと思いました。法人設立や物件売却などの提案は所得税・法人税だけでなく、相続税も含めて提案することで成約率が上がると考えました。
S様
相続対策メニューを今回の講義で頂き、生前対策といった対策について、来年度以降正社員として働く上で参考にしたいと思いました。また、所得税や資産税といった令和3年度の税制改正について詳しく教えて頂き、税制について勉強するとともに税制の動きについて日々注力していきたいと思いました。社内ではまだ税について触れる機会があまりないですが、内定者のうちに税制について勉強したり、税制の動きについて理解していくことで来年度以降社内での業務に活かせると思いました。
H様
今回の講義の前半では、相続税の入門的な内容を含め、清田さんが実際にお父様から相続したときの実例をもとに、さまざまな節税方法を勉強することができました。自分が相続案件に携わるのは4月以降であると思いますが、これから視聴する相続税研修と結び付けながら、理解を深めていきたいと考えています。また、清田さんが農家出身者ということもあり、農地を所有しているお客様も多くいらっしゃると思うので、今回学習した生産緑地制度や、来年迎える2022年問題に向けてより一層理解を深めて来年に活かしていきたいと考えています。
M様
前半では清田さんの実体験から、相続対策の大切さや、実際に行った相続対策についてお話してくださった。 いかに遺言、生前贈与、所得の分散、保険など普通の一般人では考えられない内容を提案し、実行することが大切か分かった。また、税金を抑える考え方のみではなく、実際のお客さんの感情的な面でもサポートをしつつ、家庭全体を考える相続対策を手伝うことができて一人前であるとわかったので、それを目指していきたい。 税制改正の内容は、ちょうど一年目の自分にとっては確定申告の作業で使う知識が多く、医療費控除についてなどすぐに実践的に使う機会が出るのでとてもためになった。ちょうど納税猶予の継続の手続きを行うところだったので、いかに大切で責任重大な作業を今行っているかを知ることができた。
A様
清田さんの実体験を詳しく聞けたことでより想像が付きやすく実際に相続が起こった時にどう動くか、なにを気を付ければいいか再確認する点も含めてとても参考になりました。
納税猶予に関しては実際に届出の作成も行ったので、話がより入ってきたのと改めてその重要性を知ることができました。
税制改正についてはお客様でも気になっている方が多くいらっしゃるので日々動向をうかがっておきたいと思います。
生産緑地と納税猶予は少し頭の中でこんがらがることがあったので、しっかり復習をしてお客様からの質問等にも対応できるようにしていきたいと思います。
K様
遺産分割協議が遅れた際のデメリットをお客様にお伝えすることで、遺言等の話にも繋げられるのではないかと感じた。 また、養子縁組について、関与先の中に既に養子をとられているお客様がいらっしゃるので、今回学んだことを質問された際には自信をもって答えていきたい。 生産緑地についてはメリット・デメリットを踏まえた上で、2022年問題についての話に繋げられており、非常に飲み込みやすかった。こうした話の展開を参考にして、お客様に説明することも意識していきたい。
Y様
冒頭の1時間では相続にはじめて触れる方でもわかる相続税の講義がありました。私は月次部署で有料試算くらいでしか相続税に増える機会がないのでいい復習になりました。清田さんの相続対策の実体験を基に話が進んでいたので想像しやすく、現在進めている法人化の試算や同族法人への物件売却がどのような効果があるのかより深く理解することができました。
O様
生産緑地制度とは何か、メリット・デメリットを踏まえてご説明していただきました。生産緑地では相続税・贈与税の納税猶予を受けることができますが、建設した土地は対象外となるため、その点も注意しながら、メリット・デメリットを正しくお客様にご説明できたらよいと思います。
生産緑地は、相続税の評価に関係してくるため、生産緑地の評価方法をしっかりと理解し、評価する際には活かしていきます。
また、農地の納税猶予の適用された場合、相続税額を大きく減額できるケースもあるため、適用の可否についてもポイントをしっかりと抑えて、判断できるようにしていきたいと思います。
T様
今回の講義では相続の基本的な流れを教えて頂き、相続発生からの素早い対応やより円滑に進めるための対策等、業務を行うにあたってまず頭に入れておくべき知識を学ぶ事が出来た。相続は感情が大きく伴ってくるため、お客様に寄り添って柔軟な提案を行う必要があることも理解した。また、軽く触れられた税制改正の話を受けて、変化していく法や制度を見落とさず、専門的な知識をいちはやく習得する必要があると感じた。
K様
生産緑地制度と農地の納税猶予について詳しくご説明頂きました。生産緑地が売却できるケースとして生産緑地の指定後、30年経過後売却できるというお話がありました。そのお話の中で翌年2022年に生産緑地改正後30年を経過するため今後お客様への提案として大きく関わってくる制度だと思います。また、生産緑地の指定を受けているお客様において、土地の保有を継続するのか、土地を活用するのかによって相続税金額が大きく変わってくるので適切な対策に促せるよう今回の講義で得た知識を活用すべきだと感じました。 また、納税猶予においても、土地の状況によって適用できる土地なのかという判断を自ら判断し、摘要された場合には大幅な削減が期待できるので知識として身につけるべきだと感じました。
S様
講義を通して税務コンサルタントという職業の奥深さ、面白さを学ぶことができました。講義の前半で、清田さんが、相続対策メニューを用いて、お客様にどういった提案をすれば節税ができるのか、納税額を減らすことができるのかということを、一つ一つ丁寧に教えてくださいました。その中でも特に、生前対策について、様々な案があり、非常に勉行になりました。相続税という税金、相続税法という税法をいま一度しっかりと学習していきたいと感じました。
また同時に、ランドマーク税理士法人では、そういった提案から準備、相続まで他の会計事務所や税理士法人よりも迅速に進めることができるということも仰っていました。その一員になったからには、これからこの先、ずっと勉強していく姿勢を忘れずに、業務に取り組んでいきたいと感じました。
後半は、主に生産緑地の問題について考えていきました。正直、自分のレベルでは、どのくらい大きな問題なのかを理解することは難しかったですが、地価の下落が見込まれるということで、そういった点にも常にアンテナを張っていかなければいけないと感じました。
相続税の業務に携わるにあたり、最後に清田さんが仰っていたように、人とのつながり、信頼を大事していきたいと思いました。生前対策においても、例えば法人の設立であれば保険会社や建設会社とのつながりが生まれます。そもそも、相続そのものが、人の死をきっかけに始まる財産の取得であるために、人との信頼を大事にしていかなければなりません。本講義では、清田さん自らの経験をもとに、相続について教えて頂きました。今日学んだことを忘れずに、自身の今後の人生に活かしていきたいと思います。
H様
使う予定のない問題地などは売却までに相当の期間を要するため、何年も前から売却などの計画を立てておく必要がある。 ただ賃貸物件を購入するだけではなく利回りを意識することが重要であり、利回りが低いと今後の資金繰りが厳しくなるため賃貸物件の購入を進める場合はその点もしっかりと吟味する必要がある。
法人設立は財産の分散、所得税、相続税など様々な点から有利であるため財産規模の大きいお客様には提案できるように勧めていく。
贈与は生前贈与、教育贈与、建築贈与など様々なケースが存在するため1つ1つしっかり理解して節税の提案をする。 相続税の申告期間は10か月と長いように見えるがそんなに余裕がないためスピードを意識することが重要である。 相続人に相続税を引いた後の手渡しでいくら渡してほしいという要求も多くくるため相続税の計算を完璧にしておく必要がある。
お客様が所有している土地が何の目的で所有しているか明確にするため色分けすることが大切である。
生産緑地制度は土地の評価額を大幅に減少させることができるが、建築できないなどのデメリットも存在するため、制度を利用するかどうかしっかりと考える必要がある。
遺言は被相続人が方向性を作って、その後相続人と相談しながら遺言を作っていく方法も非常に有効である。
K様
相続税の試算について、ランドマーク税理士法人以外の税理士は申告期限がギリギリになってしまうが、他よりも素早く処理することでお客様から信頼と安心を得ることができると思いました。そのため、スピードを意識して仕事に臨むことが大切になってくると思いました。
遺言書の作成について、必ずお客様にお勧めすることで新たなビジネスチャンスが生まれるため、営業をする際は忘れずにお話することが必要だと思いました。
お客様の中に生産緑地2022年問題に該当する土地を所有している方が少なからずいらっしゃると思うため、この制度を理解することとどのような対策ができるか事前に調べ、答えられるようにできるといいのではと思いました。
K様
相続対策については、月次監査時にもお客様から相続の話がありますので今回学んだ、生前贈与や生命保険等の説明は実際に活用できるお客様が多いので、監査時にお客様に話すときに活かしていきたい。
また、土地の活用は相続に関しては大きな影響を持つので的確なアドバイスができるよう本日の講義を参考にしていきたい。
生産緑地や農地の納税猶予は生産緑地が解除される来年に向けて、問題となる点や解除した場合の注意点等はとても勉強になりました。
N様
本日の講義では、相続税についての基礎的な知識や相続税の節税方法について学びました。
私は現在、エントリ作業を業務として行っているため、直接的に相続税に関わる事はしていませんが、今度入社してから相続税に関しての業務はどのような物なのか、イメージしやすくなりました。
また、かなりの種類の節税対策がある事を学び、多くの知識を得る必要があると考えたため、今後も勉学に力を入れて行きたいと考えました。
I様
ランドマーク税理士法人の原点は相続税・所得税をどのように減らすかというところにあったというお話を伺って、クレドにもあるように出発点を見失わないことが重要だと感じました。基本的な税務の知識だけでなく、お客様がどのようなことに疑問を抱かれることが多いのか、どんな資料であれば理解しやすいかなどを意識して学びたいと思います。
2022年に生産緑地の登録30年を迎える土地が多いため地価が下落する可能性が高いという事実は、地主層のお客様にとっては大きく影響する場合もあると思うので、知識として共有することが必要だと考えました。
N様
清田さんの相続税納税に関して具体的にご説明があり、難しく捉えがちな相続税に関して、税について初学者である私でも明確に理解ができました。また、相談を頂いて一か月後には実際に土地を見に行き、昨年の路線価を基に概算納税額を二か月後には出すなど、スピードが圧倒的で、ランドと他社との業務の進め方の違い等が明確になりました。自分が今後業務にあたった時に自信をもって説明できるようなイメージを持つことができました。
相続は分割に際して、骨肉の争いに発展する場合もありますが、対策次第では各方面が満足した結果を得られるようにもなる、非常にやりがいのある分野だと感じ、ますます意欲が増しました。農協や銀行とのお付き合いについて、昔からのお取引だ、くらいに考えておりましたが、相続に際して、様々な節税策に各方面が関与している結果の現在に至るお取引だと理解できました。これまで積み重ねてきた信頼を失うことが発生しないよう、忠実に業務にあたる所存です。
生産緑地や農地の納税猶予などは、初めて勉強するテーマでした。メリットデメリットの両面を理解し、お客様へのご提案の幅が広がったと感じました。また、このような複雑多様な相続にかかわる各制度に対して、まだまだ理解が足りないことを実感し、ランドマークの研修はもちろん、意欲的に勉強を続けていく所存です。
A様
全て入社後の業務に活かすことができる知識であったと思います。特に、相続税の生前対策については、入社後お客様に説明ができるくらいにはならないといけないと思うので、今回生前対策はどのようなものがあるのか、ざっと知ることができたことは、これから知識を増やしていくための大きな一歩になったと感じました。今回お話があった内容以外にも、生前対策の方法はあると思うので、これを機にいろいろ調べて学びたいと思います。
それから、相続税の計算方法について、お話にあったドーナツとお饅頭をイメージしながら、入社後相続に関わるときにすぐに計算できるようにしておきたいと思いました。
W様
遺言の重要性や相続人の順位は事前に学んだことがありましたが、養子縁組の基礎控除額について、またアパートを建設すると相続税は少なくなること等、知らないことが多く、今後の業務に必要なことを学ぶことができたと思います。入社後には、お客様に分かりやすく説明できることが大切だと思うので、今の時期に生前対策について触れ、知識を得ることができ、貴重な講座でした。今回いただいた教材の税金ガイドを活用しながら今回学んだ生前対策だけではなく、他の方法について幅広く深く学習を進めていきたいです。
また、相続税の計算時に今までは混乱していたこともありましたが、ドーナツとお饅頭を用いて説明してくださり、とても理解しやすかったので、今後もドーナツとお饅頭をイメージしながら考えようと思いました。入社後に相続に関するときにすぐに説明、計算できるようにしておきたいです。
T様
相続税対策の提案の具体例を学びました。相続税対策にはどのようなものがあるのか全体の流れを把握することができ、今後相続税対策の対応をする際にお客様の選択肢を増やすより多くの提案ができるようになると考えます。また相続税対策では我々は提案する立場であり選択するのはお客様であること、金額面だけでなく感情面にも寄り添わなければならないことは今後お客様の対応をする上で大きな指針としたいです。生産緑地については2022年に約8割の土地が期限である30年を迎えるということで、これらについて知識を深めることで今後のお客様の相談により多くの知識をもって対応できることが期待できます。
S様
土地などの不良資産を相続税の納税資金に充てる。講義の中で出てきた山の活用例ですが、これは事前準備が功を奏した事であり、逆に対策をせずそのままにしてしまうと現金化が難しく税金も発生するデメリットがあります。
ここで学べることは事前の対策が大切であり、それはまさに我々の業務だということです。お客様に良いアドバイスを行い弊社も潤いお客様も節税に繋がる。
K様
・逆算して取り組む姿勢を持つ
お客様に「早め・速さ・正確さ」がそろったものをお届けするには、日頃の業務がその申告の1部であるかもしれないと思い、自分自身の業務もこれを意識して効率よく行うことが必要であると感じました。
・固定概念を強く持たない
遺言書作成などについて、それぞれの家族によって正しい形は変わってくるというお話がありました。お客様に提案する場面では、より多くのパターンをご提案し、これが絶対にいいと固執してしまわないように注意するべきだと思います。一方でお客様なりの相続を優先するあまり、何も提案をしないというのは避けるべきだと考えました。提案がされないのであればお客様も依頼したかいがないと思われるかもしれませんし、ご家族同士の争いにならない為にこうされるとよいですよ、という引き出しを全ての担当者が多く持てるよう社内での情報共有が必須であると感じました。
相続マイスター講座18期 第2講座の感想

現在新型コロナウイルスの影響もあり、訴訟の件数、処理数等は減少しているものの、現在感染者が減っていることもあり、訴訟の件数はまた増加していくことが予想することができるため対策をしていくことが必要。 I様

再調査の請求や審査請求の発生は、法改正によって減少する傾向にある。
不服申立制度として、様々な組み合わせがある。
再調査の請求は処分通知受領から3か月以内の申立期間がある。
申立費用や弁護士費用は不要で、申立から決定まで3か月程度。
しかし証拠資料の補完が難しく、最近は理由付記がかなり詳細になっている。
取消訴訟は三審制で最高裁まで行くと終結まで数年を要する。
審査請求は費用がかからない、決着がはやいなどのメリットがある一方で、判断が保守的であったり、証拠上の限界がある事件があるなどのデメリットもある。 M様

コロナが収束していくにつれて、税務調査がどうなっていくのか。
税務調査は主に修正申告で対応するが、稀なケースの場合にどう対応するかでお客様に信頼されるか否か左右されるため、知識をつけることが必要。S様
今回の講義を受講するまで審査請求や税務訴訟がどのようなものであるかについて全く知りませんでした。審査請求や税務訴訟等納税者と課税当局の間で起こっていることを知ることにより、日々変化する税務情勢についていくきっかけになりました。
S様
コロナの影響もあり、訴訟の発生件数は低くなっているが、税理士法人にとって訴訟は避けられないものになっている。また、裁判例でもあげられていた、「死亡共済金の申告漏れ」みなし相続財産に該当するが、聞き取りが甘く、漏れてしまっていた。聞き取り表を用いて漏れないようチェックをし、それを改めて事務所でチェックすることが必要。
W様
財務調査のほとんどが審査請求にまで至らず、修正申告で決着がつくことや、修正申告で処理すべきではないこともあること等、知らないことを多く学ぶことができ、今後の業務で重要な知識を得ることができたと思います。確定申告から是正、再調査の請求、審査請求の流れや、不服申立制度の流れなど図を用いて解説してくださり、理解を深めることが出来ました。今まで税務訴訟についてほとんど学んだことが無かったため、大変貴重な講座となりました。今後、自分でも勉強を進め、理解を深めたいと思います。
K様
税務訴訟を中心に様々な対応が求められることを学びました。過去の判例等から業務に生かせる内容などを取り上げ、実際に行かせるよう意識したいと思います。
K様
以前に修正申告をしてしまったお客様に対して、更正の請求をおこなう事で基本的には争う事ができるという制度もあるため、税務争訟についての知識を一人ひとりが身に付けておくとお客様のためになると思いました。そのため、お客様に実際に合う時にそのお客様が争う意思のある可能性がある場合は、会う前に上司の方と知識の確認をすると良いのではないかと思いました。
不服申し立て制度について、1番多い方法として審査請求を介して訴訟することがあるということですが、それぞれの方法にメリットとデメリットが存在していることをしっかりと把握できるように学習しておく必要があると思いました。
以上に述べたように、裁判に至るまでの各手続について、お客さまにお話しすることでお客様のためになると思うため、勉強会を開催して知識の定着を図ることが大切になってくると思いました。
K様
近年減少傾向にある税務調査の中でも元々少ない取消訴訟ですが、客観的にみて、訴訟が必要ないと考えられる場合でも納税者が少しでも納得いかない、訴訟をして納得したいと考えている場合はじめからその選択肢をないことにしてしまうのはその後のご不満などに繋がる可能性があると学びました。これを起こさない為、可視化することが必要だと考えました。本日先生にお話頂いたように取消訴訟と審査請求を実際にした場合、どのような点で違いがあるのか、最終的な時間、費用の面での結果などを明確にご提示する説明方法が活かせると感じました。ご提示することでお客様が重視する点に合わせてご提案がしやすくなるのではないかと思います。
H様
自分がお客様の担当を持った際に、再調査の請求や審査請求の最新の認容率はどれくらいかを把握していたり、平均でどのくらいの期間を要するのか等を把握しておくことにより、適切な対応に繋がる考えられるため、押さえておくことで実務で役に立つと思いました。
また、多く用いられている審査請求にもメリットとデメリットがあることを学んだので、実務で活用できるように知識として身に着けておきたいと思います。
K様
現在、相続部署の方で過去の相続申告の見直しが行われて、私の担当先でも修正申告をして更正の請求を行うケースがあったので、そこで更生が通らない場合、今回の講座で習った通り、不服申立制度の説明や争う案件かどうかの判断等行っていけたらいいと思いました。
M様
税務訴訟についての流れと各事例の説明の元、実際に税務調査が行われた際には、焦らず対処できると思う。修正申告によって決着するケースが多く、税務調査官は裁判という自信のもと指摘をしてくるので、ほとんどの場合修正申告で決着がつく。しかし、どうしても納得いかない場合は訴訟を起こす必要はあるが、訴訟を起こしても負ける可能性が多いため慎重に考えることが必要。
A様
税務調査の件数自体は減ってきてはいるもののいつ立ち会うかわからないので、税務訴訟や、不服申立制度などについて深く理解を持つことでもしもの時に円滑な対応が可能だと思いました。 石井先生の講義を受け、修正申告をしないことが一番だと改めて思わされたのでより丁寧な仕事を心がけなければと思いました。
O様
税務申告後に税務調査が実施され、修正申告・税務訴訟といった問題が起こりうることがある。この場合ほとんどのケースは修正申告で決着がつく。一方で税務訴訟まで発展するケースもある。その際はお客様がどのような解決方法を望んでいるのかを把握したうえで手続きのメリットデメリットを詳細にお伝えする必要がある。お客様が更正を受けずに穏便に解決したいのか、新しい評価方法で妥協的な解決を図りたいのかの意思決定が自信を持って行えるためにも各手続きの特徴を分かりやすく説明することが不可欠である。
N様
申告後に起こる問題として、税務調査、その後に税務争訟という可能性があり、これらの対応は税理士業務を行う側の損害賠償にもつながりかねない重大な問題で、慎重な対応を要します。こういった税務署側からの指摘に対して異議を申し立てるか否かの判断は、申告者側にはかなり難しく、相談にいらっしゃると思われます。その時に、税務調査から稀なケースですが税務争訟まで、概要や手続き、メリットデメリットを体系的に理解することが必要です。単に、税務調査の際の修正申告で決着をつけようと話を進めても、お客様のご要望に沿っていない場合、損害賠償を請求されるリスクもあるためです。修正申告以降の様々な不服申立手続を理解し、お客様のご要望に沿った提案ができれば、申告のミスがあった時でも、信頼を取り戻すチャンスにもなります。
T様
税務調査は基本的に修正申告で決着することが合理的だが、納税者が不服である場合等、争訟するかどうかの判断を慎重に行い臨機応変に対応する必要がある。現状新型コロナウイルスの影響で訴訟件数は減少しており法改正に伴ってさらに減少する可能性もある。審査請求についても、費用や時間がかからないというメリットと、判断が保守的かつ限界があるというデメリットの両者についての知識を得た。
I様
審査請求のメリットとして、非公開であることや決着がつくのが早い、費用がかからないということが分かり、訴訟との違いが分かりました。
修正申告で決着がつくことは妥協を余儀なくされることも多く、先例がなかったり、納税者自身が納得いっていない場合は修正申告で処理すべきでないこともあることが分かりました。
再調査、審査請求、税務訴訟の、発生件数、処理件数が減っており、コロナが大きく影響していることが分かる。
相続財産の所持を認識していながら申告漏れがあった場合で、税理士からの具体的な確認等がない場合は必ずしも納税者が秘匿していたとはいえず、重加算税が賦課れないこともあることが分かりました。
相続マイスター講座18期 第3講座の感想



また、後見人制度の回避策だけでなく二次相続対策、認知症対策においても高い効果を持つので、常に頭の片隅にとどめておき、将来お客様に対応したとき最適な提案ができるようにならなければならないと強く感じました。特に、認知症対策に家族信託制度を利用する場合は家族信託制度が契約によって成立する以上契約者に認知症の兆候が出る前に提案し、実行に移すことが大切だと思いました。 S様
節税対策はないが、認知症対策としての生前における財産管理や遺産分割対策としての役割を把握し、お客様に一つの選択肢として提案できるよう、自分自身の理解を深めていきたいと感じました。また信託スキームの設計における事例演習を通して、どのような点に留意して検討すべきかなどを意識して今後も取り組んでいきたいと感じました。
I様
家族信託は受託者に財産の管理を託すことであり、生前贈与にはならないことが分かりました。
生前贈与ではないが、最終的に遺産承継者を決めていることになることが分かりました。
受託者は信託報酬の定めを設けていなければ信託報酬をとることができないため、委託者と前もって話し合いをしておくことが重要だと感じました。
家族信託は、信託契約後、認知症になっても財産の管理、運用を受託者が継続できるため相続直前まで相続対策ができることが分かりました。
また、家族信託といっても、いざ相続が発生した時に遺言がないと、もめてしまいそうだと感じたため、前もって話し合っておく必要があると感じました。
K様
家族信託は遺言書の作成だけではできない資産組み換え機能を持っているとのことなので、はじめのご提案の際に自由度の高さなどを説明し、選択肢のひとつとしてお客様にお考え頂くようにすると良いと思いました。そうすることでその時はお客様に合わなくても、その後お客様に認知症などの発祥が確認された際にお客様の「そういえば」ひらめきにもつながりスムーズなご提案につながると思います。
S様
財産を所有している方が元気な内に行う財産管理として家族信託があるということは耳にしたことはありましたが、詳細については知りませんでした。ただ講義を聞くだけではなく、実際に自分自身で委託者や受託者がこの事例だと誰が該当するかを考えることで講義の内容がより理解出来ました。入社後に相続税に関わることがありましたら活かしていきたいと思いました。
H様
家族信託の制度を活用することによる財産管理によって、認知症対策に加え、後の相続においても大きく影響してくるので、しっかりと理解しておくことでお客様の選択肢を増やすことにつながると思いました。
また、直系の親族に財産を承継させたいなどを解決できるのも家族信託なので、来年に備えてしっかりと理解していきたいと思います。
K様
今後、自分の関与先でも高齢者の方が不動産管理等、事業を行っていることが出てくると思うので管理や相続に不安があるお客様には家族信託も1つの手段である事をアドバイスできるようにしていきます。
また、有料試算等組む際に家族信託をしている方がいると思うので、気を付けて処理を行っていく。
A様
相続対策を提案する際に必要となる知識だと思いました。
遺言、遺産分割協議書作成の際に家族信託を視野に入れておくことが大事だと感じました。
所有者が年老いて物件の売却等の判断能力が鈍ってしまうことは多々あると思うので、そういった点で家族信託をしておけばスムーズに相続対策を進められるのではないかと思いました。
また家族信託するのであれば遺言も作っておかないといざ相続になったときにもめごとになるケースもありそうだなと感じました。
I様
資産承継・財産管理制度の弱点は知識不足だった部分なので、財産を守るために注意しなければならない点を知ることが出来ました。お客様に直接提案する機会は少ないとは思いますが、少しでも多くの財産を残すためにより良い提案をすることに役立てられると感じました。
信託財産の仕組みは具体的に理解していなかったため、生前対策に活用できることを初めて知りました。ただ身辺整理を行うだけでなく、意思がはっきりしているうちに財産を有効に活用する準備ができるというのはお客様にとっても分かりやすく、利益の大きい方法ではないかと感じました。
相続が発生した際には受益権のある信託財産について贈与税・相続税が課税されると学びました。各種特例を活用することもできる点に留意し、最も利益の大きい方法を考えることが必要だと感じました。
A様
財産を持っている人が認知症になってしまうなど、判断が出来なくなったときにどういったことが起こるのか、成年後見制度や家族信託など、どの方法を取るかによって財産がどうなるかも変わることを知りました。実例を用いて実際に考えることができたので、イメージがしやすく、理解しやすかったです。成年後見人制度や家族信託について、言葉は聞いたことはありましたが、内容については知らないことが多く、今回知る事が出来たので、今後相続税などに関わる際に活かしていきたいです。
W様
認知症になった人の相続は本人の意思の確認がとりづらく、難航することが多いと聞いたことがありました。そこで家族信託は認知症対策や遺産分割対策に活用できると知り、効果的な手段の一つだと感じました。後見制度のみを利用すると受託者の財産管理は出来ませんが、家族信託を併用すれば信託財産の財産管理は可能になること、信託が始まると名義は受託者に移っても生前贈与にはならないこと等知らないことが多くあり、とても貴重な講義でした。受益者連続型信託など、かなり複雑な仕組みだと思っていましたが、ワークで実際に図を書いて考えることで、より理解を深めることが出来ました。今後の業務においても、遺言などに加えて家族信託について分かりやすく利点を説明できるように学びを進めようと思います。
A様
委託者・受益者の死亡により信託契約は終了するため、委託者が元気なうちに委託者と受託者の間で信託契約を結ぶことが重要であることを知りました。そのため、家族信託についてお客様からご相談があった場合にはこの点を伝えるべきだと思いました。また、信託財産と個人財産、信託財産と信託財産とでは損益通算が出来ない為、この点は注意深いチェックが必要だと思いました。
相続マイスター講座18期 第4講座の感想

お客様が疑問を抱かれる点も、解決方法も知識不足だと感じたので、相続税申告や事前対策に関する知識だけでなく、実際にお客様が悩まれることも知識として蓄えておくべきだと感じました。そのために税金ガイドが役に立つと考えられるので、お客様の疑問解決の糧にしたいと思います。 I様


今回の講義で相続の面談からの受注効率を高める営業手法について学びましたが、お客様との面談や相談を受けることは仕事をしていくなかでとても重要だと思うので、社内でも日ごろからお客様から相談などを受けても対応できるように考えておくことやメモを取る習慣をつけておくことが大切だと思いました。
S様
お客様と対応する際に、自社の製品に自信があってもそれを押し付けるような営業はお客様のためにならず、お客様からの信頼を得ることが難しいという点が目から鱗でした。つねにお客様の視点に立つことができるならば、そのお客様の実情に即したプランを提示することもお客様からの信頼を得ることもできると思うので、その視点を忘れないことが肝要だと思います。また、スピードが命であることは変わりないのでその場で上席や税理士先生に確認を取るマインドの重要性を再認識しました。
K様
お客様に対する対応が実際に依頼されるかどうかに大きく関わり、専門的知識の豊富さも大切だが、どれだけ相手の目線に立ち親身になれるかも重要だということを学びました。 また一問一答は絶対に避け、全体像を説明することが大切だと知り、自分自身が全体の流れをきちんと把握することが重要だと感じました。
K様
相続マーケットを見てみると、士業に相談せずに自分たちで申告していることが分かりました。また、相続が発生しても何もしていないご家庭が2割も存在していることも分かりました。このことから面談に来て下さったお客様は大事にしていく心構えが必要だと思ました。そして、世間に相続のプロフェッショナルは誰かと質問したところ、税理士と答える割合が一番高いということで、税理士業務をしている人はそのことを意識して、相続に関する全体像を把握している必要があると思いました。また、お客様のことを第一に考えた(担当者が独りよがりにならない)面談を意識することが大切になると思いました。 今回の講義の中の相続面談のノウハウがいくつかあったと思うのですが、面談シートとともに実際に面談する時に非常に役立つと思うため、この内容をしっかりと頭に入れて準備していきたいと思いました。
M様
普段は社内で事務処理を行うことが多いので、直接面談で関わることはないが、無料相談の電話対応などお客様と関わる機会はあるので、丁寧な対応を心掛ける。
相続のマーケットを理解するとお客様が求めているのはなにかということが理解できたので今回の講習を忘れないようにしたい。
K様
JAは本来提携するのが難しいとのことで、あらためて紹介先への感謝を忘れずに仕事に取り組んでいきたい。
また、世の中の人は(実際に最も業務にかかわるわけではないが)相続のプロは税理士という見解を持っているということを聞いて、世の中の見識との齟齬が発生しないように知識や態度を改めていきたい。
K様
相続マーケットの変化や、分野ごとの市場規模、新規お客様獲得に向けての対応の仕方について学ぶことができました。 市場規模に関しては、税理士がかかわる相続税申告は税制改正前90%前後であるといわれていたが現在は70%前後ではないかといわれており、顧客拡大はしたとしても、専門家に依頼をする人が拡大した分すべてに当てはまるわけではないと学びました。相続が起こっているうちの30%~40%の方に対してきちんと専門家がかかわるメリットを伝えてしっかりと対応することが必要だと感じました。
社内では、お客様に安心と信頼を感じていただくために、事務所に入った時のあいさつや身だしなみなど、担当者だけでなく社内全体で清潔感をもって対応することが大事だと感じました。
H様
相続税の申告対象となる人が限られるにも関わらず、その半分近くが自分自身で調べて申告をしているため、会社で行っている無料面談に来て頂いたお客様をいかに契約に結び付けることができるかが大事であり、そのためには有効な営業手法を身につけることが大切だと思いました。経験して自分なりの手法を身につけることも大事だが、営業のプロが行っている手法を身につけることは高受注率への近道だと思うので、勉強をして来年に活かしていきたいと思います。
K様
無料面談等は、会社の特色を知らないお客様が多いので、良いイメージを植え付けるためにも、会社の説明は端的に詳しく説明を行うことが大事なので、しっかり会社の強み等を理解しておく。
また、今回の講義は無料面談ベースの話でしたが、現在の関与先から有料試算等を受注するためにも必要なことであるので、しっかり応用していく。
M様
どんな営業にも言えるか、マーケットを把握することで客の需要を考えることは大事なことであり、税理士業界でも今後考えていかなければならない。
お客様の多くは相続イコール税理士と考える人も多く、それは実際どうであれそういう印象がある以上、客がある以上専門家としてそれにこたえなければならない。
そのため、不動産に詳しいなど、他社との差をつけることも必要となる。また、自社PRをできるようになることで自信と信頼につながる。
S様
一問一答方式の面談では受注は取れない。現在だとネットで調べればある程度お客様自身で申告が出来てしまう。面談にこられたお客様に、「あなたが相談している内容はこれだけ難しく、これだけ時間がかかりますよ」と伝えることで弊社へ依頼しようと思う気持ちを引き出す。内容の説明は専門的な事ではなく、申告開始から終了までの全体像を説明する。
A様
相続という分野がマーケットでどれだけ伸びているか改めて理解することができました。月次部署ではありますが相続の話はお客様とお話ししていてよく出るところなので確かに相続での売上は今後も継続してあり続けるのだろうなと感じました。
相続の面談についてはまだ経験がありませんが、会話の流れや、受注につなげる話の持って行き方は参考になったので自分もシミュレーションを提示する際に参考にしたい。
I様
ただ税務的な会話を行うのではなく、お客様の気持ちを思いやった話を行うことで受注率が向上する。またただ税務面に詳しいだけでなく、不動産など他分野にも見識があれば、他社との差別化に繋がる。 その点ランドマークには、長年のノウハウや社外との連携がしっかりしているのでその点をお客様にアピールすることができれば他者との差別化が図れるのではないかと考えました。 面談のビデオを拝見することができたので面談の際の内容の進め方や、会話の運びは大変参考になりました。
K様
紹介ではない一見客の場合、実際に顔を合わせる前段階の問い合わせの電話の対応から、依頼をするかどうかの判断材料になってくるため、フリーダイヤルを受電した際には丁寧な対応を行うように心がけたいです。 また、お客様目線で話をし、難しい専門的な話をいかに噛砕いて説明できるか、分かりやすくサービスの全体像を説明できるかなど、説明のスキルも重要だと感じました。
W様
相続が発生した場合、多くの方が専門家に手続きを依頼すると思っており、さらに2015年に税制改正が行われたことで、一般家庭でも相続税の申告をしなければならないようになったことで、手続きの依頼件数はさらに増加したと思っていました。しかし実際は30-40%程しか依頼せず、費用が多くかかることも考慮して、自分で行う人も多いことを知りました。そのため、専門家に依頼するか迷っている人に対しての丁寧かつ細やかなアプローチが重要になると感じました。実際に相続面談の様子を動画で見ることで、面談を進める流れやお客様に専門的な情報を説明する時の伝え方を理解することが出来ました。今後、入社後にお客様にご説明をするときに、相続面談ではなくても、共感や親身なスタイル、説明の前に自社紹介をすることなど、参考にするべきだと感じた点が多くあったので、この講座で学んだことを活かしていきたいです。
T様
相続の手続きを専門家に依頼する人は全体の30~40%しかいない。そのため、お客様自身で行ってもらうことも可能であることを念頭にいれ、サポートさせて頂くという姿勢を忘れない。 また、受注のために求められるものとして知識よりコミュニケーション能力が重視され、お客様に親身になって、この人になら任せたいと思って頂く事が重要である。
H様
資格の有無も大事だが、それ以上に誰にお願いしたいかといった、人間性の部分が相続面談においても大事になってくると知り、税務について相談しやすい存在となりたいと感じました。
A様
無料面談を通して突然「~万円です」と言われても、お客様側から見ると、その金額が妥当かわからない為、丁寧な説明が重要であることを知りました。そのため、お客様とのコミュニケーションをとる際には、細かな説明・配慮が必要だと思います。
T様
今後、お客様との面談を行う機会があると大いに考えられます。本日は相続面談が主な内容でしたが月次関与先のお客様への対応にも活かせると考えます。ホームページからのお問い合わせは紹介に比べ面談から受注まではハードルが高いです。そのため、よりお客様との信頼関係が重要になり担当者の人柄が求められます。料金の話は受注が決まってから確実に伝えること、すぐに決断できないお客様をサポートするため期限を付けて連絡先を必ず渡すことは今後活かせるポイントです。また、相続面談の一連の流れを動画視聴したことでお客様の面談対応のイメージをつかむことができ、今後面談を行う際の参考になりました。
Y様
お客様の話に耳を傾けニーズをくみ取ることが大切ということを学びました。月次で営業するときは何を不安に感じているのかヒアリングをし、お客様にあった商品を提案していきたいと思います。
相続マイスター講座18期 第5講座の感想

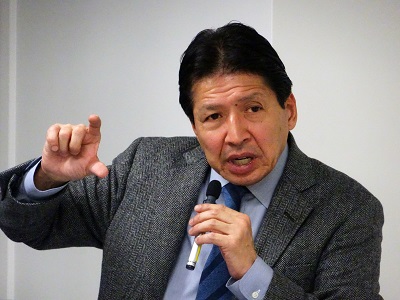

路線価は、正面路線の判定や地域区分を間違えると、お客様が多くの損失を負う可能性があるということを学んだので、お客様を担当している人だけでなく社内全体で、今進めようとしている土地の評価方法であっているのか、それよりもお客様にとってもっと良い方法があるのかを共有、確認して進めていくべきだと感じます。 T様
土地評価には様々な要素があるため、パターンを知っておくことが重要です。積極的に知ろうとし、複数の提案ができるようにしていきたいです。
K様
今回のお話を聞いて、最後の事例にある正面路線の決定による評価額ならびに税金額が大幅に異なることが印象に残りました。このように、担当者の判断によってお客様が喜ぶのか多額の税金がかかるのか変わってくるため、慎重な判断を行うとともに知識の定着を図りたいと思いました。
K様
土地の評価の基礎となる評価方法(路線価方式)のパターンを理解することができました。土地の評価の際、作図や正面路線価の判定、奥行の計算等の知識は今後の相続の有料試算に生かしていけると思いました。また、土地評価明細書の見方、計算方法を改めて理解することができました。
O様
日々の生活で目にする土地や道路に関心を持ち、この土地はどの地目に該当するのか、この道路の幅はどのくらいあるのか等考える意識を持ちたいと思いました。
A様
東京近郊では、土地の値段が高い為、何割くらい陰地があるのかといった、土地評価によって相続税が大きく変わるという事を知りました。そのため、お客様の土地を測量する際には地積・形状を基にした丁寧な測量が必要であると思います。
T様
土地の評価については、以前動画研修を受けた際は数式的な学習でした。しかし今回の研修では実際の写真や具体的な例示や図解を用いた土地評価を行うことができ、今後実際に相続税のご相談に対応するときの参考にすることができます。二面路線価の土地評価では地区区分の異なる2つの路線価を持つ土地評価を行いました。このような場合はどちらの路線価を正面路線とするかで評価額は大きく異なります。お客様の信用を裏切らないためにもこのような事例があることを把握しておくことは、今後お客様の対応をするうえで活かせると思います。また、土地評価明細書の具体的な記入方法も見ることができ、今後の実務に役立てられると考えます。
相続マイスター講座18期 第6講座の感想
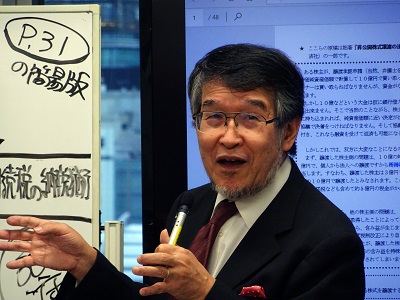


非公開株式の基本や事業承継の際の中小企業の株式の取り扱い方法や個人・法人の違いについて詳しく知ることが出来、譲渡制限株式についてのイメージが出来ました。また、コロナへの対応として相続の納税猶予の特例が適用され、担当者は毎日の管理等によるリスクが増えることとなりましたが、将来的にこの特例が上手に扱うことが出来ると良いと思いました。
H様
お客様の中には、会社を経営している方もおり、その人たちは自分の会社の株式を所有しています。上場していない会社がほとんどであり、株価を算定する時には専門的な知識が求められるため、勉強すべきだと感じました。特に「みなし~」などは相続時など気を付けないと多額の損失につながるので、注意したいです。
M様
今回は主に株式の評価方法と事業承継についての内容でした。非上場株式の評価は相続のシミュレーションで何度か計算したことがありましたが、法人設立時や法人が物件をもっていなかったりすると株価が安かったりします。贈与を考えている際は評価額の算定は念入りにする必要がありますし、単発の場合でも高額な報酬を頂くため、注意して評価を行っていきたいです。また、同族法人などの株を相続する際の相続税の納税猶予は大きな節税に繋がりますが、とても手間がかかり、都度継続届け出の申請を怠ってはならない点はデメリットになり得るため、慎重に考える必要があります。申告するだけの関係で終わらせないことが仕事をする上で大事なポイントであることを念頭に、今後取り組んでいきたいと思います。
S様
講義の中で、事象の結果である決算書等を作成しているだけではお客様は喜んでくれない。これからの経営に役立つ会計が必要と述べていました。納税猶予や節税など付加価値のある提案を心がけたいと思います。
K様
相続部署として、非上場株についてのメリット、デメリットを確認、理解したうえで、相続が発生した際にどのようなリスクがあるのか、評価の方法などしっかり説明した上で申告書づくりを行おうと思います。
K様
ランドマーク税理士法人で扱う顧客では家族で経営する同族経営の会社が多いため、今回の講座で扱った非公開株式は特に取り扱うことが多いと思います。フリーダイヤルでも聞き取った内容を理解できるようにしていきたいです。 法人・個人間での株式の移動がみなし譲渡、みなし配当等とされると多額の税額がかかる場合があると学びました。
A様
W様
H様
H様
K様
相続マイスター講座18期 第7講座の感想



養子縁組と遺言の実例が沢山聞けましたので大変参考になりました。
O様
なかなか知り得ない争族のお話が伺えて興味深かったです。ありがとうございました。
K様
養子縁組について、相続税対策として活用するお客様が実際に居る可能性があるため、税金対策等節税の意思のみなのか孫等に相続権を発生させる意思があるのかをはっきりさせることで、最高裁の判例にもあった通り、子供の取り分が変わってくることを学んだため、お客様への提案の際にはこれをはっきりさせることを徹底することが大切になると思いました。また、養子縁組の届け出を勝手に提出することはもめごとにつながる可能性が高いことから、お客様が勝手に提出しないか注意して対応していくことを徹底すること、お客様対応する方に周知することが大切になると思いました。
K様
相続にあたり、誰の目線からみるかでやらなければならないこと、やったほうがいいこと、やらないほうがいいことが変わってくることを、今回多くの事例をお話しいただく中で学びました。一般的によいとされることでも、自分のお客様には合わないということがあると認識しベストなプランを提案できるよう、はじめからこうすると決め込まないことが重要であると学び、活かせそうだなと思いました。
S様
争族について計12の事例を説明していただくことによって、相続に関する様々なトラブルについて知ることが出来ました。ランドマーク税理士法人で働くにあたってこのようなお客様に出会うことが今後あると思います。今回の講義で多くのトラブルへの対策(遺言の作成の仕方や養子縁組の重要性)を学びましたので、今後提案出来るようにしたいと思います。
H様
相続の持分割合を巡って家族であっても本気で財産を奪い合い争続に発展することが多くあり、今回、多くの事例に絡めて学ぶことが出来たことは実務で大いに活かせると感じました。また、遺言にも大きく分けて二つ種類があるため、紛失などのリスクを考えて公正証書遺言を活用することが良いと感じました。
K様
弊社のお客様にも生前贈与や遺産分割協議書等、生前対策に興味のあるお客様が多いので、今回の講義で養子縁組、遺言等の理解が深まりました。様々な事案を通じて遺言の有効性や遺留分侵害等理解することができました。
M様
養子縁組については、確かな節税対策につながるが、不公平が起きうる場合があるので、養子縁組、遺言両方を推進することが望まれると思います。また、遺言についても推定被相続人がなくなる前に相続人がなくなる場合もあるので、その時に備えて予備的遺言の作成も視野に入れるとよいと思います。相続人たちが争わない円満な相続をするために、養子縁組、遺言の活用は必要不可欠だと思いました。
K様
税理士法人として、家庭内事情に踏み込んで一緒に協議をすることは許されません。あくまで税額の計算などの申告書の作成を補助するという立場であるため、小嶋事務所のような弁護士という調停代理人に頼るということも一つの選択肢であると気づきました。倫理は遵守したうえで、それぞれのお客様にきちんと向き合いたいと思いました。
K様
遺産分割の協議において相続人の間で争いが起こった場合には、税理士の業務範囲ですべてに対応することは難しいので、対応できるその他士業と連携していくことも大切であると感じました。フリーダイヤルで遺言についてや相続人同士で争っていて困っているという問い合わせも多く取るため、だれに任せるのが適切かケースごとに対応できるようにしたいです。
O様
相続は遺言書と養子縁組で決定すると学びました。遺言書は、自筆証書遺言と公証人遺言書があります。自筆証書遺言の場合、保管等が難しいといった問題があります。特に相続財産が多い場合には、第三者の関わる公証人遺言書を作成し、確実に保管したほうが良いです。相続の相談を受ける際には、公証人遺言書の作成を積極的に進めたいと思います。養子縁組について、養子縁組は陣取りであることを学びました。養子縁組は解消するのが困難なケースが多いので、よく考えて養子縁組をするべきか判断する必要があります。
N様
農協組合員の相続案件は、長男が家を継ぐため、長男に遺産を多く取得させるという点に特色があります。ランドマークのお客様も多くが農協関係であり、遺産分割などではなく申告のお手伝いをするのがこちらの仕事ですが、相続税申告の前提である相続分割について、具体的な例をいくつかあげながらご説明頂き、具体的なイメージがつかめました。遺産の分割について、遺言や縁組の有無により、クライアントの取り分がかなり変化することに驚きました。ただ、遺言や縁組などの対策をとっていても、状況の変化やその対策をとった時期によって後々効力を否定される場合があり、どこに注意する必要があるのかなどを詳しく提示していただきました。
遺留分について、改正前民法の減殺請求と現行の侵害額請求は、潜在的持ち分からの遺留分主張なのか、侵害額の金銭的な請求なのかと性質が異なっていることや、遺留分を請求される側からすれば、今まで無制限に遺留分の対象財産としてカウントされていたのに対し、持ち戻しの対象が遡って10年前までの生前贈与までが対象であること、さらに遺留分侵害額の請求の順序まで、実務の詳しいお話をしていただきました。
A様
実際に争族となった事例を12パターン知る事ができ、遺言・養子縁組が相続においてどれだけ重要なのかが理解する事が出来ました。逆に、相続を成功させるには、どのようなことに注意しなければならないのかを知る事が出来たので、今後相続税に関わるお仕事をさせていただくときに、今回得た知識を活かしていきたいです。
W様
今までの丸の内相続大学校の講義の中でも、遺言の重要性について学んできましたが、養子縁組を早めにすることで、自分のグループを増やす(相続分を増やす)ことに繋がることは、生前対策としてお客様に提唱すべきだと感じました。遺言にも公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言は子に託すか、保管場所に注意しないと効力をなくす可能性があることを知り、そのリスクをお伝えしたうえで公正証書遺言の作成を勧めるべきだと思いました。遺言や養子縁組の重要さを12の事例から学ぶことができ、重要な点と気を付けなければいけない点を理解することが出来ました。
H様
遺言や養子縁組を活用して頂くことで争続予防が期待出来るということから、相続を控えるご家族に対してこのような生前対策を提唱すると良いと改めて感じました。今回までの講義を通じて、寄与分等を譲られる側で協議することは、家族内であってももめやすいものであるということをよく知る機会になりました。
A様
遺言を書きたいと考えているお客様に対してご案内する際には、自筆遺言という形をとると修正が困難であること、紛失の危険性があることなどを説明する必要があると思います。また、遺言を書き直していないことで失敗するケースもあるため、この点もご案内する必要があると思いました。
K様
小嶋先生には、特に農協組合員の方々が陥ってしまった相続のケースを基に、養子縁組や遺言を書く際の注意点などを踏まえて講義をしていただきました。私が特に社内で活かせると感じたポイントは、相続をする上で地主さんが土地に対してどのような思いを持っているかという点です。講義の中では、「あまり地主さんは土地を細分化したがらない。」「基本的には長男に遺産を譲りたい」などのワードがありました。地主さんによって思うことは様々ですがこのように地主さん側の事情を少しでも理解しておくことで担当者になった際により良い相続の提案を行えるのではないか感じました。また、その地主さんの方々が求める相続の形をできるだけ実現するために養子縁組と公正証書遺言の二つを使い、長男に遺産を集中させることや「争族」が起きないような生前の対策を提案するために法律上の知識が社内で活かせるポイントになると思いました。
H様
関与先の子供間の関係性はどうなのか、子供とは疎遠になっていないかなどをしっかりと聞き取ることが非常に大切なため、今の内からわからないことや疑問点が浮かんだらすぐにそれが分かる人に聞くことを心掛けようと思います。相続に関する話はデリケートな場合が多く、こちら側が失言をしてしまいクレームにつながる可能性があるため、話し方や言葉遣いに気を付けていこうと思います。税法上の養子縁組と民法上の養子縁組は多少意味合いが異なるように、税法と民法で言葉の意味合いが異なるものも存在するため、今のうちにわかるものは勉強することを心掛けます。
T様
養子縁組や、遺言など様々な方法で相続分を増やす手段があるとわかり、相続についての制度の知識を付ける必要があると感じました。また、その家を後世につなげていくということが目的ならば、長男にこだわらずその家業を継いでくれる方に相続してもらうのもよいと思いました。
T様
本日の研修は、主に東京近郊に農地、宅地を含む不動産を持つ地主等に焦点を当てての養子縁組や遺言等と関係した相続についてでした。ランドマーク税理士法人の相続では、主なお客様はこのような都市農家であることがほとんどで、長男に遺産を多く残したいという考え方が根強く残っています。このような相続ならではのトラブルを知ることは、今後相続対策のお客様を対応するうえで節税対策として提案する養子縁組や遺言にはどのような危険があるのか、どのようなことに注意しなければならないのかを説明する際に活かすことができます。また、今回の研修では多くの具体例を取り上げていただき、今後様々な事情をお持ちのお客様の対応をする際に、今回の具体例と似たような事例があれば、研修を活かした提案ができるのではないかと思います。
相続マイスター講座18期 第8講座の感想



両刃の剣と言われている書面添付制度について、ランドマーク税理士法人はこれを行うことで税務調査に来る確率を大幅に減らしているため、これを活用している事務所はレベルが高いというお話を聞いて、自信をもってお客様にお話をして信頼を得ることができると思いました。 K様
相続税の税額を下げることだけが目的なのではなく、二次相続など、下の世代のことも考えたうえで相続税の申告を行うことが大切なのだと改めてわかりました。「相続税に強い」のではなく「相続に強い」事務所だとお客様にも喜んでもらえると感じたので、お客様に喜んでもらえる仕事ができるよう意識していきたいと思います。
S様
単に支払う相続税額が減ることだけを考えるのではなく、将来を見据えた相続全体を俯瞰出来る“相続”に強い税理士についてのポイントを相続税申告の流れに沿って教えて頂きました。資料の最後にありました「相続人や後継者に寄り添ってくれる心から信頼できる税理士」のフレーズはこれからお客様対応していくうえで心がけていきたいと思いました。
H様
今回の講義では、お客様目線でどのような税理士に依頼すると良いのかを学習する事が出来ました。先生の事務所では、すべての申告書に書面添付制度を活用しており、書面添付をすれば税務調査は来ないというわけではないけれども、1%未満に抑えることができていると仰っており、時間と費用を勘案する必要はあるけれども、行うことによるメリットは大きいため、活用すべきだと感じました。また、税務調査の際の捜査官が発した言葉や行動の奥にある本当の意図を知る事が出来、万が一のことがあった時のことを学習できたので、来年に活かすことが出来ると感じました。
M様
相続税の申告は10カ月以内という短い期間内で行うものであり、スピーディに対応することが必要不可欠です。この点に関しては経験が少ない他の税理士よりランドマークはアドバンテージを持っています。そのため、まずスピードを意識することが大事であり、スピードが信頼につながります。これはほかのことにも言えることですし、クイックレスポンスは相続が発生したお客様の我々ができる気遣いであると考えます。また、二次相続まで考えることがお客様のためになり、お客様の視点に立ちお手伝いをすることを常に忘れないで業務に取り組んでいきたいです。
K様
相続に強い税理士とはどんな人かという内容でご講演いただきました。具体的なタイミングとその時にどんなことを行うとよいかについて理解することができました。お客様の目線から考えると、相続税の申告を安心して任せられる税理士ということになると思いますが、しっかりとした実績や相談の時の対応はもちろん、申告後やもしも不具合があったという場合の対応がしっかりとできることがお客様からは求められることになると考えられます。今回のレジュメには、事例とその時にどういった対応をするとよいかが書かれているので、時間のある時にもう一度読んで、そのようなことが起こった場合に対応できるようにしていきたいです。
K様
相続部署として、土地評価、預金不明点の作成やお客様から預かった資料から申告書を作成するという事務処理を行っていたので、とてもイメージがしやすかったです。税務調査を行われ、摘発される可能性などを想定しながら正確な申告書づくりを行おうと思います。
N様
相続税を扱う人間として、どのような志を持って仕事をしていけばよいのか、どのような税理士を目指していけばよいのか、質の高い税理士とはどのようなものなのかを具体的に教えて頂けたため、少しでも早く近づけるように努めてまいります。
K様
信頼できる税理士とはどのようなものか。また、そのような税理士と出会うために留意すべきことは何かを学びました。税理士法人で働く上で、今回の講義は、最も重要な「お客様視点」を考えるきっかけになったと感じています。お客様の「心」に寄り添うためには、経験の蓄積だけではなく、人間性を涵養させることも忘れてはならないと、改めて認識しました。加えて、社員、スタッフ、アルバイト等、ランドマーク税理士法人に携わる一人一人が、お客様との繋がりは一度限りではないことを念頭に、お客様のため、会社のためにできることを模索する必要があると感じました。私もその一員であることを胸に、日々努めていく所存です。
O様
「相続に関する税務調査ではどういう目的でどんな資料を調べるのか」「申告漏れを防止するためのチェックリスト」について抜粋して説明がありました。講義の中では時間の制約上説明されなかった部分にも目を通し、税務調査に入られない申告書とはどういったものなのか理解を深めていきたいと思います。
N様
相続をメインに活動する事務所として、お客様へのアピールポイントが明確になりました。圧倒的な申告件数、迅速な対応(1-2か月後には現地まで調査し、概算で税額提示をできる点等)、これまで培ってきたネットワークを用いてワンストップで対応できる点、当該申告だけでなく生前対策・2次相続まで対応する点、あまり多く活用されていない書面添付をすべての申告で行っている点、国税OBを多数擁し評価額の減額や万が一の税務調査まで対応できる点など、お客様が求めている点を踏まえて、ランドマークを選んでいただける決め手を考えるきっかけになりました。また、税務調査における国税官の調査対象の資料を基にご説明いただきました。特に印象的だったのは、税理士がご焼香する場合は、故人を想う気持ちから来ますが、国税官は仏間に入り、高価な物品や最近使った印鑑はないか、そこから隠し口座がないかまで推察できるようです。まるで刑事ドラマのように感じましたが、国税官の調査対象を知ることで、申告の抜け漏れが発生しないようどこに注意するかが明確になりました。
S様
支払う相続税額を減らすことだけを考える“相続税”に強い税理士ではなく、指導的な立場でその家の将来まで見据えた相続全体を俯瞰できる強い味方になれる“相続”に強い税理士になれるように、とありました。相続だけに限らず、お客様と直接関わりながら仕事をする以上、税の事ももちろんですが、お客様のことも考え、寄り添いながら提案などしていきたいと思いました。
H様
相続の相談を受けるときには節税のことだけを考えるのではなく、二次相続等の相続人の家族の将来のことも考えること、また、家族など亡くされているお客様の気持ちを汲んだ対応をすることなど、相続税に強いだけでなく相続に強い税理士事務所を目指していくことが重要であると感じました。
S様
相続税について強くなるのではなく、全体的に相続について強くなることが大切であると感じました。また、それらを含めて、お客様に対してしっかり説明し、寄り添った応対が出来るようにしていきたいと思います。税務調査については、しっかりと対策を立てて申告書を作成することは勿論重要であり、お客様との日頃からの信頼関係もより重要であると感じました。
T様
相続と相続税の違いを理解しておくことは今後お客様の対応をするうえで非常に重要であると考えられます。ただ節税を考えるだけでなく、相続において発生する不動産や預金の名義変更、2次相続を想定しての遺産分割、さらに不動産等の遺産を相続した場合にはその不動産の今後の運用なども考えなくてはならないことです。このような一連の相続の知識が必要であることは常に意識し、お客様に寄り添える存在でありたいと思います。また、税務調査についてはあまり知識がなかったのですが、今回の研修で税務調査がどのようなものであるか知ることができました。税務調査はお客様にとっても我々にとっても負担の大きいものです。今後申告書を作成する場面では、調査官がどのような点を見ているのかを踏まえた申告書を作ることを意識したいです。
相続マイスター講座18期 第9講座の感想

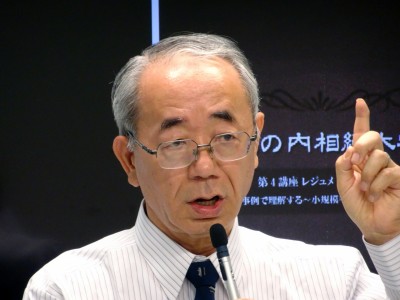

今回の講義で、小規模宅地の特例についての条文を用いて、条文内の用語の定義等を学習する事が出来ました。また、レジュメには条文の中に先生が詳しく補足してくださっており、小規模宅地の特例について詳しく理解することができると感じました。朝礼の中でも、小規模宅地の特例についての内容が頻繁に出てきているので、相続業務を行う上で必須の制度だと思うので、知識としてしっかりと定着させていきたいです。
また、法律以外にも施工令、施行規則、通達、情報等、タックスアンサーがあり、法律だけでは知識として十分ではないことも仰っていたので、それぞれの小規模宅地の特例についての関係性などをよく理解し、来年以降実務で活かせるようにしていきたいと思います。
I様
小規模宅地等の特例の適用要件の共通項目についておおまかな要点を知ることができたので、相続が発生した際に迅速な判断で対応できるように努めたいと思います。
相続開始時点と申告期限時点では要件や判定が異なることを知りました。自身の知識を整理することにより分かりやすい説明ができるようになると思うので、それぞれの要件を再確認したいと思います。
W様
租税特別措置法第69条の4の条文の用語の意味や定義について学び、法律を正しく読んで理解し、曖昧な時等は法令(法律・施行令・施行規則)と通達・情報などで判断することが必要だと感じました。小規模宅地特例には期限があり、提出したものを後から取り消すことや適用することができないため、気づかなければ顧客は多く税金を支払うことになり、損害賠償を請求されるため、申告期限前に気づき、適用することが重要だと感じました。また、相続開始時点と申告期限時点では要件や判定が異なるため、理解したうえでお客様に分かりやすく説明できるようにしたいと思います。
A様
租税特別措置法69条の4の文言について、1項における「個人」には、人格なき社団法人は含まれない事、1項2号における「当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む」とは、老人ホームなどに入所直前の元の居住用宅地などに相続開始まで居住していたと認めたようなものだと教えて頂きました。これにより、小規模宅地に関する条文とは非常に細かく理解が困難なものであると分かったため、お客様に対してご説明する際には、どのような要件があり、どういった場合に特例が適用されるのかなどを可能な限り分かりやすく丁寧に説明する必要があると思いました。
T様
本日は小規模宅地特例についての研修でした。小規模宅地特例は今後相続のお客様の対応をするうえでよく利用する重要なものでありながら、正しく適用しなければ多大な損害賠償等の可能性もあるものです。本日は主に当該法令の条文を正しく理解することに焦点を当てた研修でした。普段の動画研修では条文をかみ砕いた解説での理解が中心ですが、その根拠となる条文を正しく理解することでお客様のご案内の際も根拠を持って安心していただくことができ、判断が難しい時も活かすことができるのではないかと思います。また法令の読み方というのは今回の小規模宅地特例だけでなくその他全て、相続税以外の税金計算にも同様に活かすことができます。常に法令、通達、情報から判断を行うということを意識したいです。
相続マイスター講座18期 第10講座の感想

M&Aの失敗事例として、オーナーの急逝に対応できず、事前対策も不十分であり失敗したケースが取り上げられている。こうした場合に備え、後継者を決めておいたり事業を引き継ぐ準備等を生前に行うことが大切だと感じた。 K様


また、失敗事例、成功事例の対比はとても分かりやすかったので、お客様の監査時に参考にしていきます。 K様
会社の高齢化が進む中で、後継者の問題が出てきている。そのような中で、事業承継の問題や納税の問題がある。今回講義してもらった、各事例(M&A、組織再編、新会社方式、新事業承継税制、DES)について、成功事例と失敗事例を教えていただけたので、この例を参考にしつつ、ほかの事例を自分でも探し、しっかりとした知識を身につけておく。そうすることで、こういった事例に対応できるようにしておく。
I様
中小企業の経営者が高齢化していることから事業承継が難しくなっていることを学びました。ご高齢のお客様に限らずどんなお客様にも、早い段階から事業承継を提案し、ご健在のうちに実行できるよう進めることが必要だと感じました。また、突然の病でM&Aを決断した事例をご紹介いただき、廃業するにも現在会社で保有する資産の処分手続き自体にかなりの時間と労力を要するため御体への負担も少なからずあると学びました。このような不測の事態に備えるという意味でも様々な選択肢をお客様に提示することが必要だと強く感じました。
会社を順調に経営してきた社長が突然亡くなり、幹部も含め従業員が動揺、特にワンマン経営を続けてきており会社の意思決定権者が不在であったことも拍車をかけたという事例をご紹介いただきました。この事例から、意思決定権者が先々のことを想定して事前に方針を示しておくことが必要だと感じました。
K様
少子高齢化や医療の発展により、平均年齢が上がっている。(2025年問題) 横川先生は成功事例6件と失敗事例1件を参考にお話をされていた。急逝された代表の事業承継は、生前に対策できてなく、1ヶ月以内に買手企業を探すという厳しいもので、結果失敗事例になっている。逆に、代表が健在のときから、事業承継をしている事例が成功事例として挙げられている。
相続対策、事業承継は生前に行うべきということを改めて感じた。
W様
中小企業のM&Aには双方の同意と秘密保持契約が必要であり、事業承継の際にその対象企業の特色や財務状況を理解しておくこと、事業承継に至った背景について考慮することが必要だと感じました。事業承継についてそれほど知識はありませんでしたが、会社を分割する方法、分社する方法、新しく会社を設立する方法など多くの方法があることを知り、お客様の求めていることにあった方法をすすめることが重要だと考えました。貸付金を減らすために債務免除することに加え、債務を株式化する方法もあるため、様々な方法について学びを深め、今後の業務で活かしていきたいと思います。
O様
事業承継では単に税に関してだけでなく、承継先を見つけることや事業主とその家族らの意向等、柔軟に対応しなければならない。この点について気を付けなければならない。また、この点に関しては事業承継だけでなく、相続税全般に言えることであると再認識すべきであるということに気づけた。単に税金を安く済ませるということにとらわれず、顧客へのヒアリングを丁寧に行うよう今後活かしていきたい。
H様
弊社では多くのお客様の相続に関わるが、その中で後継者に悩んでいる中小企業の経営者の方も少なからずいるものと考え、時と場合に応じてM&Aなどを視野に入れて提案し、税理士事務所からの視点で企業の存続に貢献していきたいと思った。
経営者目線で物事を考えることや、経営者の意思をよく汲み取ることをすべきと感じた。
T様
事業承継についてはまだ学習が足りず事業承継の一環としてM&Aがあるということほどの知識でした。今回の研修で事業承継の様々な方法を知ることができました。今後お客様の対応をするうえでお客様の実情に合った方法をより多くの選択肢から提案することに活かせます。またそれぞれの方法にはメリットも多くありますが、注意しなければ損害賠償などの大きなリスクもあります。例えばDESでは社長からの借入金を株式とすることができますがその分だけ資本が増えるため資本金が1億円を超え中小企業の税制特例を利用できなくなってしまわないよう注意とお客様への説明が必要です。常に税制度の改革や新設には気を配り、お客様には正しい情報をお伝えできるように社内の研修だけでなく自身でも学習が必要です。
H様
2025年における中小企業・小規模経営者の約65%が70歳以上になり、その内の約半数が後継者未定という現状があるため、今後事業承継が必要なお客様も出てくることが考えられるということなど、様々な事例に触れることができたことはとても良かったです。経営者が亡くなってから事業承継を考え始めると、時間とお金が多くかかってきてしまうため、未来を見据えて様々な選択肢をお客様に提案することが大切であると考えられる。そのための会社法などの知識を普段から勉強しておくことが重要であると感じました。
また、最後に学習したDESも、会社への貸付金が多額のオーナーがいた場合には、相続税対策に活用できるため、しっかり理解しておきたいと思います。
相続マイスター講座18期 第11講座の感想

納税資金がないという理由で、安易に延納を選択したら、後に日々の収入から生活費等を差し引いた中で、納税資金を捻出することになるため、将来年賦による納税が困難となるということを学びました。そのため、延納を選択するときは、担保となる財産があるのかどうか確認しなければならないと思いました。
また、先生が、勉強したことを、現場で言語化し、自分で考えて行動することが大事だとおっしゃっていて、その通りだと思いましたし、現場でできるように練習しなければいけないと感じました。 T様


また、節税対策として建物の法人化という選択肢があることを学習しました。しかし、これも長期間をかけて行うことでより大きな効果を得ることができるものであるため、どの選択をするにしても早く対策をはじめることが大切であると学習しました。
また、学習した知識を言語化することは、練習しなければできないため、日々練習するべきだと感じました。 H様
遺産分割検討のポイントの説明の中で、後継者の意向に沿った分割ができるかどうかという話があり、遺産分割に限らず、お客様の意向に沿うという考え方は仕事を行う上で大切であり、この考え方は社内でも活かせそうだと感じました。
S様
K様
最初の納税資金準備のフローチャートは今後、有料試算を受注した場合やお客様に説明する際に、とても分かりやすいのでパターン作成時に参考にしていきたいと思います。
お客様によって、預金、土地、同族法人等ケースが様々なので今回の講義はケースによって相続対策を知ることができたのでお客様に弊社の商品を進めるときに活用していきます。
K様
相続税の納税資金対策は、納税資金がなく延納をしてしまう場合のデメリットを回避することができる。また、納税者にとってもあらかじめ納税額を想定しておくことによって、節税などの税金対策をすることができる。節税をするかどうかで納税額も大きく変わってくるため、相続税の納税資金対策は内容を覚えておきたい。また、もし法人化をする場合も、しっかりと検討した方がよいということを再認識することができた。法人化してしまいデメリットがある場合があるからである。私が法人化を扱うときは、しっかりとシミュレーションして扱っていく。
I様
納税資金対策において最も大切なことは、相続税のかからない納税資金をいかに生前に確保しておくかということと、建物の法人化を行うことだと学びました。生前対策でできる限りのことを行っておくことで実際に相続が発生した際にお客様が安心して弊社に任せていただけるようになると思うので、早めにお客様にお伝えして対応していきたいと思います。
納税資金が確保できるかどうかは、分割がスムーズにできるかどうかが前提となると学び、お客様の納得のいく遺産分割を早い段階から定めておくことが必要だと感じました。お客様に寄り添った提案ができるように、お客様目線に立って業務に当たりたいと思います。
K様
会計の仕事では、持っている知識を難しくではなくお客様に分かりやすくご説明し、信頼を獲得していくことが大切。
フリーダイヤル対応では、お客様から見ると最初に接する職員になるため、いい印象を与えられるようにしたい。専門用語など難しいものを簡単にかみ砕いて説明するのは難しいが、お客様目線に立つことを心掛けていきたい。
N様
確定申告や名寄帳は、情報量が豊富で、今後の相続税申告に繋がるなどとてもメリットのある仕事であり、大事にしていることだと妹尾先生がおっしゃっていました。相続税申告だけでなく、先日行った確定申告手書き研修などを通じて、基礎的な税務の知識をつけ、メインとなる相続税申告に繋げていきたいです。また、会計の仕事は、知識をつけてお客様に分かりやすくお話し、信頼を獲得していく仕事とお聞きしました。人生であまり経験することのない相続税申告では、お客様は担当者が信頼できる者なのか、相続税は相続した財産から支払いが完了するのか心配しているようなので、知識をつけて場数を踏み、自信をもって税務知識をお話しし、早めに概算額を試算してこれからの対策、また二次相続やその後の相続に繋がるような対応ができるようにしていきたいです。
W様
不動産等、建物を法人化することで相続税のかからない資金を生前に作っておくことや分割対策など、3つの相続対策をお客様によって使い分けることが重要だと考えました。また、納税資金が無いために延納することや不動産を共有、未分割にしておくことは将来相続人間でトラブルになる危険性が高いため、その場で解決しておくべきだと知り、お客様へもしっかりと説明したうえで進めていきたいと感じました。相続対策・納税資金対策には生前贈与や遺言書等、相続が発生する前に行うべきことが多くあるため、お客様の意向に沿うこと、尚且つスムーズに相続を行うことが出来るよう、日頃からお客様に寄り添うことが重要だと改めて感じました。
O様
相続税において重要なのはお客様への提案を行うことである。現代の税理士は、単に言われたことをこなすだけでなく、お客様一人一人の状況を分析し、コンサルティングを行うことである。このことは社内で活かすべきポイントであると感じた。
相続税において提案をするものとしては生前対策がある。生前対策は月次のお客様担当になった場合でもお客様の資産・年齢次第ではご案内を提案することができるため、何も考えずに作業するのではなく今後は相続税についても勉強していく。
H様
弊社では、税理士・行政書士としての機能を持つだけでなく、不動産賃貸会社や司法書士法人等との関わりも多くもっているため、お客様に対する建物法人化の勧めを円滑に行うことができるのではないかと感じた。
A様
二次相続を考慮した遺産分割をする場合には、後継者の意向に沿った分割ができるのかどうか、二次相続対策として養子縁組が可能かどうかといった細かな点を検討し、また、二次相続までに相続財産の圧縮が可能かといった点も併せて検討することで、お客様に対してより良い相続対策をご提案することに繋がると思いました。
H様
相続税の基本的な考え方として、分割対策・納税資金対策・相続税評価引き下げ対策の3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあるため状況に合わせた判断が必要であると感じました。また、相続の業務においては、相続税の申告だけでなくその後の納税資金の確保や二次相続のことを考慮しながらお客様対応をしていかなくてはならないということを学びました。
H様
最近税務調査で相続税精算課税制度に該当する贈与が発見され追加の税金を要求されているケースを見たので、被相続人や相続人と話し合いをするとき本当に相続税精算課税制度に該当する贈与を行っていないかを確認することを心掛けていく。
T様
今までは主に相続税そのものについての研修が多く、相続税の為の土地等の評価方法や小規模宅地の特例等を利用した節税対策についての研修がほとんどでした。しかし、今回の研修は実際に相続税を現金で納めなければならないというお客様の目線に立った内容でした。このようなお客様の目線に合わせた考え方は今後いつでも必要。だと感じました。今回の研修では建物の法人化についても学びました。家族信託のように万が一推定被相続人に認知症等の恐れがあっても資産の凍結を防ぐこともでき、節税対策として有効です。お客様の財産の管理の方法について様々な方法を知り、より多くの案を提案するために、活かせると思います。同時に節税対策にはならない場合があることも知っておき注意することが必要です。
O様
11回目、大変面白かったです。10回目までの内容と補完し合って理解が深まりました。ありがとうございました。
相続マイスター講座18期 第12講座の感想


税理士の先生方でも借地権の定義があいまいな人が多いと仰っていたので、詳しい定義をしっかりと抑えていきたいと思います。また、最後の借地権関連の内容が曖昧なところがあったため、末尾についている練習問題を解いて理解を深めたいと思います。 H様
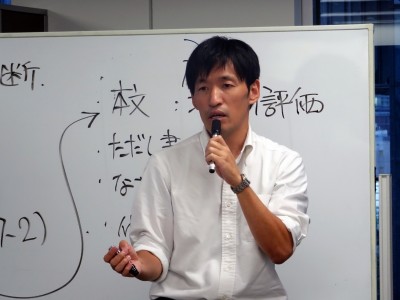
また、借地権、貸宅地、相当地代通達についても確認することができ、土地評価を行う際に、評価する土地はどこなのか、また、それに基づいた正確な評価を行うことができるためしっかりと理解し、実務で使えるようにしたい。 K様
法改正の背景の説明が大変分かりやすく、理解が深まりました。相続税の実務についている訳ではないのですが、大変勉強になりました。ありがとうございました。
K様
土地の評価をするにあたり、現在Canvasで測定して評価を行っているが、不動産鑑定とまた違った不動産の評価の仕方があるということに気づきました。今ある評価方法だけにとらわれずに、柔軟な評価の行い方をしていきたいと思います。
S様
基本は財産評価基本通達であるけど、それだけではカバー出来ないため鑑定評価書があるということ等、鑑定評価書の基礎から教わり大変参考になりました。鑑定評価書には取引事例比較法、収益還元法、開発法の3つの評価方法があり、それぞれどの場面で使用するべきなのか等説明が出来るようになりたいと思います。
K様
相続の試算や申告を行う際に、土地の売却や物件の売却があると思うので、様々な鑑定方法を知れたので、有料試算の成約につながる話題になると思いました。
また、借地権、貸宅地については、実際まだしっかり分かりきっていなかったので、今回の講義で理解が深まったので、シミュレーションの作成等を円滑にこなして行くための勉強になりました。
I様
土地の個別性を評価しているのか地域性を評価しているのか分けて提示することが必要だと学びました。評価する際に何を参考にしているのか自身が明確に把握することでお客様にも丁寧な説明ができるようになると感じました。
鑑定評価書や土地評価自体に用いられる用語は難解なものが多いため、お客様に説明する際に簡素化できるよう、用いられる用語の意味を正しく理解し、簡単な言葉に置き換えて説明できるように努めます。
O様
規模が大きい土地の評価については所有している土地の条件によって変わってくる。通達評価を適用するか、鑑定評価を適用するかは税理士の判断に委ねられる。土地の面積、地区区分、基準容積率、路線価といった情報をもとに判断する必要がある。お客様の所有している土地に対し適切な判断を行うことが重要である。
W様
不動産の評価方法についての知識が無かったため、鑑定評価書の構成や借地権価格などの基礎的なことについて理解することが出来ました。鑑定評価には3つの方法がありますが、土地の大きさなどお客様によって方法を変えるとのことだったので、3つの方法のそれぞれの特徴を理解し、違いを分かりやすく説明できるようにすることが重要だと感じました。また、借地権は借り得分を資本還元したものであり、図に書いて考えた方が分かりやすいため、お客様にも簡潔にお伝えできるよう、今回講義の中で用いた図を活用したいと思います。地代の価格によって、財産評価基本通達と相当の地代通達を使い分けるとのことでしたが、その知識を深めると共に、お客様に寄り添った形で相談に応じることが出来るよう、学びたいと感じました。
T様
土地評価に際して、一般的には取引事例比較法が適用されるが、収益還元法や開発法も用いられることがある。それぞれの手法を頭に入れ、土地に応じて違いを分かりやすく説明できるようにする。また、借地権の定義についても今回改めて学習することができたので、混同しがちな点を有耶無耶にせず理解を深めていきたい。
T様
不動産鑑定についてはほとんど知らなかったので非常に勉強になりました。今後、特に相続税を担当する際は不動産の評価については知っていなければならなりません。実際にどのような評価手法から鑑定評価額が計算されているのかお客様に説明できるように活かしたいです。借地権についても正しく説明できるものではなかったので、勉強になりました。このようなことについて正しくわかりやすく説明することは、お客様の信頼を得る上で重要と思われます。今後お客様を対応する際に活かしたいです。また、今回の研修では借地権や借地権価格等がどのような仕組みで発生し計算されているのかについても詳しい解説をしていただきました。今後、評価額等の先輩からの指示にはこのような理屈があることを理解し、さらに自分のものにするために活かせると思います。
相続マイスター講座16期 第1講座の感想

特例の制度は、2022年直前にかけてみて適用しようとするお客様が増える可能性も考えられるので、そこまで学習した内容を忘れないようにしっかりと復習していきたいと思います。
また、納税猶予適用の可否の判断で、植木畑は「ひざより下」たけのこ畑や竹林などは傘をさせる程度、等の線引きは非常に分かりやすかったため、この説明をする場面がある場合は積極的に活用していきたいと思います。 K様

今回の講座を受講し、次の2つのことを学びました。
1つ目は、税制をしっかりと学ぶことで、莫大な金額の税金を節税できるということです。例えば事業承継税制には特例措置があるため、期限までに特例承継計画を提出するのとしないのとでは税金が大きく変わると知りました。
2つ目は、担当するそれぞれのお客様の状況に応じて、お客様にとって一番メリットが生まれるにはどうすれば良いかを第一に考えることを、仕事をする上で忘れてはいけないということです。例えば、事業用小規模宅地等の特例との選択適用では、お客様が事業を継続したいのかしたくないのか等でどちらにすべきかが変わると知りました。 Y様

2022年には生産緑地の指定から30年が経過し解除という選択が可能となり、転換期を迎えます。今後の有効な土地所有、活用について考えるに際し「あと3年弱もある」と捉えるのではなく、各制度のメリット・デメリットの洗い出し等、早め早めの準備をして多様な観点から検討していく必要があります。
基礎知識の不足のために難しく感じた部分もありましたが、たとえを用いて噛み砕いて説明してくださったので理解を深めることができました。また、私自身9月にFP3級を受験し、それに向けて勉強したことで知っていた制度や語句などもあり、これも理解の助けとなりました。
FP3級は入門的な位置づけではありますが、スムーズに業務を行っていくために金融や資産の基礎知識を学ぶことでは意味のあることだと思いました。 M様
入社前に、貴重な慣習の機会を頂き、ありがとうございます。本日の内容は、所得税、資産税、生産緑地についてでした。特に、後半の部で説明頂いた生産緑地については、ランドマーク税理士法人の主な顧客である地主層の方に関係のある話だと思いました。なんとなく、農地は簡単に家に建てかえられないというのは知っていましたが、売却もできないということは初めて知りました。今回の研修を受けて、今後、業務をしていく中で、学ばなければいけないことが沢山あると思いました。社員になった時に、お客様へ安心感を与えられる説明ができるよう、これから勉強していきます。
S様
①税制改正の流れ
個人事業者の事業承継税制や配偶者居住権などの新たな制度の創設、既存の制度の見直し等、税制は景気と表裏一体となって改正が行われていることがわかりました。今後、経済政策などにも着目するとともに、税制の細かい内容も勉強していきたいと思います。
K様
税制改正の流れについて理解が深まりました。特に事業承継の特定事業用宅地と特定住居用宅地の2つを併用できることが印象的でした。また、後半の生産緑地2022年問題はタイムリーな問題であり、顧客の方に説明できるよう復習しようと考えました。
M様
今回の講義は、私自身の前提知識、基礎知識不足のため、講義自体は難しく感じました。平成31年度の税制改正や消費税改正による請求書等保存方法など様々なことが変更になる際、変更(改正)される点を知識として身につけなければならないと感じました。加えて、事業承継税制と事業用小規模宅地の有利選択など税金を支払う際の制度の抜け道を利用し、いかに少ない額で支払うことができるかを考えて提案できるよう自分自身勉強し、知識を身につけていきたいと考えています。これから東京オリンピックや生産緑地の2022年問題等大きく動くことがあるので、それらの事象、その先に備え精進していきたいと思います。 本日は貴重なお時間ありがとうございました。
N様
相続税中心のお話で、日々無料面談の同席や、受電をしている時にお客様の話を理解すること、こちらからの提案としての知識を蓄えることができました。セミナー資料だけでなく、税金ガイドにも連携して講演をしていただいたことで、復習の際に関連する項目をまとめて勉強することができると感じました。相続税の話となると必ずでてくる小規模宅地の特例ですが、新しくいただいた資料を読むたびに知らなかった知識、理解が届かなかった点が出てくるので、しっかりと自分の知識にできるようにしていきます。
私自身税に関する知識がなかったため、税制改正前と後の違いという視点から学ぶことができ、税に対して難しいと感じていた部分がなくなりました。その時々の様々な状況に合わせて対応しなければならないため、より細かく法律で定められていることもわかりました。働くにあたり、お客様によって状況が異なることで提案する内容も異なる点が難しいのだと感じ、自分自身が細かく理解することが必須であると改めて感じました。また、事前に準備しておくことが良いものもあることから、今後、お客様に提案するような際には先のことまで考え見通しておく点が重要で、常に意識するべきことであると思いました。
T様
税法改正で制度が変わることでお客様にご案内する内容も変わってくるので、日々自分でどう変わったのかチェックしていくことが大切だと感じました。どの制度もメリットやデメリットがあるためお客様のご意向をしっかり聞いて判断することが今後仕事をするうえで必要になってくると思いました。
T様
非常に濃い内容でした。知っているかどうかの世界だと実感しました。贈与がからむと消費税10%で住宅を購入したほうが、所得税が得であるというケースに驚きました。住宅取得資金援助の非課税枠は活用できると思います。個人事業者の事業承継税制ははじめて知りました(法人税は先生の本で知りました)。特定事業用宅地の特例と比較しながら判断する必要があります。消費税の改正に免税事業者を「なくす」というインボイス方式は驚きました。生産緑地指定を継続するかどうかはお客様の状況を考えて不動産の棚卸を行う必要があります。いろいろ勉強になり、本当にありがとうございました。
I様
税に関して勉強したことがほとんど無かったため、今回の講座では初めて聞くことが多くとてもためになりました。今年の10月から消費税が10%に引き上げられ軽減税率が導入されたことによりエントリ入力時には気を付けて入力していかなければならないと思いました。また、生産緑地2022年問題では、地価の下落や地主層への税の負担が増加することが予想されているようなので、今後の所有・活用のあり方について地主さんにとって何がベストであるかを考え早めの行動がこれから必要になっていくなと感じました。私の地元練馬にも生産緑地が多くあることを今回知ったので、もっと興味を持ち勉強していきたいなと思いました。
M様
税制改正について、改正の前後を比較しながら制度が作られた背景から知ることが出来たので、深く理解出来ました。2022年に生産緑地指定を解除される農家が多く、税制改正による選択肢が増えたことや、生産緑地制度のメリットデメリットなど様々な事を知ることが出来ました。生産緑地制度が複雑化した今、今後増加すると思われる相続業務に活かすことのできる知識を得ることが出来ました。相続の事業継承では、個人事業者と法人でかなり差異があるということを知ることが出来ました。複雑な制度を理解して組み合わせることで柔軟に顧客のニーズに対応し、売り上げやリピート率を増やすことにつながると思いました。講義で得た知識を今後の業務に活かしていけるよう尽力します。
K様
本日の講義を受講して、消費税改正に伴うポイントと生産緑地制度、農地の納税猶予についてのお話を聞きました。消費税改正については一番のポイントとなってくる請求書等の保存方式が変更になるということで、2023年10月1日から変更になる適格請求書等保存方式が重要になってくるということを知りました。生産緑地制度については、生産緑地が売却できるケースで生産緑地が指定されてから30年経過したときのみ売却することが可能なところ、生産緑地法の改正により買取申し出可能時期を10年先送りにできることが可能だと分かりました。そのためには、期限が来る前の早めの申告が必要なので早めにやっていただくことが重要ということを理解しました。今回の講義を受けて、相続税額をできるだけ減らすために納税猶予適用可否の判断をしっかり学び、今後に活かしていきたいと思います。
K様
入学金などはその都度費用であり非課税であるが、父が払って祖父から父に後に渡すと、課税対象になることもあるのでお客様に注意を促すことが重要だと思いました。また、特定生産緑地制度は30年の期限が切れる前に申し出なければ、損をすることになる場合もあるのでこちらも注意を促します。当たり前ではありますが、私がまだ知らないことがたくさんありました。この業界を専門にしようとしている私たちでさえ難しく奥が深い税制を、おそらく私たちより詳しくないであろうお客様の不安要素や金銭面の問題をより親身に立って対応できるように、まず自分がたくさん学んでいきたいと思います。
M様
税制改正を踏まえた様々な税金の話を講義を通して学ぶことができました。特に、小規模宅地の特例など相続でよく使う税制については、今後業務に活かせるうえ、自らの言葉で丁寧に理解できるようにしていきます。配偶者居住権についても理解はできても言葉で説明できるレベルまで向上できるように復習していかなければならないと思いました。今回の講義において学んだことは、お客様とかかわる上で必要不可欠な知識なので復習を欠かさずすることで知識を向上させていきたいです。
①住宅ローン控除及びふるさと納税等
個人の確定申告の際に改正点が適用できるか、改正前で適用されていたりしないかの確認の際のポイントにもなります。
②個人事業者の事業承継税制
所得制限が設けられた点は、細かい改正なだけに失念しないように気を付ける必要があります。
④配偶者居住権について
これからの相続にはほぼ適用がありそうな論点でした。登記手続きについて、お客様に事前に説明する項目になると思われます(アニー化も必要かと)。
⑤消費税改正
現時点で税率については適用されていますが、月次の処理で軽減税率・標準税率の判断をしておかないと、申告時に修正が頻発しそうに感じました。ただ、ランドマークは不動産管理法人がメインなので、あまり大きな問題にはなってないと思いますが。
⑥生産緑地
清田さんが一番力入れて説明したテーマに感じました。私も相続税は勉強中なので、生産緑地を1から理解できて勉強になりました。ランドマークの主顧客層にとっては特に必要な知識ですので、今後の相続の判断については欠かせない知識でした。
相続マイスター講座16期 第2講座の感想

前回の講義内容であった生産緑地においても、2022年に向けての準備が必要であるとありました。税に関わる業務にあたるに際して期限の把握やスケジュール管理、ミスのない正確な準備が非常に重要であり、ここに欠陥があった場合にはお客様の納税額や還付金額が大きく変わってしまうのだと知りました。
これまで消費税について学んだことがなかったため、理解が難しかった点が多くありました。
今後は、来年度の法改正等にも注目しながら勉強していきたいと思います。 M様

消費税自体が煩雑かつ頻繁に改正が入ることで税理士の理解が追いつかないことや、過去に消費税の不正還付事件が起こったことから、合法にも関わらず、還付申告を手掛けない税理士が多くなったと知り、今後仕事をする上で常に意識すべきではありますが、特に消費税に関しては正確に慎重に行動するよう心がけようと思いました。
また、税理士でさえ理解するのが難しいと感じるのであればお客様がお困りになるのは当然です。我々は税金のプロとしてお客様のお役に立つことが第一であるため、消費税還付に関する理解を深め、普段以上に慎重に対応することで、お客様から信頼していただくことが大切だと感じました。 Y様

消費税還付について、数多の法改正による煩雑な仕組みになっていることを知ることが出来ました。仕事では、合法的な節税対策をアドバイスするために必要な知識を得ることが出来たので、その点を活かすことが出来ると思います。
また、消費税還付をめぐるトラブルが多く発生しているということを知り、消費税還付に関する専門的な知識を持ったうえで顧客対応に当たることが大切だと知りました。不動産を所有する際、法人か個人かで消費税還付に差異が出ることについて、メリットデメリットなどを知ることが出来ました。
講義で得た知識を今後の業務に活かしていけるよう尽力します。M様
消費税は、消費者の目線からすれば最も身近な税だと思っていましたが、実務上はとても複雑であり、注意深く取り組む必要があるものだと感じました。還付額の計算方法は、仮受消費税-仮払消費税×課税売上/課税売上+非課税売上(課税割合%)であるため、これを1(100%)になるよう調整して還付を受け、その後は没収されないよう以後3年間の課税割合も50%を超えるように調整するなど、効果的に還付を受けることは非常に難しいのだなと感じました。当事務所の顧問先には不動産賃貸業をやられているお客様が多い(=売上のほとんどが非課税)ので還付を受けるのは難しいかもわかりませんが、利用することが出来ればお客様にとって大きな利益となるので、しっかり覚えておきたいと思いました。
T様
まず初めに、田中先生がこの「相続」大学校で、消費税還付についてご講演下さる意味をご説明頂きました。消費税還付から顧客となって頂くことで、相続税までの長い付き合いができるということでした。消費税還付がこれからの業務にどうプラスになるのかがよくわかりました。後半のお話は、私自身の知識が乏しいため分からない点が多かったのですが、ドラマなど意外な税理士の業務と関係なさそうに見える事からも勉強できるということを教わり、とても為になりました。 どうもありがとうございました。
K様
消費税還付を目的とした顧客の獲得は、私は現在、月次関与先を中心としたお客様を担当しているため、難しい部分もあるように感じましたが、消費税還付スキームにおける届出のタイミングの重要性やとにかくスピードが求められる業務姿勢という点を今後の業務に活かしていきます。田中先生は、業務の特殊性もあり、税制改正に常に注目しているとおっしゃっていましたが、相続税、消費税共に毎年重要な改正が行われているため、私も税制改正へのアンテナを常に張っておくことが重要だと学びました。
S様
消費税還付に関して馴染みがなく、最初はなかなかピンと来ない内容が多く、難しいと感じました。ただ、具体的な例をケースバイケースでどうしたらいいか、細かく教えてくださったおかげで後半はかなり分かりやすくなりました。税理士は一期終われば良しというわけではなく、税法の動きを常に読み、お客様のために何期も先読みして対応していく必要があると学び、不動産や銀行などの他業種についてもよく知ることや金利、経済の流れや交渉についても精通していくことがとても重要になってくると感じました。特に地主が顧客に多い弊社は家賃収入を上回る課税売上を作るためにノウハウを欲するのではないかと考えたので、個人的に消費税還付のコンサルができればさらに満足していただける結果につながると思いました。
A様
本講義では消費税還付についてでした。消費税還付はランドマーク税理士法人が特化している相続税とは分野が異なります。しかし、消費税還付の課税売上割合は家賃収入・駐車場収入・自販機収入と密接に関係しています。 ランドマーク税理士法人のお客様は家賃収入・駐車場収入が多いとエントリ入力からは感じ取れます。 そこで、お客様とのひとつのコミュニケーションの内容として消費税還付の話を交えた場合、多少ではありますがお客様からの信頼も増すのではないかと考えました。また、本講義では田中会計事務所の方針に関しても触れられました。田中会計事務所は消費税還付に特化している事務所ですが、田中先生は「すべてが出来るオールラウンダーよりは、何か一つに特化した方が通用する」とおっしゃっていました。この話から、特化したものがある事務所の方が収益力は高いことが実感できました。ランドマーク税理士法人も相続税に特化した事務所です。この特化を維持・発展していくには、我々職員がスペシャリストを目指さなければなりません。そのための大学校、研修であると私は考えているため怠らずに受けていきたいと思います。
S様
私にとっては初めて耳にする「消費税還付」でしたが、今後事務所の新たな強みにできる可能性が大いにあると感じました。ランドマークのお客様には建物を持ったお客様が多くいらっしゃいます。12月の税制改革に阻止されなければの話にはなりますが、そういったお客様が今後新たに建物を購入する際に還付を提案することができるようになれば、お客様側はその資金で新たな投資が可能になり、ランドマークには手数料としてのかなり大きな収益が見込めると考えます。もちろん、コストやリスクもある程度あるため、リターンが見込めるかをしっかり検証し、もし実務に携わる場合の選択肢の一つにできたらと思います。
N様
今まで、消費税還付についての勉強をしていなかったので、講義内容が難しく感じました。税理士のなかでも特別間違いが多く、賠償金額が多くあることが印象に残りました。消費税還付の具体例として、自動販売機を設置した不動産業を営んでいる例を挙げてくださいましたが、実際に取り組んだ案件を、数字を交えて教えて頂きたいと思いました。私のように初めて消費税還付について聞く身としては、話に取り残されることもありましたので、ちょっとした問題提示をして自分で考える時間をくださると復習をする際にも大変役立つと思いました。
A様
下記2点を実践するために基礎的な知識のみならず、周辺知識の獲得とそれらを有効に活かすためにレベルアップの必要性を感じました。
① 実務家として専門性(非対象性)を持つことは、利益率(田中先生は20%)の高い仕事をすることができ、本人のみならず事務所全体のモチベーションアップに直結します。
② 私自身、消費税法の科目合格者ですが、受験勉強で得た知識レベルでも発想と準備しだいでいくらでも節税のコンサルティングをお客様に提供でき、税制改正に対応し続けることで紹介先の不動産業者との信頼関係を更に構築します。
O様
不動産投資の消費税還付を受け取るにはどうしたら良いか、そのノウハウ、歴史について学びました。当社は不動産を所有しているお客様が相談に来ることは珍しくありません。不動産を所有しようとしているお客様もいます。そのお客様に消費税還付の提案、不動産の所有が相続税対策になるという提案、そこから法人化の提案などお客様が喜ばれる提案ができ、当社にとっても利益に繋がる事になると思います。
K様
消費税に還付ができることを今回はじめて知りました。田中先生がおっしゃっていたように『税理士のキャリアが長い方でも還付をするのは怖い』と聞き、かなり驚きました。税理士の立場としてお客様から責められる可能性がある中で、このような難しい消費税の還付を長年続けていたのはすごいと思いました。ランドマークも不動産経営をされているお客様が多いのでこういった消費税還付の制度があることをお伝えできれば頼りにされるのではないかと思いました。
H様
(1)消費税の基本
売上げに掛かる「仮受消費税」から仕入れ・経費に掛かる「仮払消費税」を控除した金額が「消費税」として納付される。
(2)還付(不動産中心に)
マンションアパートの建築費に掛かる消費税は多額なため、支払った期の消費税は還付になる場合が多い。
①前提
・課税事業者であること(事前に「課税事業者選択届出書」の提出が必要)
・通算課税売上割合が課税売上割合の50%超であること
②コンサルタント
・還付処理しても3年後に「没収」されるケースが税理士の知識不足で多く見受けられる。
・お客様に提案する際に、事前に説明して指導して関わっていくとともに、あらかじめ対応策を用意しておく(田中先生は節税用の会社を複数作っている)。
③税制改正への目配り
・国の税制改正の狙いは何か、それによってコンサルがどう変わっていくか。
・「金地金」による課税売上の増加スキームを例に説明。(通算課税売上割合を50%超にする方法)
(3)感想
今回先生が講義された消費税の話は、消費税法を合格しているため知っておりました。しかし、「知っていること」と「使えること」にこれほど如実に差があるということは思ったこともありませんでした。
今後、情報を網羅していきながらそれが仕事とどう結びつくのかを考えていく必要があると思った講義でした。
T様
非常に面白い講義でした。新しい会社の一期二期目資産投資が多い場合、課税事業主を選択した方が良いという考えがありましたが、消費税の還付をねらって不動産投資の一部として考えることはすごいと思っております。課税売上の通算の出し方や還付額の「没収」なども知ることができて勉強になりました。また、お客様の決算をやること、金利を見て提案につなげることを今後注意してやっていきたいと思います。
S様
消費税法は改正が多く煩雑であるため、内容を深く理解していない税理士が対応すると訴えられる場合があります。消費税還付を受けるにはミスなく段階を経る必要があり、不動産取得前の期間における準備が特に重要となります。また、還付金が振り込まれたからといって終わりではなく、調整計算の規定の適用を受けてしまうと還付金が没収されてしまいます。今回のお話を通して、税理士には丁寧さや緻密さのほか、何をいつまでにすべきなのかをお客様にわかりやすく、そして漏れなく伝えることが大切なのだと学びました。
K様
今回の講義では消費税は還付されることを学びました。一見、相続とは関係ありませんが、消費税還付をきっかけにして相続の話につなげるとのことでした。注意は必要ですが、いつかは担当の顧客の方に提案できるようにしたいです。また、消費税は税理士が間違えやすい税金であることを知り、税制改正を意識しつつ、特に勉強しようと考えました。
K様
本日は、消費税還付についての講座を受けました。消費税の還付については、様々なスキームがありましたが、税制改正により、使えなくなったスキームが増えたそうです。その中でも、消費税還付を売りとして税理士事務所を続けていることはすごいことだと思いました。1つを特化として専門分野を極めることで、お客様を得ることができると知り、私自身何かに特化した知識を得ることが重要だと感じました。
K様
今回の講義では、消費税についての基礎的なことから分かりやすくお話をしていただいて、消費税還付についての流れを具体的にイメージすることができました。消費税還付を受けるためには4段階の流れがあり、そのどれか一つでも期間を間違えてしまったり、計算を間違えてしまうと還付金を没収されてしまうので細かいところにも注意して行わなければならないということが分かりました。また、消費税の分野は改正がよく入ることから、内容を深く理解していないことから損害賠償を請求される件数が一番多い税金であるため、業務で行うときには、注意深く行うことが重要だと思いました。
T様
内容が複雑で改正によって大幅に変わることもあるので、今後も改正の際はこれまでとどう変わり、今までは使えた制度も使えなくなるとしたら、どう対応したら良いか考える必要があると感じました。わずかな計算の違いで還付額が全然違うので、細心の注意を払って対応していきたいと思います。
M様
今回の田中先生の講義は私自身の知識不足の為、大変難しく感じました。毎年改正が行われる消費税は税理士にとっても難しい部類であり、脱法行為にもなりやすいとのことでしたので、今後扱う際には慎重に扱いたいと思います。また、今年も増税されましたが、増税されることで受けられる消費税還付額が大きくなるため、今後働くうえで、お客様にとって消費税還付を受けると受けられないでは大きな差異が生まれてしまうため、よく復習し、勉強しておきたいと思います。
F様
マンション・アパートを利用して多額の消費税還付を受けるスキームについて説明を受けました。合法ということは理解できましたが、なかなかにリスキーな方法であると感じました。実際に、損害賠償請求の事例が多くあるとのことなので、無暗に手を出すことは非常に危険だと思います。お客様から説明を求められた際には、より丁寧に説明をして、メリットとリスクをしっかりと把握していただいく必要があります。 講義については、非常にわかりやすく、また話も面白いためよく理解できました。田中先生の別のセミナーがあれば是非とも参加させていただきたいと思います。
M様
消費税の還付の講義を受講して、普段生活に密着している消費税の還付を中心に貴重な話をたくさん学ぶことが出来ました。消費税の還付、調整計算など初めて聞く内容が多く、ついていくのに精一杯でしたが、月次などの担当になった際、お客様にも提案できるようにしていきます。消費税は税理士の方でもミスしやすい科目となっており、それだけ難しい科目なので相続税ももちろんですが、消費税も並行して勉強していきます。
相続マイスター講座16期 第3講座の感想


今回、相続面談における受注率を高める営業手法の講義を受講して接客がいかに大事であるかを実感できました。 士業で業務知識があるとはいえ、無料面談など新規で相談を承る際は、いかに接客対応ができるか、安心して相談できる環境(清掃、チームでの連携)作りが受注率に差がでることが分かりました。 今後業務をするうえで知識向上はもちろんですが、お客様との接し方についても他社よりも優れてこの事務所に頼みたいと思われるような接客をしていけるように、日々意識して取り組んでまいります。 M様

1点目は、相続マーケットについて正確に認識する事です。2015年の税制改正により、相続税申告の裾野が広がっている事は既知の事実でした。しかしながら、増加した層は圧倒的に中流階級の世帯であり、資産家ではないことは初めて知るに至りました。この事から分かるのは、今まで資産関連の専門家との繋がりが殆ど無い人々が対象になってしまったという事です。これにより、今後相続マーケットで伸びていくために、その様な層と専門家をどの様にして繋げるかが課題だと思われました。その上で、弊社の広告に労を惜しまない姿勢が非常に重要であると改めて認識しました。
お客様とお話する時に注意すること、伝えておきたいことを事前にしっかりおさえておくことが大事だと感じました。自分がお客様と面談することになったら、自分本位で話していくのではなく、お客様の立場になって話していきたいと思います。また、自分が面談の担当ではなくても、事務所の雰囲気の良さでも受注率を高める要因になっていると知り、常に意識しておこうと思いました。
S様
相続面談において受注率を高めるためには、相続マーケットを正確に理解することが重要です。2015年の税制改正により、客層が資産家だけではなく一般家庭にも広がりました。そのため、金融機関等からの紹介のほか、ホームページ経由での問い合わせが増加しています。しかし、紹介客とホームページから問い合わせた一見のお客様は属性が大きく異なるため、対応方法も変えなければなりません。特に、お客様が初めて事務所に来所された際の第一印象は、今後の受注につながるか否かを左右するため、笑顔や挨拶、部屋の清潔さなど、基本的なことを疎かにしないことが大切だと思いました。
K様
相続面談における受注率を高める営業手法について、講義を受けました。はじめに、相続マーケットについて説明を受け、私たちが業務を行っているこのマーケットについて客観的に知ることができました。相続税申告を自ら行う人が増えている中、税理士に依頼をしてくださるお客様は貴重であり、お客様が大金を払って依頼してくれているというありがたみを再確認することができました。また、電話対応についても最初が肝心であり、一本の電話でも受注率に関わってくると知り、普段から電話対応をしっかりと丁寧に行っていきたいと思いました。本日の内容は初回面談にとても密接な内容でした。これから同行する機会もあると思いますので、そのときに今日習ったことを意識して対応していきたいと思います。
T様
①相続マーケットを把握すること
2035年頃まで相続マーケットの拡大が見込まれます。税制改定後は中流階級の一般家庭が新しい市場となっているため、この層の開拓が重要であると感じました。また、この層はHP経由の場合が多く紹介客との受注に差があるため、接客力、提案、コーディネート力を駆使し、受注率UPを狙うことが大切であると学びました。
②受注率を高める営業方法
無料面談では90分しっかり時間をかけることが大切です。また、アイスブレイクをしてお客様との距離感を縮めることが受注率を高めることにつながることがわかりました。
自社の強みをプレゼンできるようにしておくこともお客様が依頼をする際の決め手のひとつになると感じました。
N様
無料面談申し込みの電話をとる機会がある私にとって、大変勉強になる時間でした。無料面談をしっかりと生産性のある時間とすることが重要であり、同席をする人の役目も改めて認識しました。お客様が欲しがるようなA3シートの書き方や、簡潔にまとめることができるように努力してまいります。無料面談をすることで、弊社のことをより深く知っていただき、何ができて、何ができないのかの説明をしっかりと伝えることができ、お客様の状況を理解することで受注にもつながっていくと思います。同席をさせて頂く際は、この講義の内容を思い出し、臨もうと思います。
A様
今回の講義では、税理士業はサービス業(接客業)であると改めて認識致しました。また、お客様の属性は、次の2つに大きく分類できることを学びました。①富裕層のお客様は金融機関等からの紹介で、受注率はほぼ100%である。 ②中間層のお客様はHP・無料相談からのアクセスで、受注率は対応次第で変動する。営業手法としては、①のお客様は金融機関等からの紹介であるので、失礼がない限り問題ないはずですが、②のお客様は、相続についてはゼロベースである前提で、丁寧に流れをお話しして当事務所が信頼できる相続の専門家であると認めて頂くことが受注率アップとなりますので、そのために常にお客様目線を忘れずに業務に努めて参ります。
I様
相続面談から受注率を高めるためには知識よりも接客が大切であると知り、私にも受注率を高めるお手伝いができると感じました。私は税理士志望ではない為、知識が必要になる場面では役に立つことが難しいですが、お客様が訪問された際に最初に対応するのが内勤職であると思うので、お客様にとっての第一印象を良いものに出来るように意識したいと思いました。また、面談時に使うA3シートはお客様の情報を得るとともに一問一答にならないようにする為にとても有効なシートだと感じました。
M様
今回の講義は、どの内容も今後税務をしていく上で大切なお話を伺えたと感じられました。税理士業界においては、しばしコミュニケーション能力が必要だといわれています。明るい挨拶を心がける事や、飲み物をお出しするか否かでお客様からの受注率が大きく異なる事を実際に黒田先生がおっしゃるエピソードから実感しました。私は今回のお話を伺って、より積極的にお客様に対して丁寧な心がけをしなければならないといけないと思いました。また、ヒアリングの際にも、ホームページから来られたお客様に対し、自社の強みをプレゼンし、様々な角度での質問を可能にすべきだと教わりました。私は、先輩社員についてお客様と関わり、実際に経験を積む事や、社員同士でもシミュレーションを行う事で、そのような能力を身につける事に特化した訓練が必要だと考えました。
M様
まず、相続マーケットを正確に把握することが大切であり、金融機関などから紹介された紹介客と、ホームページ経由で来た一見客に同じ対応をしてはなりません。次に、一見客は依頼をする意思が30%ほどであり、ただ質疑応答のような面談をするだけでは受注率は上がりません。面談時間は60分から90分、できれば時間いっぱいまでかけ、その間に顧客情報をしっかりヒアリングし、当事務所としてできることをどんどん提案していくことが大事だと感じました。また、受注率を上げるには、ノウハウや知識と同じくらい、事務所の感じの良い対応が大事だということも学びました。3月まではアルバイトなので私が面談する機会はないですが、お客様が来店された際に挨拶を徹底するなど、感じの良い事務所だと思ってもらえるよう尽力したいと思います。
S様
相続税の申告を必要とするお客様層、増加傾向、税理士への依頼状況等の現状がとてもよくわかりました。増加傾向にあるお客様層は、金融機関紹介ではなく、インターネットで検索してくる方が多く、その場合、税理士法人としての競合が激しく、新顧客の獲得のために工夫や配慮が必要です。自社の強みを意識し、お客様目線に立った対応で、受注につなげるようにしたいです。
M様
相続に関する業務の受注率を伸ばすためのノウハウを学ぶことができました。法改正によって相続税申告額が3000万円に引き下げられた今、一般企業に勤めている客層を取り込むためには相談の際の接客が大切だと言うことを知りました。来客して最初の「いらっしゃいませ」の一言やお茶出しなどの基本的な接客、心遣いで受注率が上がるということを知り、接客の際にためになる知識を得ることができました。実務に活かせるように尽力します。
H様
(1)相続マーケットの拡大
団塊の世代の平均余命からすると、今後15年近くはマーケットが拡大します。また、法改正により、申告対象者が拡大していますが、拡大した分は中流階級の一般家庭。拡大したマーケットがどんな層か把握して営業する必要があります。
(2)拡大マーケット層への対応
従来の顧客層は富裕層であり、銀行・農協との付き合いがある資産家なので、ここから顧客を紹介されることので、受注率はほぼ100%。それに対して、新規顧客層である中流階級は銀行等と付き合いもなく、相続が発生して初めて対応を考えます。現在だと、HPなどで検索してどうするか調べます。HPの一見客は不安でいっぱい。紹介客と同じ対応すると受注につながりません。
(3)HP客への対応
とにかく丁寧に説明して信頼を得ていくことが必要です。時間配分をしっかりと。一問一答のタダ働きにしない。お客様に質問しながら相続に必要な情報を集めていくことが大事です。また、専門家目線にならずにお客様目線で説明します。税理士法人内で当たり前なこともお客様にはわからないこいとが多いです。
(4)感想
前職がスーパーだったので、接客の説明については腑に落ちることが多かったです。今後、相続のスケジュール感を学んで無料面談等の機会があったときに自信をもって説明できるようにしたいと思います。
K様
T様
相続のマーケットとして、以前と比べ、3000万円~5000万円の層のお客様が増えてきました。お客様自身でもある程度手続きができる中、営業手法を活用して、受注率をあげていくことが重要であることをよく理解できました。紹介のお客様でも一見のお客様でも、日々の些細なことから信頼関係を築きたく考えています。相談シートというツールは非常にいいと思います。話のタネにもなりますし、お客様の情報を得ることもできます。事務所の業務の標準化にもつながります。以上のことを実現するためには業務をよく理解し、全体像を知り、会社の強みを自信をもって言えるようになる必要があります。
S様
相続面談の受注率を上げるために行うべきことや注意する点を黒田先生の経験談を交えて、具体例を出しながら話を進めてくださったので、これから自分がお客様対応をすることになった時の課題を見つけることができました。例えば、普段行っている相続シミュレーションの目的やその内容を分かりやすく説明できるかどうかということです。教えられた業務をマニュアル通りこなすことはもちろんのこと、そこからさらにステップアップするには自分の行っている業務内容を図解や言葉で相手に伝えられるかがカギとなると思いました。
相続マイスター講座16期 第4講座の感想

対象となる宅地は「特定居住用」「特定事業用」「貸付事業用」の3種類であり、それぞれ対象となる宅地の面積や軽減率は異なります。「特定居住用」なら330㎡まで80%減額、「特定事業用」は400㎡まで80%減、「貸付事業用」であれば200㎡まで50%減額されます。
利用する条件としては、「特定居住用」であれば配偶者か同居人が相続した場合や3年間以上借家していた人に限定されており、「特定事業用」と「貸付事業用」に関しては、相続開始前から事業の用に供されていることが条件となっておりますが、H31年度の改正により「相続開始前3年以内に事業用に使われ始めた土地」は特定居住用宅地等の対象外となるなど変更点もあるためしっかりと確認、理解し提案に繋げていきたいと思いました。 T様
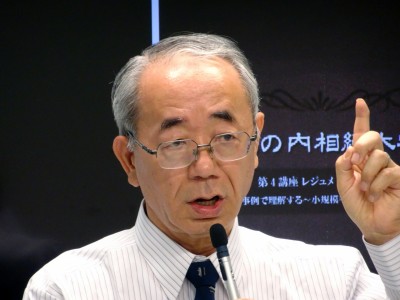
・「六親等以内の血族」については『血族』と規定していないこと
・「三親等以内の姻族」については『本人の三親等以内の’’配偶者’’』も含まれること
・配偶者の死亡後に再婚した者と、死亡した配偶者の両親の親族関係が自然消滅しないこと
この三点について認識が無かったため、本講義にて理解することができました。
実務上ではあまり遭遇するケースはないと思いますが、たとえば顧客から適用親族の範囲に関し相談を受けた際には、自身の感覚で応答することは決してせず、税法上に規定されている条文と特例を正確に理解し、回答することを心がけます。 A様

また、小規模に限った話ではありませんが、「どの場面でどの法令が使えるのか」が判断できる能力が実務においては必要であると高橋先生の話の趣旨から理解しました。しかし、これは実務経験を積んでいくことが最も近道であると思います。
そのため、今与えられている業務を速く・正確にこなすことで相続関連の業務に多く触れる機会を作っていくことが内定者の今後の課題であると言えるのかもしれないと思いました。 A様
小規模宅地特例の活用をテーマに、本来の定義規定・略称規定・別の引用方法から条文を正しく読み解くことにより、事例を正確に理解するということの重要性についてお話ししていただきました。租税特別措置法の条文を読み、言葉一つ一つをどう理解するかによって意味が変わってしまうこと、正しく読み解くことにより条文の意味をしっかり理解する重要性について学びました。相続を行う上で宅地等をしっかりと理解してうまく活用することによって、お客様により良い相続についてのアドバイスを行うことができ仕事に役立たせることができると思いました。
S様
とても大事な話をしてくださったのですが、図解での具体例が少なかったので、ケースバイケースの場合分けが少し分かりにくかったです。小規模宅地特例を理解するには、税法の「親族」にあたるか否かということ、建物と家屋の規定や違いをよく理解することが特にキーポイントだと感じました。平成26年に法律が変わったことで、高齢化、家族形態の著しく変化した現代に適応する形に整えられたことも知り、社会の変化に応じて変化していく税法の特例を今後も細かい部分まで理解し勉強していくことで、お客様のニーズに答えられる幅が広がり、事務所の強みも増えると思いました。
K様
小規模宅地特例の活用についての講義を受講いたしました。民法で規定されている語彙と、小規模宅地等の特例で使われているものとでは、意味や範囲が違うことが多々あり、実務で小規模宅地等の特例を適用する場合には注意が必要であると感じました。特に親族の範囲についてはよく確認する必要があると思いました。この小規模宅地の軽減措置は、適用されるかされないかで大きく税額が変わるものなので、お客様にとっては非常に重要なものであり、問題になることもあるのでしっかりと復習して実務に活かしていきたいと思います。
S様
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、
①被相続人に対する相続開始直前要件
②特定事業用宅地等、特定居住用宅地等など四種類の小規模宅地等に該当するか否かの直後要件
③申告期限時点継続要件
のすべての審査に通らなければなりません。条文を読むときは通達や情報のみで判断するのではなく、原則は法令で判断し、定義規定を理解することが大切なのだと学びました。今後、勉強する際には一つ一つの定義の意味を調べながら理解できるようにしていきたいと思います。
N様
小規模宅地の特例を中心とした講義でした。言葉の概念や条例に即した講義では、新たに自分の勉強不足だった点も浮き彫りになり、充実した時間になりました。小規模宅地は相続時には必ずと言っていいほどでてくることではありながら、非常に難しい内容だと感じておりますので、実務や無料面談同席時を通して勉強を進めて参ります。今回の講義で特に勉強になったのは、親族という言葉の定義です。今までは、特に気に留めずに学習していましたが、小規模宅地の特例を受けられる相続人をしっかり把握しておこうと思います。
K様
小規模宅地の特例についてでしたが、条文を読んでいても分からないことを丁寧に事例を用いて解説して頂いたので、難しい小規模宅地の特例について知識を深めることが出来ました。法律で定められている事柄が国税庁の通達や情報等などで規制が緩和されている措置が取られていたりするので条文だけが全てではないのだと思いました。税法などは時代に合わせて適宜変化していくので、私も随時確認しながら仕事を進めていきたいと思いました。
T様
事例を基にしたり設定を決めたりして説明してくださったため、小規模宅地のイメージがつかみやすかったです。特に興味深かったのは、養子と養親の血族関係に関する部分です。養子と養親の血族は親族にあたるが養親と養子の血族は親族にあたるかどうかという疑問に、どこからが親族になるのかきちんと把握していなければならないとわかりました。同時に姻族関係の部分で、書類による手続きをしているかしていないかでどちらに属するのか決まると知り、あらかじめ理解しておかなければならないことだと感じました。
M様
小規模宅地については、第一回目の清田さんの講座で触れていた為、話自体は入りやすかったですが、やはり複雑で難しいと感じました。また、親族についてはどこまでの範囲が親族を指すのか、さらに建物と家屋の違いや個人と法人の違いなど細かい部分についても複雑で理解しきれていない為よく勉強していかなければならないと思いました。実際の業務でも小規模宅地の適用は重要になってくると思うので、今回の講義で理解できていないところはよく復習しておきたいと思います。
S様
条文の解釈を、事例を通して説明されていて、とてもわかりやすかったです。普段は条文だけ読んでもなかなか理解できないことが多いのですが、一言一言丁寧に解説してくださったので、実務に応用できそうです。講義を受けたことを頭に入れて、お客様に適用漏れや適用の誤りがないようしっかり実務で運用してきたいと思います。
A様
セミナー名が「小規模宅地特例の活用」となっておりましたので、事例形式の講義だと予想しておりましたが、前半1時間が法令の成り立ちとかなり学術的で戸惑いました。税法は法律なので、判断の拠り所は条文等に明記されているかいないかで判断するものであるので、入社間もない身で実務最優先ですが税理士として当然目を通すべきものであると認識致しました。税理士受験生だった時に小規模宅地特例の理論が、国税四法の理論暗記の中で最も回りくどい言い回しで暗記時間を相当掛けたのを思い出しました。今回の講義は相続税受験生の初回に受けたかったです。
M様
相続人が被相続人と同居していたか経営を共にしていたかなどの違いにより、小規模宅地等の特例の適用が変わってくることを学びました。相続人はただ宅地を相続するだけでなく、その事実を踏まえて事業を継続するか業種を変更するかによって事前に考えておく必要があると学びました。仕事では、この知識を持っていることで、事業を行うお客様の要望に柔軟に対応することが出来るのではないかと考えました。この講義で学んだ知識を活かせるよう尽力します。
I様
小規模宅地について初めてしっかり学びましたがとても難しかったです。特に小規模宅地を受けることの出来るのは親族に限られているという説明の中で、養子と養親の血族との関係は親族であるが、養親と養子の血族との関係は親族ではないというように、どこまでを親族というのかの判断がとても難しいと感じました。実際の業務で今回学んだ事をどう活かしていけるかまだ分かりませんが、小規模宅地の適用の判断は難しいところがいくつもあると今回知ったので、もっとしっかり学んでいきたいなと思いました。
M様
小規模宅地に関しての前提知識がほとんどなかったために今回の講義を理解するのは非常に難しかったです。解説書ばかりを読むのではなく、条文を理解するというのは大学の法律の授業でも言われたことがありましたが、この講義を通して改めてその重要性を学びました。「個人」、「遺贈」、「親族」等、その言葉が示す範囲、定義は全ての法律において共通するわけではないため、該当の条文はもちろんのこと、その前の条文から確認していく必要があります。言葉の定義の捉え方で小規模宅地の特例を適用できるか否かが左右されます。お客様はこれによって納税額が大きく変わってくるため、場合によっては損害賠償につながることになります。条文に照らし合わせて、一つ一つ丁寧かつ正確なチェックが求められると思いました。
T様
小規模宅地等の特例の話だけではなく、条文を読み解く方法などの勉強もでき、非常にためになりました。いつも立法趣旨を確認してすぐ解説に頼りましたが、今後は条文から理解して最後は定義に戻り、しっかり確認するようにします。また、3月末や11月末など、官報、通達、情報などにも気を配るようにします。借用概念(民法から)の親族や、条文の中の「建物」や「家屋」などそれぞれの意味を理解したうえで、お客様にご案内するように心がけます。
M様
今回小規模宅地の特例の講義を受講して、普段の私の関与している分野に直結している内容であり、非常に勉強になりました。「親族」「三親等」など、小規模宅地の特例を適用するうえでの条件にある各事項についての認識、どこまでが対象なのかについて私自身の認識での違いがありました。今後色々なお客様の相続に携わるなかで、今回勉強したケースも想定されるので本日の講義を活かしていきます。
相続マイスター講座16期 第5講座の感想

贈与には贈与税がかかり、成年後見制度では財産を自由に動かせない、遺言では認知症対策にならないなど、資産継承の方法には種類はありますが、それぞれ問題を抱えています。


・認知症の方や高齢で資産管理が難しい方に対して活用できる。
・特定の資産を子孫代々相続させたいなど、資産承継に契約で対応できる。
②家族信託の活用
・資産の管理は名義人が行うので、認知症の方などだと保全・修繕・売却などの判断ができない。又、成年後見制度を利用した場合、後見人の弁護士などが運用を保守的・被後見人中心に考えるため、資産の積極的な活用を行わない。
・遺言だと、法定相続分や遺留分を主張する相続人が出た場合に被相続人の当初の考え通り資産の相続にならない。
・上記のような場合に、被相続人(予定)の方が生前に家族信託を活用して特定の資産を相続させたい方を「受託者(管理者)」にしておくことで、渡したい財産を渡したい人に渡せる。
・信託は「契約」なので、受益者=委託者にしておけば、生前「贈与」にも該当せず、遺留分を他の相続人に主張されることもない。
・連続型の信託にすることによって、次の次まで資産を託す人を決めることができる。
③家族信託のデメリット
・節税できるわけではないので、節税対策にはならない。
・家族信託で託した不動産に修繕などで損失が出た場合に他の不動産と損益通算できない。
④感想
これまで、資産の相続方法としては相続(遺言含む)・生前贈与・生命保険の活用は学びましたが、今回「家族信託」という方法があることを理解しました。まだそれほど活用されていないようですが、メリット・デメリットを理解しておけば、お客様への提案が1つ増えるので理解できればと思いました。 H様
K様
遺言で対応しきれない要望に応えるために連続信託などの方法があり、有効に活用することで遺産を代々受け継いでいく事等ができるということ、実務では、認知症などで意思表示ができない場合などを想定しなくてはいけない(認知症になり後見人がついてしまった場合などは後見人は被後見人の生活を保障することを最重要視するため資産の積極的な運用ということができない)という事や相続税や贈与税なども考慮したうえで信託のスキームを考えなければいけないということ、税金面では、信託契約は複数結ぶことができるが契約間での損益通算ができない点に注意しなくてはいけないということを学びました。家族信託を利用することで、被相続人とだけの関係だけではなく、相続人との関係を築くことができる点も関与先との関係を続けていくうえでメリットであると感じました。
K様
今回の講義では、家族信託について学びました。家族信託をすることで生前から家族が財産の管理をすることができるとともに、相続対策できることには驚きました。また、受託者を会社、受益者を株主と分かりやすく説明してくださったのが印象的でした。しかし、委託者と受託者は同一人物でなければならないこと、また、信託の受託者は、毎年税務署に「信託の計算書」、「信託の計算書合計」を提出しなくてはならないことに注意して、機会があれば、顧客の方に提案していきたいと考えました。
Y様
家族信託についての講義をして頂きました。初心者にもわかりやすい説明でとても参考になりました。相続の生前対策の一つの案として家族信託を取り入れられると、より質の高いサービスにつながると強く感じました。財産を売却・運用する可能性があるのであれば、積極的に取り入れられると良いと感じました。ただし、損益通算や財産変換に関するリスク・課税の可能性について、お客様に損害を与えかねないので、詳しく勉強する必要があると思います。家族信託を活用して、子の代・孫の代と長いお付き合いができると良いと思います。
Y様
認知症対策として成年後見制度を使った場合は財産が凍結してしまうため不安に思っているお客様や、自分の家系に資産を遺したいため二次相続以降の財産の引継先を考えたいお客様等に家族信託は検討するべきだと知りました。また、家族信託することを決定し、信託設計をする際には、お客様が資産組換を検討する(例えば信託財産である建物を売る等)可能性がある場合とない場合で組むべき信託スキーム図が変わってくるので、お客様の些細な要望を聞き漏らさないことが重要だと感じました。
K様
本日は、家族信託についての講座を受講しました。メリットデメリットを把握することができ、この家族信託をすることにより、相続での争いを緩和することができると思いました。相続において意思疎通の有無は非常に大切になる部分ですが、その対策としてこの家族信託が使えると知り、生前対策として実務でも活用できると思いました。また、信託に関しては、いろいろなパターンが考えられるので、様々な実例や経験が必要になってくると感じました。講義中に自分ならどのようにスキームを組むかというのを実施して、講師の模範と異なっていた部分もあったため、よく復習してメリットデメリットを把握していきたいと思います。
A様
家族信託を用いることで、たとえば認知症を患った被相続人に制限されない柔軟な資産管理ができることや、思い通りの資産承継を実現できるということを学びました。特に、被相続人や相続人の一人が制限行為能力者となった時に備える、という点に関しては、とても素晴らしい制度であると改めて感じました。しかし、実務上においてお客様へ提案するとなると、現状での理解では難易度がとても高いため、まずは基本的な家族信託のパターンをいくつか抑え、わかりやすく説明できる状態を目指したいと思います。また、家族信託を利用することで、信託財産と信託財産以外の損益通算はできないというデメリットや、そもそも家族信託が節税そのものに繋がることではなく、家族信託の先にどのような節税計画を描くかが何よりも重要であることを念頭に置き、理解を深めていきたいと思います。
M様
タイトルの通りゼロから学べる家族信託の講義でした。成年後見制度と比べると特別法である信託法についてはあまり馴染みのない内容ですが、高齢者資産の運用面で有効活用できる制度であり、税制面でも優遇される面がございましたので、当社の本業である税務面でも身につけておくべき内容でした。また、信託受益権の所得税、相続税との関連についても触れており業務に結びつく内容でした。当制度の活用面では、前述の通り税制面で優遇(信託財産の運用益は贈与にならない)され、委託者死後も受贈者の資産承継ができることから生前対策としてワンストップサービスが提供できると思われます。個人不動産賃貸や証券投資、オーナー企業などでは管理面で非常に有効に使える制度であり、遺言や贈与よりも円滑に資産承継が出来ますので、今回学んだ内容を業務生かしていきたいと思います。
M様
A様
本講座では家族信託がテーマでした。齊藤先生は講義では家族信託について最低限押さえて欲しいことをいくつかあげてくださいました。家族信託において私たちが最低限覚えておかなければならないことは「効力が及ぶのは託した財産だけ」「信託する財産は自由に決められる」「家族信託は損益通算ができない」「自益信託と他益信託の違い」でした。また、家族信託提案はお客様の資産状況を把握でき、各種の生前対策商品とつなげることができ、契約顧客を次の世代まで囲い込める可能性があることも多いと齊藤先生はおっしゃっていました。全てを覚えることは難しいですが、講義内容は必要最低限の知識としておさえておきたいと思います。
S様
高齢化社会に向けて家族信託へのニーズや有用性について、具体的な事例を挙げて講義していただき、とても分かりやすかったです。事例について自ら検討する時間をいただき、解説もとても丁寧でした。後世に財産を託す方法として、相続税対策や遺言の他に、家族信託も一つの選択としてお客様に提案していきたいです。また、提案時の注意点についてもしっかり説明していただいたので、その点も踏まえてしっかり取り組んでいきます。
A様
信託は事業承継・財産管理の一手段という認識はございましたが、今回の講義で理解を深める事が出来ました。信託を選択した際のメリットは、名義人の認知症対策として、受託者に信託財産の管理を一任でき、相続開始時の帰属権利者を指定できる点がございます。デメリットは、信託契約ごとの損益通算ができないこと、関係者・信託財産に異動があった場合に対応できない点がございます。相続や認知症は不可抗力な事由で当初の予想と違った展開も考慮して、お客様の家族構成ごとに合ったコンサルティングの提案ができる税理士を目指します。
T様
提案を実際に自分で考える時間があり、提案を考えることは初めてでしたが、イメージすることが出来ました。正解がなく提案には色々なパターンがあることがわかり、今後実際に自分がお客様に提案するときには、そのお客様に合ったものを提案できるようあらかじめ知識を入れておく必要があると改めて感じました。
F様
家族信託とはどういった制度か、また、成年後見制度等と比較した際のメリット等について学びました。信託契約により受益権化することで、遺言に比べて柔軟な財産承継を行えることに驚きました。財産の承継者を連続して指定することが出来ることが大きなメリットであると思います。具体的な事例を使った説明を多くしていたので、とてもわかりやすく、ためになる講義でした。自分でどのように信託契約を組むか考える時間も設けられており、理解が深まりました。
M様
今回、ゼロから始める家族信託を受講して、家族信託は非常にメリットがあることがよく分かりました。損益通算の禁止などの課題もある中、ご家族の資産状況を把握でき、各種の生前対策商品の提案につなげることができ次世代まで囲い込むことができます。今後の高齢化社会の中では必要不可欠な手法になると確信しました。
Y様
M様
財産管理について、遺言や生前贈与などでは難しい場合に、家族信託を利用することが有効だと学びました。資産を他の家系に流したくない場合、受益者連続型信託で資産の相続をある程度指定できることなどを理解できました。仕事では、財産の相続に悩んでいるお客様に有効なアドバイスをできることや、家族信託を一緒に考えることで、資産状況の把握が可能になり、孫の世代まで会社として有効な交友関係を築く事ができると思います。この講義で得た知識を活かせるように尽力します。
相続マイスター講座16期 第6講座の感想
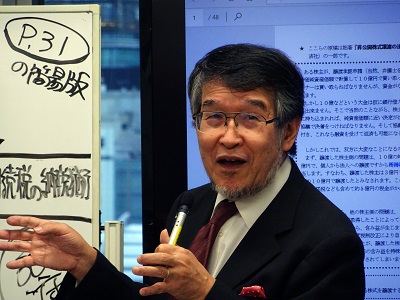
納税猶予では、申告期限を5年と3年でしっかり把握して申告忘れをしないよう注意をすること、一世代で終わらず何代にも渡るので数十年先までの影響を考慮して業務にあたることが重要になることが分かりました。 K様

この「経営計画書」の作成を戦略的に指導していくことが、今後の税理士法人、会計事務所の大きな課題の一つになっていくのだなと思いました。そのため、経常的な業務だけでなく、お客様の事業内容をよく理解したうえで、今後について一緒に考えていくような姿勢が必要なのだなと感じました。 T様

「非公開株式譲渡の時価」では、月次関与先が中小企業の場合はその知識が必要となると牧口講師はおっしゃっていました。
「納税猶予(事業承継税制)の改正点」では、相続税の申告期限もタイムテーブルに代表取締役就任期限と納税猶予申請期限が追加された事について触れられました。牧口講師はこの追加によって納税猶予を利用されるお客様は今後増加すると推測されていました。しかし、お客様が納税猶予を適用した場合には、税理士事務所の対応として報告書の作成が半永久的に必要となります。
税理士事務所は、新規顧客の獲得の努力をしなくても、継続のお客様がいるビジネスモデルが作れているため、あまり顧客を引き留めておく努力をしていませんでしたが、贈与税の納税猶予は継続届出を出さなくてはいけないので、継続して顧客を掴んでおくことができます。この制度を活用することで、顧客の引き留めをすることができます。しかし、継続届出等を怠ってしまうと、制度の適用を受けることができなくなるため、今回の研修で利用した「納税猶予取消しチェックシート」を活用して、そのようなミスがないようにします。
S様
納税猶予に関して、今までどういうものでどんな要件のもと使われるのか具体的な事案を知らなかったので、今回、牧口先生のお話で、中小企業の後継者、相続問題を解決するための大きなポイントになるだけでなく、この税法が税理士の業務や需要にも大きくかかわってくると感じました。多くの税理士は納税猶予などの新しく複雑な税法のデメリットを危惧して避けようとしますが、牧口先生のように考え方を変えてこれを新たな需要と捉え、AIクラウド化などから生き残るチャンスとして事業継承や税務コンサルを中小企業に提案していけるように、牧口先生が執筆された書籍でも勉強していきたいと思いました。
Y様
相続税・贈与税の納税猶予について講義していただきました。納税猶予について勉強不足だったため、とても参考になりました。事業承継に関して、納税資金をどうするかという話を聞いたこともあります。改正され、利用しやすい制度になったことを積極的にお客様に伝えていく責任があると感じました。先生の仰る通り、税理士と事業を継承していくお客様と将来的に長くお付き合いが出来る制度であると感じ、取り入れていけば継続的な売上に繋がると思います。5年間の毎年報告やその後3年ごとの報告業務を忘れないための対策は必ず行わなければならない課題です。専用のカレンダーシステムや手書きの管理、さらには管理をする担当者を配置するなどの工夫により、報告業務を怠ることは防げると思います。
Y様
5年間毎年報告書を提出し、以降は3年ごと長きに渡って報告書を出し続けなければならないなど、税理士事務所にとって納税猶予の改正は多くの煩雑さとリスクを生み出します。一見事務所にとってマイナスな出来事に思えますが、発想を変えれば、従来は相続税申告を一度すればその顧客が再来店するのは数十年後になることも多かったけれど、納税猶予が厳格になったことで、5年間毎年、以降は3年ごとにずっと顧客に再来店してもらえるチャンスと捉えることも出来ると知りました。このように危機をチャンスと捉えられる考え方は、事務所で働いていく上で重要になると感じました。
K様
本日は、非公開株式の納税猶予についての講義を受けました。特例措置は条件が多く税理士事務所は何十年にわたって管理をしなくてはいけなくなります。加えて、リスクも多いと知りました。ここまでを聞いた段階では、特例措置は事務所にとって使いにくいのではないかと思いましたが、発想を転換させ対策を立てることにより活用可能であると学びました。活用できれば他社との差別化につながり、優位性を持つことができると思います。今後は、このような他社にとって取り扱いづらい業務を多く取り入れていくことが重要ではないかと感じました。特に、相続に関してはお客様の反復利用は難しい分野であるため、制度的にお客様を維持することは会社の利益につながると思いました。
M様
本日の講義については、
・事業承継の際に贈与税と相続税の納税猶予が可能であり早期に後継者を決め役員にする
・決まっていない場合、会社の役員として登記をし経営者が亡くなってすぐに申請可能な体制を取っておく
ことが重要だということを学びました。加えて、税制改正により納税猶予制度が複数の贈与者・複数の後継者に対してもできるようになりましたが、複数人に承継しても経営がうまくいかなくなることが多いため相続は原則として一人に対して行うことが重要だということも学びました。本日学んだことをよく復習し理解しておきたいと思います。
S様
非公開株式や非上場会社というものはこれまでの私にとって、調べればいつでも株価が分かり、財務諸表等も公開している上場会社とは異なり関わりが薄い印象でした。今ランドマークの顧客となっている法人はほとんどがこの非公開株式を持つ会社であるため、今回の講義は今後本当に必要な知識を見極める重要なきっかけとなったと思います。納税猶予に関しては、お客様にとってはできるだけ受けたいもの、会社にとってはリスクも時間も人件費も多く取られるもので、今後会社にとっては重荷になる件だと感じました。制度がある以上、全く説明をしないというわけにもいかず、しかしなるべくリスクをお客様に理解していただくためにどのような説明をしたらいいか、よく考えていく必要があると思います。
N様
本日の講義のテーマは納税猶予でした。率直な感想としては、結局は納税するのを後に後に延期しているだけですので、より重荷になるのではないかと思いました。さらに、猶予してもらえている期間は、5年経過するまでは毎年、その後は3年ごとに報告しなければならないと手間が非常に多いです。また、猶予期間中に、その猶予が取り消される可能性もあり、何代にも渡って事業承継している場合はその相続税が一括でかかってしまうため計画性を持つことが重要だと感じました。事業承継する前から、家族を役員に置くなどして対策を行っていけば非常に便利なシステムだと思います。
A様
会社に対して個人(その役員・株主等)が定額譲渡を行った場合には、個人には所得税・贈与税が、会社には法人税が課税される事は存じておりました。所得税に関しては、譲渡対価が時価の1/2以上でも【みなし譲渡】として課税される【同族会社の計算行為の否認】に該当する場合もありえると説明が欲しかったです。事業承継税制は手続きが永続的に管理する必要があるので、メリット(需要)とデメリット(面倒で取り消しのリスク)の表裏一体の関係がありますが、そもそもランドマーク税理士法人は事業承継税制を事業として受けているかという重要な疑問が生じました。事業承継税制担当の税理士は、国税三法と会社法、経営の知識が必要で難易度が高いですが、レベルの高い先生で勉強になりました。
I様
相続の納税猶予について今回初めて学びました。納税猶予を受けるためには相続開始日から8か月以内に提出しなければいけない為、今まで以上にスピード対応が必要であると知りました。また、相続開始直前までに後継者を役員登記していなければいけないので、このような事を月次巡回監査の時にアドバイスすべきポイントであると知りました。納税猶予制度は、5年間毎年報告書を提出しそれ以降3年ごとに報告書を提出しなければいけないため管理がとても大変な制度ではありますが、一度受ければ長くお客様と関わっていけるものでもあり、そこからまた依頼に繋がっていくのではないかと思いました。
N様
講師の牧口先生の説明は税務初心者の私も理解できるようなわかりやすい説明でした。また、動画や小道具等ジョークも入れながら話してくださり大変面白く内容が頭に入ってきやすかったです。講義内容の中で、中小企業の株を時価より著しく低い価格で譲渡すると納める税金がむしろ多くなり損をするということを知り、まだまだ税金の知識が浅い私ですが、今後お客様へのご提案の際に活かしていきたいと思いました。講義後半の内容は私には難しく理解できない部分が多かったため、税金の勉強をしていく中で理解できるようしていきたいと思います。
T様
相続・譲渡の違いとそれぞれのメリット・デメリットを理解することができました。非公開株式の場合、非公開であることで意識しなければならないことや注意する点もあると知ることができました。また、決算書は外部の人に向けて作成されるというところが印象的でした。会計事務所でもコンサルすることの必要性について考えるきっかけとなり、今後働いていくにあたって常に考えていきたい課題であると感じました。
M様
今回、非公式株式譲渡の時価納税猶予(事業承継制)の改正点についての講義を受講し、今まで関与したことのない分野の話を楽しく学ぶことができました。納税猶予の期限、リスク、非公開株式譲渡の法務、税務など基本的な話を楽しく学ぶことができました。今の部門では直接は関係しないですが、月次、法人などを担当する際は知っておくと有効だと思うので、しっかり復習して知識として定着させていきます。
K様
今回は非公開株式譲渡と納税猶予についてでしたが、どちらもとても難解で税理士の方でもなかなか手の出しにくい内容と聞いて驚きました。そのような難しい論点をイラストと先生のユーモアあふれる講演で楽しく学ぶことができました。また、講演の最後の方で、決算書は必要ないとおっしゃっていましたが、私は決算書で過去の数値を読み取っていかないと未来会計や、経営計画書も作れないと思っています。税理士の方でもそれぞれ考え方は違うと思いました。
H様
①非公開株式の取り扱い
一般的に譲渡価額の算定が難しく、また、譲渡先が見つかりにくいですが譲渡自体はできます。低額譲渡にならないように注意。また、オーナー企業で少数株主の株式をそのまま放置しておくと、株主によっては意思決定の際に障害になることもあります。
②事業承継・納税猶予
純資産額が高いと相続人が相続で事業を引き継ぐ際に株式が濃い宇額になり、相続税が高額になります。これに対し「納税猶予」の制度が創設されました。平成31年度改正では、個人事業についても同様の制度が創設されました。相続時に対応しようとしても適用できない項目もあるので、生前対策が重要です。顧問先に「知らなかった」は通りません。リスクとして、適用後毎年5年間、それ以降でも3年に1回「経営計画書」を税務署及び都道府県(最初の5年間)に継続して提出する必要があり、提出忘れは納税猶予の取り消しになります。取り消し自由はそれ以外にもあるので、顧問先との情報の齟齬がないようにしておかなければ、損害賠償問題に発展するので注意が必要です。
③付加価値
損害賠償のことや今後何十年も続けることを考えるとリスクですが、逆に顧問先と継続して取引してもらえると考えればチャンスになります。提出する経営計画書にしても提出用としてだけでなく、顧問先の今後の経営計画に役に立つように作成して喜ばれようと思います。そのためには、会計事務所は過去の数字の作成作業から脱却し、経営者の経営の手助けになるようなサービスを提供し、発展していこうと思います。
④感想
講義が単調にならないよう、笑いを入れて飽きさせないようにしていたのが印象的でした。これも1つのサービスでしょうか。顧客への提案を行っていくうえで、出来上がった財務諸表を基にどんな提案をお客様にしていくかが重要だと思いました。そのためには、数字だけでなく、お客様の実態を普段の訪問時に結び付けながら仕事をしていく必要があると思いました。
T様
内容の面白さはさることながら、会計事務所の未来を見据えの提言でもありました。講義の内容として、非公開株式譲渡の時価と納税猶予(事業承継税制)の改正点の2部構成です。非公開株式の譲渡は相続、贈与と異なり、通達がないことを確認できました。原則、株主を譲渡する権利がありますが、国税の三法に則しない価格設定をする場合、牧口先生のいう「山より大きいイノシシ」のように税金がかかる可能性があります。もしお客様から譲渡絡みの相談がある場合、相談に応じられるように、純資産価額方式等を中心に勉強していきたいと思います。納税猶予(事業承継税制)について、清田さんの「社長、その税金ゼロにできる」で内容の概要を事前に知っていますが、今回の講義をきっかけに、この改正に会計・税理士事務に与える影響を改めて考えることができました。事業承継が起こりうるお客様に後継者を選定し、役員にすることに提案します。また、しっかり環境整備を整え、納税猶予を取ったお客様について、都道府県や税務署の報告書の提出を忘れないようにします。
M様
非公開株式譲渡の際は時価をきちんと評価し、その価格で譲渡しないと税金が多くかかってしまうことなどを学びました。また、納税猶予のリスクについて当てはまる法律やその対策とともに知識を得ることが出来ました。日本の多くの企業は非公開株式の企業なので、事業主の方の役に立てる知識を得られました。仕事では、日本に多くいる事業主のお客様の役に立てる知識を得られたと思います。この講義で得た知識を活かせるように尽力します。
S様
非公開株式譲渡の時価
上場株式とは異なり、取引相場がない株式については評価方法が細かく規定されています。国税三法で「時価」の意味は異なるため、違いを把握することが必要です。
・事業承継税制の改正点
平成31年度税制改正により、個人事業主にも納税猶予の特例が創設されました。納税猶予制度を利用するためには、8ヶ月以内に申請を行うとともに、その後5年間は毎年報告書の提出、それ以降は3年ごとに提出と、累積的に管理数は増えることとなります。これを煩雑だと考えるのではなく、永久顧客になってもらえるチャンスと捉えて、管理を怠らずに事務所の売上に繋げることが大切だと思いました。
T様
一見納税者にとってプラスになる新しい制度が作られたと思っても、仕組みをきちんと見てみるとややこしい部分があり、気をつけないといけないと思いました。また、これからも色々な制度が出来、時には事務所のリスクが増えることもあるかもしれませんが、そこで手を引くのではなく、きちんとした処理や管理をすることで、こなせる仕事であると思いました。これから自分のできる仕事の範囲を広げて自分の付加価値をつけていきたいと思います。
相続マイスター講座16期 第8講座の感想



遺言は相続を円満に完了する上で非常に大切な要素です。遺言は、「誰に、何を、どれくらい渡す」ことを明記するのが最大の要点ですが、好き勝手に書いてしまうとその効果を失いやすいため、遺留分を侵害しない範囲で作成するのが好ましい、ということが分かりました。他にも、作成日時を明記することや、押印、自筆証書の場合は自筆で作成する等、有効な遺言を作成するには必要な要件が多くある点にも注意が必要です。自筆証書遺言は自分で作成出来るメリットがありますが、それが有効なものなのかどうかは相続発生後に家庭裁判所の検認を受けるまで分からない、というデメリットもあります。そのため、弁護士への相談や、公正証書遺言の活用が勧められています。
T様
お客様にアドバイスをする際に、あらゆる手段を自分が考えておかなければいけないと感じました。今回の事例で、相続を開始してみると相続人が戸籍上増えていたり、遺言に思ってもみなかったことが書き残されていることが実際に起こっていることを知りました。それゆえ前もっていろいろな事態を想像して、被相続人が望むようなかたちで相続できるように万全な対策をしていきたいと思います。
S様
「争続」は、相続人と被相続人お互いの想いの違いによって起きるため、遺言や養子縁組を活用して争続を防ぐ必要があります。遺言には公正証書と自筆証書がありますが、重要なことは、効力のある遺言を作成することです。また、養子縁組を活用する際には、お客様それぞれの状況を把握した上でアドバイスする必要があります。さらに、相続税法の改正に伴い新たな規定や変更点などもあるため、常に新しい情報をお客様に伝えられるように勉強していかなければならないと思いました。
M様
相続争いの様々なパターンを元に遺言の効力の有無や、財産を残すために出来る限り有効な方法、養子縁組の人の選び方などを学びました。自筆証書遺言の危険さや公正証書遺言の大切さ、遺言の失敗パターンなど詳しく学ぶことが出来ました。仕事では、今回学んだ多くのパターンが事業主など遺産の額が大きく揉めやすかったので、そのような事態にお困りの方に知識として提供することで役立たせることが出来るのではないかと思います。相続対策は早めにしっかりとすることや養子縁組を安易に組まないことが大切だと知ることが出来てよかったです。
T様
遺言と養子縁組の活用による争族予防を学びました。相続発生から相続税の申告までわずか10か月。その間に、相続財産の洗い出しから法定相続人の確定、放棄の是非、遺産分割協議、各種特例が適用かなど、全ての確認を終えなければならず、「時間がない」という理由で不本意な相続になることもあり得ます。相続争いは、誤解や疑心暗鬼が大きな要因になっているケースが多いようです。生前の話し合いで無駄な争いを避ける場合もあります。生前対策の重要性を再確認しました。
T様
「弁護士が語る「争族」解決のツボ」を題し、小嶋先生は事例を中心にドラマチックに、非常に分かりやすく講義をしていただきました。一般的な税理士事務所等と異なる立場の士業のお話が聞けて、相続の認識を改めることができました。農協組合員を主な顧客とする小嶋先生が言うには、クライアントが農家の方が多く、長男・家承継の思想があるため、通常の法定遺留分ではなく、なるべく遺産を集中させるスキームで仕事を進むことが多い様です。「遺言」「生前贈与」「養子縁組」の三つは、スキームのキーとなります。特に印象に残っていて、今後の業務にも活かせると思ったのが次の二つです。まず遺言について、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。「自筆証書遺言」の場合、決まったフォームがある上、紛失等の可能性があります(2020年7月10日以降に保管制度が整えます)。一方で、「公正証書遺言」では、検査の方法等をはじめて知ることができました。また、養子縁組について、単に相続税を減らす(1人分)ためではなく、「争族」のグループの自分側の勢力(取り分)を増やす目的もあります。前述の遺言も養子縁組も生前でしっかり対策できれば、トラブル軽減に繋がります。
H様
①家中心の相続
一般的な相続は相続人で平等に分けようという考え方だが、土地の多い地主の場合は、これをやると先祖代々の財産が細切れになるので、長男(地主の相続人)に土地を集める相続をする。JAの弁護士として長男中心に相続の手伝いを行いますが、「遺言」「養子」の扱いは慎重に行うべき。
②遺言
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。自筆証書遺言は自分ですべて記入する。自由度は高いが、素人のため不備が多く無効になるケースもある。※本日の事例でも、訂正の不備、紛失、意思能力が疑わしい時点での作成で争いになっている。公正証書遺言は公証人2名の立ち合いで作成。作成後に公証役場で保管しているため、信頼性が高く保管してもらえる。また、全国の公証役場でデータ共有されているので、作成・保管した公証役場以外からでも検索が可能。
③養子
法定相続人を増やすことにより相続税を下げる効果があるが、「争族」においては自分の陣営の味方を増やそうとしてその養子縁組自体に争いがおこる。事例でも見てきたように、結局は人間性が問われるので、養子は本人と元の親の背景も含めて慎重に検討する必要がある。
④感想
具体的な事例を交えて興味深く聞けました。今後相続に対応するにあたり、民法の知識やその家族の背景も考えながら仕事に当たる必要があると思いました。
K様
今回は農協の弁護士の立場になって考えてみて、税理士とは違った視点で相続について考えることができました。ランドマークも農家出身者の目線で、とよく聞きますが地主の家庭だと通常の相続と異なった問題点があり、こういった案件をよく扱う小嶋先生の具体例を用いながらの説明は大変興味深く、理解が深まりました。養子縁組の取り扱いから、遺言書の説明までご丁寧に説明してくださりました。お客様に生前対策をすることをお勧めすることは本当に大切だと再認識しました。
F様
遺言や養子縁組について、先生が立ち会った相続の実例をもとに解説してくださいました。
・寄与分はなかなか認められないので、遺言や縁組をしておくべき。
・遺言の方式、書き方についても注意が必要。
遺言を作成しても不備のあるものを作成してしまう例がよくあります。自筆証書遺言よりも公正証書遺言にしたほうが良いのはもちろんのこと、公正証書遺言においても、受贈者が先に亡くなってしまい、無効な遺言になってしまうことなどもあるので、細心の注意が必要です。講義がとても面白く、ためになりました。現在、自分の担当で、相続人間でもめている案件が一件あるので、今日学んだ知識が役立つかもしれないと思いました。
N様
今回の講座は弁護士の観点から相続における争いが起きたときのケースを12パターン紹介してくださり、その時々にどう解決するか、またどのようにすれば弁護に立った側の有利になるかをご教授いただきました。 その中で特に遺言と養子縁組の重要性を学びました。どちらも上手に使えば財産を多くもらうことができますが、被相続人に遺言には意思能力があったこと、養子縁組には縁組能力があったことが要件になり、それがなかったと裁判所に判断されてしまうとそれらが無効になってしまうということを知りました。事前の相続対策提案の際にこれらは活かせる知識だと思いました。そして相続法の改正についても学んだため、今後活かしていきたいと思います。
A様
講師の小嶋先生がJA横浜の顧問税理士をされているため、当社の主要な御客様である地主の方々の争続問題に対して具体的な事例で講義されていたので、大変生々しいものがございました。 争続にならないためには相続発生時に対応するのでは無く、事前に予防策として①遺言、②養子縁組等の対応が求められます。その際に手続きに不備が無いか専門家のチェックを受けていないと大変なリスクがあることを学びました。弁護士・司法書士等の他士業の先生方の講義を伺っていて常々悩むのが、我々ランドマーク税理士法人の人間がどこまで御客様にコンサルティングしても良いのか?です。どこからが非弁行為等の越権行為になるのかの線引きもして頂けると有り難いです。
N様
農協専属の弁護士ということで、法定相続分で均等に分けるのではなく、いかに長男に先代から引き継いできた農地を相続させるかを論点とした講義でした。養子縁組をすることで自分のグループの取り分を多くするやり方は例としても多く出てきており、家族間での争いというのは珍しくないことのように思えました。また、生前にしておくべきこととして公正証書遺言は必ず作成しておくべきだと痛感しました。自筆証書遺言だと無くしてしまう可能性や、作成された遺言書に不備があった場合、無効とされる可能性があるからです。口約束などはなんの効力も持たないため、相続が争族にならないように、推定相続人と推定被相続人間での話し合いの場を前もって設けておく必要性が分かりました。
S様
相続対策として、養子縁組や遺言をする場合の失敗や反省についてレクチャーいただきました。「こうすればうまくいく」という必勝テクニックではなく、失敗事例から課題を掘り起こしていて、わかりやすかったです。特に、対策が遅れたことによる失敗や、後回しにして手遅れになったという失敗が多く、早めに手を打っておけば上手くいったのに、、、というケースは、今後の関与先への提案に役立ちそうです。縁組や遺言は、提案しても実行に移すまでに時間がかかることが多いようなので、提案したらすぐに実行に移せるような信頼関係を結びながら進めていきたいです。
M様
今まで、私は相続税についてこれからマーケットが増えていくという認識しかなく、相続の問題については知識が乏しい状態でした。自筆証書遺言や公正証書遺言、養子縁組といったものが形成されるタイミングで相続の問題がそれぞれ異なってくることを(例えば、被相続人の危篤の状態で遺言が急遽作成されると被相続人の遺言書作成能力が問われるなど)、小嶋先生のお話を伺って知る事が出来ました。税理士という実務家の立場から相続税の相談を受けるときは、相続の知識を深めるのはもちろんの事、小嶋先生のおっしゃった様に相続をスムーズにする為の早めの対策を行う様にお客様に促さなければならないと思いました。
M様
遺産分割はただ法定相続分に基づいて形式的に行うだけではないと言うことを知りました。地主のお客様の場合、いかに資産を分散させず、長男に集中して相続させるかが主眼となることが多いようです。その手段としては遺言や養子縁組、生前贈与などがあげられます。いずれも相続を見越した事前の準備が必要です。遺言能力とその内容の複雑さは相関関係にあります。たとえば、遺言能力が低いとみなされた場合、その内容は簡単なものでないと後に覆されることも多いようです。遺言を作成したとしても不備があっては意味をなしません。実務を行うにあたっては、被相続人の認知能力に応じて遺言事項の簡便化など、リスクヘッジの提案も重要です。
M様
法律含め相続(争族)の実際の事例を絡めての講義でした。実際の事例を用いて講義して頂いたので、流れとして掴みやすかったです。争族の場合、いかに身内を増やして相続資産をもらうかが鍵であり、養子縁組はその手段として使われることが多いということが印象に残っています。また、遺言能力と遺言は相関関係にあり、複雑な遺言を作成したのちに遺言能力が落ちたとき、争いで不利になる可能性があることも学びました。相続についての裁判事例も様々なものがあるのでこれからそういった知識もつけつつ、事例にも触れていき理解を深めていきたいと思います。
K様
争族を解決するためのポイントや注意点などを様々な事例を用いながら学習しました。争族を解決するためには、遺言が非常に重要なポイントになると知り、遺言の重要性を再確認しました。特に自筆証書遺言は紛失のリスクや無効の可能性があるなど不安要素も多いことから、公正証書遺言の方が確実であると知りました。また、相続法改正が近年多数あり、この内容についてもしっかりと知っておく必要があると感じました。遺言能力と遺言の中身の複雑さは相関関係にあると学習しました。意思疎通に問題が起きそう又は、能力が低下している場合に、難しい(複雑な)遺言を作成すると将来争いになる可能性があるということを知り、実務で役に立つ情報だと感じました。
Y様
遺産分割は画一的なものではなく、家系図や遺言の有無、養子縁組の活用などによって、何通りにもなると知りました。そのため、お客様の状況を細かく理解し、相続が「争族」にならないように尽力することが何よりも重要だと感じました。また、遺言能力と遺言の複雑さは相関関係にあると考えられるため、被相続人が遺言を作成する際にすでに意思能力が低いと判断されてしまう状態ならば、遺言は複雑でないものにしないと後に無効となる可能性があるなど、具体的な注意点を常に頭に入れておくことを心がけようと思います。
Y様
争族とならないためにすべき事について講義していただきました。これまで均等に相続する立場からしか考えていなかったことに気付かされました。別の立場に立つと、こういう考え方をするのかととても参考になりました。遺言や養子縁組をどのように行っているかを、様々な立場から検討する必要があります。依頼に来た相続人の代表の立場のみならず、全員の立場に立つことを改めて意識することが争族にならないための第一歩だと感じました。この点を意識しながら取り組みたいと思います。
S様
地主をメインにした相続での争いや遺産の相続において相続先を分散させたくない場合にとるべき行動、注意すべき法律について小嶋先生が実際に立ち会ったケースを元に説明して下さり、実務の中でもし自分が同じ状況に立った際にまず何を優先してやるべきか、親族に説明するべきかということが明確に分かりました。遺留分の請求ができる立場にあるのか否か、代襲相続や養子になっているかどうかの考慮をした上で認知症や病気になる前に時間に余裕をもって進めていくことも大切です。また、書き換え忘れもないように定期的に遺言者の様子を確認することも私たちの仕事だと思いました。
K様
推定相続人の誰かに財産を残したくないというお客様の場合において、遺留分を考えずに遺言を作るということは勉強になりました。前職では、息子に財産を残したくないというお客様に対して遺留分を考慮したアドバイスをしていたので、今後は今回の相続大学校で学んだことを生かしていきます。遺言失敗のパターンについて勉強ができたので今回のような事例に該当しないかどうかをチェックし、該当しそうな場合には早め早めのアドバイスを行っていきます。
T様
JA横浜の顧問弁護士をされている小嶋和也先生から、具体的事例を中心に、相続に関するリアルな問題を教えて頂きました。代襲相続や養子縁組、成年後見など法学科の授業で習ったことが出てきました。事務所でも、争族となるケースがあるかと思うので、まだまだ勉強ですが、今日教えていただいたことも頭に入れて仕事をしたいです。内定者である私たちにもわかりやすい説明で、とても理解が進みました。遺言実務を実際にされている弁護士の方からお話を聞くことができて、貴重な経験になりました。
相続マイスター講座16期 第9講座の感想



M&Aといっても、ただ会社と会社を一緒にするだけのことではないと思いました。今後、会社の特徴を生かせるようなかたちでM&Aが行われるように相手先を探さないといけないと思いました。事業承継では、買い手企業を探す期間が短すぎたことが原因で失敗したという例があったので、今後、自分のお客様に対してそのような可能性がある場合は、早い段階で打診していきたいと思います。また、後継者の家族関係が事業承継に大きく関わっていることが分かりました。講座で紹介されていたように、会社を分けることによってのちに事業がうまくいったという事例があったので、いろいろな対策を考えて柔軟に対応していきたいと思います。
S様
事業承継は、「家業」として同族経営者へ引き継がれていくことが一般的でしたが、他社に事業を譲渡したいと考える経営者も増加しています。また、中小企業の経営者が高齢化しているため、誰が事業を引き継ぐのかなど、早めの対策をとることが必要です。中小企業は、日本そして世界の産業を担う重要な役割をもっているため、廃業や倒産という結果にならないよう、それぞれの会社の実態を見つめ直したうえで組織再編やM&Aなど活用する必要があると思いました。
M様
事業継承について、たくさんの事例を参考にしながら学ぶことができました。一人一人のお客様の境遇や状況、要望に合わせて円満に解決するポイントなどを学びました。分割型と分社型新設分割をうまく使い分けながら事業継承問題を解決する方法について詳しく知る事が出来ました。仕事では、相続にあたり事業継承問題に悩んでいるお客様に知識として提案し、専門の方へ斡旋する事が出来るのではないかと思います。今回の講義で学んだことを仕事で活かせるようにします。
T様
事業承継事例について学びました。中小企業の経営者の高齢化により、数年後には平均年齢が70歳を超えるとされているようです。高齢の経営者は誰が会社経営を引継ぐのか「後継者」の問題と事業承継時の「納税」の問題を抱えているようです。データからは本来経営を続けていくことが可能な中小企業も後継者難等の理由で休廃業を余儀なくされているという実態があるようです。相続税納税猶予制度の活用が出来るケースも多いようです。お客様にご提案が出来るよう、知識を身につけたいと思いました。
H様
①M&Aによる株式買い取り
後継者が不在な場合などに事業を同業他社などに売却することで事業の継続・雇用の確保を図る。ただし、M&Aの候補先や資産評価など時間がかかるので後継者の不在が分かっているなら時間をかけて行わないと失敗する。
②会社分割
後継者が同族外だったり逆に後継者が複数いる場合に会社を分けることで親族や同族外後継者の生活の維持を図る。税務上のリスクがあるので、専門家と組んでリスクを見積もる必要がある。
③持株会社化
後継者が株を集約する際に、持株会社を作りここで株式を買い取る。個人で購入すると相続の際にまた株が分散する。持株会社で株式の購入資金を借りて購入することで株式の相続の際に評価を下げることもできる。※会社が株式を購入すると自己株式の買取になり、自社株の1株当たりの純資産額が高くなり、打った側もみなし配当課税で総合課税されるので、よろしくない。
④相続税の納税猶予
後継者が事業を相続することを前提として相続する株式分の相続税額の納税額を猶予する制度。特例措置の事業承継計画を2023年3/31までに提出し、2027年3/31までに株式移転する必要がある。適用期限及び提出書類などが決まっているので、適用要件に注意。
⑤感想
実際の事例を基に講義されてましたので、頭に入りやすかったです。また、やり方はいろいろあっても、実際当事者の人間関係や事業があるので、必ずしも最適な方法で実施することにならないこともわかりました。この点は相続案件についても同じだと思いました。
K様
今回は事業承継についての講座で、私は事業承継のことはこの大学校でしか学んでいないので無知の状態でした。横川先生のクライアントで実際に起こった事例を基に説明してくださったので、最近の事業承継税制のことからお客様がどんなことを望み、考えているのかを知ることができました。株式の譲渡が一番のネックになることや、上場会社と非上場会社では株の評価の仕方が変わってくることを学ぶことができました。私もお客様に説明する際に、そうしたことをわかりやすく説明できたら理解しやすいと思いました。
M様
今回事業承継について細かい講義を受講することができとても勉強になり、今後生かしていきたいと感じました。今まで事業承継についてはイメージでしか知らない分野でしたが、横川先生の講義で成功事例、失敗事例など様々な事例を通して事業承継について分かりやすく説明頂き、まずどういうものなのかというイメージが湧きました。ランドマーク税理士法人は相続と事業承継に特化していることから、今私が担当している相続業務以外に事業承継についても並行して勉強し、自分の武器として活用できるよう日々取り組んでまいります。
F様
事例をもって事業承継の成功例と失敗例を解説
・M&A(事業承継型)の活用事例
・M&A(経営統合型)の活用事例
・会社分割型の活用事例
・新事業承継税制の活用事例
事業承継の二大問題は後継者と納税についてです。経営者の平均年齢は年々上がっており、今後更に増えるとのこと。社長が急病等で急に対応するケースが多く、あらかじめ準備を整えておくことが非常に重要です。会社を引き継ぐ兄弟同士で争いが起きるというパターンもありがちですが、そういった場合には会社分割型の活用が有効です。次世代への事業承継も見据えて事業承継を行うことも非常に重要であると思います。業務とは直結しない分野のため理解が難しかったですが、事例の説明が詳しくわかりやすかったですし、話の仕方も上手で、また受講したいと思いました。
T様
事例を使ってお話をしてくださったのでイメージもしやすく理解できました。成功事例、失敗事例と分けて考えることで、それぞれの事例で注目するべき点や改善点を明確にして考えることができました。事業承継には時間がかかることと、突然の事態に備えてあらかじめ準備をしておくことが重要であるとわかりました。何事も早めの行動と先を見据えた考えが必要であると感じました。
N様
事業承継の現状として後継者の問題と税金の問題があり、講義の中で成功例、失敗例を紹介して頂き、失敗を回避する対策方法を学びました。今回注目した点は、会社分割の活用事例にあった分割型新設分割と分社型新設分割の成功事例です。後継者がいないパターン、後継者が複数いるパターンと場合によって対策の仕方が変わり、内部統制的にも外への世間体的にもうまく収められる方法があることを学びました。まだまだ知識がない私には難しく感じた話でしたが、今後活かしていけそうな内容だと思いました。
I様
数年後には中小企業の経営者の平均年齢も70歳を超えるとされている2025年問題というものを今回初めて知りました。そして、後継者の問題・事業承継時の納税の問題の2点があり、中小企業でも今M&Aが増加傾向にあると知りました。今回は、非上場のM&Aの活用について学びました。オーナー1人のワンマン経営状態にある時にオーナーが急死してしまい後継者などの準備をしていなかった場合、会社全体がパニックになってしまい数か月で資金繰りが上手くいかなくなってしまう事、そしてM&Aをするにも短期間で行うのは困難であるので半年ほどみて行動しなければいけない事を知ったので、ワンマン経営にあるようなお客様にはなるべく後継者を早い段階で決めて実務を教えていく事を勧めるべきだと感じました。また、後継者がいない場合と後継者が複数いる場合で会社分割の活用は大きく変わり、活用次第で会社がより発展する可能性もあると知ったのでお客様に合わせて活用方法を判断する必要があると思いました。
A様
今回は、事業承継の講義の中でもM&Aが関わる組織再編税制(法人税)の要素が多く盛り込まれていました。第6講座の牧口晴一先生(税理士)の相続税要素の強い事業承継とは違い弁護士である立場でいらっしゃるので、遺産分割にまで介入しクライアントであるお客様にアプローチできるのが羨ましく感じました。当社でも相続の生前対策として事業承継の案件が今後増加していくと考えられますが、税理士法人の人間としてどこまでお客様にアプローチして良いのかの線引きをして頂けると有難いです。
N様
事業承継事例ということで、講義内容は難しく感じておりました。企業を次世代に渡すということは、株をどのように分配すればよいかという話になると思います。さらに非上場の株式となれば、計算方法が複雑になってくるので、苦手意識を感じております。講義を聞いていて特に感じたことは、誰に託すかという問題を、承継直前ではなく、話し合いの場や準備期間を余裕を持って設定しておくことが重要だと思いました。相続でも、相続財産を巡った争族が発生することが多くあります。事業承継でも同じような問題を抱えており、実際に行った成功例・失敗例を聞かせていただいたので、今後の参考にさせて頂きます。
M様
高齢化に伴い企業経営者の平均年齢も上昇している中で、事業承継のかたちにも変化が起こっています。経営状況は良好であっても、後継者難によって休廃業に追い込まれる企業が増加しています。このような状況から納税猶予等、法改正の動きがみられます。講義では、短期間でのM&Aの後に事業も土地もなくなってしまったといった失敗事例もあげられており、事業承継に限ったことではありませんが、入念な準備がいかに重要かということを学びました。事業承継自体の成功だけでなく、承継後の経営や従業員の方々のことなど、会社の未来を見据えた提案が必要であると思いました。
A様
本講座では、少子高齢化における事業承継ではM&Aや組織再編が近年主流になっていることをまず理解しました。中小企業の後継者不足は現在深刻な問題であり、2025年問題まで予測されています。私たちはお客様と関わっていく中でこういった声を聞くケースもあることを想定しておきたいと思います。また、本講座でならった事業承継の手法は、お客様の相続案件を手掛ける中で、被相続人が会社経営を行っていた場合に必要となる可能性があると感じました。ここで事業承継にも私たちが対応できれば相続案件と追加で利益が得られる可能性があるため、事業承継システム(M&A、会社分割、親子会社関係の形成、株式交換、株式移転等)は税理士試験対策も兼ねているので深く理解できるようにしておきたいと思います。
K様
事業承継について事例を用いながらの講義でした。一つ目の成功例では、買い手側と売り手側の見解が異なり折り合いがつかなさそうだった案件を適当な着地点を見極め、最終的にはお互いの企業とも合意の元でM&Aを成功させた事例です。非上場の株式譲渡の場合ほとんどが全株式を譲渡し、お互い握手をするように合意をしなければならないと学びました。それを行う上で、どこで折り合い(着地点)をつけるかを考えるのが重要であると感じました。新事業承継税制の活用事例についての成功事例についても学びました。この特例は2023年3月31日までに申請をしないといけないため、この機会を逃さずに活用していくことができれば売り上げにつながるのではないかと感じました。
Y様
事業承継には、誰が会社経営を引き継ぐのかという「後継者」の問題と、事業承継時の「納税」の問題が2つの大きな障壁であるということ、従業員と売上規模は少ないが利益は大きく本来は経営を続けていける中小企業にも関わらず、後継難などの理由で休廃業となってしまう企業が数多くあることを知りました。そのような中で、たとえ親族に後継者がいなくても同族外の者に承継することを想定し、分割型分割をおこなうことで再編をはかることができる事例を知り、多くの事例を学ぶことは様々な状況に対応する力が身につくと感じました。
Y様
事業承継の流れについて、事例を用いた講義をしていただきました。実際の事例を用いた講義だったため、とても具体的でお客様に寄り添った事業承継を心掛けていることがよく伝わってくる講義でした。先日受けた納税猶予の制度と併用して活用できると感じました。事業承継にも様々な形があるため、お客様に最適な事業承継案を提出することが望ましいです。そこで、お客様の現在置かれている状況をよくヒアリングし、また専門家に相談するなど、ある程度時間をかけてでも適切な判断をすることが大切だと感じました。どのような事項を聞き出す必要があるのかを考えていきたいと思います。
S様
事業承継については書籍で読んだことはありましたが、具体的な実際の事例を載せているものは少なく、今まで上場企業と非上場企業のM&Aの違いや実務でどう動けばよいか、どのような対処法があるのかということが分かりませんでした。しかし、具体的に横川先生はお話してくださったので、税務に携わるものとして事業承継をする際に相続人争いを避けるためにホールディングス化したり、または分業化してファミリー会社と家族外の人間に承継させる会社の2つに分けることで家族の生活を保障できるだけでなく、同族外でも昇進のチャンスがあるとモチベーション向上にもなり会社の発展につながる可能性も大きいので、教えていただいたことをコンサルティングできるように勉強をすすめていきたいと思います。
K様
事業承継税制については、一昨年改正された非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予の特例については税理士試験の勉強等で把握できていました。しかし、その他のM&Aの事例についてはあまり把握していませんでした。成功事例と失敗事例を交えた講演内容でしたので、特に失敗事例のようにならないよう注意します。今後、一般事業会社を担当した際には、お客様への提案をしていきたいです。今後活用していきます。
T様
事業承継について、実務を手がける横川先生から講義を受けました。事業承継にM&A以外に分割型、分社型があるということを初めて知りました。具体的事例と共に、買収の場合の買い手候補企業のピックアップの基準や、兄弟間親族間の経営を巡る衝突などリアルな話を聞きました。事務所では、お客様の中で事業をされている方がいると思うので、相続が発生する前の事前準備が大切だという本日のポイントを忘れずに業務に取り組みます。
相続マイスター講座16期 第10講座の感想



近年の税務訴訟の動向や傾向、審査請求の実務的活用について講義していただきました。税務調査のほとんどは修正申告で決着することに加え、納税者が納得出来ないとき争うべきか否かの判断基準の提供が必要であるため、税務訴訟の動向や概要については理解することが必須だと感じました。また、審査請求のメリット・デメリットや審査請求を利用したほうが良い場合、訴訟を利用すべき場合など詳細に説明していただきましたが、理解しきれていない部分もあるためその部分は今後理解をできるよう自主学習していきたいと思います。
S様
税務調査は、修正申告によって決着することが多いですが、修正申告は妥協的な方法であるため、納税者が納得できない場合もあります。この場合、修正申告後に更正の請求を行った上で、再調査の請求、審査請求、取消訴訟などの不服申立制度を利用することが可能です。これらの制度にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、お客様が争うべきか否かの判断基準を提供するためにも、税務訴訟についても勉強していく必要があると思いました。
M様
税務訴訟の最新の動向や救済手続き、審査請求や取消訴訟のメリット・デメリットについて詳しく学ぶことが出来ました。その中でも、最近は審査請求の件数が増えていることや、メリットがほかの手段に比べて多いことが印象的でした。最新の判例なども含めて学ぶことができたので、どのような流れで税務訴訟が起こるのかについても知る事が出来ました。仕事では、税務訴訟を防ぐことや訴訟になった際の対処に役立てることができると思います。今回の講義で学んだことを仕事で活かせるようにします。
T様
再調査の請求・審査請求・訴訟について学びました。手順につきましては、理解していない部分が多く、勉強になりました。税務調査は修正申告で決着させることが多いですが、不服がある場合、下記のような救済手続きがあります。それぞれメリット、デメリットがあり、戦略的に活用する必要があるようです。税務署長が行った処分に不服があるとき、3か月以内に税務署長に対し「再調査の請求」を行うことができ、これに替え、直接国税不服審判所長に対し「審査請求」を行うこともできます。「再調査の請求」についての処分に不服があるときは、1か月以内に国税不服審判所長に対し「審査請求」を行うことが出来ます。なお、処分に不服があるときは、6か月以内に裁判所に「訴訟」を起こすことが出来ます。
H様
①税務訴訟
税務調査にて修正申告を受け入れない場合、訴訟手続きがあります。各税務訴訟についてはそれぞれ特徴があり、特徴を踏まえたうえで訴訟を起こす必要があります。各訴訟内容については、平成25年度の税制改正にて国税通則法が改正され、処分の理由が提示されるようになり、調査件数も減り併せて訴訟件数も減っています。(税務訴訟の流れ)(再調査の請求)→審査請求→取消訴訟
②再調査の請求
再調査処分庁(税務署長等)で審査し、処分通知受領から3か月以内に申し立てが必要です。申立費用・弁護士費用も掛からず、決定も3か月程度で出ます。ただし、再調査時に証拠資料を補完収集されるためメリットはあまりありません。
③審査請求
国税不服審判所(国税庁の外局で裁判官や検察官が上部にいる)で審理し、再調査決定書受領から1か月以内に申し立てが必要です。申立費用・弁護士費用も掛からず、裁決は原則1年以内。第三者的機関のため、行政側でもある程度独立した判断がされます。不当を理由に取り消ししてくれることもあります。行政側の最終判断のため、ここで勝てば終了。保守的な先例遵守主義。違法かどうかの法律的な判断はしません。また、HPで判決が公表されるため、知られたくない場合はデメリットとなります。
④取消訴訟
取消訴訟は裁判所にて審理。裁決書受領から6か月以内に出訴が必要。上記と違って、新しい法律判断が下される可能性があります。ただし、三審制のため事件終結まで数年かかる上、弁護士費用も含めた費用が多額になります。
⑤感想
修正申告に不服な場合にどこを着地点にして訴訟を起こすかで、どこから訴訟を起こしていくかを特徴を踏まえながら行う必要があると思いました。
K様
今回は税務訴訟についての講義で、弁護士の方からの視点で講義を聞くことができました。少し内容としては難しかったですが、税務に関わる私たちがお客様と接していく中で、難しい案件も扱う事もあると思います。そうした際に気をつけなければならない事案がたくさんあることに気づかされました。審査請求の難しさやどうやったらできるのかということも丁寧に教えてくださったので知識を深めることができました。これから先何が起こるか分かりませんが、税務のことだけでなく、こういった訴訟のことも学んでいきたいと思いました。
M様
税務訴訟の最新動向と審査請求の実務の講義を受講して、税務調査についての知識などたくさんの基本的なことを学びました。税務調査という言葉自体は朝礼発表時などで聞いていましたが、私が関与しているお客様はもちろん税務調査に入ったケースはまだないため、どのようなものなのかを確認することができました。税理士法人は税務に関わる上で様々なケースが今後想定されるので、今回学んだ知識は最低限の知識として復習し理解できるようにしたいと思います。
N様
税務における争訟について学びました。私はそもそも税務訴訟というものがどんなものなのか知りませんでした。今回の講義でその重要性を認識することができました。税務調査のほとんどが修正申告で決着している現状と修正申告で決着すべきでない時もあり、その判断基準をもっておく必要があることを知り、今後業務にあたる上で頭に入れておくと役に立つことだなと思いました。また、修正申告後でも5年は更正の請求ができるということで、審査請求に関してももっと勉強すべき事項だと感じました。
I様
行審法改正に伴い異議前置が廃止されたことにより、審査請求が中心となっているのが最近の傾向だと知りました。申告漏れが多いのが順に預貯金・有価証券・土地である事を今回初めて知ったので、これらを行う時には注意するべき点だと思いました。取消訴訟は、弁護士でないと代理が出来ず、再調査・審査・訴訟という順で行うことを知りました。第1審を頑張らないと負けてしまうので、2年ほど時間をかけて行っていく為時間がとてもかかると知りました。また、出訴期間が裁決書受理から6カ月以内と時間があるため、早めに相談してもらうことが大事であると感じました。本人訴訟もたまにあり、年金の二重課税についての訴訟で勝ったことがあるというのは興味がわきました。
N様
税務訴訟について講義をしていただきました。税務調査のほとんどが修正申告で決着するというのを知りました。しかし、もちろん修正申告で決着すべきでない場合もあり、その理由として納税者の心情的な理由があります。4つほど理由をあげていただきましたが、この理由が最も多いのではないかと個人的に思いました。争うべき案件がある時は、税務訴訟の概要や動向について理解し、判断基準をもつことが大事だと学びました。一旦修正申告をした後でも、5年経過前であれば更正の請求も可能なので、争うべき案件がある時はしっかりと計画性を持つべきだと思いました。
S様
税務訴訟について、近年の傾向や実務上の手続きについて講義いただきました。税務調査で指摘を受けた場合は、修正申告で済ませてしまえば解決が早いのかもしれませんが、大きく税額が変わる時や指摘に納得できない場合は、税務訴訟に強い弁護士に相談して審査請求や訴訟を検討する方法もあると知りました。実務では、期間や費用を見極めながら、また、お客様の意向も十分にヒアリングしたうえで、実績のある専門家と進めていかなければならないと感じました。
K様
税務訴訟の最新動向と審査請求の実務についての講義でした。再調査・審査請求の処理は、再調査が3ヶ月以内に99.6%、審査請求が1年以内に99.5%と短期間で処理が終わると知り、このような統計で実態を知ることはとても勉強になりました。また、最近の傾向として異議前置の廃止によって審査請求が中心になったと知りました。上記のことや審査請求のメリット、再調査の請求のデメリットを聞いて、再調査の請求は必要なのかどうか疑問に思いました。審査請求の判決は事例を元に判断することが多く、保守的であると知り、判決をたくさん知っており、ストックされていることが重要であると感じました。また、最新の事例を把握しておくことも重要であると感じました。
Y様
税務訴訟についての講義をしていただきました。弁護士の視点から、再調査や審査請求、そして税務訴訟がどのように行われているかを知ることができてとても参考になりました。いつどのような事案で訴訟になるか分からないので、訴訟に対する知識をつけておくことも必要です。まずは税務調査がどのような点を問題としているか(事実認定か、法令解釈か)を把握することが大切です。再調査や審査請求のみで解決できることは、そこで解決するように導き、訴訟にならざるを得ないものはなるべく早く弁護士を紹介することが私達ができる最善のことだと感じました。
S様
業務上、国税局との衝突は避けられないことがあるので、今回の講義はとても為になりました。というのも、追加徴税に対して納税者側が異議を唱える時にどういう経路を経ることができるのか知らなかったので、それぞれの方法のメリット・デメリットや、問題に応じた提訴の向き・不向きについて教えていただき勉強になりました。単なる国税側の錯誤であれば、裁判にするよりも調査を進めていく方が長期戦にならずスムーズに納税者の要望に応えることができるが、判例のない新しい事案に関しては、裁判を起こすことで認められるケースもあるので、可能性を踏まえて弁護士の先生と連携して判断していきたいと思いました。
K様
T様
税務訴訟についての講義を受けました。前半の講座では、審査請求の最近の動向について、2度の改正を経て増加傾向にあるということを教えて頂きました。後半は、審査請求の実務について、実務上、根拠資料の保管の必要性から再調査の請求が利用されないこと、審査請求が費用・コスト面においてメリットが多いということを学びました。事務所で今後、争訟が起こる可能性も無くはないと思うので、しっかり勉強していきます。
Y様
税務に携わる上で、すべての案件で争うべきではないが争うべき案件もあり、納税者が納得できない場合に争うべきか判断基準を提供することが必要となるため、税務争訟の概要や動向について理解する必要があると知りました。不服申立制度のうち、審査請求は最大のメリットとして訴訟と比べると決着が早く、審理留保事件以外は1年以内に裁決がでることがあげられ、おもなデメリットとしては、判断が保守的であることがあげられるなど、各々の制度にメリットとデメリットがあるため、状況にあわせて判断する力を身につける必要があると感じました。
相続マイスター講座16期 第11講座の感想



1点目は、相続税の納税資金対策として遺言書、とりわけ公正証書遺言書が良いという事です。被相続人が一人で書けてしまう自筆証書遺言書より公証役場の公証人の指導の元に作成される事から、前者よりも内容の確実性が高く、無効の恐れが低いことなどがその理由です。また、遺言書を作成するメリットとして、相続が実際に発生した場合、遺言書があれば相続税申告に必要な様々な手続を円滑に進めることが可能である事が挙げられます。これに対し、遺言書を作成していなかった場合は分割協議書が必要となります。民法上では期限が設けられていませんが、相続税法上では10ヶ月以内に協議をまとめなければ軽減措置を受けられないとしています。この事からも、遺言書の作成が非常に大切だと思われます。
2点目は、生前贈与にはいくつかの要点があり、満たしていない場合には贈与として認められない可能性があるという事です。第一に税務署側としてはより多くの課税を徴収するのが目的です。この点で、贈与者から受贈者へ贈与したという証拠が無ければ名義預金だったと言われてしまう恐れがあります。具体的に証拠を残す方法としては贈与者が自らの口座から受贈者の口座に振り込むことが挙げられます。ただし、受贈者本人が管理運用・使用収益を行っていたと証明できなければならない点で注意が必要です。贈与者からの送金のみで預金が構成されている場合は、名義預金としてみなされる可能性があるため、受贈者が日常的に使用している口座が好ましいとされています。これにより贈与者の名義財産ではなく受贈者固有の財産として認められるため相続財産の対象となりません。よって、生前贈与による節税の効果が発生します。
以上より、生前贈与をする場合には客観的に贈与したという証拠が必要である為、厳密に要件を確認し実行することが重要です。最後に、妹尾先生が仰っていた社会人として成長していくために必要な事について、以下、述べます。
士業は専門家である前に人として信頼される人物か否かが重要であり、その為には周囲の言葉に耳を傾けたり、自身ができない事を認めて改善したりするような素直さ、また、コミュニケーションを密に測るためのレスポンスの早さなどが重要だと仰っていました。専門知識や社会経験は無くとも、上記のような事は日常的に意識して出来る事であり、成長していくための基礎部分と言えます。今後、働く上でこれらの事を肝に銘じて仕事に取り組んでいきたいと思います。 I様
相続時精算課税について、一度適用を受けた場合にはその適用を受けた年度以降、暦年課税適用を受けることができなくなる点。相続時精算課税は将来確実に値段が上がるようなものがある場合以外には極力適用を受けないほうが良いということ。国の調査が入った場合には不用意に反抗すると追徴される金額が多くなることもあるということ。いかに相続税を課税されない財産を増やしていく事が節税に繋がっていくという事が実践的な学びでした。
Y様
納税資金対策と税務調査対策について講義していただきました。納税資金対策と税務調査対策の両方に通ずるものとして「名義預金」が挙げられると思います。被相続人の思いを無駄にしないためにも、生前対策の段階で出来ることがいくつかあります。贈与は双務契約ですので受贈者に伝えておくことや、契約が成立していることを証明するために通常使用している口座への送金をすることなどです。税務署もこの点に注目しているようで、追徴課税となることは避けられるよう、事前の対策をしっかりとすべきだと感じました。
M様
まず、相続税対策には、節税対策のみでなく納税資金対策、税務調査対策も含まれていることを知りました。ただ、節税対策だけを行うのではなく、納税資金を確保することや税務調査への不安からくるお客様の精神的なストレスを極力減らすことが大切だと感じました。また、税務調査対策としては、度々話に出てきた「名義口座」のお話が大変勉強になりました。相続税対策として暦年贈与していても、実体が伴わないとして無効になってしまったらとても悲しいことです。暦年贈与を勧める場合には、「名義口座」であると税務署に突っ込まれないようなやり方で進めるように気を付けたいと思いました。図らずも税務調査の対象となってしまった場合、税理士法人としてもお客様としても、非常に大きなエネルギーを消費してしまうというお話もありました。そうならないためにも、税務署との信頼関係を築くことが大切だと感じました。
M様
相続税対策とひとことに言っても、分割対策と納税資金対策、そして、相続税評価引き下げ対策の3本の柱があります。今回の講座ではこれらを全体的に学びました。様々な制度が存在する中で、お客様にとって最も有効な選択の提案が求められます。この最適な選択というのはお客様の事業や経済状況等によっても異なり、申告までの10ヶ月という限られた期間でいかに信頼関係を構築するかが重要です。たとえば、生前贈与の課税方式の選択や法人化するか否かにしても、制度メリットだけでなくデメリットまで知っておかなければならないと思いました。相続税における税務調査は「金融資産の申告漏れの調査」であることが多いようです。税務調査は金銭的負担だけでなく、精神的負担も大きいため、いかに税務調査の来ない申告書を作成するかがポイントとなります。相続税対策の際には、お客様の目線に立つことはもちろん、税務署の調査官の立場からも検討することが求められます。
M様
今回の講義で一番印象的だったのは、税務調査について、調査件数の内、申告漏れ等の非遺件数が8割を超えている事でした。私は本講義を受講して、税理士としての信用を失わない為にも、様々な視点から物事をとらえ(お客様の経歴や財産評価等)税務調査の非遺件数を減らす意識を持つべきだと思いました。妹尾先生は、税理士としての仕事をするにあたって、お客様の立場に立つだけでなく、調査官の立場に立ってものを考えることが大切だとおっしゃっていました。これは、税理士に限った話ではありませんが、他人の立場に立って物事を行うことは、仕事上非常に大切だという事を実感しました。
S様
資産がたくさんあっても、現金がなければ納税資金の捻出が必要になります。シミュレーションで概算の税額を出したら、節税対策だけでなく、納税資金の確保もご提案していきたいです。土地はあるけど現金がない関与先もありますので、納税資金確保のために土地の売却を念頭に置くのか、生命保険を活用していくのか、不動産収入をストックして備えるのか等、資産バランスを見極めたうえで提案が必要だと感じました。まだ税務調査の経験はありませんが、申告前に調査のポイントを押さえて調査に入らないような対策をし、もし調査が確定した場合は、税理士の先生と相談しながらしっかり対応していきます。
N様
今回のセミナーでは、相続税の対策や税務調査に入られないようにするにはどうすればよいか、という点を学ばせて頂きました。相続時精算課税制度については、改めて学べたことが多かったです。贈与時の価格から下落したものであると、余分な納税負担がでてしまうことや、暦年贈与には戻せない点など妹尾先生も使うべきではないとおっしゃっていましたが、その通りだと講演を聞いて感じました。また、相続税の税務調査では、申告漏れが一番多いものが現金・預貯金が割合的にとても多いのが印象に残りました。財産の名義については税務調査が入ることが多いと教わったので、「原資」が名義人本人のものか、過去に「贈与」が成立しているか等、注目すべきポイントが分かったのは収穫となりました。
A様
妹尾先生の業務内容がランドマークと類似点が多く、今までの特定分野に特化した他士業の先生方の講義よりも実際の業務にフィードバック出来るものが多かったです。講義後に講義内で説明されなかった資料(納税資金対策と税務調査対策以外)を一読致しましたが、財産評価・申告手続きで間違いやすい論点も掲載されており大変参考になりました。妹尾先生のいらっしゃるひょうご税理士法人様の税務調査の割合が毎年提出件数の5%以下とのことでしたので、ランドマークの割合が如何に低いかと改めて認識致しました。
N様
納税資金対策では相続税に対する生命保険の活用、生前贈与、不動産の有効利用等様々な方法を学びました。また、気を付ける点として、例えば生前贈与の際には贈与をしたという証拠をきちんと残す(通帳印字等)ということが大事であり、後の税務調査等でのトラブル回避にもなることを学びました。税務調査対策では相続税の税務調査の現状として現金預金・有価証券等の金融資産の申告漏れがほぼ半分を占めており、申告誤りが多い事項を学びました。まずは税務調査の来ない申告書づくりが重要であり、その方法として税務署への事前確認や疎明資料を添付することなどを学びました。今後の業務に活かしていきたいと思います。
H様
(1)納税資金対策
①生命保険が有効
生命保険金は受取人に確実に現金で受け取れるので、納税資金対策、代償分割の時に利用できる。
ただし、保険料負担者が被相続人か、受取人が誰かなど、保険のかけ方に注意する。
②生前贈与(暦年贈与中心)
相続時精算課税は確実に値上がりが見込める土地・株式がなければ使わないほうが良い。年間基礎控除は110万円だが、被相続人に金融資産が多く、まだ被相続人が若いなら相続対策として有効。贈与税を払ってもトータルの相続税と比較して有利なら、基礎控除以上の贈与も有効。
③法人設立
利回りの良い優良不動産を多く持っている場合に有効。上記①②を実施しても被相続人に家賃収入が入金され続けると結局金融資産が減らずに相続税が多くなる。相続人のうち、後継者を定めて不動産管理会社を設立して資金をプールしておけば、納税資金対策につながる。ただし、出資方法で被相続人にも出資させると株式が親の相続財産になるので、注意。修繕のタイミングなど、キャッシュフローの増減も含めた相続対策をコンサルする必要がある。
(2)税務調査のポイント
①現状 調査件数自体は減少傾向だが、調査されると80%超申告漏れを指摘される。また、現預金・株式も申告漏れが約50%、保険積立や貸付金関係も含めると80%前後になる。申告漏れの中心は「名義財産」。
・名義財産の見つけ方
・ゆうちょ・かんぽ保険など、身近にある金融機関で取引がないか。
・地位・収入のわりに現預金が少ない。
・株式を保有しているのに、配当金が口座に入ってない。
・市町村の不動産情報から物件を売却したのに、通帳に入金がない。
・貸金庫がある。
③税務調査に入りたくなる申告書
・誤り・資料不備が多い、添付資料が少ない。
・課税価格3憶円以上の申告書、農地等の納税猶予の特例を受けている。
・家族名義の金融資産が多い。税務署で親族図を作って、銀行預金口座の照会依頼をかける。
(3)感想
1回相続税の税務調査に立ち会ったことがありますが、確かに税務署側で家族関係の口座・土地関係を調べてから調査に来たように見受けられました。相続の仕事は件数が多いと土地中心に時間をかけがちですが、金融資産のほうが調査の比重は高いことを考えると、金融資産も意識してチェックしておく必要があると思いました。また、個人的に申告書や税計算を手で書いて体で覚えるという発言には好感を持てました。
T様
ひょうご税理士法人代表の妹尾先生より講義でした。先生の経験に基づいて、納税資金の対策及び税務調査の対策を教えてもらいました。身近な業務と関りの深い内容で、すごくためになりました。例えば、遺言なしで分割協議書を10ヶ月以内に協議出来ない場合、軽減措置が受けられないなど、日々業務は何のためにしているかを再認識しました。また、遺言予備的条項のことについて、妻と兄弟姉妹のみの例が分かりやすかったです。予備を設定しなければ、遺産は妻の兄弟に渡すことになります。このようなケースも想定しながら、お客様にマッチした提案をすることに心掛けます。また、先生が経験された税務調査のことも聞けました。税務署からの金融機関等への事前照会が予測される事項のチェックの重要性を再三しました。真にお客様と信頼関係を築くため、名義預金等の可能性も想定して接することが必要です。私は今担当者の見習いで、預金不明点のマーカー入れ等の業務をしています。税務署の資料の見方について理解が深まりました。
S様
①納税資金対策
納税方法には、物納や延納という方法もありますが、相続開始から10ヶ月以内に金銭で納税ができるように提案することが大切です。例えば、建物の法人化を行うと土地の評価額が下がるため相続税対策に有効ですが、被相続人の年齢や所得などを検討した上で判断する必要があります。
②税務調査対策
相続税の申告漏れの内訳は、現預金や有価証券などの金融資産及び保険関係が多くなっています。そこで、名義資産や生前贈与、大口入出金の確認を行い、税務調査が来ないように対策を進める必要があります。
Y様
相続税税務調査が来ないように対策をとる必要があるのは、お客様にとっては税務の専門家として安心して任せているにも関わらず、税務調査が来た場合、築き上げてきた信頼関係が崩れてしまう恐れがあるからであると知り、やはり仕事をする上で第一に重要なのはお客様との信頼関係を崩さないように心がけることだと感じました。また、そのために税務調査などが来ないようにするには、調査官の立場に立って、調査確認事項や調査指摘されやすい項目を検討することや問題点をおさえるということ、納税者の立場に立って、疎明資料を添付することや問題点を解決すること、財産を評価することが重要だと学びました。
I様
生前贈与を行うときは、贈与をしたという証拠をきちんと残すことがポイントであり、毎年110万円という贈与税がかからない金額で子供や孫に贈与していても、子供や孫が贈与されているという両者の意思がなければならないので、生きているうちにきちんと伝えておくべきことだと思いました。また、建築をすることで相続税対策になると今回知りました。1億の土地を持っている方が建築すると7600万円評価額が下がる結果になり十分な相続税対策になると知りました。しかし、利回りが中途半端な場合長期的な相続税対策とはならない場合があるので、相続税対策になっているかのフォローをしていくことが大切だと感じました。
M様
今回納税資金対策と税務調査対策の講義を受講して非常に業務の上で勉強になりました。円満相続や相続発生の流れ、相続税税務調査の現状など丁寧な説明をして頂きました。申告漏れの財産は現金、預貯金が49.3%と半分近い割合で指摘されている事がわかり、ランドマーク税理士法人がなぜ預金不明点など5年調査しているかがよくわかりました。今回学んだ知識については、相続業務を担当する上で必要不可欠な知識でありますので、復習を徹底して自分の知識として定着させていきたいです。
相続マイスター講座16期 第12講座の感想

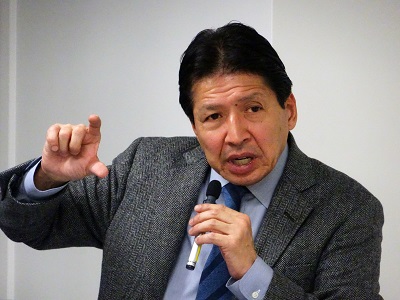

土地の評価については、宅地や山林、雑種地などの地目ごとに評価するように財産評価基本通達に定められています。また、貸家建付地を評価する場合には、各棟の敷地ごとに1画地の宅地として評価をするため、かげ地割合や間口狭小補正率などを考慮すると評価額が下がることとなります。今回の講座では、実際に税理士がどのように土地の評価を行っているのかを知ることができたため、今後勉強をして経験を積み、課税上の弊害がない「答え」を自ら作れるようになりたいと思います。
Y様
土地の評価は主に財産評価基本通達7「土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。」にしたがって行いますが、この主たる地目とは、広さではなく主として利用されるのはどちらかによるといったことや、一見宅地として処理するように見えても実は雑種地として処理することがあると知り、ただ規定を文字で理解するだけでなく、写真や実物を見て土地評価をするなどの経験を積むことが実務では重要だと感じました。
M様
貸家建付地の評価について、たくさんの事例を参考にしながら学ぶことができました。複雑な事例などで貸家建付地の評価のポイントなどを学びました。実際に土地に赴いて評価をすることが大切だということなど、業務内容について詳しく知る事が出来ました。仕事では、貸家建付地の評価に悩んでいるお客様に知識として提案し、専門の方へ斡旋する事が出来るのではないかと思います。今回の講義で学んだことを仕事で活かせるようにします。
A様
土地ファイルは最終的にはお客様と税務署に提出するため、それに伴い土地の評価は必ず行わなければならない業務です。本講義では土地の評価を行う際に抑えておくべき事項を説明頂きました。以下、土地評価の際に抑えておくべき事項です。
1 土地評価上の区分・土地の地目の判定(財産評価通達7)
2 貸家建付地の評価(財産評価通達26)
特にアパートで駐車場を住民のみに貸している場合、それ以外の第三者にも貸している場合の評価の相違には注意する。
3 貸家の評価(財産評価通達93)
4 借家権の評価(財産評価通達94)
5 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価(国税庁HP 質疑応答事例)
6 宅地の評価単位である1画地の判定(国税庁HP 質疑応答事例)
7 整形地か不整形地の評価の相違
アルバイトの際も土地の評価明細書を作成したことがありますが、その際は上司にこれらの判断を行ってもらったうえで作業しました。しかし、4月から社員になるにあたり、土地評価はまずは自分で作業しなければならないと思うのでこれらのことは最低限抑えておきたいと思います。
K様
主に貸家建付地の評価についてでしたが、借地権や、借家権の用語の意義から条文の解説、公図を使った土地の評価の仕方についても詳しく教えて頂きました。今の仕事でも土地の評価をすることがあるので大変勉強になりました。一体評価になるのか、ならないのかを十分に見極めていき、これからも土地の評価をする際は、今回宮田先生に教わったことを注意しながら行っていきたいと思います。評価する前にしっかり確認をとってどのような現況にあるのかを調べていこうと思いました。
K様
貸家建付地の評価上の留意点と見えない落とし穴について講義を受けました。貸家建付地の評価の仕方をまなび、その後、事例を通じて貸家建付地が適用できるのか、できないのか等を見ていきました。貸家建付地の評価で、基本はアパートの前の駐車場はアパートの人専用にすることにより貸家建付地で評価することができ減額することができるが、そこをあえてよその人に一部を貸して、貸家建付地で評価する部分と自用地で評価する部分に分けることにより、全体を貸家建付地で評価するよりも、貸家建付地と自用地で分けて評価した方が安くなる場合があると知り、とても勉強になりました。これを利用した節税対策ができると感じました。
T様
土地の評価方法の基本的な考え方について学びました。土地の価額は、宅地、田、畑、山林といった地目別に評価されますが、一体として利用されている一団の土地が2つ以上の地目から成り立っている場合、その一団の土地は、そのうち主たる地目から成るものとして評価します。アパート等に隣接して駐車場がある場合、原則としてアパート敷地部分は地目:宅地、利用区分:貸家建付地とし、駐車場部分は地目:雑種地、利用区分:自用地として評価します。ただし、駐車場の契約者すべてがそのアパートの入居者であり、かつアパート敷地内の駐車場であるなど、「アパートと駐車場の貸付が一体」と認められる場合には、その全体を主たる地目により評価するなど様々なパターンがあるため、多くの事例を見てその判断力を高めていきたいと思いました。
T様
貸家建付地の評価について大変面白く講義をして頂きました。初めに、通達の重要部分を丁寧に読み解いて下さったので、基礎から理解する事が出来ました。残りは、写真や図を多く使った「紙芝居」のようなレジュメだったので、実務上大切なことを分かりやすく教えて頂きました。評価の仕方で、借家率が高い方が、処分価格ベースにより評価額が低くなると知り、とても意外でした。本日教えて頂いたことは、町田事務所で今後活かせると思います。評価明細書の見方も少し教えて頂いたので、コピー業務の際、意識して見ることから始めます。
I様
貸家建付地に評価を行うとき、建物を分けて評価していく方が評価は下がると知りました。また、戸建ての貸家は相続発生時に空き家になっていると自用地評価となってしまうと知りました。また、新しく貸そうとしたアパートで15部屋あったとして相続発生時に内3部屋しか契約が済んでいなかった場合、3部屋分しか7割評価が適用されないので、警備会社などに全部屋貸すというようにして鍵を持たせておけば全部屋に7割評価が適用されるので、新しくアパートを貸そうとしている方には提案すべき事だと感じました。貸家建付地の評価は難しかったですが、分けて評価することで時間は掛かるが何百万円も変わると知りお客様との信頼にも大きく関わってくると感じたので、大変でも行うことが大切だと思いました。
K様
「土地の時価に答えはない。」どのような評価なら税務署が納得してくれるのかといったことは経験が重要なのだという事を知りました。相続開始時に賃貸物件が空き家になっていた場合にマンションなどで、屋根の下に一部でも借人が居住している部屋がある場合には、賃貸の募集をしていれば貸家建付地としての評価ができるが、一軒家などの場合には募集を継続していても貸家としては扱えないということが勉強になりました。
A様
貸家建付地の財産評価は税理士試験でも必須項目で、家屋の評価→宅地の評価の順で財産評価するのが原則となっております。家屋の評価については、賃貸割合(各独立部分の床面積)で按分するのは受験上でも学習しておりますが、その計算をするための現物の家屋の図面や資料を見たことが未だないので、参考資料として付属して頂きたかったです。土地の評価については講義の後半で話されて、「貸家が複数連棟する場合の宅地の判定と具体的な評価額」は宅地の評価単位としての評価方法を存じていなかったので勉強になりました。
S様
貸家建付地だからといって、何も考えずに一体で貸家建付地評価するのではなく、駐車場の利用状況や土地の形状によって臨機応変に評価することで、相続税評価を下げられる可能性があることがわかりました。アパートだから「全部一体で貸家建付地」と決めつけるのではなく、お客様からしっかり聞き取りをして、分けて評価すべきかどうか、一体とわけて評価するのとどちらが評価額を下げることができるのかをしっかり検討していきたいです。また、どこまで評価額を下げられるかは経験などに依るところが大きいようなので、審理課の先生と相談しながら決めていきたいと思います。
M様
貸家建付地の評価上の留意点と見えない落とし穴を受講し、実務で日々業務に通じる内容で非常に勉強になりました。特に、今回の事例はまだ私も関与したことのないケースもあり、今後評価をする上で参考になる点が多かったです。通達などもあまり読む機会がなく新鮮でした。相続の分野の中で土地評価についてはまだまだ知識不足な点があるので、今回の講義を復習して、より自分の知識として業務に生かせるよう取り組んでまいります。
S様
普段業務の中で相続シミュレーションや10万円パックで取り扱っている土地や建物の評価について、数字やマニュアルのみで覚えていたので測量図を見てもピンとこなかった点が多かったのですが、今回の宮田先生の講義で写真や実際の測量の様子を載せた写真を見せてくださったおかげで、間口の取り方や想定整形補正の方法が具体的にイメージできました。また、土地の分け方についてもなぜこの方法で分けるのか、どんなメリットがあるのかということも詳しくお話してくださり、非常に役に立ちました。
M様
実務的な土地評価の方法や注意点等についてでした。写真等を用いての講義だったため非常に理解しやすかったです。土地評価については必ず9つのいずれかの地目で評価しなければいけないこと、また、一つの土地が2つ以上の地目からなる場合にはその土地の主たる地目からなるとして評価する事を学びました。加えて、宅地と雑種地の区別として、建物が土地にのっていたら「宅地」、土地に構築物が付随していたら「雑種地」と判断されることも理解しました。本日学んだことは実務の一部の基礎だと思うので、これからより詳細まで学んでいきたいと思います。
H様
(1)貸家建付地と自用地の評価
アパートなどは、賃借人に部屋を貸すことによって持ち主の使用権が制限されるため、土地評価の際に評価額を下げることができる。よって、空室が発生した場合は制限がなくなるので、その分貸家建付地でなく自用地の評価となる。相続税対策としては、一括借り上げにしておけば、空室が発生しても貸しているのは管理会社なので空室の扱いにはならない。
(2)駐車場の評価
駐車場は一般的に雑種地として別評価になるが、アパートに付属してアパート住人のみに貸している場合は、アパートと一体として地目宅地で評価する。ただし、駐車場をアパート住人以外にも貸している場合は、駐車場は原則通り別評価する。実務では、この場合、アパート本体と駐車場で別評価することにより、不整形地として評価を下げることができる。
(3)旗竿地について
平屋の貸家数棟が連なっている場合に空家があるときは、通路も含めて別に分解してそれぞれ評価することで旗竿地の状態で評価することができる。
(4)感想
現在、相続の実務をまさにしているところなので、本日の講義は大変ためになりました。実務で理解不足な部分を補足できたので大変満足しています。欲を言えば、第12講義でなく、最初のほうだとよかったかもしれないです。
N様
土地の評価の基礎的なことから貸家建付地等の評価について学びました。まず、地目の判定として立体駐車場は建物ではなく構築物が乗っているだけなので宅地ではなく雑種地であることを知りました。本題の貸家建付地の評価については、計算式の中で賃貸割合を掛ける部分があり、空室が少なければ少ないほど評価を下げることができ相続税を少なくできることを学びました。また、継続的に賃貸されていた貸家で、課税時期において一時的に賃貸されていなかったとしても、アパート等であれば(一軒家を除く)賃貸割合に含むこととして良いことも学びました。土地の評価において注意すべき点を学んだので実務で活かしていけるようにしていきたいです。
T様
土地評価時にどうすれば納税額を抑えられるか、事例を見ながら学ぶことができました。土地の広さや用途は様々で実際に足を運び自分で確かめて測量することが大切なことだと感じました。また、同じように土地の上に住居がある場合でも、住人がいるかいないかで評価が変わることを知り興味深かったです。納税額に大きな差が出てくるため、該当するお客様がいる場合は事前に対策を考えていきたいと思います。そして、これまでの研修で学んだことをこれからアウトプットできるよう、しっかり復習していきたいと思います。
相続マイスター講座15期 第1講座の感想
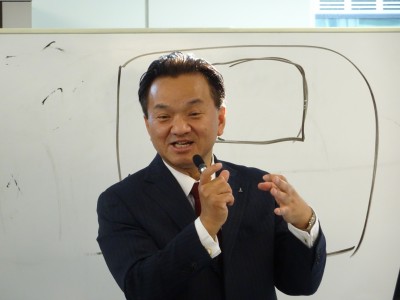
そこから、生産緑地制度のメリット・デメリットについても学びました。メリットとしては、固定資産税・都市計画税は農地課税となることにより減額され、相続税・贈与税の納税猶予を受けることが出来る点で、デメリットとしては、生産緑地に指定されることによって宅地造成や建物等の建築などには市町村の許可がなければ建築できない点や融資を受ける際などに担保にすることができない点、また、指定の日から30年間を経過した時、農業の主たる従事者が死亡した時、病気などの理由で農業に従事できなくなった時でないと市町村に対する時価での買取り申し出ができなくなるということも学びました。 生産緑地制度という言葉は聞いたことはありましたが、具体的な制度の内容等は知らなかったため、今回の講座で少し生産緑地制度について知識を深めることができたと感じました。
いずれ私もお客様の担当を持つ日がくるので、その時に今回学んだことは活きてくると思いました。お客様に生産緑地制度の適用を勧める場面が今後あると思います。その際にしっかりと生産緑地制度を適用することで受けるメリット・デメリットを説明して、そのお客様にとって最善の案を提供していきたいと思いました。 W様

例えば、相続税で関与させていただいたお客様をその後、所得税や法人税でも関与させていただいたり、信託、融資、保険をつける等相談に乗ることができます。また、他の税理士との差別化を図るためにコンサルが重要ということが分かりました。お客様が税理士を選ぶ際、信頼に足る能力を有する税理士なのか、自分の方向を向いて自分のために仕事をしてくれる税理士なのか、という点がポイントになるだろうと思います。
例えば、ふるさと納税をすすめることもコンサルの一つだと分かりました。最近のふるさと納税では、思いやり返礼プロジェクトなども実施されており、寄付だけで終わらない関係を築くことができます。
これらを通してよりお客様のニーズに答えることができ、他の事務所、税理士との差別化を図ることができると思いました。 S様

前者は空き家の増加や少子高齢化などの背景があり、相続を行う際には節税のスキームとして使える特例だと思いました。
後者の話を聞いた際、バブル時代に土地の評価を下げるために生産緑地制度が設けられたこと、それの有効期限が30年であること等の背景を知りました。そしてその期限が2020年であり、それに伴って土地の売却が多く起こることが想定されるため、生産緑地を継続するかを選択できる法律ができました。
そのような土地を所有しているお客様は多いそうなので、今回の講義で学んだ知識を軸にしてお客様にしっかり話ができるよう、努めていきたいと思いました。 E様
前半は平成31年度税制改正についての講義で、後半は生産緑地と納税猶予についての講義でした。
所得税の税制改正については確定申告で対応することになるので、それまでにしっかりと理解を深めておきたいです。
また、消費税も今年引き上げが行われ、軽減税率などこれまでよりも複雑化しているので、お客様にしっかりと説明できるようにしておきたいです。
生産緑地と農地の納税猶予は、事務所でもかかわることが多いと思いますし、特に適用の可否については間違えないように勉強していきたいです。
S様
今回は、平成31年度の税制改正と消費税改正、生産緑地と農地等納税猶予について学びました。
特に、今後生産緑地2022年問題はオリンピックを経て関わってくる問題だと思ったので、きちんと知っておかないといけないと感じました。
事務所で活かせると思ったことは、ふるさと納税の提案をするということです。今回の改正により返礼品の割合が減るということになっていますが、便利という面では変わりがないため、自分もおすすめ出来るときはしていきたいと思いました。
I様
所得税の話では身近な話題も多く興味深いものでした。贈与扱いになるのかならないのかで税金が変わってしまうので気を付けなければならないことが多いと思いました。特に、私の祖母は祖父が亡くなって遺産を相続しビルや土地を持っているので、将来的に祖母に何かあった場合に備えて正しい知識をもっとつける必要があると思いました。
生産緑地の話ではメリット、デメリットがそれぞれあるのは分かりましたが、生産緑地に対して知らないことが多かったため、もっと知ることで今回の講義がより一層実のあるものになると感じました。
M様
平成31年度の税制改正や消費税も改定、生産緑地などを学ぶことができました。
特に生産緑地の2022年問題を詳しく解説してくださり、生産緑地法の改定内容やメリット・デメリット等、生産緑地の評価方法など分かりやすくご説明していただき、とても理解しやすかったです。
ふるさと納税や消費税改定など、今後お客様とお話しする際に、役立てていけると感じ、より知識を高めていけるように勉強していきたいです。
A様
前半は、今年度に適用される税制改正について税金の種類ごとに説明していただきました。改正内容はいくつかありましたが、教育資金の一括贈与の非課税というお話は私自身、大学の費用などで利用していたので、今回のお話でどういった仕組みなのかようやく理解できました。
また、清田さんのお話はお客様に実際どのように提案するか、ということが分かりやすいのでこれから担当を持つようになった時活かしていきたいです。後半の生産緑地の問題は、2022年以降に向けて相談に来る方が増えると思うのでしっかり勉強しておきたいです。
O様
小規模宅地等の特例や、配偶者居住権、生産緑地の知識について、「なんとなく」頭で知識として知っていましたが、具体的な事例を交えて説明をしていただけたため、より理解を深めることができました。
また、平成31年度税制改正に関しては、法人のものしか聞いたことがなかったため、個人事業主にも適用があること、他にも住宅ローン控除や空き家対策としての改正が行われていることを学べました。
ただ知識として理解を深めるだけでなく、どのような背景でこの改正に至ったのか?農協や信託銀行などではどのような考え方をしているのか?など生の声を交えて講義をしていただけたことで、より興味深いものになりました。
特に、理解した知識を身につけることで、今後、業務に役立てていくのはもちろんのこと、改正の背景などは、今後お客様と会話をしていく中で、とても良い話の種になるかと思いますし、お客様に伝えることで、お客様もより税制について理解をしやすくなると考えます。
とはいえ、小規模宅地の特例など、実際はお客様の数だけ適用例があり、より複雑なものであるかと思いますので、今後もこの大学校でより多くのことを学び、最終的にアウトプットできるようになればと思います。
K様
今回の講義内容は相続税に関する制度と生産緑地の納税猶予制度でした。
清田さんの講義はとても分かりやすく、具体的な事例を基に説明してくださるので、相続税に関する知識が無い私にも理解することが出来ました。
ほとんどの生産緑地が2022年に買取申出が出来るようになるため、2022年が近づくにつれ、特定生産緑地制度に関する知識が必要になってくると思います。
今回の講義はその知識を詳しく知る良い機会となりました。
セミナーの前半では、法改正に伴う税制度の具体的な変更ポイントについて、後半では、生産緑地2022年問題について学びました。 新制度(配偶者居住権など)や、既存の制度(生産緑地2022年問題、地価下落予想)を把握し、仕事に取り組むことは(たとえ、コピーや入力作業といった単純作業であっても)、先輩社員や士業の先生方の意図を理解することにつながり、仕事の効率化や自身の成長にもつながるように感じました。
W様
ふるさと納税は所得控除となり返礼品がもらえるため、お客様に勧めてあげると他の税理士事務所と差別化になりお客様にも喜んでもらえるので、覚えておこうと思いました。また、自身でもふるさと納税をし、理解を深めようと思います。
消費税が10%になりますが、その際の住宅購入など個人的にも気になっていたので、今回お話を聞くことができてよかったです。社会人になったので、このような知識はニュースなども参考に情報収集をしっかりしていこうと思います。
お客様に何を話してあげれば喜ばれるのかをお話してくださり大変勉強になりました。
生産緑地については知らなかった内容でしたので、どういうものなのか自分で説明できるようさらに勉強していきたいと思います。
M様
非課税になる贈与や空き家控除など、それぞれの人に合った節税提案をしていることがわかりました。
小規模宅地の軽減は、FPで学習したことがありましたが、今回の講義で数字だけでなく少し深い所を理解することができました。特定事業用宅地と特定居住用宅地は併用できるということも知ることができました。
特に2022年問題が興味深かったです。多くの生産緑地が2022年に買取の申し出が可能になるということで、より知識を身に着けていかなければならないと感じました。
M様
今年度の税制改正と生産緑地についてでした。資産税関連の税制改正も多く、中でも小規模宅地等の特例の改正は今後従事する上でよく知っておくべきなのではないかと思いました。また、消費税引上げは自身の生活にも身近な改正であり、帳簿の記載方法も変わることから、業務にも影響があるなと感じました。
生産緑地に関しては、2022年に指定を解除できることにより起こる土地の下落等の懸念事項が実際どうなるのか、目を惹かれる話題だなと興味が湧きました。
N様
本日の講義ではかなりの量の知識を得ることが出来ました。税制改正の所得税の引き上げによる保存方式の変更については、現在、エントリ・収入表の入力をしているため、この先々で注意しなければならないという意識を持つとともに、軽減税率の対象の知識の熟知、その場合の仕分けの仕方を学んでまいります。
生産緑地については、私の家の近所は農地が広がる横浜の羽沢という場所で、近々駅が完成するため、地価が上昇しております。しかし、2022年問題に伴い、地価が下落し、駅周辺の土地が売りに出されることが予想されるため、その前までに羽沢の生産緑地を調べ、今後どのような動きを見せるのか注視してまいります。
そしてあわよくば土地を購入し、マイホームを建てる家族計画の構想もしていきたいと思います。
I様
今回は、生産緑地と農地の納税猶予についての講義でした。
TVCMでよく見かけるふるさと納税はどのような制度なのか、どういう人がするのか理解していませんでしたが、税金を少なくするために有効かつ特典付きの面白い制度だと思いました。節税のために他にも様々な制度が考えらえつくられていますが、中にはあまり使われていない制度もあることを知りました。あまり使われていない制度はCM等でも見かけることがなく推されていないことが目に見えてわかります。
相続関連の仕事は亡くなった時だけに携わるのではなく、残された人がそこからどう生きていくか提案するなどあらゆる関わり方があると学習しました。
また、講義で例にあげていたように、泥を固めるだけで4000万円も税額が変わる例もあると知り、少しお金をかけて手を加えるようにとアドバイスすることで大きな節税になることもあり、わたしたちの仕事は大切な仕事だと改めて実感しました。
平成31年度は税制改正が多くあると感じました。消費税の引き上げについて、先日池袋で反対の署名活動が行われているのを目にしました。消費税の増税はほとんどの人が反対の意識を持っていると思いますが、署名がたくさん集まったら増税はなくなるのか疑問に思いました。
K様
今回の内容は、とっつきやすく分かりやすい内容だと感じました。ふるさと納税はすでに母がやっておりますが、自分でもやってみようという気持ちになりました。
また、特に印象に残ったのは、小規模宅地の特例の見直しです。そろばん塾でもなんでもいいからやってしまおうという考えの人が増えたため、相続開始前3年以内に事業用に供された宅地等が除外になったということに驚きました。このような人が増えると、税制改正せざるを得ないということをこの例をもって実感しました。
マーケティング企画室に配属になったので、改正事項について広報を通じて詳しくお伝えすることが必要だと感じました。
Y様
親が自分の子供の学費のために自己の財産から出資をする。そんな当たり前のように思っていた行為でさえ、贈与に該当し本来であれば贈与税の対象になることを今まで全く気にしたことがなかったため印象に残りました。実際は、親が子供に費やす教育資金は非課税となりますが、日常生活に溶け込んでいる取引行為にもっと注意深く目を向けることにより、税金の知識がより深まっていくと思います。
さらに、今では周知となっているふるさと納税も詳しくはよく知らなかったため、今回の講義で学ぶことができ教養が深まったと思います。
T様
教育資金と子育て・結婚資金の非課税制度についてお話しを聞いて、実例を混ぜながら違いを解説して下さり、とても理解が深まりました。
また、勉強不足のため生産緑地制度についての知識がありませんでしたが、生産緑地がどのようなものなのか、生産緑地にすることで税金がほとんどかからなくなるというメリットと、長期間自由の利かない土地になるというデメリットがあることがあるということを学びました。
初めて聞く内容が多く、今後も勉強を続け、知識を身に着けていきたいと思います。
K様
税制改正に関する説明では、レジュメに加えて図を使って解説をしてくださったため聴きやすかったです。しかし、知らないことも多くあり理解が難しかったため、税制についての書籍を参考にしたり上司の方や自身の経験から学ぶようにしたりして変化する制度に対応していくようにしようと感じました。
また、生産緑地について詳しく知らなかったので新たな学びとなりました。今後2022年問題について考える方が出てくると考えられますが、いくつかの選択肢の中からそのお客様に合わせた提案をしていく必要があると思います。この問題に限らず、一人一人のお客様に合わせた対応・提案が大切だと考えるため、日頃から知識や経験の引き出しを増やす努力を怠らないようにします。
全体を通して知らないことや難しいと感じる内容が多くありましたので、税や相続に関し知識を増やすことと理解を深めることに力を入れたいと感じました。
W様
生産緑地問題について初めて知りました。当時の生産緑地制度が導入されたきっかけや流れまで遡り説明をしてくださったので、税務に関する知識を全く持ち合わせていない私にも説明が理解しやすかったです。
配属のマーケティング企画室はフリーダイヤルや外部からの電話を受ける機会が多いので、その際、お客様は何について相談したいのか、困っているのかを的確に把握し、担当者に繋ぐことが大切だと思いました。
今回の講義で得た知識を自分のものにし、電話対応に活かしていきたいと思います。
相続マイスター講座15期 第2講座の感想

内容も【条文編】と【解説編】に別れて説明され、小規模宅地を理解するときは、解説書を読むだけでなく、法令(法律・施行令・施行規則)+(通達+情報など)で判断していく、ということは、他の条文を理解する上でも基本的なことで実務に役立つことでした。
小規模宅地の条文は措置法69の4で定められており、それを①書類審査、②入学試験、③卒業試験の3段階で解説され、分りやすかったです。特に、個人とみなして課税すること、親族の定義、宅地等は重要でした。【家なき子】の開設を表にして説明されたのは分りやすく、よく理解できました。
相続等で被相続人居住用宅地等を取得した親族本人が、相続開始前3年以内に居住していた家屋の所有者が該当する場合の事例を具体的にあげられ、難しい判断がわかりやすく判断できるのには感心しました。
やはり、小規模宅地の第一人者で、是非、執筆の本を買って読もうと思います。 Y様
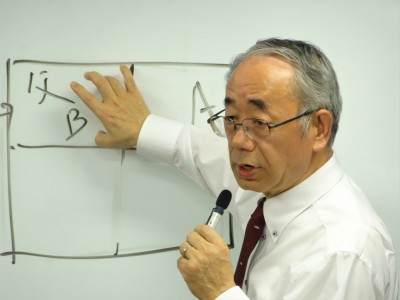
特定居住用宅地は相続人によって居住・保有の要件が変わると学びました。親族はどこまでを親族と呼ぶのか、同居・生計一はどう違うのか、曖昧な境界線をはっきりさせることがポイントになることがわかりました。先生が言葉は似ている=同じではないといっていた通りだと思います。法令を読み解く上では、言葉の本質や法令用語を正しく理解することが大切だと学びました。その作業はとても大変だし、慎重に考え進めていく必要があると思いました。
夫婦の一方が死亡した場合に姻族関係終了届を出す人が増えてきているといっていましたが、それは何故なのか気になりました。また、今まで勉強してきた中で相続に関する特例をたくさん扱いましたが、配偶者の救済が手厚いと感じました。 I様

具体的には、それぞれの用語の定義、例えば「建物」と「家屋」の表す意味が違うとか、法令の文中で使われている「又は」は場合によってはandの意味に使われている時があるとか、法令や通達を読む際も注意深く読まなければならないということを教えられた気がします。
一番目からうろこであった点は、法令、通達や情報に書いていないことを、勝手に「論理的にはこうだ」と解釈してはいけないということです。
講演中に「お父さんと同居していた息子の嫁が、息子と死別して再婚した場合、お父さんが亡くなった際に小規模宅地等の特例を受けられるか」との質問を講師からいただき、法令の精神から論理的に推察して「No」だろうと答えたら、答えは「Yes」。
なぜならば、法令にも通達にも「No」という記述や根拠はないから、ということでした。 M様
今回の講義で印象的だったのが、たとえ似ている単語であっても条文上では意味が異なってくることです。
例えば、租税特別措置法第69条の4上の「居住したことがないこと」と「居住していたことがないこと」は一見同じ意味に聞こえます。しかし、実際は「居住したことがないこと」は相続開始時も含めたいずれかの過去に居住したことがないという意味に対し「居住していたことがないこと」は相続開始時は含まないいずれかの過去に居住したことがないという意味になります。
このように知識として把握していなければ、思わず用いた文章の意味が変わってくるという点に注意して文章を書いていこうと思います。
O様
講義は小規模宅地についてでした。また、法律の仕組みや読み解き方を主に学びました。
小規模宅地は非常に難しい内容で、理解しきれたかと言われるとまだ触りの部分しか理解できていないかと思います。
しかしながら、今後も小規模宅地に触れる機会は非常に多いかと思いますし、多くの人が利用したい特例かと思いますので、少しずつでも理解を深め、お客様にかみ砕いて説明できるレベルになれるよう努めます。
前回もそうでしたが、やはり、具体的な、身近な例に置き換えることで「法律・相続」という距離の遠いものが、少しでも簡単に感じられるようになるかと思います。また、法律等の読み込みなどにおいて、基礎的な知識が足りていないと非常に感じたため、早急に身に着けていかなければならないと感じました。次回の大学校では、その点も補って講義に参加していきたいと思います。
I様
今回の「小規模宅地の特例の活用」の講義では法令の内容はもちろんのこと、その法令で用いられる言葉の意味を改めて確認することができました。特に講義で重要だった「親族」は何となくの認知しかなく、その意味を詳しく言葉で説明するのが難しかったのですが、「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の婚姻」と詳しく分けられていたことを初めて知りました。言葉の意味を知らないだけで何をどのように説明しているのかと理解する深さが変わってしまうため今回説明された言葉は確実に覚えたいと思います。また、小規模宅地は仕事を行う上で知っておくべきことであり自分でも改めて勉強しようと思いました。
K様
小規模宅地の特例について学びました。大学では学ぶことの出来なかった借地法について、最新の情報を知る事ができたので、とても良い機会となりました。小規模宅地については、私が来所されるお客様にお茶を出す際に、何度もお客様と上司の方が話しているのを聞いたことがあり、また、アグリタイムズでも取り上げられるなど、頻繁に用いられる知識なのだと日々の日常から実感していました。そのため、今回の講義でより深い知識を付けることが出来たので、今後、お客様と上司の方が話している際に内容を詳しく聞いてみたいと思います。
S様
小規模宅地について学びました。親族や家屋など基本的な用語についての理解を疎かにすると、実務に携わるうえで致命的なミスにつながることを、髙橋先生が事例を用いてご説明なさったことで大変よく伝わってきました。
大学時代で学んだ法律用語が、学問上の説明と、実務での考え方(捉え方)との違いも垣間見えました。仕事に取り組むうえでも、大学で学んだことも改めて実務の視点から学びなおす姿勢で臨みたいと思います。
M様
貸付事業用宅地等はH30.4、特定事業等宅地等はH31.4に大幅に改正され、厳しくなったことを知りました。
贈与-死因贈与-遺贈の関係で、死因贈与は贈与でもあり遺贈でもあるとおっしゃっており、あげるという行為でも様々な種類があることがわかりました。
小規模宅地の特例はよく耳にすることなので、家なき子なども含めて特例が使えるか使えないか、学習して実務に取り込めるようにしたいです。
M様
法律・施行令・施行規則や通達のそれぞれの立ち位置、読み方等の基本的なことや、小規模宅地特例の一部の条文を用語やポイント等の細部まで具体例も交えながら詳しく説明して頂きました。
平成30年に改正された特定居住用宅地等の"家なき子"として扱ってもらうための条件や、姻族関係は離婚によって終了するが、死別・再婚した場合には姻族関係は継続される事など、新しく知った事が多数ありました。
今後案件を持つにあたって有しておくべき知識を得ることができました。
N様
今回は小規模宅地の特例の活用と普段であれば自分が関わることのないものを知ることが出来ました。
内容としては、法令がどのようにして作られて国民に流れていくのかというフローを聞き、今回の特例では、国税庁が法令の解釈や緩和などをしており、解釈一つでかなり適応される対象も変わるため、文言の一つ一つにも注意が必要だと感じました。
一番業務的に入れておくと良いと思ったものとしては、「死因贈与は贈与とも遺贈ともとれる」というところで、どちらにも定義できる可能性があるため、法令や解釈によってどちらに当たるのか、今後その機会がありましたら使っていきたいと思います。
E様
今回の講義では、小規模宅地の特例について学びました。 条文に沿ってその内容を掘り下げていくというもので、特例を適用できる要件を具体的に取り上げていきました。
前回の清田さんの講義と対応していることもあり、前回の内容を思い出すことにもなり、より知識を深めることが出来ました。とても細かい内容でしたので、すぐに完璧に理解することは難しいですが、身につければより小規模宅地の特例に強くなれると思います。自身、資産税グループに配属になり、この特例を使うことは少なくないと思うので、早く理解できるように適時復習していきたいと思います。
I様
前半は税法が施工されるまでの流れと小規模宅地等の特例の基本的な枠組み、後半は条文の読み方とより細かい特例の読み方に関しての講義でした。はじめに説明のあった法令が施工されるまでの流れは、税法のすべてに該当するものなので、それぞれの関係性などを含めて覚えておきたいです。また、1Pの下半分が小規模宅地等の特例の基本的な枠組みであり、実務にも役立てるものと思うので、しっかりと復習して実務に活かせるようにしたいです。後半の条文の講義は、正直ほとんど理解できなかったので、解説等を読みながら学んでいきたいです。
A様
小規模宅地特例について、法令の意味から細かいところまでお話していただきました。 1つの法令にも多くの附属の規則などがあり、その読み解き方からお教えいただけたので他の法令もどのように読めばよいのかが分かりました。細かい事例を話していただきながら通達などの説明をしてくださったのでイメージがつかみやすかったです。小規模宅地の特例は朝礼などでもよく耳にする、相続人にとって利益が大きな特例なのでよく勉強して実務に活かしたいです。
K様
小規模宅地の特例についての内容でした。条文の内容など、やや難しいと感じました。法令の意味や、親族でもどなたが亡くなったのかをしっかり見極めることが大切だと感じました。今回は改めて知識があることはもちろん、親族、という簡単な単語ひとつでも意味をきちんと理解して説明することが必要不可欠だと考えさせられました。
特定居住用宅地等は先生もおっしゃっていた通り難しかったです。特に措令40条は例外があったりしてややこしいので注意が必要だと感じました。広報をやる機会があれば、様々な例外やややこしい部分を分かりやすくお伝えしていこうと思います。
M様
今回の講義では、小規模宅地等の特例を学んで条文の適切な読み方や、解釈の仕方など学ぶことができました。
「家無き子」や建物と家屋の違いなど、今後実際の業務で役立つ用語が多く今回の講義で取り扱われていたため、受講前より条例の読み方や解釈が理解できました。また、今回の条例改正によっての指摘点や「家無き子」の重要な条文の読み替えなど貴重なお話を聞くことができました。今後業務で条例を参照する際に、非常に役立つ内容となり勉強になりました。
W様
今回は法令に沿って小規模宅地の特例を見ていきました。今回初めて、ひと言で宅地といっても小規模宅地、特定居住用宅地等複数あることを知りました。大変難しい話でしたが、今回の講義を少しずつでも理解していけばお客様と会社とをつなぐ広報の仕事に繋がるのではないかと思いました。
講義の中で興味深かったのは、法令内で使用される単語の意味が、普段日常で使用している意味とは異なることでした。法令を読む前に、それに出てくる単語の意味をまず理解、確認していないと法令を誤って理解してしまうことが発生しかねないと思いました。
O様
読むだけでは難しい条文を分かりやすい言葉や図で解説してくださり理解が深まりました。そのため、小規模宅地について興味を持つ事ができました。また、租税特別措置法に関するお話の中で親族かどうかが重要だと強調しておられましたが、親族であるか否かの判断が難しいと感じました。
今後、お客様の期待に応えていくため、また信頼を裏切らないためにも、勉強して知識を増やしたいと改めて感じました。
T様
今回のセミナーでは、法令の読み方をはじめ、小規模宅地の特例まで教えていただきました。
特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地、特定事業用宅地の四種類の宅地の定それぞれに細かくただし書きがあり、どのような状況でどの特例を活用できるかを検討する必要があることが分かりました。
これからは朝礼発表で聞くような難しい土地評価のお話でも、少しでも理解できるように今回学んだことを活かしながら注意して聞いていきたいと思いました。
S様
今回は小規模宅地の特例について学びました。相続の際、「相続人が被相続人と同居していた家」や「被相続人が事業のために使っていた土地」等が問題となることでしょう。なぜならば、残された遺族が暮らせなくなったり、お店や会社でビジネスを継続することが出来なくなってしまい、生活の基盤が大きく揺るぎかねません。そこで、小規模宅地の特例という制度が用意されていることを知りました。
最近は高齢化が進んでいるので老人ホームに入居される方が増えています。入居を考える際に、小規模宅地の特例を知っていると得をすることが分かって良かったです。
また、今回の講義の中で、「同居」の定義が難しいと感じました。今後、民放改正などに伴い、「同居」の定義が変わっていくのかが気になります。
S様
今回は租税特別措置法第69条の4の事例と条文から小規模宅地について学びました。
これからお客様と接していく上で、条文の引用には気を付けなければいけないと感じました。解説書のみや通達・情報のみだけでの判断ではなく2つをあわせて判断していかなければいけないことがわかりました。
また、条例ではいつも使っている言葉でも違う意味になってしまう時があるので一言一言に注意していきたいです。
相続マイスター講座14期 第1講座の感想

税理士によって土地評価の金額が大きく異なることが多々あると初めて知りました。頼む税理士によって損得の差が出てしまうのは怖いと思いました。
税に関しての知識は知らないと損してしまう金額が大きくなってしまうので、自分が損をしないように今後知識をつけていきたいと思いました。
また、税制は毎年変化していくので、その変化についていけるよう勉強していきたいです。
今回の講義では、ランドマーク税理士法人が実際に扱った還付を受けることが出来る例が複数紹介されましたが、現在、相続の依頼を考えている人にも還付を受けられるケースがたくさんあるという事実を知ってもらえたらより良いと思います。 I様

近年税制改正が行われた箇所を、現行と比較し変更箇所を実際の事例を使い説明して頂いたことで、イメージができ理解を深めることができました。
また、実際あった事例を使い、案件ごとに税務署への申告をどれくらいの解釈で判断し、特例などを使って還付や節税を行うことができるかの判断をこれからの業務に活かしていきたいです。 M様

まず、税制改正のお話では、今までの物と今後の改正後のものを比較しながら学ぶことができて、とてもわかりやすかったです。
このように、改正によって変更点があることをお客様にも以前のものと比較しながら説明するとわかりやすく伝わり、顧客満足度が高まるのではないかと思いました。
次に、生産緑地と納税猶予のお話では、今後起こる生産緑地2022年問題について学ぶことができました。
今後起こることはどんなことで、だから今後を見据えてこのように提案させていただきますなどのしっかりとした理由をもってお客様に提案できれば、お客様にこの人なら信頼できると、よりランドマーク税理士法人の信頼度を向上できるのではないかと考えます。 K様
税制改正、土地評価の減額要素、更正の請求などについての講義でした。
税制改正や生産緑地2022年問題に伴う今後の市場の動きについてのお話がとても興味深く、ランドマークの今後の仕事につながる内容だと感じました。
常に市場の動向に注目し、反応していくことが大切だと思いました。
お客様の関心ポイントを意識しながら業務に取り組んでいきたいと思います。
M様
平成30年度の税制改正と更正の請求、農地の納税猶予についての講義でした。
平成30年度で変わった税制のポイントを、税目全てに関して満遍なく押さえることができました。
土地の形状や周辺の環境からどういった場合に評価を減額できるのか、日々の朝礼でも実例は目にしていますが、改めて理解することができました。
生産緑地に関しては、東京オリンピックの後に地価が下落すると言われている中で生産緑地2022年問題もありますので、どのような影響があるのか注目していきたいです。
S様
内容は主に、平成29年、30年度の税制の改正について、更生の請求について、生産緑地と農地等納税猶予についてでした。
今回、相続税の還付について減額できる可能性の高い土地について学びました。
事務所では、今後相続税について還付に触れる機会は必ずあると思うので、事例を含めた説明やホワイトボードでの説明がとても分かりやすく、今後の仕事に活かしていけると思えた内容でした。
今回は初回ということで話の内容についていけるかが心配でした。
しかし、くわしく丁寧に話してくださったおかげで理解を深めることができたと思いました。
相続マイスター講座14期 第2講座の感想

条文内で使われている「等」や「又」がどこまでの範囲を意味しているか、普段何気なく使っている「親族」や「事業」がどこまでの範囲を含むのかを正確に理解する必要があると思いました。
また、読み解いていく上ではあまり難しく考えずに、法律を作る立場となってみることが大切だと学びました。
法令は新しくなった(新しく追加された)所に注目するのではなく、改正前と比べて消された所についても注目することで自分の中で更新していくことができるということを、この講座を通して実感することができました。I様

「家無き子」や建物と家屋の違いなど、今後、実際の業務で役立つ用語が多く今回の講義で取り扱われていたため、受講前より条例の読み方や解釈が理解できました。
また、今回の条例改正によっての指摘点や「家無き子」の重要な条文の読み替えなど、貴重なお話を聞くことができました。
今後、業務で条例を参照する際に、非常に役立つ内容となり勉強になりました。 M様
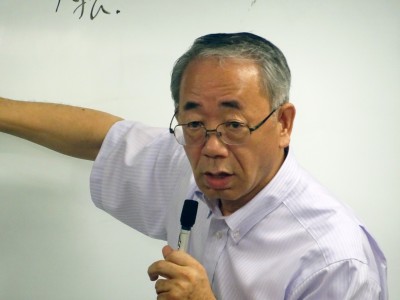
特に一点、業務に生かすことができるであろうことを学ぶことができました。それは、専門用語を誰が聞いても分かりやすく説明できるようにすることです。
この講義では、高橋先生や税理士業界の人の間で使われる専門用語(例えば、書類審査や入学試験)を自分たちはこのような言葉で表現しているが、実際の条例ではどのように言い表しているのか説明していただきました。
このように分かりやすい言葉に直して、それを用いて難しいことを説明することは、お客様に対しての提案の際などにも活かせると思いました。 K様
69-4 1項と3項を知ることで全体像が見えてくるので、内容をしっかり理解することが必要だと思いました。
実際に業務を行う上でも、土地+建物を所有している場合、土地だけ所有している場合、建物だけ所有している場合とで評価の方法が異なっていたので、とても複雑ですが正しい評価ができるように資料から情報を読み取る力を身につけたいです。
括弧が多く使われていて、その号でしか使われない注意書きもあったので、該当場所と別の場所に書かれていることが必ずしも一緒でないことに気をつけたいです。
W様
今回の講義では、条文の読み方について学ぶことができました。
仕事をする中で、分からないこともたくさん出てくると思いますが、そうした時に条文等を調べようとしても、読み方が分からなかったり、読み方を間違えていたりすれば意味がありません。
「建物」と「家屋」の違いや「したこと」と「していたこと」の違い等、一見すると同じ意味だと思ってしまいますが、ちゃんと使い分けられていることが分かり、大変面白いと感じました。
まだまだ未熟な私にはとても難しい講義でしたが、今回学んだことを忘れず、今後の業務そして勉強する際に活かしていきたいと思います。
U様
条文の読み方を中心に小規模宅地の特例について学びました。
小規模宅地の特例については実務でほぼ出てくる論点でもあり、近年の改正論点でもある家なき子特例についても触れられていたので、今後、事務所で出てきたときに活かせるのではないかと思いました。
法令や条文の読み方は実務で仕事をする上で判断材料になるので大切な事だと改めて感じました。
S様
今回は事例と条文を使った講義でした。
まずは、条文の読む上での大事なことを教わりました。そのため、今まで普通に読んでいた本来の定義規定や略称規定について理解を深めることができ、今後、条文関係を読むときに活かしていけると思いました。
講義を通して条文で出てきた多くの単語の意味を解説していくことが多かったですが、法律関係に詳しくなかったこともあり、本講義はとても難しく感じました。
高橋講師は説明の際にわかりやすい例を合わせていたため、すべてを理解したとは言い難いですが、自分にとって知識が増えたことは将来の活動に利用することができると思いました。
Y様
小規模宅地の特例の要件についてとても良く理解することができました。
また、いつも条文から制度を理解することが大事だと再認識しました。
ありがとうございました。
相続マイスター講座14期 第3講座の感想

どの事例でも、ただし書きとなお書きによく注意してから検討することが最重要だと感じました。
また、貸家敷地に併設された貸駐車場は、外から見たときは同じなので、駐車場の使用有無をしっかり確認しなければ評価単位が変わってしまい、そちらも注意が必要です。
評価をする前には、段階を経てしっかり確認することで正確な評価ができるのだと思いました。 K様

近年多いアパート経営の節税対策や複雑な遺産分割の裁決事例も取り扱われており勉強になりました。
また、赤道や青道など農業地域によくある対処方法も取材メモを元に詳しく説明がされ、それに伴った土地評価も具体的に記載してあり参考になりました。
そして、相続での土地評価は複雑な案件も多いと考えられるため、今後の業務に役立つ講義となりました。 M様
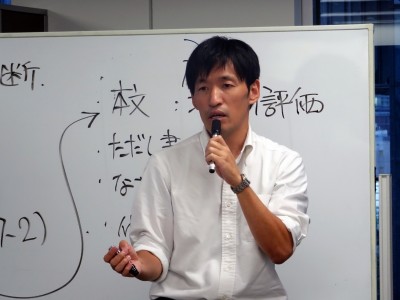
畑と宅地が隣接しているような事例で、一見畑に見えても使用状況によっては地目が変わり(畑として扱わず)、評価も大きく変わってくると初めて知りました。
評価基本通達を読む上では、地目別に評価をし、ただし書き・なお書きの情報を正確に理解することが大切だと学びました。
今後、業務の中で土地の評価をすることが多くあると思います。
たくさんの事例を扱いながら、自分自身で自信を持って評価できるように今日学んだポイントを活かしていきたいです。 I様
評価対象となる土地は、⑴物理的分断、⑵遺産分割、⑶財産評価基本通達の順に照準して評価単位を構築することで、⑶の評価通達についてを中心に学びました。
地目の判別にあたって、裁判やある程度の慣習、常識に基づいて行うと知りました。
また、田中先生の言葉で、事務所ごとに評価についての慣習が異なり、それに従って仕事をしているのが現実であるが、実務をする際は、通達や法律等の判断の根拠をきちんと抑えてほしいというのが印象に残りました。
そのような気持ちを持って仕事に向かいたいです。
U様
今回の相続大学校の講座は、土地の評価区分と評価単位でした。
土地の評価をする時に最初に確認するところであり、まだ土地の評価はほとんどしたことがありませんが、物理的分断、遺産分割通達の順番でまずは考えることを教えてもらい、今後の事務所で活かしていけると思いました。
また、通達をベースに事例を紹介していただき、分かりやすく実務上のことも考えられると思いました。
W様
土地の評価は、区切らず評価するのと2つ以上に区切って評価するのとでは、評価価額が変わると知り驚きました。
区切ることで、細長くて使いにくかったり、道路と面していなかったりするからだと知り納得しました。
しかし、区切ると評価価額が常に下がるかというとそうではなく、とても大きい土地だと区切った方がいい場合もあると学びました。また、宅地になるかの判断基準について詳しく知ることができました。
土地評価は、アルバイトではなく社員になった時に必要になってくる事だと思うので、今回学んだことを忘れず実務で活かせるようにしたいと思います。
相続マイスター講座14期 第4講座の感想

事業承継を生前に行うことで、節税対策や株主の権利関係においても相続事業承継後に問題が起こることがないよう対策でき、ストレス軽減になることを学びました。
また、旧商法と現行の会社法の違いや、会社法施行に伴う相続・事業継承の問題など具体的な事例なども取り扱われ、非常にわかりやすいものとなりました。
私は、現在も多くの経営者が相続・事業継承に不安を感じ対策をしたいという方が多くいると考えており、今後の業務に大きく活かしていける講義となりました。 M様

特に事業承継は専門性が高く、財産権と経営権の2つの問題が同時に起こるため、税法や会社法など幅広い知識が必要になります。
また、事前に対策をしておくことで会社への債権において問題を解消することができます。
事業承継に対して悩む経営者は、自社株、後継者、相続の大きく3つの問題を抱えていることがわかりました。
経営者によって問題は様々なので、いかにニーズに合った提案ができるかがカギになると思います。 M様

相続は個人の話で、事業承継は会社の話で、この二つは税理士の専門分野だということを知りました。
また、事業承継は財産権と経営権の二つの問題が生じ、財産権では株式の評価があり、ほとんどの会社が非上場会社であることから、株式の市場がなく価格が分からないので一定のルールで株式を評価します。業績の良い会社ほど株式の評価が高くなり、また担税力がないといった問題があります。
財産権では税法の知識が必要になり、経営権では会社法の知識が必要になってくることから幅広い知識が必要であり、このことから事業承継がややこしくなっているのだと思いました。
また、相続・事業承継対策は生前にやっておけば必ず効果があるとのことだったので、お客様からこういった話を持ち出された時には被相続人の方がご健在のうちに出来るだけ早く実施するべきだと思いました。 W様
事業承継をきちんと生前に行うことで、事業承継後に起こる様々な問題を減らすことができるので、早めに対策を行うことが大切だとよく理解することができました。
会社法についてきちんと理解しておかなければ、しっかりとしたコンサルティングはできないということを知ったので、実務は一旦つけた知識をどんどんグレードアップさせ、お客様に提案しなければならないと改めて感じました。
また、先生が実務で意識されている雑談をしてお客様に寄り添うという点は、コンサルティング業務でなくても重要なので実践していこうと思いました。
M様
少数株主の対策が必須という点について実務でも悩まれているお客様がいるので、種類株式を活用する事を検討・提案しようと思いました。 ただ、同族法人(不動産管理会社)のため、純粋に株式を買い取る方法についても検討していきます。
事業承継対策については、株価自体が0円となる会社もありますが、株価が高い会社について、対策提案等のコンサル報酬をもらえるように知識を身につけるとともに、実際に試算等で関わっていければと思いました。
I様
相続するには被相続人の意思の合致がかなり重要であるため、信託をして予め対策をする必要があると初めて知りました。
信託する、しないに関わらず、相続の準備は早い段階から始める必要があると改めて思いました。
私も祖母がいるのでとても身近に感じました。
相続マイスター講座14期 第5講座の感想

養子縁組という言葉は聞いたことはあったのですが、どういったことなのかは知りませんでした。
養子縁組はよく相続税の軽減対策になると聞きますが、本来は財産を承継することが目的なのだと知りました。
また、養子縁組は双方の同意がなければ解消することができないと知り、安易に組むのは危険だとも思いました。
また、養子縁組は遺言とセットで効果を発揮するとのことだったので遺言も重要だと思いました。遺言もただ書けばいいというものではなく、判断能力がない時には遺言能力が無いと捉えられてしまうこともあり、せっかく書いた遺言も無効になってしまう危険性があるため、元気なうちに書いておく必要があると思いました。
今回の講座を受けて改めて相続対策は早め早めのうちにしておく必要があると思いました。 W様

自筆証書遺言と公正証書遺言の説明及び養子縁組の捉え方、また認知症の度合いや死亡時期によってそれが有効かどうか左右されてしまう危険性を知りました。
私のお客様でも地主はおりますが、養子縁組は既にされている方も多く、遺言等でも対策を考えられている方が多いです。
結論としては、遺産相続対策は、専門家への相談と事前の準備が非常に大切でした。 Y様

遺言と養子縁組がそれぞれ有効・無効となった場合に、それぞれの取り分がどのように変わるのか、実際に相続分・遺留分の割合を計算しました。ある事例では最大で3分の1も相続分に差が出てきてしまうことがわかりました。
遺言および養子縁組の無効訴訟では、意思や判断能力があるかどうかが裁決の基準であり、実行するタイミングが重要であることも学びました。
養子縁組というと節税対策の一つというイメージが大きかったのですが、財産が分散せず承継すべき人が承継できるようにする手段としても有効であると感じました。
弁護士ではなく、定期的に地主層のお客様と関わりがある税理士が、このような対策の啓蒙活動の担い手になることが必要と小嶋先生のお言葉にもありました。
遺言や養子縁組を「節税」以外の観点から学ぶことができ、大変有意義な講義でした。 W様
今回は、争族について事例を見ながら学習しました。
はじめに扱った事例を通じて、遺言と養子縁組の有無により取り分がどれ程変わってくるのかがよくわかりました。
FPの勉強の中で公正証書遺言については少し知っていましたが、公証人と作っても遺言無効になることがあると初めて知りました。自分の取り分を増やす為に、養子縁組をうまく利用する人がたくさんいることも学びました。一方で、養子縁組をした被相続人が、養子縁組が何なのかよくわかっていないケースも少なくないと知りました。
相続は大きな資産が動く大切な瞬間であると同時に、その資産を左右する力を持っている遺言や養子縁組の重要性を理解することができました。
M様
遺言と養子縁組を有効利用して、節税や「争族」の相手方の取り分を減らすことで、遺産の分散・分割を最低限に防ぎ、代々続く家を守ることができる、という事を12の事例を用いて判例や法改正後のことも交えて説明していただきました。
相続対策の一環として遺言や養子が有用だとは前々から知っていましたが、遺言の有無・公正証書遺言かどうか・養子縁組のタイミング等で取り分が数十%異なるとは予想外であり、為になるなと思いました。
U様
今回の相続大学校は遺言や養子縁組についての講義でした。
まだ実務では遺言は見たことがありませんが、自筆証書遺言や公正証書遺言は何かという事も分かり勉強になりました。
改正により自筆証書遺言の緩和や寄与分についても少し学べたので実務で役に立つと思いました。
また、遺言と養子縁組によって節税対策だけではなく遺留分請求の話も繋がるとこが学べ、難しい話でしたが、今後のお客様対応に繋げられればと思いました。
O様
よく養子縁組で基礎控除枠が増えると提案等を行いますが、遺留分対策であったり、財産を守ったりという観点からは考えたことが無かったため、とても勉強になりました。
今回小嶋先生が色々なパターンで争族の実例をお話ししてくださったので、今後、相続で関与であったり月次で関与するお客様だったりに向けてお話しできるようにしていきたいと思います。
I様
相続をめぐって争いとなった事例を、遺言と養子縁組にポイントを絞って、紹介と解説がなされました。
全体としては、自身の経験話をされていたという印象でした。
お話としては面白いと感じましたが、もう少し全体を俯瞰した立場からの解説やまとめがあればよかったと思いました。
K様
今回は先生が実務をやりながら感じた弁護士ならではの視点もお話してくださったので、非常に分かりやすく興味深かったです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いなど細かいところも丁寧に説明してくださったので、知識がない私でもきちんと理解することができました。
養子縁組は適任者をしっかり選ばなければいけない等、気を付けなければいけないことがたくさんあると感じました。
M様
相続の争いにはどのような種類があるかをたくさん知ることができました。
相続税の計算でもたまに使われる養子縁組も、税法と民法では使い方が変わってくることが分かりました。
また、遺言を作成する際に、被相続人になる方がいつ亡くなってしまうかによって、法廷で争う場合に勝てるかどうかが左右されるのは大変だなと思いました。
前回講義を受けた時よりも、遺留分減殺請求の意味等が分かっていたので理解がしやすかったです。
色々な場合を想定した時の相続割合がすぐに計算できなかったので、しっかりと復習したいと思いました。
M様
遺言と養子縁組のケースをいくつか見て、遺言と養子縁組をどのように使うかによって金額の取り分が大きく変わることがわかりました。特に4パターンから配分を考えるワークで理解できました。
また、遺言書作成のための判断能力と遺言の複雑さは関連しているということだったので、難しいものは早めに作成するなどの対策が必要になることも知ることができました。
相続マイスター講座14期 第6講座の感想

納税資金対策方法には、生命保険を活用した遺産分割や生前贈与を利用した生命保険、建物の法人化、土地を活用した相続税対策、小規模企業共済制度を活用した所得税対策、債務の株式化を活用した節税など、たくさんの納税資金対策方法を学びました。
その中でも建物の法人化には間違った法人設立というのがあり、被相続人となるべき親が出資すると法人の株式が親の財産になってしまったり、株価対策必要になってしまったりすることを学びました。
また、相続人となる子供が共同出資してしまうと、不動産を共有するのと同じ状況になってしまったりするので、ただ建物を法人化すればいいのではないと思いました。
本日の講座を受けて、税金にはいろんな種類の税金があるがそれぞれ対策方法があるということを学んだので、今回得た知識を確実に定着させて、これからの業務でお客様にとっての最善の対策を提案していければなと思いました。 W様

後半は、税務調査に関する講義で、税務調査がきてしまうと高確率で追徴課税が発生するため、いかに税務調査が行われないようにするか実例を交えながらの講義でした。
その中で、納税者だけでなく、税務署側の立場になって進めていくことで税務調査のリスクを減らせるということを学びました。
納税資金対策は、コンサルの腕によるところが大きいので、今後活かせるようにしたいです。 I様

後半の税務調査については、知識がまだほとんどないため難しいと感じたところもありましたが、最後の相続税税務調査がこないようにするための5つのポイントがとても分かりやすかったです。
調査官と納税者の両方の立場に立って考えることで、税務調査がくることを防げるということがよく理解できました。
改めて、実務は財産管理を誰がしているかだけでなく趣味など細部までしっかり検討しないと成り立たないものだと感じ、今後実務をすることがありましたら活かしていきたいと思いました。 K様
今回の講義では、遺産分割や納税資金対策・土地活用の正しい節税方法などを学ぶことができました。
また、生前贈与では、贈与を行なった証拠を残すことや暦年贈与と相続時精算課税制度の詳しいメリット・デメリットなど知ることができました。
そして、税務調査事例も具体例を元に取り扱われ、税務調査官に指摘されないような書類作りや添付資料を付けること、調査官と納税者の立場に沿って問題点をおさえ解決していくこと、お客様との信頼関係の重要さを教わることができました。
K様
相続対策には、分割対策、納税資金対策、相続税評価引き下げ対策の3つがあることを学びました。
また、遺言書をつくるメリットについても学ぶことができました。
税務調査では、十中八九追微課税の結果になっているということで申告漏れが数多くあるということに驚きました。
I様
今回の講座では、公正証書遺言を作成することがいかに重要なのかがわかりました。
知人から、法的に作成されなかった遺言が原因で遺産の相続がとても面倒だったという話を聞いたことがあります。
確かに遺言を作成するのは時間や手間がかかりますが、後のことを考えるときちんと作成しておくべきだと思いました。
私の親戚も遺言について考えているので話し合いをしたいと思います。
M様
納税資金対策の有効な手立てとして生命保険が挙げられていました。
預貯金を保険金に変えておくことで遺産分割の対象にならないため、保険金を財産として子孫に残す人も少なくないそうです。
税務調査を来させないようにするために、調査官と納税者の2つの立場に立った5つのポイントが勉強になりました。
幅広い知識はもちろん必要になりますが、お客様が何を求めるかをくみ取れるように仕事をしていらっしゃるとお聞きしたので、常にお客様目線で考えられるようになりたいです。
相続マイスター講座14期 第7講座の感想

実際にあった事業承継の成功例と失敗例を幾つかお話しして頂きました。その中でも一番印象に残っているのが、老舗繊維会社の株式買取りの成功例です。
この会社は、現社長の病気が発覚して事業承継を検討し会社分割や会社分社等検討したものの折り合わず合同会社を設立し株式を買い取ったという事例でした。
私は、この事例を通して学んだことは、株式投資をする場合には個人で投資するよりも会社で投資した方が良いということと、非上場会社の場合は、業績がいい会社ほど株式の評価が高くなるため自社株買いをしない方が良いということです。
本日の講座で得た知識は、事業承継をする時に知っていないとお客さんが損をすることになるかもしれないので、この知識があるかないかでお客さんからの信頼度も変わってくると思いました。
この講座で得た知識は事業承継の際に是非活かしたいです。 W様

株をたくさん保有している会社が事業承継をするとき、その保有している株や、事業承継を目前にしてはじめて目を向けた持て余している財産などをどのように扱うかで支払う税金が大きく変わってくると学習しました。また、プロに事業承継をお願いしても長期化することもあると初めて知りました。
少子化や人手不足によって、今後、後継者難はますます増え事業承継も難航するのかなと思いました。
講義を受ける前は、事業承継がうまくいかない会社は廃業するしかないと思っていましたが、廃業するのも簡単ではないことがわかりました。M&Aの失敗事例を扱い、事業承継の準備は余裕をもってする必要があると感じました。 I様

この場合、相続税の申告は2カ月短縮され10か月が8か月となるので注意が必要です。この点は実務に役に立つことであり、参考になりました。DESを行う場合、資本金が1億円超になれば中小企業の優遇税制が適用できなくなり、増資後すぐに減資をすると租税回避目的となるので、2~3年は間をおくことにする必要があるということは実務に役立つことでした。中小企業対象の納税猶予も適用できなくなるので重要なことです。 Y様
今回の講座では事業承継の実務について事例を通じて学びました。
印象的だったことは、事業承継の際には後継者の問題と納税の問題が生じており、昨今の少子化や、子供が事業を継ぎたがらないという理由からくる後継者不足と、株価の評価・承継、企業価値評価から来る税金の問題に悩まされている、ということです。
横川講師には、これらの承継の問題に対して有効なM&Aや組織再編について説明していただきました。今までの生活からでは知ることの無かった、中小企業の現実や悩みを実務に当たる方からお伺いできてよかったです。
今後、仕事の際にお客様の目線に沿った考えを持つ為の一助になるのではないかと思います。
M様
事業承継は会社の相続ともいえるもので、現代では後継者や納税が大きな問題となっていることがわかりました。
実際に事例を見ていくなかで、同族後継者の事業承継が減少していたり、経営者の平均年齢の上昇も問題になっているということを感じることができました。
Y様
徐々に景気が回復している昨今、中小企業の倒産件数は減少している一方で、休廃業・解散件数は増加していることが興味深かったです。現在の少子高齢化問題も相まって、今後も需要が増えると予測される事業承継対策を学習することは重要性がとても高いと思います。
今回の講義では、後継者がいない場合や複数いる場合の円滑な運営のための様々な成功事例と共に時間がひっ迫した中での失敗事例も学べたので、今後のステップアップに活かせると思います。
S様
今回は、事業承継の事例をM&A、組織再編、持株会社、経営承継円滑化法に分けての説明でした。
今日では、会社引継ぎを行う際に少子化や息子が継ぎたがらないといったための後継者問題や納税の問題が重くのしかかっていることがわかりました。また、会社分割の2つの型を紹介してもらい、分割型、分社型の違いについて知ることができました。
今回の講義で会社の株主構成や先代社長の家族構成については事業承継の時に大切になること、相続税の納税猶予制度もしっかり確認しないと後に問題となる可能性があるため、今後関わることがあった場合はしっかりと確認していきたいと思いました。
M様
今回の講義では、事業承継について学びました。
近年、中小企業の休廃業・解散が過去最高となっていることからM&Aの重要性について知ることができました。
そして、中でも利益は大きい会社が多いということが印象に残りました。また、M&Aによって従業員の理解や協力・そして承継していく会社がどのようにして経営していくかが重要となることがわかりました。
今回様々な事例を聞き、私もそのような業務に携わる場合は、両会社とも時間をかけて協議し、双方の納得いく事業承継をしていきたいです。
相続マイスター講座14期 第8講座の感想

消費税の還付を受けるためには、個人あるいは法人が課税事業者でなければなりません。そのため、課税事業者でないものは「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。これを提出すれば、2年間は消費税を納めなければならないものの、過大に申告した分の還付を受けることができます。その後、課税売上割合を100%にしないために自販機や駐車場などを設け、非課税売上の賃貸料だけではなく、課税売上も計上することができます。そうすることで、課税売上割合が95%以上かつ課税売上割合が5億円以上でない限りは課税事業者となります。そして、消費税の還付申告書を提出してから3か月後に還付金が振り込まれます。
注意点としては、課税事業者である間に新しく建物などの高額な資産を取得した場合、課税売上割合が大きく変動する可能性があり、変動率が5%以上かつ変動差が50%以上だった場合は還付金が没収されてしまうこともあるため気をつけなければなりません。課税売上割合の計算上、自販機だけでは課税売上を増やすことができないため、金の売買を行うことで課税売上を増やし、建設時に発生した分の消費税を還付する方法があると学びました。
今回の講義では、自身の消費税法の知識を復習するいい機会になり、また実務でも使えそうな節税のスキームを学ぶことができました。これからも消費税法を勉強していく上で、適切な節税を行うためにはそれに従った経験、知識が必要だと感じました。 E様

還付金を没収されないように自販機や駐車場で課税売上をするということや、調整計算に引っかからないようにするなど、還付金を得るのは大変だと分かりました。
厳しい税制改正により、金の売買をして調整計算を免れるようにしたり、不動産を所有するなら個人より法人の方がいいなど学ぶことがたくさんありました。
消費税は、損害賠償を請求される件数が1番多い税金なので、勉強をしつつ、分からないことは確認するようにして、お客様の相談にのれたらと思います。 W様
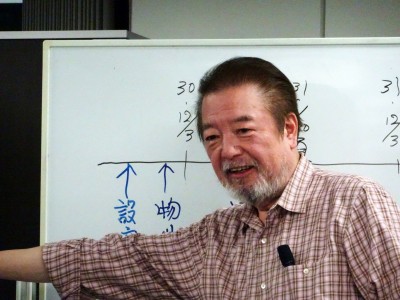
消費税自体は昔から知っているにもかかわらず、消費税還付制度は全く身近でなく、本講座で習った全てが新しい知識となりました。
消費税還付制度について特に大事な仕組みが調整計算というものです。この調整計算という規定の適用を受けた場合、折角受け取った還付金が没収されてしまいます。
どのような場合に調整計算に引っかかってしまうのか、細かい規定があるため正確な知識のインプットが必要だと思います。 Y様
損害賠償請求がもっとも多く、税理士にとっても怖い税金である消費税を、どのようにして還付してもらうか、実例や時系列等を整理しながらの講義でした。
なぜ相続大学校で消費税を学ぶかについては、消費税還付で恩恵を受けるのはより資産を持っている顧客であり、消費税還付を切り口に獲得し、きたる相続の際につなげるというものでした。
実際に消費税還付のコンサルティングを行うのは難しいかもしれませんが、それを踏まえた法人設立の提案など、つなげられることは多いように感じました。
U様
今回初めての消費税還付ということで丸の内相続大学校を受講させて頂きました。
消費税の基礎から自販機スキーム、金取引による消費税スキーム、また、届出関係の改正の期限が大切等幅広く学ばさせていただきました。
特に、課税売上割合を調整するために日割り家賃や礼金を放棄するかまたは月割りにすることは大切であり、消費税還付を受けるためにお客様への提示として事務所で活かせると思いました。
消費税還付は法人が有利な点なども、法人のお客様を担当するようになったら常に考え提案していきたいと思いました。
相続マイスター講座14期 第9講座の感想

土地の公的価格には、時価・地価公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税路線価・競売価格があり、それぞれ、不動産業者、国土交通省HP、国税庁HP、資産評価研究センターHP、地方裁判所東京目黒出張所で確認できるということを知りました。
また、鑑定評価の方式についても学びました。取引事例比較法と収益還元法と原価法があり、取引事例比較法は対象の物件と同等の条件を比べ、取引事例を考慮して評価する方法で、収益還元法はその物件の持つ将来的に見込める利益を考慮して評価する方法で、過去に運用した実績も参考にし、収益を基に考えるので事業に関した不動産に適している方法です。
原価法は、もしも建物を最初から立て直したらどのくらいの費用が掛かるかという点に基づいて評価する方法だということを知りました。
今回の講座の内容は難しかったのですが、知っていれば絶対に実務で役立てられることばかりで、実務で相続に携わることの多い弊社では、実務において今回の講座で得た知識はとても活かせると思いましたし、今回得た知識が無駄にならないように活かしていきたいと思いました。 W様

土地や不動産の価格は、アンケートを集計した結果をもとに作成された土地総合評価システムで誰でも見ることができると初めて知りました。
最近、引越しを検討していて色々な家を見ていますが、家の価格はあらゆる基準・情報・事情などを考慮して考えられているのだと実感します。価格に正解はないし、多様な見方ができるので、土地や不動産の価格を決めることは難しいと思いました。そのためにも一定の基準をしっかり決めておくことは大切だと思いました。
また、高低差の評価減については、よく朝礼で検討していますが、似たような件はあっても全く同じものはないので、これから業務にあたるうえで慣れていきたいと思います。 I様

財産評価の中でも土地の評価は難しく、減額できる土地の要件や時価の概念を教えていただきとても勉強になり、今後の事務所の仕事で活かせると思いました。
特に、高低差がある場合の減額は3mを目安に考えるという事も学び、その点も利用できると思いました。
また、相続税路線価は約時価の8割であり、固定資産税路線価は約時価の7割という事や、特定路線価は固定資産税路線価を基に決定されていることも、今後の事務所での10万円パックの試算などで活かせると思いました。 U様
今回の講義では、公的評価について学びました。
公的評価は、資料の中にも様々な鑑定評価方式があり、鑑定評価書として全て記載され、大まかな意味も知ることができました。インターネット上に不動産取引価格が地域別に掲載されていることもわかり、今後の業務に関連してくる内容となりました。
また、固定資産評価の問題点もいくつか取り扱われ、具体的な内容で説明していただき、理解がしやすい内容でした。
土地の高低差の評価減については業務でも特に取り扱う事例が多く、非常に業務に役立つ内容となりました。
M様
土地評価の業務の際、路線価や公示価格など耳にしていたことのポイントをそれぞれ詳しく知ることができました。
評価の方法は他にも基準値評価、競売価格などがあり、価格の算出の仕方や発表される時期が異なっていました。
また、評価は机上で見ただけでは本当にその情報が正しいかどうかはわからないので、現地・現場・現物での細かい調査が必要になるとおっしゃっていました。
Y様
土地評価のために用いられる書式がかなり細かく記載されていることが印象的でした。
土地の住所や形状などといった一目見て分かるものの他に方角によって価値が異なるなどの知識がなければどのように解釈すればいいかわからないものも多いので知識のインプットが必要だと思いました。
また、アルバイトをして初めて耳にした路線価も学ぶことができ、地価に対する理解がより深められたと思います。
S様
知っておきたい公的評価として時価公示価格、基準値価格、相続税路線価、固定資産税路線価についてや、市街化調整区域の土地評価、宅地の評価、雑種地について学びました。
講義のなかで高低差の評価減についての話があり、いくつかのパターンの例で10%評価減の適用が受けられるのかを紹介してもらい、今まで朝礼の際などに聞いていた土地評価の話が、講義では簡単ではあった例ですが、このような内容だということを知ることができ今後の参考になると思いました。
相続マイスター講座14期 第10講座の感想

信託とは、簡単に言うと財産の管理を委託することで、信託をする際には財産を預ける委託者と財産を預かる受託者と利益をもらう受益者がいます。委託者と受益者が異なる人だとみなし贈与になってしまいますが、委託者と受益者が同一人物であれば贈与税などは発生せず、また、財産を信託することによって名義が委託者から受託者に名義が変わることが信託の一番のポイントだと思いました。
今回の講座を受けて、信託を活用した相続スキームは幾つかあり、遺言書を書くよりも遺言代用信託を利用した方が楽なケースがあると知り、これから相続を担当することがあったとき、お客様にとって一番ベストな選択をしていただくためには、信託の知識も必要不可欠だと思いました。
今回の講座をきっかけに、信託の知識を更に深めて実務でしっかりと活かせるようにしたいです。 W様

また、信託をすることで会社を後継者に移転する際にも、受益者を後継者にし議決権指図権を現オーナーにすることで会社の経営権を維持することができる方法は、今後の事業承継に大きな存在となると思いました。
そして、信託をすることによって贈与を行う際にも、委託者が収益受益者である程度の節税効果が見込まれ、信託のイメージが変わった講義となりました。
相続の業務にもお客様に提案できる内容でありましたので、今後の業務に活かしていきたいです。 M様

節税ではなく、「自分の財産を如何に後世に残していくか」と言うことを考える際に使用するツールです。
主に3つの信託活用方法があり、以下のようになります。
①高齢になった親の財産管理を成年後見制度等を利用せずに行う
財産管理としての受託
②遺産を残す人、そして、その次に残す人まで指定できる受益者
連続の信託
③一括で相続させるのではなく、月10万円といった具合に分割で
相続させる遺言書の保管機能としての信託
相談するには、一般的には信託銀行が窓口になることが多いですが、昨今では、信託銀行以外でも許可を受け信託業務を行っている事業者は存在し、内容により、相談先を選ぶことが重要となってきます。
そして、相続対策として信託を検討する際には、”税務”に関わる問題が必ず関わってくるため、ランドマーク税理士法人でも多くの方の相続対策のご相談をお受けした際、お客様のお悩みや問題点をしっかり確認させて頂いたうえで、適切な信託会社をご紹介させて頂くことが可能であると思います。 K様
信託を用いた相続対策について、実務で使える複数のスキームをベースとした講義でした。
基本的には相続対策でしたが、応用することにより相続税対策にもなるということでした。
しかし、学んだスキームで相続税対策をするには弁護士レベルで法を理解してないと難しいようにも感じました。
第4講座と学んだことなども応用しつつ、法人を間にかませることによる相続税対策は多くあるので、それらとともに活用していけたらなと思います。
K様
株式会社と一般社団法人についての違いを学びました。
上場すると会社の情報を誰でも見ることができてしまいます。しかし、財産を信託することにより名義が変わり、上場しても名前が出ないため、そのデメリットを防ぐことができ非常に良いと思いました。
信託は相続税対策にしっかりと有効活用できることがよく理解できました。信託は信託銀行でやるイメージでしたが、今日では様々な場所で信託について相談できるのだと感じました。
他の講座に比べて、あまり知られていない情報が多いように感じましたので、メディアを通してこの内容について理解できる方が増えるといいと思いました。
U様
本日は一般社団法人を使った信託スキーム及び家族信託について学びました。
信託を利用したスキームは実務ではとても重要であり、委託者から受託者に財産を信託すると名義が変わる点や、課税関係で家族信託もできる点などが今後の事務所でも活かせそうと思いました。
また、委託者と受託者が違うとみなし贈与になるところもとても勉強になりました。
信託を活用した新しい相続対策は難しかったですが、自分でも勉強して事務所でも利用できるレベルになりたいと思います。
M様
信託という言葉はよく耳にしますが、基礎知識として仕組みを知らなかったので、今回知ることができてよかったです。
特に、信託の受託者名義にすることによるメリットを、カルビーノ例を用いて説明していただいたので、とてもわかりやすかったです。信託を活用することで財産の名義が受託者へ移りますが、家族信託では形式的な名義変更と理解していても、実際に相応の責任も発生し背負うことになるので注意が必要とのことでした。
S様
信託を活用した相続スキーム事例についての内容でした。
初めに信託と一般社団法人についての基礎知識について学びました。内容にふれ、財産を信託すると受託者の名義が変わり、メリットとして、息子などが株を持っている際などには、信託することによって上場しても名前がでないため、とても良いシステムであると感じました。
今回のスキーム事例を通し、遺言では事実上難しいことであっても、信託を使うことによって遺言に近しい相続の対策ができることが分かりました。
今後、遺言などの相続対策としていい参考になりました。
相続マイスター講座14期 第11 講座の感想

・行審法改正によって「異議」が「再調査の請求」に変更され、不服申立期間が1か月延長されて判断に余裕を持てるようになったこと
を知ることができました。
また、再調査の請求の発生数・処理数が、平成24年度から25年度と、平成27年度から28年度にかけて大きく減少していましたが、現在は徐々に増えてきていました。
処理件数のカウントの仕方も納税者単位で1件ではなく、1人で何件もカウントされる場合もあることが分かりました。 M様

近年の税務調査の動向や件数、税務官のことについて詳しく知ることができました。
また、再調査の請求の発生件数や処理の最新の状況についても、今後の傾向を踏まえながら学ぶことができました。
そして、審査請求の戦略やメリット・デメリットなど具体的に説明がされており、今後最新の裁決・判例など業務に関わることが多い講義内容となりました。
最新の裁判事例や裁決例を読みながら理解を深めていきたいです。 M様

大学のテキストでは、審査請求より取消訴訟の方が細かく説明されていたため、取消訴訟が主流なのかと思っていましたが、今回の講義で審査請求で決着がつくことが大半であることが分かりました。
その理由として、審査請求は訴訟ほど費用がかからず決着までか早いことだと思います。
このように、今までの知識を訂正することができることを経験できたので、大変有意義なものとなりました。 Y様
今回は、税務訴訟の最新動向と審査請求の実務について学習しました。
税務調査のほとんどが修正申告で決着がつく理由としてあげられたものは共感ができますが、争いたくないからという理由で何でも終わらせてしまうのは違うということが分かりました。
納税者が心情的に納得いかない場合や、先例がない場合は慎重に進めていく必要があると思いました。
相続マイスター講座14期 第12 講座の感想
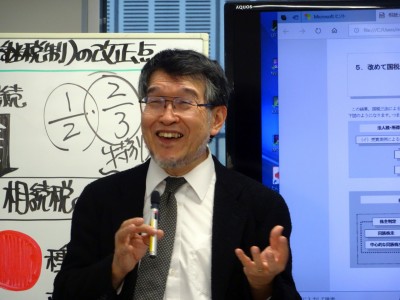
改正により変わった重要な点は、中小企業の株式は実質的に税金なしで相続が可能になったという点です。
これまでは対象株式数にも割引割合にも制限がありましたが、特定の手続きを踏むことにより特例納税猶予が適用され税金を支払う必要がなくなりました。よって、個人の財産などを法人の株式に変えることにより大きな節税効果が得られます。
しかし、税理士事務所側の準備が整っていないことが現状であり、特例承継計画の提出など、勧めることはすばやく、しかし、譲渡を実際に行うことはぎりぎりまでゆっくり行うことが重要です。
別講座の事業承継でも学んだ通り、事業承継のポイントは、なるべく早く行動する点、株を集める点が最重要ポイントなので、そういった提案をしっかりできるように復習していきたいです。 I様

ただ、上場している企業とは違い、時価が分からないため、相続・法人・所得の3つの視点から時価を計算する方法を学びました。
法人・所得の基本通達で、原則的な取り扱いがありますが、実際には売買実例がなかったり、個人では分からないため、原則的な取り扱いは使われず、5つの条件の下「取引相場のない株式」の評価方法が使われていると知りました。
そして、平成30年度税制改正の「事業承継税制」により、10年間、中小企業の株式だけ実質無税で相続できるため、個人企業は法人成りし、個人財産を会社に出資等して株式にする人が増えます。
しかし、そうすると、相続の時に争いが起きやすいため、争いを避けるためにしっかりとした準備が必要だと思いました。
入社したら相続に関わることが多いと思うので、こうした相続税削減の手段は知っておくべきだと感じました。
また、この特例は延長されるのではないか、という観測もあるので、これから注目していきたいなと思います。 W様

中小企業のほとんどは非上場会社であるため、株には株価が無い。
そのため、相続や贈与で株をもらうときに株価がないため評価のしようがない。その時に使われるのが財産評価基本通達だということを学びました。
株式の評価方法には、原則的評価方法と特例的評価方法があり、原則的評価方法は経営者が持っている株を評価するときに使う評価方法、特例的評価補法は従業員が持っている株を評価するときに使う方法だということも知りました。
納税猶予(事業承継制度)は4種類あるということと、今年から先代以外からの贈与にも猶予が使えるということを学びました。
また、先代の死去で贈与した自社株は相続財産に取り込まれみなし相続とされ、猶予贈与税は免除されるということも学びました。
今回の講座の内容は相続の案件が多い弊社ではとても活かせる内容だと思いました。
特に、株式を贈与、譲渡する際には事前にやっておかなければいけない事があるとのことだったので、今回学んだことをしっかり実務で活かせるように知識をさらに深めていきたいと思いました。 W様
非公開株式の譲渡や納税猶予などを学ぶことができました。
今年の税法で改定された非公開株式贈与について詳しく知ることができ、具体的な事業承継の納税猶予期間や納税猶予を使うことで実際の納税額を計算するなど、イメージがつきやすい講義となりました。
そして、株式贈与や譲渡は特に、会社の定款を変更し、役員を登記することが非常に重要だということも知ることができ、非常に業務に役に立つ内容となりました。
M様
相続税と贈与税の申告のために財産評価基本通達があること、納税猶予は相続税・贈与税、一般・特例を掛け合わせた4種類があることが分かりました。
また、特例について認定有効期間内であれば納税猶予を受けることができますが、期間外であると受けることができないので気を付けなければならないとのことでした。
P27で実際に自分で相続税と納税猶予を計算しましたが、とても難しかったです。
相続マイスター講座13期 第1講座の感想
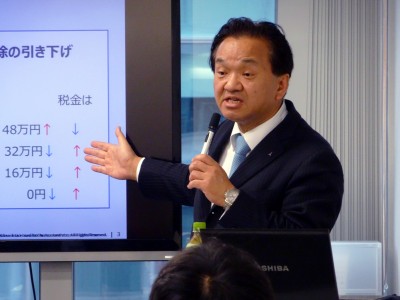
一緒に住んでいることやお金を持っているのではなく、それを駐車場として貸し出すだけで税額が変わるなど、税に関する知識のないお客様は知る由もないと思い、生前にそういったアドバイスをして差し上げられたら…と感じました。
相続時精算課税制度で今後土地の値段が下がり、かえって良くないことになってしまうというのも、こういったセミナーに参加したり、税理士の知り合いがいないと分からないことだと思います。
ですので、お客様にも積極的にセミナーを受けていただきたいと思うのと、私の祖父母は父方も母方も農地を持っていますので、家族のためにももっと勉強に励みたいと改めて思います。
生産緑地についてとても分かりやすかったです。 O様

しかし、人によって解釈が異なる場合があるため、どこまでが妥当な範囲であるか、またどのような土地の分割方法が相続税を低く捉えることができるのか、今後、さまざまな事例をもとに勉強していきたいと思いました。 N様

平成30年度改正では、主に所得税の改正が行われ、所得が比較的低い人は税金が下がり、所得が比較的多い人は税金が上がるということで、実務でもお客様へ説明できるよう理解を深めたいと思いました。
平成29年度税制改正は、相続税の土地の評価の改正が行われ、特に広大地を持たれているお客様の税金を大きく下げられる可能性があると分かり、お客様に提案できるようにしたいと思いました。
平成29年度改正の広大地の問題を受けて、更正の請求が今後増える可能性があるということで、一つビジネスチャンスだと感じました。
お客様によっては大きく還付を受けることができるため、理解しておきたいと思います。 M様
平成29年度税制改正により、様々な変化が起こりました。
具体的には、今までは103万円といわれていた所得の壁が、今後93万円の壁として成立してくるということはとても身近に感じました。
広大地の適用についても大きな変化が見られました。広大地が適用できなかった土地が、広大地の適用を受けることができ、評価を大幅に下げることができました。
しかし、適用できない土地ももちろん出てくるだけでなく、規模格差補正率が上がり、相続税が上がる可能性が出てきます。
また、更生の請求により、納めた税金が還付されることがあり、土地の評価を変えることで還付金も変わってきます。
これは実力次第で変化するので、自分も力をつけ、努力していきたいと思いました。
M様
平成29年度の税制改正により、広大地評価の見直しが行われ、広大地評価は廃止になり、地籍規模の大きな宅地の評価に改正されました。これによりほとんどのケースで増税となりますが、極端な不整形地の場合、評価減になることもあります。
今後、このような特殊ケースに出会うことは少ないでしょうが、評価減になる事実がないか注視したいと思いました。
30年度の税制改正についても実例とどのように影響を及ぼすのか着目し業務にあたりたいと思います。
更生の請求に関しては、毎朝の朝礼にて多様な実例のやりとりがなされているので、各見解と何を用いて何を更生するかを学んでいきたいと思いました。
K様
宅建で勉強していた内容よりさらに深く、土地評価等について学ぶことができ、大変参考になりました。
相続税対策といっても、様々な手法があるということを学びました。
生産緑地、2022年問題については以前からニュースで見ていましたが、この問題によって、どういった影響があるのかあいまいな部分があったので、今回理解することができました。
今後、実務上で使う知識ばかりなので、復習を重ねて身につけたいです。
T様
税制改正により、相続税が上がり、少しでも節税したいという需要が高くなっていると思いました。
だからこそ、専門的な知識を身につけ、お客様に提供できるよう勉強しなければいけないと思いました。
今日の講義で最も興味深かったのは、更正の請求です。5年間の内に土地を見直すことで1億以上還付されるケースがあることに驚きました。
また、生産緑地の2022年問題についても、地価の下落や宅地化など、お客様が相談に訪れる機会も増えると思います。
普段、朝礼で触れる話もありましたが、講義を受け、今後の実務の参考になりました。
H様
毎朝朝礼で発表されている小規模宅地・家なき子や生産緑地の詳細を知ることができ、よかったです。
勉強して知識を増やすことで、朝礼発表の内容を理解できるように努めます。
また、税制改正が頻繁に行われるため、現行の法律を学ぶことだけでなく、ニュースに目を向けることも心がけようと思います。
建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地が評価額半減となったり、家の上に高圧線がある場合、最低1割減となるなど、多額の税を減額できる方法があるにも関わらず、意外とそのままの評価で申告している土地が多いという話に驚きました。
お客様は細かい税制や節税対策について詳しくないため、自分がしっかりと勉強することで、お客様のお役に立ちたいと強く感じました。
また、税は申告したら終わりと考えていましたが、更正の請求や生産緑地解除など、常に油断できないことが知れました。
I様
朝礼発表で、広大地や小規模宅地などの使用について話し合われているのを見ています。
資料を見ても分からなかったり、正直、どのような結果になったのか分からないものもあったのですが、広大地評価=潰れ地が出るかどうかで、潰れ地がでたら比較的評価額が低くなることが、大変よく分かりました。
大学校の第一講座を受講したのは2回目ですが、前回よりも理解でき、大変勉強になりました。
また、更正の請求を中心に行っている他の事務所もあるというほど、還付される可能性の高いものも広大地評価の見直しであり、あえて当初からリスクを取ってギリギリのラインを攻めるより、後に違う税理士先生の方に更正の請求をしてもらうというような様々なやり方があり、おもしろいと思いました。
土地の評価は、税理士や税務署、人によって様々なので、頭を使って、最適な評価方法を見つけるのは楽しそうだと思いました。
勉強していきたいです。
S様
入社以前、大学や資格講座を通して税法を学んだことはありましたが、農業や相続税、また、実務に即した講座を聞いたことが無かったので、これまでとはレベルの違う講座で、とても興味深かったです。
特に、税制改正において広大地を扱った際お話されていた、税務署や税理士によって相続税が違う点、相続税の還付を扱った際にお話されていた、減額できる可能性が高い土地の事例紹介が実務的で興味深かったです。
一方で、自分の税についての知識の少なさを痛感したので、知識を深め、現代の税制に対応した最適な判断をできるよう努めたいです。
I様
税制改正により、こんなにも影響が出ることを知らず、驚きました。
時代の流れに素早く反応し、対応することで、顧客のニーズに応えることができるようになるのだと思いました。
毎朝の朝礼でよく出てくるワードや議論の内容が、今回の講義で少し理解できたように思います。
今後も日々勉強し続けなければならない業界なのだと改めて思いました。
生産緑地2022年問題は、これからすぐにやってくるので、とても身近な問題だと感じました。
M様
今まで朝礼で耳にした広大地や更生の請求のお話を今回詳しく聞くことができてよかったです。
また、業務でたまに耳にする市街化区域や調整区域の話も聞くことができたので、よかったです。
広大地については、適用されると良いことばかりなのかと思いきや、増税につながる場合もあるのだと理解しました。
市街化区域については、新横浜や市が尾の駅近くが調整区域で、住宅でなく、病院や税務署が多いということも聞けて、理解しやすかったです。
生産緑地など、今後、関わりのある問題が起こってくるので、関係のありそうな新聞記事やニュースには目を通すようにしていきたいです。
O様
税制がここまで大きく変わるということを知りませんでした。
時代の流れや現状を把握した上で、改正された税制の知識を身に付けていく必要性を感じました。
知識を踏まえることで、1億円以上の節税が可能になることもあることに驚き、土地の価値が一通りの方法では決まらないということが深く理解できました。
相続税の値段というのは、税理士の実力差が顕著に現れることが分かりましたし、知識を付けた上でそれを状況に合わせ応用していく必要があるため、経験も必要不可欠であると感じました。
我が社が秀でている広大地評価に関する知識は特に身に付けていきたいと思います。
T様
本日の講義は近年の税制改正のポイントについて学ぶものでした。
所得税、資産税の改正ポイントについて、今後何に着目すべきなのか、どの様な事例、要件に注意していくべきなのかということについて大変分かり易く解説して頂き、理解することができました。
特に、本年度からその制度が大きく変わる地積規模の大きな土地の評価については、今後の業務の中で大いに関わってくるものであり、きちんと習得することが出来るようにしようと改めて意識しました。
又、生産緑地についても、将来的に確実に自身の業務に関わってくるものであり、充分に理解して、きちんと説明することが出来るまでにしていこうと感じました。
相続マイスター講座13期 第2講座の感想

一見難しい文章に見えても、単語の意味を噛み砕いて解釈していくことで、あらゆる場面でも対応できるルールとなっていることが分かり法律のおもしろさを感じました。
父と子が二世帯住宅や、隣同士・上の階で暮らしているときに、どのような状況なら小規模が使えるのかを理解することができました。
「家屋」と「建物」という言葉の違いについて、H25年までは「家屋」で同居でないといけなかったのに対し、H26年以降は「建物」の中で行き来ができない別居でも認められるようになったということを聞きました。
条文の中の短い単語の裏側に新法の成り立ちの意味が沢山含まれていることを知り、今後勉強していく上で表面をなぞるだけでなく、細かい部分に疑問をもち不明瞭な部分を消していくことが大事だと学びました。 M様
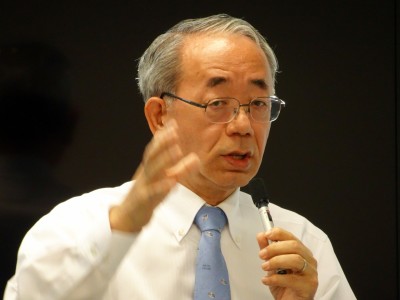
レジュメやお話の中で、難しい言葉が出てきた際、わかりやすくするために、自分で考えた簡単な用語に置き換えていたり、改正前と改正後の違いを簡単な事例とともに紹介していただいたことで理解が早まりました。
小規模宅地の内容だけでなく、こういった話し方の手法も、相続などについてあまりよくわかっていないお客様を対応させていただく際に活用できると思うので、覚えておきたいと思います。 S様

見た目上は親戚関係のような間柄でも、後妻の子供で養子縁組をしていない場合などは適用できないなど、実情に惑わされず「親戚」という言葉の定義に基づいて判断しなければならないという事例には危機感を感じました。
実際に相続人や関係者の方々と面会した際に、窓口になっている方や話の中心になる方が相続人ではないこともありうるため、よく家族関係を理解して、適用の可否を判断しなければならないと思いました。
また、配偶者以外の場合には居住要件や事業継続要件が厳しく定められており、これらの要件をすべて満たしているか確認することが重要であると改めて認識しました。
特に、貸付事業用は今年からより要件が厳しくなるということで、再度新しい要件を復習して、今後の業務に活かしていきたいと思います。 M様
今回の講義では、小規模宅地の特例の活用ということで、特例を使用できる場合と使用できない場合の具体例を踏まえて講義頂きました。
小規模宅地の特例の使用をする場合、適用要件をすべて満たさないといけないことや、申告後の修正を行うことが出来ないなど、条件が厳しく使用するのにはしっかりした調査と吟味が必要ということがわかりました。
また、使用が難しいからと特例を使わず申告して、後々小規模宅地特例が使用できることがわかり、高額な損害賠償を支払わなければいけなくなったケースも有ることを教えて頂き、お客様に最初から特例を使用できるとお話はしてはいけないけれど、使用できるかどうかの吟味もしっかり行わなければいけないと思いました。
特に、相続対象家屋の居住者が親族なのかまた何親等内なのか、以前親族が所有していたことは無いかなどが重要になってくるので、間違ってはいけないと思いました。 また、法令が何よりも絶対なので条文をしっかり読み、またその際にもそれより以前の項目で規定されており含まれていないかなどの確認は怠ってはいけないと学びました。
I様
小規模宅地の要件はたくさんあり、厳しいものだと思いました。
平成22年から親族でないと適用不可で、親族の範囲が厳しくなってしまいました。
あまり聞かないパターンだと思いますが、自分の父と義父が同じ敷地、しかし別の建物に住んでいても親族とはみなされず、高校生ぐらいの孫が両方を行き来していなければならないなど、生前対策をきちんとしていなければならないことが多いと思いました。
家屋と建物は違うなど、同じように思えますが、違う意味のものがあると今回の講義で改めて気が付きました。
自己判断や間違った認識で何か起こってしまうのは怖いので、確認を怠らないようにしていこうと思います。
Y様
小規模宅地等の課税の特例については、各種要件がとても重要だと思います。
適用可能かどうかの要件チェック表や実務上のチェック体制があるといいと思います。
親族の意義、特に6親等内の血族と3親等内の姻族については担当者はしっかりと確認する必要があると思います。
家なき子については、同族会社の所有に係る家屋に過去一度も居住したことが無い事等、要件がかなり厳しくなりました。
租税回避に該当するような事件が多々あったのだと推測しますが、当然弊社としてはそのような誘導はせず、純粋に該当するかどうかを判定していかないとならないと感じます。
また、3年以内に貸付事業開始の場合は貸付事業用の適用がないこと、事業的規模でないと貸付事業用宅地等に該当しないなどの要件は、弊社の顧問先には大変関係のある改正であるため、担当者は顧問先へ早めに対策を講じる必要があると思いました。
上記の改正を踏まえ、小規模宅地等の課税の特例は納税者にとっては大きな減税要因であり、しっかりと勉強し今後の業務に活かしていければと思います。
M様
小規模宅地の特例は親族のみが受けられます。
例えば、結婚相手の連れ子とは離婚した時点で親族ではなくなるので、連れ子は特例を受けることができません。
また、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思(姻族関係終了届を役所に提出)を表示した時も同じ、どこまでが親族なのかをしっかりわかっておく必要があると感じました。
被相続人が老人ホームで所有権や終身利用権を取得していたとしても、自宅を貸し出していなければ小規模宅地の特例が適用できます。被相続人が住んでいなくても特例を適用できる場合があるので確認が必要だと思いました。
M様
今回の講義では、小規模宅地における条文の読み方や、同じ言葉でも条文が違えば意味が異なることがあるということが勉強になりました。
小規模宅地は課税価格の特例であり、高橋安志先生が名づけるところの「書類審査」、「入学試験」、「卒業試験」を通過した(措法の要件を満たした)ものが適用できる制度であることがわかりました。
これは言い換えれば、要件を満たしていないものについて適用してはいけない制度ということであり、慎重な判断が求められる制度です。
事務所の方針上、小規模宅地の制度を用いての計算は、他の基本的なシュミレーションの計算が終わってから行うこととなっているため、急いで行うことはないと思いますが、行う際には慎重に要件を確認しながら行いたいと思います。
また、条文上の「建物」と「家屋」の解釈の違いについてのお話には驚きました。
「建物」はいわゆる建っているものそれ自体であり、「家屋」は建物のなかで人が住んでいる単位であるというような内容で、大変参考になりました。
しかしながら、同じ制度について書いてある条文でも、法令なのか通達なのかでは解釈が異なることがあるため、予備知識があったとしても読む際には注意して読みたいと思います。
O様
今回の講義では、言葉の意味を明確に理解することの大切さを学びました。
例えば、家屋と建物はそれぞれ違うものを示していることなどがありました。言葉が異なることによって別のものを意味することになり、相手との意思疎通が取れない原因にもなってしまうので、言葉を選ぶときは誤解がないように的確なものを使うように心がけたいと思いました。
また、親族関係について理解できるようにしたいと思いました。
六親等内の血族が親族であることや三親等内の姻族は誰までが入るのかを十分に理解することが大切だと思いました。
これらは、同居の仕方により小規模宅地が使えるか使えないかの判断材料になるので、親族を正しく解釈できるようにしていきたいです。
O様
小規模宅地の特例を活用できる場合、できない場合の具体的な事例を学びました。
親族や姻族関係にまで及ぶ話を聞くことができ、より実用的でした。
また、宅地等の名称にもいろいろあり、その名称が何を指すのかということも意識することが重要であると思いました。
特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等というものは特例対象宅地等というものに置き換えることもでき、実際の実務を行う上ではこれらの言葉をしっかりと意識して使い分けることによってお客様にもわかりやすく説明できるのではないかと感じました。
T様
小規模宅地の特例を中心に法令の条文解釈、用語理解を学ぶ内容でした。
使用されている単語が違う場合は勿論のこと、同じ単語であったとしても定義規定や括弧書きによってその意味を変えることがあるため、法令条文解釈は多大な注意を必要とするということを改めて学びました。
租税法上、税務職員の発言に対する信義則の適用が極めて限定されること、解説書その他の解釈が必ずしも正しいと言う訳ではないと言う点からも、法令条文と、その正しい解釈が必要であると言う事についても改めて意識しました。
資産税分野は、扱う金額が大変大きいと同時に、特に広大地評価や本項で扱った小規模宅地の特例等、その運用に大なる注意を要するものも多いため、特に気を付けて今後の業務に当たって行こうと思います。
O様
法令や施行令において文言が少しでも異なれば、意味や指し示すものが異なること、定義が重要であることがよくわかりました。
特に小規模宅地の特例では「親族」でなければ適用することができず、その親族の定義にあたるのは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族だとおっしゃっていましたが、その中でも姻族の場合には縁を切ってしまえば姻族でなくなると同時この親族にも当たらなくなり特例が使えないということになるので、お客様の関係性を正確に把握することがまずは大切だと思いました。
また、拡大同居もよくある事例だと思うので、改正前、改正後のお話を聞けたことでより理解が深まりお客様に説明ができそうです。
W様
以前にも相続大学校で高橋安志先生の受講したことがありました。
その時は入社当初で小規模宅地の名前すら聞いたことがなく、内容の理解ができませんでしたが、今回は実務で小規模宅地の特例を適用する機会があったため、内容の理解ができました。
書類審査・入学試験・卒業試験の流れがわかりやすく、細分化して適用要件を確認することで、事務所内でミスを防げるようになると感じました。
広大地のようにフローチャートがあるとさらにわかりやすく、誰でも要件を確認できるようになると思います。
用語の意味の解説内容が多く、事例はたくさん話していただいたのですが、あまりイメージができなかったので図があるとさらにわかりやすかったです。
改正の内容をもっと聞きたかったです。
S様
以前にもこの研修を受けさせていただきましたが、今回受講させていただくまでの間に実務でも小規模宅地の特例を適用した相続に触れさせていただく機会がありました。
私が関わらせていただいたものは特定居住用宅地で特に論点となるようなところがあるものではなかったのですが、適用できたおかげで税額を大幅に減らすことができました。
小規模宅地の特例の重要性がよくわかりました。
小規模宅地の特例を適用できるかは、しっかりと条文を読み解き理解することが必要と学びました。
「建物」と「家屋」の違い、「親族」の範囲などを例に教わりました。
どれも難しい内容でしたが、これらをしっかりと理解しておかないとそもそも論点となるところを見逃してしまったり、本当は適用できるのに適用しないで申告してしまったり、またその逆もあったり、すごく重要だと感じました。
今も実務で調べものをすることがありますが、なかなか意味が入ってこないものもあります。
条文は読みづらいですが、繰り返し読むことで練習をしてしっかりと理解していきたいと思いました。
相続マイスター講座13期 第3講座の感想

特に今回重要なポイントであったと感じたことは、どんな対策も「生前」に行なうことで最大限の節税につなげられるということです。
社長は返してもらうつもりもないお金であったとしても、 事前に債務免除しておかないと相続税がかかってしまうだとか、名義資産や名義株の問題、定款の変更による議決権数の操作など、制度的な問題もありますが、当事者しか知らないことというのは亡くなってしまった後では本当に闇の中になってしまうので、事実関係を正確に確認しておくきっかけとしても生前対策の重要性がもっと広がってほしいと思いました。
また、これから社会のIT化が進む中で会計業界もAIに仕事を取られてしまう可能性が否めませんが、池田講師のおっしゃっていた、それぞれのお客様にあった真のオーダーメイドサービスという点では、コンサルティングの側面を持つ仕事は人にしか成し得ない部分がきっとあるはずというお話が心に残っています。
営業方法に関しては、お客様にこちらから月次から事業承継、遺言、相続…などふくらませて提案していくことが必要で、そのためには、お客様のニーズ=困っていることを、現状を分析することで把握することが重要だとわかりました。 O様
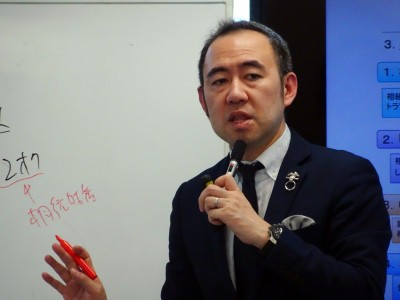
私はこれまで、相続は「資産を受け継ぐこと」で、事業承継は「事業を受け継ぐこと」という漠然としたイメージでしか相続と事業承継を捉えていませんでした。
しかしながら、今回の講義でその漠然としたイメージが具体的なイメージとして固まりました。
相続は、個人から「財産権」を受け継ぐものであり、事業承継は、法人から「財産権」と「経営権」を受け継ぐものです。
事業承継は経営権の承継がある分、より多くの専門的な知識が必要になり複雑になる、という説明は大変理解しやすかったです。
まずは、相続の基礎及び応用ができるようにし、培った知識の延長線として、事業承継を学びたいと思います。
また、事業承継を行ううえでの実務上の注意点として、株の評価のお話が印象に残りました。
株の評価は、税務上の評価に則れば、決まって金額が算出されますが、会社法上の評価は、いわゆる「言い値」であるということには驚きました。
相続税評価額を算出するときもそうですが、このような法律や規定での評価の違いにも細心の注意を払わなければならないのだと改めて感じました。 M様

内容として、事業承継の悩みには後継者・相続財産・自社株問題などがあり、これらは必ずしも税務の知識だけでは解決できるわけではなく、会社法の知識・ノウハウも活かすことで、より良い提案が可能であるといったことが印象的でした。
また、法人のお客様だけあって、個人と比べ、当たり前ですが見込める利益が大きい事、それもその法人からの報酬だけでなく様々なところから仲介料といった副収入も見込め、自社への大きな利益に繋がるといったことも言っておられました。
やはり、私たちはただお客様の申告等をやっていくのではなく、こういったコンサルティングが必要であり、そのためには税務だけでなく様々な知識・ノウハウを身につけ、お客様毎によりよい提案をしなくてはと感じました。 S様
平成18年5月以前は商法により原則株券発行しなければならなかったので、株券の流失や盗難被害にあう可能性がありました。
会社法ができてから、原則不発行という形になり、意図しない流失を防げるようになりました。
このことから、社歴が50年を超える会社は定款変更をしておらず、株券流失への備えが整っていないところもあると講義でお話があったので、もしこれから事業承継に関わる機会があれば、株式の行方をしっかり確認し、社長が元気で会社がまとまっているうちに特別決議を行い、定款を最適な状態にアップグレードしていく提案ができたらと思いました。
T様
商法と会社法で大きく会社のシステムが違い、会社法になったことで会社は運営しやすくなったことを感じました。
生前対策で、会社法のシステムを使い過半数を支配するために属人的種類株式として創業家のみ1株につき20議決権とする「株主の属人的な定め」を設け、設ける前は700株すべて移転しなければいけなかったのに、100株の移転のみで過半数握れるようになり、贈与税も100株にしかかからない点に事業継承コンサルティングの可能性を感じ、この点が今後会社の経営に悩む方に関して実務で活かすことができると思いました。
O様
本日のコンサルティング実務の講義を受けて、事例を踏まえた上でお話頂いたので、状況が想像しやすくとても為になりました。
特に、事業所受けに関しては会社法も入ってきて、普段の相続の話とは違った視点で考えなければいけないので、具体例はとても参考になりました。
まず、事業承継を行う上で絶対必要なのが、社長が元気なうちに対応をしたほうが良い、ということです。
これは、会社設立や経営を行ってきた当人にしか分からないことも沢山有るので、生前に対応を行ったほうがスムーズに行えるからです。
事業承継では、会社法を使用し様々な方法でお客様の為になる事業承継の方法がいくつもあります。
決議等が必要になりますが、属人的株式を導入し「創業家のみ1株につき20議決権とする」などを行うと、贈与税負担額も抑えることができ、会社支配権を獲得が出来るもそのうちの1つです。
また、コンサルティングを行う上でも、やはり、お客様との信頼関係があるかどうかで提案した際の反応も変わってくるので、信頼関係の構築が大切です。
S様
相続・事業承継のコンサルティング実務について学びました。
このセミナーを通じて学んだことの中で最も印象に残っている内容は「事業承継はケースバイケースであり、オーダーメイドである。お客様が必要としている情報を提供することが大切」ということです。
このセミナーを受けて、「お客様が必要としている情報」には二通りのものがあると感じました。
まず1つ目は「お客様が悩んでいることについての解決策の提示」、2つ目が「お客様が潜在的に欲している情報の提示」です。
前者はお客様から相談をしていただくことに対してお答えするというものですが、後者は会話やお客様の状況から、必要としている情報を察知する必要があります。
今後、お客様と接する際には、お客様が潜在的に欲している情報はあるのか、あるのであれば、どのように提案することが効果的なのかを意識して仕事するよう心がけていきたいです。
M様
事業承継対策が必要な理由として、税法上の問題である財産権の承継、会社法の問題である経営権の承継の二点が挙げられます。
上記の問題を回避するためには、やはり生前対策、予防法務が必要になってきます。
担当するであろうお客さまの多くが抱える問題として、自社株問題・後継者問題・相続問題が挙げられます。
今回の講義では、お客さまのニーズに対してどの様なアプローチをすれば満足していただけるか、事例を絡めて説明していただいたので、実務でも何をどう活かすかイメージがしやすく利用できると思いました。
S様
相続も事業承継も「想いの承継」という点では同じですが、事業承継は財産権の承継だけでなく、経営権の承継という点も考慮しないといけないため、気を付けなければならないと思いました。
相続・事業承継対策は将来起こりうるトラブルを回避するためのものであり、生前に対策することで効果があるので、上手く活用していきたいと思いました。
事業承継の悩みを抱える経営者の中には、自社株に対する悩みなのか、後継者に対する悩みなのか、相続に対する悩みなのか、それぞれ人ごとに異なる悩みを抱えていると思うので、それぞれの悩みに合わせた提案をしていけるように勉強していきたいと思いました。
O様
平成18年5月より前の商法と後の会社法では内容が全く異なるということが分かりました。
例えば、法令と自治の割合の違いや、以前は株券を発行するのが原則でしたが会社法では不発行でも良いなどがあげられます。
現在適用されている会社法は大企業向けというよりも小規模零細企業向けに便利な法令になっているのだと思いました。
中小企業が多い現代では、会社の運営がしやすい法令をよく理解し、企業継承やそれに関わる相続の対策に役立てたいと思います。
T様
事業承継コンサルティングについて、その基本的なあり方や必要な知識を広く学ぶ内容でした。
事業承継問題が相続問題と深く関わっており、相続問題方面からの提案に大きな意義があること、会社法成立以前設立の株式会社の経営者に対して、事業承継を見越した税務・法務的アプローチの余地が大きいことなど、今後のコンサルティング業務に大変有意義なものであったように思います。
今後はこれらを自身のものとして業務の中で活かしていくことのできるよう取り組んでいきたいと思います。
K様
事業承継という言葉は聞いたことがありましたが、実際にどういう問題があるのかまでは分からなかったので、今回の講義を通してたくさんの事を学びました。
中でも、名義株の整理については、例を交えて説明して頂いたのでとても分かりやすかったです。
また、お客様へ提案するのに様々な状況に応じた提案ができるよう常に自己学習が大切だということ、お客様とコミュニケーションをしていく中でニーズを読みとっていくことがその後の成果につながることを知りました。
以前、経営者が高齢化し、後継者がいない事例が増えているとニュースで見たことがあります。
相続・事業承継は今後ますます需要が増えていくと感じました。
今回、事業承継の全てを学んだわけではないと思うので、より深く学習していきたいと思います。
T様
相続と事業承継は同時に起こり得ることで、相続税等の知識だけではなく、会社法や民放の知識も理解していなければならないそうです。
社長の想いをくみ取り引き継ぐため、そして、自社株が原因で揉め相続が争続にならないよう生前対策が一番効果的だと思いました。
事業承継の株のお話は、実際の業務ではなかなか触れることができない内容でした。
株の持ち分により大きく会社が変わってしまうので、大変興味深かったです。
A様
非常に重要な内容を分かりやすくご説明していただき、貴重な講座でした。
事業承継とは、財産権と経営権の両方を承継することなので、税法だけではなく、会社法の知識が無いとお客様の力になれないことを、今更ですが知り勉強することを決意致しました。
名義株を整理してあげる等、余裕があるときにやればよいことではなく、危険回避の為、会社の経営と将来の継承のために急ぐ必要性があること、コンサルすることの重要性、しかも生前にこそ社長の声も届くし、効果があること、何を見てコンサルすべきことを見つけることができるか等、大変ありがたいことを教えていただきました。
属人的株式と種類株式の活用の全体像を展開して頂き、議決権制限株式、配当優先株式を使用して、例えば兄に経営権を、弟に配当を多く行う形等で、兄弟間の納得のいく形を実現できることは聞いておりましたが、9種類もあり、それを複数組み合わせて、関係者の同意のもとに会社の経営の安定に資することができる仕組みを作っていけるとのご提案業務に感心致しましたし、個々の会社の状況に合わせて、信頼関係を作りながらご提案されるご苦労も知りました。
お客様にご提案をすべき問題点がないかを探せる力を付けたいものだと今回強く感じました。
相続マイスター講座13期 第4講座の感想

公的価格には、時価、地価公示価格、基準地価格などがあり、これらの価格はどこの団体が発表しているかで異なります。
時価なら不動産業者、地価公示価格や基準地価格なら国土交通省といったように、それぞれ出所が異なり、公的価格はそれを発表する団体の数だけ存在することが分かりました。
公的価格の中でも、時価、地価基準額、相続税路線価、固定資産税路線価の4つの価格は「一物四価」と呼ばれるそうで、実務でこれらの価格を使うときには、どれがどの価格なのかをよく考えながら使う必要があると思いました。
また、土地の評価を行うときは、鑑定評価書に記載されている「標準化補正」を考慮する必要があること、「市場の特性」欄には、土地を知るうえで重要な情報が詰まっていることなど、鑑定評価書の読み方についても少し理解を深めることができました。
鑑定評価書を読む際にはこれらの情報をしっかり読み取り、間違いなく使用したいと思います。 M様

また、「市街化調整区域内の宅地の評価」において、農林漁業に従事する者の居住用宅地では、農家の次男や三男には適用されるが、売却してしまった場合には第三者となるため適用外となることも分かりました。
しかし、その場合においても、宅地が建っていればセーフであることなど、その点をお客様にお伝えすることで、お力になれるのではないかと思いました。 I様
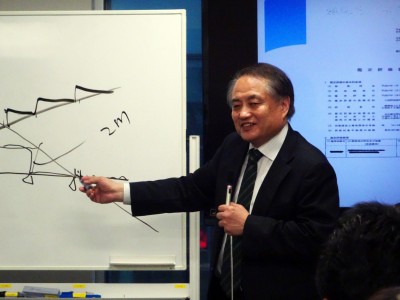
平成30年に改正されるので、価格に対し不満があればそれを聞き届けてもらえる機会であること、価格以外の間違い(家が建っているのにずっと更地として評価されていたような事案など)であればいつでも正してもらうことができ、原則5年、市町村によっては10年~20年還付が受けられるとのことでした。
評価をする側も、今は航空写真と公図を合わせて見ているのでそんなに間違いは起きないうえに、そこまで大きい額ではないけれど5%の還付加算金もつきます。
還付があるとお客様はやはり喜んでくださるとのことでした。
他に気になったお話は、外国人が売る不動産についてです。
非居住者の外国人が売っている不動産を買うと源泉税を徴収されてしまうというもので、売主がその旨を申告すれば取り返せるが、非協力的なケースも少なくはないそうです。
日本人の場合でも出張でマレーシアに住所があり、非居住とみなされ源泉税がかかってしまった例もあるそうで、注意が必要だと思いました。 O様
今回のセミナーで特に印象に残っていることは、土地の公的価格には、時価・地価公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産路線価があり、それらがどのようにして決定されているか、それぞれの公的価格にはどのようなポイントがあるのかということです。
例えば、「地価公示価格には標準地が設定されており、道路の方位格差がある」ということを学びました。
相続が発生した際、土地の価格はお客様にとって非常に気になる点だと思います。
申告の際の土地の価格がどのようにして決定されるのかをお客様に説明することで、お客様に安心していただくことができるのではないかと感じました。
I様
土地評価するときは、必ず現地を見に行く、上を見て高圧線がないか確認する、下水道だったら評価が下がるので、下を見てマンホールの色を確認する、隣が工場になっていないか調べる、この4点を怠ってはいけないとのことでした。
自分で聞いて調べて現地に行くことが大切です。
私は現地へ行く機会はありませんが、日々の業務で分からないことは上司に聞いた後に必ず自分でも調べることで知識にできると改めて気が付きました。
S様
土地の鑑定評価は難しく、複雑であると感じました。
相続税の路線化より固定資産税の路線化の方が厳密であったりと固定資産税はやはり土地評価において重いウエイトであるのだなと思いました。
また、土地総合情報システムでは地域の平均地価を出している人がいるなど、地価も分かるくらい情報があることが分かりました。
土地評価は日陰か日に当たるなどでも全然変わるものなので、家がある場所が近くても、道路側に面していたり住宅地の真ん中にあるかだけで評価額はとても変わるので、評価額が高い方に住みたいと思いました。
W様
講義の始めの方で解説されていた、韓国は土地に関する情報はデータベースで管理されているため、今後はAIに置き換わってしまうとのことで、「土地評価は人間が考えていかざるを得ない」という日本との違いを感じました。
講義中の「土地は同じものはない。個性がある」というお言葉が印象に残りました。
また、国土交通省のHPで実際に行われた不動産の取引価格が閲覧可能であることは知りませんでした。
S様
路線価が発表される7月より前に、過去の地価公示を通して路線価を知ることができること、借地権割合を決めるのは不動産鑑定士であること、路線価には道路方位の補正が無い等でメリット等も存在することなど、最近実務において、相続税シミュレーションや10万パックを通して触れている路線価について、実務を行っているだけでは知れない知識を多く知ることができました。
やはり、実務がいくらできても、そこで登場する事柄の本質までを理解していないと、その道のプロとは言えないので、今回のような、これまでも、これからも触れていく物事の本質を知れたことは、いずれ実務の中で今以上に不動産について深い知識が求められる仕事をする際にプロとして対応することができるなど、役に立つことがあると思うので、レジュメに書かれていること、メモしたことを自分の知識として蓄えておきたいと思いました。
M様
今回は土地の公的評価についてのお話でした。
国土交通省のHPにて実際に行われた不動産の取引価格や標準地や基準地の価格が公開されており、閲覧できることを知りました。国全ての土地に値段がつけられているのは日本のみであることに驚きました。
路線価は固定資産税と相続税とがありますが、固定資産税路線価のほうが、突っ込み道路などが記載されており、相続税路線価より厳密であると学びました。
土地評価をする際は、固定資産税路線価を使用するのが良いことも学びました。
A様
土地の評価は実務の中においてもとても重要な仕事だと思います。
同じ土地でも評価する人によって見解が異なることもありますが、なぜ異なった見解になるのか、反対に見解が一致するポイントがどこなのか見極めるためにも、土地の評価方法や評価基準は学ぶ必要があると思いました。
借地権の割合について、今までは路線価図などに書いてある割合を見ても何も考えませんでしたが、借地権の割合の評価の基準なども少し分かったので、これからはなぜその借地権の割合なのか、土地ごとに注意して見てみたいと思いました。
O様
公的価格とは値段を示しているものではなく、前の年からどのくらい変動したのかを数値化したものだということが分かりました。前年からの変動率が表されているもので、何%上がったかを示しており、5000単位で区切っているということも分かりました。例えば、103.000の場合は100と表わされます。
また、地面の下に下水が通っていたり、周囲の工場からの臭いがあることによっても価格が変わったりすることがあり、ただ特定の土地だけを見るのではなく、周りの環境も踏まえて価格が設定されているということが分かりました。
S様
下﨑先生には、広大地評価でいつもお世話になっており、本日の講義はぜひと思って受講しました。
例年行われる地価の公示から、相続税路線価がその年にどのくらい変動するのかは、公示価格の変動率によって分かるとのことでした。対象地付近の公示値を見て、変動率を確認し、路線価が上がるか下がるかは予測がつくという話は大変興味がありました。
また、広大地の廃止に伴い、同じ路線価を挟んでも、例えば中小工業地区と普通住宅地区が両側にある場合、新制度の下では中小工業地区は規模格差補正率は適用できず、デメリットが大きいので、地区区分を見直すべきという声が上がっているとの事です。
日常的に業務で関わっていることについて、深く掘り下げた内容で、大変興味深く聴くことができました。
S様
相続税路線価は地価公示価格のおおよそ8割なので、コンサル案件の場合にはだいたいの目安評価をすることもできるというお話がありました。
事務所では路線価の発表となる7月以降に相続税シミュレーションの路線価の差し替えをしてお客様に提示しております。
実際に私は行ったことがありませんが、コンサル案件を扱う担当者の方は地価公示価格からの目安評価で提案などすることがあるのが気になりました。実際の計算のところはまだよく理解が追い付かなかったので、また個別に確認したいと思いました。
広大地から規模格差補正へ変更になったことに関して、私はデメリットの部分を多く感じていたのですが、下崎先生のお話を伺って、メリットも沢山あることが分かりました。
例えば、マンション適地が適用可能になったことや路地上敷地の適用可能となったことなどです。
お客様に提案する機会はあまりないのですが、土地の評価をする際に、規模格差補正の適用条件と広大地の適用条件を混同しないように気を付けて進めていきたいと思いました。
市街化調整区域の雑種地の評価はよく朝礼でも発表されるものです。
土地ファイルを作成する際に「市街化調整区域の雑種地がある場合は固定資産税路線価を出す」という項目がありますが、どうして出すのか意味が分からず出すよりも、少しでも意味を理解して出す方が仕事の効率があがると思うので、今回説明いただいてよかったです。
今後、教える際にも簡単にでも説明できるようにしていきたいと思います。
T様
土地の評価は普段の業務で行ったことがほとんど無く難しく感じる分野の1つだと思いました。
相続で路線価などを使用しますが、土地評価をもう少し勉強して、理解しながら業務に取り組みたいと感じました。
特に興味深かったところは、同じ土地に家を建てるにしても、日当たりや道路に面したところに建てるかなど少し違う条件で土地の評価額が変わってしまうことでした。
相続税などで土地評価はとても重要なので知識をつけ、お客様が安心できるようになりたいです。
相続マイスター講座13期 第5講座の感想

従来(平成28年以前)は、贈与税納税猶予が取消しとなった場合、猶予されていた贈与税額の全額を納税する必要があり、結果として、相続で引き継いだ場合よりも多額の税金を納める必要がありましたが、改正により、いったん贈与税の全額を納税する必要はあるものの、相続した場合の相続税以上の贈与税を納付した場合、その差額は還付されることになったということを学びました。
経営者の中には、「死ぬまで働くのではなく、早めに後継者に経営権を譲りたい」と考える人は少なくないと思います。
贈与税納税猶予のような制度の知識をしっかりと身につけ、適切な助言ができるようになる必要があると感じました。 S様

この講座を通して、贈与を早くするメリットとしては、経営権などの実権が後継者に渡るため後継者が育つ点や、税務上の株価の予想がしやすいという点が挙げられること、デメリットとしては、贈与の税率が今後どうなるか予測不能な点が挙げられることが分かりました。
また、納税猶予には、配偶者軽減や小規模宅地と同様役員になっていることや分割協議が終わっていることが条件として課されているため、そのことをお客様にお伝えすることを失念しないようにしなければいけないと思いました。 I様

今後は、お客様の株価についても、新規に担当になった時など、資本金、売上高、従業員数などの他に、株価や株主構成も気にしておくといざという時に事業承継のご提案もできると思いましたし、その際に、顧問先の家族構成も頭の片隅に入れておくことにより、ご子息が役員経験3年などの要件で認定特定会社に該当しなかったなどという事も防げると思いました。
また、毎年の税制改正で納税猶予の要件は変わっており、今年できるから今後できるとは限らず、また今年より来年の方が緩和されるかもしれない、「今できることは何か?」というスタンスで臨むのが良いと思いました。
事業承継について考えるとき、会社法の知識も非常に大切だと思いましたので、今後は少しずつでも勉強していきたいと思います。 Y様
そもそも譲渡が無効になるケースがあることを知りました。
会社法の株券を交付しなければ効力を生じなくなるので、事前に特例承継計画の提出や株券付発行会社となる旨の定款変更と登記をするなどの対策が必要です。
また、後継者が役員になっていないと納税猶予を受けることができないので、気を付けておきたいと思います。
相続と同じですが、生前に対策をするのがとても重要となるので、お客様に説明するときに念頭に置きコンサルに活かしてしていきたいと思います。
I様
平成30年より、先代の妻や親せき等から後継者への贈与なども納税猶予の適用が可能となったのは大きいと思いました。
ただし、叔父が亡くなってしまった時は、叔父が後継者に贈与していた株式を叔父の財産に戻して相続税の計算をすることになります。
また、後継者は叔父の相続税申告に加わることにもなってしまいます。目先のことだけでなく、その後のことも考えながら対策を行っていく必要があります。
制度が改正になったら、すぐに調べて勉強していくことが大切だと思いました。
M様
株式譲渡に関して、最近税制改正が行われた部分でもあり、どのような影響があるか関心がある論点でした。
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引きでしたが、特例承継計画を提出することにより、10年間限定で自社株のすべてを対象として全額を納税猶予できるようになったことを学びました。
ただし、後継者が役員になっていないと納税猶予が受けられないので、注意しなければならないと感じました。
また、生前対策として、次の後継者を決めておき、納税猶予をしっかりと受けられるようにしておかないと相続税を増やすことにもなりかねないということを知り、お客様に説明する際に活かせそうです。
O様
今回は、事業承継の納税猶予について主に学びました。
平成29年までは納税猶予は自社株の3分の2を対象に8割引で、雇用の8割を保てないなどの理由で納税猶予が取り消しされてしまうリスクがありましたが、平成30年の改正では全額猶予できるようになり、もし納税猶予が取り消しされても、そもそも払うはずであった金額を払えばよいこととなり、そのリスクが無くなりました。実質、5年無利子で納税を待ってもらえる制度という見方もできるようです。
3年ごとに必要で、税理士には損害賠償のリスクは高いですが、お客様の需要があるのであれば仕事になるということなので、積極的に、かつ慎重に取り組んでいくべきだと思いました。
M様
事業承継の税制改正により父から子への贈与が納税猶予されていたのが、母・叔父からもできるようになり、後継者が叔父の相続に関わることになってしまうため、対策・リスクへの理解なしに納税猶予を勧めることは危険であることが分かりました。
事業承継が活発化される改正だというイメージしか持っていませんでしたが、資産の管理を手伝う税理士のリスクや管理コストは高いというデメリットを知ることが出来ました。
税制改正があるときには、改正点を理解するのはもちろんのこと、改正前の制度に深い理解が必要で、そこが不足していると訴訟や賠償になる可能性がある業務なのだということを今回の講義で改めて感じました。
S様
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引でしたが、10年間限定で「特例」として承継計画を出せば、自社株の全てを対象として全額を納税猶予とすることになったので、とにかく承継計画だけは2023年3月末までに出しておくべきだということを学びました。
また、雇用確保要件が撤廃され、贈与者を先代に限定せず、相続時精算課税も使えるようになり、後継者も議決権保有割合上位最大3人までになったので、今後「特例」を考慮して対策をしていくことが重要だと思いました。
M様
実務では相続に携わることが多く、贈与や株式の譲渡についての話は新鮮でした。
相続では、小規模宅地等の特例や生命保険を適用して税額が変わってきますが、同じように生前贈与の方法次第では、また税額が変わってくるのだと思いました。
納税猶予もあるとないとでは、経営者側としては大きく違うなと感じました。
生前の対策で、贈与額が5~95%も振り幅があることに驚きました。
シミュレーションをして一番良い方法を提案していくのが私たちの仕事なのだと実感できました。
S様
特例承継計画書を提出すれば、自社株の贈与・相続は全株・全額が猶予・減免されるという特例を受けることができる、納税猶予ができるようになったとしても、やみくもに行ってはいけない、という2つのお話が講義において頻繁に出てきました。
これらの知識は、税務の仕事に携わる者にとって欠かすことのできない知識なので、自分から更に掘り下げて勉強し、実務に役立てていきたいです。
また、これら2つの内容を通して、お客様に税務のプロとして接するということは、非常にリスクの大きい仕事であるということを先生はお話されていました。
現在、自分がそのような仕事をしている自覚を強く持つこと、また、お客様にとって不利となることがない的確な提案をできるプロとしての知識量を持つことが今の自分にとっては必要であると感じました。
今後は、自分から学んでいく姿勢をさらに強くして実務・研修に臨んでいきたいです。
M様
難しい内容でしたが、図表や例、音楽を用いて講義してくださり、分かりやすいように工夫して頂いたのが印象に残っています。
平成30年度に改正された「事業承継税制」では、中小企業の株式の続税が実質無税になります。この制度はリスクが大幅に軽減するため、積極的に活用すべき項目です。
また、従来、自社株の2/3を対象に8割引でしたが、特例承継計画を提出することで10年間限定で自社株の贈与・相続は全株税額を猶予・減免になります。
以上の二つは大いに活用すべき事柄だと思いましたので、お客様にもお伝えすべきだと感じました。
S様
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引でしたが、10年間限定で「特例」として承継計画を出せば、自社株の全てを対象として全額を納税猶予とすることになったので、とにかく承継計画だけは2023年3月末までに出しておくべきだということを学びました。
また、雇用確保要件が撤廃され、贈与者を先代に限定せず、相続時精算課税も使えるようになり、後継者も議決権保有割合上位最大3人までになったので、今後「特例」を考慮して対策をしていくことが重要だと思いました。
O様
初めは6億円の相続税を支払わなければならなかったものが、納税猶予が適用されれば2億円だけの支払で済み、4億円を節税することができるのでとても相続人の負担を軽減できる法令であると思いました。
また、贈与税納税猶予に関しては、早く後継者に実権を渡すことができ、生前対策としてとても有効であることが分かりました。
納税猶予は被相続人の生前に後継者を役員として登記に記入しなければならなく、8ヶ月以内に県に申告しなければ納税猶予は適用されません。生前対策は前もって、誰が次の後継者になるのかなどを決めておき、亡くなった後に納税猶予が適用されないとならないように事前に決めておくことが重要であると思いました。
相続マイスター講座13期 第6講座の感想

中小企業の場合、債務の株式化(株価0円)に成功すれば、経営者にとっては相続税額の減少、会社にとっては表面上ではありますが、経営者に対する借入金が減少するため中小企業の税制優遇が適用されるので財務内容の改善の効果があることになります。
ただ、DESは貸付金を株式に変えるだけなので作業的には簡単ですが、株式にすることにより外部への流失、株主総会でのトラブル等危険があるということも念頭に置かなければならないと思いました。
そのため、手続きに少々時間がかかってしまいますが、債務免除が可能かどうかもDESと同時に調査しながら進めていく必要があると感じました。 I様

同族経営の中小企業の事業承継は、家族の問題も絡むことが多く、コンサルティング力だけでなく、ご家族の間に入って説明するコミュニケーション能力も無ければできない仕事だと強く感じました。
75歳のオーナー社長が急逝し、会社を継ぐご長男を全く経営に関与させていなかったために、安定していた会社が一気に崩れてしまったという事例をお聞きしました。
このように、ご自身が死んだ後のことを考えてらっしゃらなかったために問題が起こるケースは相続では多いのではないかと思います。
税理士法人として、生前対策の必要性を喚起していく必要があると感じました。 H様

事業を息子に承継するよりも、他の人に承継した方が社員の士気も高まることや、兄弟がいる場合は今の会社をホールディングス化して、新しい会社を作り、兄弟それぞれに経営させてみて、うまくいかなかった方はホールディングスの会社に戻すとうまくいくということを知りました。
また、M&Aのお話では、多くの会社を短期間のうちに調べて、お客様の要望にあった会社を提案しなければならなく、買い手はできるだけ安く買い、売り手はできるだけ高く売りたく、その中でお客様に満足のいくように取り持つということを学び、これからの仕事の上でもお客様の欲しい提案をする際に活かせそうです。 M様
今回のセミナーでは、実際に横山講師が扱ってきた様な事例をもとに、事業承継にまつわる問題や経営者たちの考え、何をしてどうなったのかを詳しく話されました。
一言に事業承継といってもその内容は様々で、経営者や後継者によっても変わっていく状況、完璧なテンプレートなど存在しないことを実感しました。
また、前回セミナーでもありました納税猶予による事業承継の話もあり、やはり納税猶予の緩和は節税を考える方にとってとても重要なことであり、こちらでの対応ができるようならなくてはならないと感じました。
事業承継は相続と強いつながりがあるため、より学んで行ければと思います。
A様
事業承継について、横川先生が担当した事例を使って説明してもらい、どのようなパターンがあり、時間がかかることが分かりました。表面上の話だけでなく、裏話や個別の事情なども説明して下さったので、実務にも役立つ内容でした。
M&Aや組織再編、DESなど様々な手法があり、会社の特徴や現状をよく見極めて選択することが必要と感じました。
もちろん、お客様の意見や考えを重視することは重要ですが、第三者の立場から客観的に指摘することで、最終的にお客様や従業員の満足度も高まり、将来的にも会社の業績が上がっていくのでこれからの業務に役立てていきたいと思います。
O様
今回の講義では実際の事業承継の成功例や失敗例について伺いました。
現在の中小企業には、後継者の問題(後継者がそもそもいない、いても継がせられない)や、株を後継者に引き継ぐ際の納税の問題があり、また、借入などの問題から精算ができず会社をたたむこともできないといった企業が増加傾向にあるそうです。
どんなに優良に見えていた会社でも突然の社長の死などで経営が悪化するケースもあり、デューディリジェンスの実施には一か月といった短期間での対応は難しく、M&Aの形が成立したとしても事業自体の承継がなされないこともあると聞きました。
中小企業は土地、地域との結びつきが強い傾向にあるため、土地やものだけを目的にしては上手くいかないと学びました。
S様
今回のセミナーでは、事業承継の事例について学びました。中でも印象に残っている内容は、会社分割についてです。
以下では、会社分割の①分割型と②分社型についてまとめたいと思います。
まず、分社型とは既存の会社を二つに分けるというものです。事業を承継する際に、所有している財産の一部は引き続き保有していきたい場合にはこの方法が適しているとのことでした。
これに対して分社型とは、既存の会社の下に100%持分会社を作るという形で、複数社に分けるというものです。
子に継承させる場合に、分割型にすると対外的に問題が生じるといった可能性が考えられますが、分社型にすることで解決できるという利点があると学びました。
W様
内容としては、事業承継の事例から成功例と失敗例を学ぶものでした。
横川先生の講義は前回も受講したため、以前の講義でも聞いたことのある事例があり、より理解を深めることができました。事業承継の本当の成功は、契約成立だけでなく、成立後もその事業が存続するかということであるということを再確認しました。
今回の講義で学んだことは、上場企業と非上場企業のM&A、自社株買いが全然違うということです。講義の中で日本の中小企業は減少していると解説がありましたが、今の日本は99%は中小企業が担っているため、中小企業を存続させることが日本の課題であることも再確認しました。
S様
事例がとても多く、その内容も基本的なものから最近話題の納税猶予を扱うものまで幅広かったので、勉強になりました。
また、その事例の中に失敗事例が含まれており、その時の原因や対策も併せて紹介されていたのが尚良かったです。
事業承継、M&Aについての知識がほとんど無かったので、事業承継対策の大切さや、廃業型など様々な種類があるM&Aについて多くを学べました。法人のお客様と対応するにあたって、事業承継に関わることがあると思うので、今日聞いた内容をベースに的確な対応ができるようにしたいです。
また、特に、事業承継は買手企業側と売手企業側の見解が異なることが多いため、どちらの意見も尊重した提案をすべきであるということの大切さを、仕事において失念しないようにしたいです。
M様
実際に関わった事業承継の事例を見ながらの講義で、成功も失敗事例も踏まえて講義してくださったので、とても分かりやすかったです。
現在、中小企業の倒産件数は減少傾向ですが、休廃業企業の件数は過去最高になっています。
休廃業企業の中には、従業員、売上規模は小さいが利益は大きいという企業が多く見られます。
中小企業の事業承継をどうするかによって、今後の日本経済に影響を及ぼすことになることを学びました。
その企業それぞれの特色や状況を見極めると共に、経営者家族、従業員の今後の生活のことも考え、最適な事業承継をすることと急がずにじっくり考えていくことも大切だと感じました。
O様
今回の講義では、さまざまな事業承継に関する事例を知ることができました。
事業承継では、家族関係やどのような内容の事業を行っているのかなどによって、それぞれ対応が異なってくるので、決して一つの対策だけではなく、一つ一つの事業承継について深く関わり、最善な対策を提案することが大切であると思いました。
また、今後もこのような事業承継についての事例を学ぶことで、似たような事業承継を見つけることができ、どのような対応を取るべきかが分かると思いました。
S様
事業承継がどういうものであるのかということだけでなく、実際の事例を元にしているので、とてもイメージがつきやすく分かりやすかったです。
事業承継と一言で言っても、M&Aや組織再編など複数の方法があるので、企業の状況や特徴に合わせて臨機応変に対応していくことが重要だと思いました。
必ずしもうまくいくとは限らないし、急ぎすぎてもいい結果が得られるものではないと思うので、時間が少しかかってもじっくりと状況を見極めながら進めていくことが重要だと思いました。
O様
事業承継について、実際に横川さんが担当した事例を使って説明していただいたのでとても理解しやすかったです。
表面上の話だけでなく、裏話や個別の事情なども含めての説明だったので、実務にも役立つ内容であったと思います。
M&Aや組織再編、DESなど様々な手法があるので、会社の特徴や現状をよく見極めて選択することが重要であると感じました。
もちろんお客様の意見や考えを重視することは重要ですが、第三者の立場から客観的に俯瞰することで、最終的にお客様や従業員の満足度も高まり、将来的にも会社の業績が上がっていくと感じました。
K様
今日の日本では、後継者不在の為廃業に追い込まれる中小企業が多いとニュースで見たことがあります。
利益が出ている優良企業も例外ではないとのことでした。そういった企業がなくなると日本経済が衰退していくと思います。
そういった背景から、事業承継は今後ますます伸びていく分野だと感じました。一言でM&Aと言っても、様々な手法があることが分かりました。
今回学んだ各事例を基に勉強を重ねていきたいと思います。
相続マイスター講座13期 第7講座の感想

講座の中で、遺言には、意志と能力が重要であり、医療・看護記録等から認知能力の有無などを判断することが分かりました。
また、相続でもめる際は、大抵は2グループに分かれ、グループの取り分を増やすため養子縁組を行うことがあることも学びました。
事例の一つには、公正証書遺言作成後に自筆証書遺言が作成されており、本来であれば、あとに作成された自筆証書遺言が効力を発揮するはずが、自筆証書遺言の二重線の上に訂正印が押されていなかったことから、印鑑の本人の意志の表れという部分が欠如され無効となっていました。
遺言に関しては、相続が発生した際スムーズに処理が行われやすいことから、自筆証書遺言より公正証書遺言の方をお勧めした方がお客様のためになることを学びました。 I様

遺言も養子縁組も、やり方を間違えると思わぬところから訴訟案件になってしまうので、「うちの家族は大丈夫」「まだやらなくても」という方に今回学んだ事例を紹介して危機感をもってもらう必要があると思いました。
もめている相手の遺留分を減らし、相続分を増やそうとするために知らない間に養子縁組がされていた、ということに対抗するためには、有効な遺言を認知能力があるうちに作成しておく必要があるので、より確実な公正証書遺言を早めに作っておくことが、その後の家族のためにいかに重要かを学びました。 M様

特に、遺言や養子縁組のあるケースについて知識を深められました。
講義内では、実際にあった事例をもとに、家系図を見ながら学習しました。相続人の法定相続分がどうなるかを基本としつつ、そこに遺言や養子縁組が入ってくるケースではどうなるかを約10ケース見ることができました。
また、遺言及び養子縁組で共通する重要なポイントとして、どちらも「意思+能力」により判断されるという事が分かりました。
遺言には大きく分けて2種類あり、民法の要件を満たすように自筆で書く「自筆証書遺言」と、公正役場で書いてもらう「公正証書遺言」があります。どちらも遺言としての優劣はなく、同じ効力を発揮しますが、最も新しく書かれた遺言が優先されます。遺言作成を提案する際には、遺言作成の時期に注意しながら提案しようと思いました。M様
多種多様な家族構成から繰り広げられる「争族」の問題点や対策を教えていただきました。
冒頭で「争族は相続税だけが敵ではなく、身内も十分敵になる。」と先生がおっしゃっていましたが、身内間で起きた様々なトラブルの実例を聞いて、本当にその通りだと感じました。
遺言があっても対立が生じた「下剋上阻止型」の実例、偽造された離縁届が勝手に作成・提出された「離縁無効」の実例、遺言があっても無効となった「遺言無効」の実例が特に興味深かったです。
また、実例だけでなく遺言作成の際のアドバイスや、税理士法人の職員がお客様に説明すべき遺言作成のタイミングなども教えていただいたので、担当させていただくお客様の「争族」を防ぐために、実務で活かしていきたいです。
H様
今回の講義では、遺言について多く触れ、様々な問題点を見ることができました。
間違えた際の訂正方法や公正証書遺言を作った後の場所の引継ぎなど、せっかく作っても意味がなくなってしまうこともあります。
また、早くから対策を立てて遺言を作ることも大切ですが、相続人が先に亡くなるパターンなどまで考えて作らなければなりません。私たちはそこに気づき、お客様に提案しなければなりません。
養子縁組についても争族の対象と成り得るため、早めに話し合いをしてどのように分割をするか決めておくべきだと思いました。
N様
争族の実例を元にした講義でした。
相続税の節税方法や対策は様々な形がありますが、早すぎる対策でも遅すぎる対策でも良くないことが分かりました。
対策方法を見極め、適切な提案をすること、不備のない内容の対策を提供することが求められていると思いました。
本人の意志が届くように、残された人が納得のいく相続になるように私たちがサポートしていかなくてはいけないと思いました。そのためにも、知識を増やし、実務での経験も増やしていきたいと思います。
I様
遺産相続で遺産を増やす方法として、養子縁組をしたり、遺言を自分宛に書かせたり、様々な手法があり驚きました。
しかし、そのような手を使っても、縁組無効を主張して縁組は遺産を増やすためにしたものであると言ったり、遺言を書いたときは認知症で意思や能力はないものとされて無効にされてしまったり、遺産分割は大変だなと感じました。
遺産対策で悩まれている人には早めの対策を進めるとともに、公正役場での遺言書作成を進めたいと思います。
E様
大変興味深い内容でとても面白かったです。
今日の講義の内容のような「争族」の場面に直接立ち入ることはありませんが、遺言の作成には関わることも多いので、とてもためになるお話でした。
養子縁組や遺留分などの複雑な部分は、思い込みや中途半端な知識では怖いとも感じました。
小嶋先生の講義は前回も受講させていただきましたが、今回は寄与分や特別受益のお話も聞くことができて、なんとなく知っていた部分の理解を深めることができました。
M様
遺言や養子縁組の争続のケースを様々な事例を用いながら話してくださって分かりやすい講義でした。
遺言や養子縁組など正しくしないとトラブルが起きやすいと学びました。自筆遺言も印鑑を押してないだけで効力を失ったり、無くしてしまうという事例を聞き、公正証書遺言の大切さを学びました。
これからお客様に遺言を勧めたりするときは、自筆遺言と公正証書遺言の利点・欠点を説明し、遺言の大切さを正しく説明できるように努めたいです。
W様
内容としては、相続で揉める事例を紹介したものでした。
相続で身内同士が敵になり、まさに骨肉の争いになるのは恐ろしいなと思いました。この講義を通して、遺言は意思能力のある時に作成しておくべきだと感じました。
また、認知症を患っていても、軽度なら遺言作成能力があるとは知りませんでした。
講義内で紹介されていた事例にいくつかありましたが、長男の妻と長男の父が養子縁組をするケースが結構あることに驚きました。
身内で争うことは、精神的にもかなりダメージを与えるので、一つでも多くの争続が発生することを回避するためにも、いずれ自分がお客様と接する機会があった際には、遺言を少しでも早く作成するよう啓蒙活動をしようと思います。
S様
相続争いが起こらないようにするためには、遺言、養子縁組、生前贈与の3つが鍵であることについて実例を挙げ解説していただきました。様々なパターンがあり、大変興味深かったです。
特別受益や寄与分の知識が全くなかったので、勉強する機会になり、大変ためになりました。
遺留分減殺請求は、最近相続した人に対して順番に行えるので、特別受益を受けていた方が賢いと思いました。
自筆証書遺言と公正証書遺言では、後者の方が管理体制等のトラブルがなく、どこの公証役場でも確認ができるのでお勧めできます。
多くの情報が凝縮されていたので飽きずに面白く聞くことができました。
代襲相続人は養子縁組すれば二重の資格が認められるのは思ってもみなかったことなので、大変勉強になる講義でした。
M様
相続は「争族」であり、たとえ仲の良い関係だったとしても争いは起こりうるものです。
なかなか酷な話ですが、生前に自身の相続について考えておく必要があります。
遺言書作成と縁組をしっかり行うことで、ある程度自身の裁量で財産分割が可能であり、争いを避けることができます。
遺言書はいくつかの方式がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主に利用されます。それぞれのメリットデメリットを踏まえて方式を決める必要があります。
縁組は縁組意思の有無が問題となりがちで、主に亡くなる直前の判断力が低下していると思われる時期の縁組が争点になる事が多いです。
したがって、早期の対策が必要ですが、あまりに早すぎると遺言書の書き換え等が必要となる場合もあるので、元気なうちに且つ早すぎない時期の対応が必須だと思いました。
S様
争いが起きる背景には様々な事情と思惑があるのだなと改めて感じました。
判断能力がしっかりしているときに遺言を作成しておくことの重要性、また、遺言を作るのであれば、管理もしっかりしていて見つけやすい公正証書遺言のほうがいいということを学びました。
自筆証書遺言は自分で保管するものなので、死後見つからなければなんの意味もないのでリスクの大きいものだと思いました。
今後、実務の中で遺言作成をする際は、自筆よりも公正証書遺言の作成を勧めるべきだと感じたので活かしていきたいと思います。
I様
理論を淡々と説明される形式ではなく実例が多く、話し方が相手に伝わりやすい話し方だったのでとても理解しやすかったです。
また、今回の大学校の講義を通じて遺言・縁組の大切さや遺留相続分や遺言の効力、生前贈与等を適切に把握できていなかったのですが、この機会を設けて頂いたお陰で少し理解することができました。
今後、相続税の案件をやらせて頂く事があると思うので、より一層勉強していき、お客様に対して適切な提案・アドバイスができるようにしていきたいです。
家族内でこのような壮絶な争いがあるのはドラマの中だけかと思っていましたが、そんなことはなかったことに驚きを覚えました。
自分達は大丈夫ではなく、備えあれば患いなしという言葉の通り適切な事前準備をして頂けるように提案内容を考えていく必要があるのだと実感いたしました。
相続マイスター講座13期 第8講座の感想

私はこれまで「株式に係る権利は分けることができず、受益権と共益権は株式名簿に記載されている人物に帰属する」と覚えていました。
しかし、投資信託を利用することにより、形式的には信託会社に受益権と共益権が帰属するものの、実質的には受益権と共益権を別の人物に帰属させることができるということを学びました。
つまり、相続にあたり「議決権は特定の相続人に、配当を受け取る権利は相続人全員に」ということが可能となり、経営者の相続の際には必要とされるスキームであると考えられるため、しっかりと理解を深めていきたいと感じました。 S様
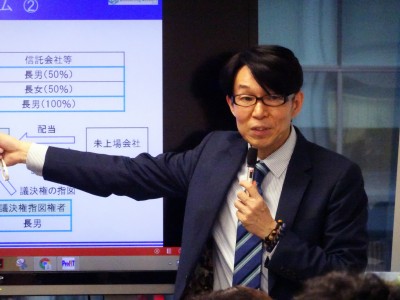
講義は大変難しく感じましたが、議決権指図権者を設定しておくことで、今まで困難であった長女への自社株式の相続回避ができるなど、信託契約書に遺言機能を持たせることでニーズが広がると思いました。
受託者が亡くなった時でも信託契約を結んでいれば、派手な身内争いで議決権の分散の可能性も無くなるので、安定的な承継ができ、お客様にとってもメリットが大きいと思いました。 I様

「子供に株式等を贈与したいが、贈与すると配当が受け取れなくなる」という問題点に対し、「信託を用いれば、財産を収益を受け取る権利と元本部分に分離させ、財産の元本部分だけを子供に移転させることができ、親は、信託期間中に配当・利息を受け取ることができる」という解決策があるという実例がとても興味深かったです。
信託を活かせば、考察の幅が非常に広がるとよくわかったので、自主的に勉強して実務に活かしていきたいと思います。
また、そのために今私が行っている仕事との関係性をもっと知っておきたいです。 S様
遺言や事業承継とは違い、信託には後継者に財産を移しつつ経営権を維持することや、1次相続だけでなく2次相続まで生前中に考えることができるというメリットがあることが分かりました。
前回、前々回の遺言、事業承継にも良い点・悪い点があるように、お客様の考えを理解したうえで、どの方法が適切かを取捨選択することが必要です。
そのためにもまずは、お客様とのコミュニケーションを大切にして、問題点が何かをこちらが理解し継承方法を考えるべきと感じました。
レジュメの相続スキーム③-1にある受益権の評価の計算が難しく、見直し等が必要な内容でした。
I様
法定相続分や遺留分でもめる可能性、遺産分割でもめる可能性、会社の経営権を万全にするため後継者の長男に自社株式を相続させる、遺留分の制約のため長女に自社株式を一部相続させる、長女に自社株式を相続させるのを回避したいといった問題点を信託を活用して解決してくのはすごいなと思いました。
最初受益権と議決権行使の指図権を共に親とし、信託契約で相続の発生場合には受益権を長男長女それぞれ50%ずつ、相続後の議決権指図権者を長男100%にするといったことを今後活かすべき術として学ぶことが出来ました。
O様
小林講師が自分のスキームだとおっしゃっていた、収益をリンゴの実、その元本に当たるものをリンゴの木とする説明はとてもわかりやすかったです。
先に相手に元本となる木を渡すけれど、向こう何年かの収益は自分がもらう、というようにすると、複利原価率により、10年で収益受益権評価を0にしてしまうこともできるという大変興味深いスキームでした。
ただし、途中で建物が倒壊してしまう(木が折れてしまう)というリスクは相手(子供)が背負わなければならないので、注意が必要だと分かりました。
M様
遺言代用信託が、遺言よりはるかに強く被相続人の意思を反映できるものであることを学びました。
普通の遺言であれば遺留分減殺請求があるため渡したくない相手に自社株が移ってしまいますが、議決権指図権者を決めておくことで、経営権を100%渡したい相手に渡せるというところに、第三者に会社を乗っ取られるリスクヘッジできるすばらしいスキームだと思いました。
今回の講義で、税法よりも信託法のほうが有無を言わせない力があるのだと思ったと同時に、関与しているお客様の相続人・被相続人が何も知らずに信託をやっていた場合にはどうなるのか、泣き寝入りになってしまうのか事例が気になりました。
M様
信託は難しいと小林さん自身がおっしゃっていた通り、権利や経済価値の移り変わりに違いがあり、難しいなと思いました。
法的には委託者から受託者に権利が移るが、経済的には委託者から受益者に価値が移るといったところが複雑だなと思いました。
信託を活用すると、公正証書遺言よりも様々な種類の悩みに万全に対処できることが分かりました。
その分、信頼関係がないとなかなか活用には至りにくいものだとも感じました。
事務所報の中にも信託の紹介がありますが、お客様にご紹介するには信託の知識を充分につける必要があると思いました。
K様
富裕層のお客様が信託を活用して相続対策を行っていることは知っていたものの、その目的や効果、スキームについては理解しておりませんので、お客様に簡単にスキームを話せる状態になることを目的として受講致しました。
特に企業オーナーのお客様に関しましては、財産に占める自社株の割合が大きくなっているケースも多く、株式の所有権を信託会社等に移転し受益権と議決権を分けることで、遺言等に比べ柔軟な相続対策が可能である旨を学びました。
一方、信託法が絡んでくる事や、国内の信託銀行等では柔軟なスキームを組めない事も多く、深い理解が必要と感じました。
M様
信託を利用した早期の相続対策を行う事で、相続税や贈与税の課税対象となる資産の評価額を下げる事ができます。
ここでポイントとなるのが受託者と受益者、収益受益者と元本受益者を分けて考えることにあります。
今回事例としてあげていただいたスキームは信託の利用のみでしたので、信託と縁組を掛け合わせた新しいスキームが組めないか等、様々なケースに合わせた独自性の高い相続対策をお客様にご提案できないか考えてみたいと思いました。
S様
言葉でただ説明するだけではなく、事例を出すことでより理解がしやすくなると思いました。
実務の中でも、お客様に説明をする際、案件に合った事例とともに説明することでより理解していただけるのではないかと思いました。
そもそも「信託」がどういうものか具体的に知りませんでしたが、信託の目的は資産の運用・管理・承継であること、また、「信託受益権」に転換することで財産が管理・運用しやすくなることを知り、正しく、そして賢く信託を利用することで得られるメリットはたくさんあるのではないかと思いました。
O様
株式を二人の子供に半分ずつ相続するときに、一人は財産部分の信託受益権だけで、議決権指図者を100%もう一人の子供にすることで議決権はその子供に留保され、それによって、議決権の分散を防止することができ、安定な継承ができるとういうことがわかりました。
指図権者は受益権を買い取るための資金をストックする時間を猶予されるので、議決権指図者にとってはとても有効な制度であると思いました。
相談者がどのような相続の仕方を希望しているのかを把握し、それに合う制度の活用ができるように知識を広げたいと思いました。
T様
今回の講義では、相続に係る信託の活用について学びました。
相続事例における信託の活用が極めて大きな可能性を有すること、また同時にその複雑さから活用には困難も伴うということを学びました。
しかしながら、信託自体は非常に大きな可能性を有するものであり、相続問題に対して、これまでのアプローチに加えて新たなアプローチを可能にするものであると感じました。
今後は、このようなアプローチの方法があることを十分に認識したうえで取り組んでいきたいと思います。
K様
今まで学習してきた内容とは違い、信託を活用した相続スキームを勉強しました。
信託のイメージは不動産のことばかりと思っていましたが、それ以外にも様々な事に関わっている事が分かりました。
贈与について印象的な事例がありました。普通に株式等を贈与すると、親は配当金を受け取れなくなってしまいますが、信託を活用することによって収益部分と元本部分を分離させることができ、信託期間中は配当金を受け取れます。
これは信託ならではの事例だと感じました。
信託について学べたので視野が広くなったと思います。今回学んだ事を実務でも活かしていきたいです。
相続マイスター講座13期 第9講座の感想

概略的ではありますが、相続税の申告で注意すべき点がまとめられており、大変参考になりました。
納税資金対策は相続対策の一つであり、このほか、分割対策と相続税評価引き下げ対策が相続対策として挙げられます。
納税資金対策には、不動産であれば建物を法人化したり、生命保険であれば保険料贈与や生命保険金の非課税の適用があります。
相続税の申告において行っているかどうか、知っているどうかというだけで税額等に影響を与える項目であるため、しっかりとおさえておきたいと思います。
また、税務調査対策では、税務署がどういったところを見ているか、どういった資料を用意すれば税務調査が入りにくいかを知ることができました。
まさに傾向と対策といった具合に、過去の事例を交えて聞くことができたので、実務で申告する際には注意しながら行いたいと思います。 M様

その中でも、建物の法人化というテーマが印象的でした。
前から、収益不動産を持っている人は法人化したほうが節税になると聞いていましたが、すべての人が法人化したほうが良いのではなく、推定被相続人の年齢が若い、物件の利回りが約10%超え、所得分散の対象となる家族がいる等、色々な基準があることは初めて知りました。
また、小規模企業共済制度についても説明して頂きましたが、この制度は中小企業の方にはとても良い制度だと思うので、今後月次監査時に当制度を説明していきたいと思います。
妹尾先生が「不動産と税金は密接に関わっている」とおっしゃっていました。
私自身、宅建を持っているので宅建で学んだ知識を今後の実務に活かしていきたいと思います。 K様

その中で最も印象に残っている内容は「税務署が相続税申告内容で目を光らせていること」についてです。
税務署が注目しているポイントには、
「過去の入出金の動き」、
「過去の大口入金の流れ」、
「直前出金の動き」などが挙げられていました。
私はこれまでに何度か預金不明点ファイルの作成を行いましたが、なぜその作業が必要かについて深く考えずに、マニュアルに従って作業をしていました。
しかし、今回のセミナーを通じて、預金不明点ファイルの重要性を感じ、その作成作業が必要な理由を学ぶことができました。
今後は「預金不明点の確認書の出来の良しあしが、税務調査の有無に直結する」という意識をもって仕事をしていきたいです。 S様
相続対策は、分割対策、納税資金対策、相続税評価引き下げ対策の3つが主に挙げられます。
分割対策としては遺言書作成、遺留分減殺請求の対象とならない生命保険加入が考えられます。
納税資金対策としては生前贈与、小規模企業共済の加入が考えられます。
相続税評価引き下げ対策としては、家族信託、同族法人への貸付金の債券化が考えられます。
相続税シミュレーションや10万円パック等の作業を行う際に今回の講義で学んだことを活かしたいと思います。
また、書面添付の必要性を改めて再確認することが出来たので、資料作成の際は一層気を引き締めたいと思います。
S様
「納税資金対策」と「最近における相続税の税務調査のポイント」の2つについて解説していただきました。
特に、「最近における相続税の税務調査のポイント」は、非常に実務に即した内容でした。
妹尾さんがお勤めされているひょうご税理士法人での「税務調査が少ない理由」や「意識しているポイント」、また、「税務署が申告内容で目を光らせていること」などは、今後、実務で判断等する際に非常に活用できると思うので参考にしたいです。
また、「表面的な財産だけではなく、隠れた財産にも注目すべき」という先生のお言葉が強く印象に残りました。
今後、預金不明点の作業をはじめとする業務を行う際は、今まで以上に自分が今やっていることの重要さを理解して仕事に臨みたいです。
I様
今回の講義内容は、業務でやっている財産や土地評価などと密接に結びついていました。
そのため、作成するうえでは自分が納税者、調査官ならどこを見るかを今後は気をつけていきたいと思います。
内容としては、例えば、預金であれば直前の出金や過去の大きな預金の流れなどです。これらはアニーにも書いてあることでもあるためそちらもしっかり利用をしていきたいと思います。
相続対策については、生前に対策できるもの(保険や生前贈与等)などあるため早めの対策が必要であると思いました。
I様
最近エントリで小規模共済というワードをよく入力していますが、いまいちその制度についてよく分かっていませんでした。
昨日の講義で小規模共済制度の活用についてお話がありました。小規模共済とは小さい企業の個人事業主や会社の役員の退職金制度であり、掛金は幅広く設定できます。また、全額所得控除という点も大きいなと思いました。
そして、今から加入し次年度分も前納することで、支払った次年度分の掛金全額が平成30年の所得控除になり節税できることも魅力的に思いました。
M様
相続の基本的なところについて、幅広く学ぶことができました。
よく、HPからきたお客様は何から始めたらいいのかわからないという方が多く、保険を絡めて提案しやすいという話を聞きますが、遺留分の対象にならないから被相続人の意向を反映しやすい点と、契約者の名義を受取人としておくことにより相続税ではなく一時所得の税率で済むという点から有効なものであると感じました。
相続の税務調査の実例は、担当官の目のつけどころの実際の話を聞くことができて勉強になりました。
ランドマークは書面添付をつけていることもあり税務調査はほぼ入りませんが、とことんお客様の資産を調べて少しでもあやしいと思ったらお客様とのコミュニケーションの中で聞き取っていくことが重要であると思いました。
M様
初めに、妹尾先生自身のことをお話ししていただいた中で、相続税について相談される際には、相続税の知識だけでなく、所得税、法人税等の知識も必要だとおっしゃっていました。
特に、不動産の知識は大変役に立つとおっしゃっていました。違う回の相続大学校でも、宅建の知識は役に立つと聞いていたので、俄然興味が湧きました。
また、お客様は、どんな人が相談に乗ってくれるのだろうと思っているので、知識だけでなく、人柄も大切にしなければいけないことなのだと感じました。
お客様のために勉強していく姿勢を大切にしていきたいです。
K様
「相続」は、不動産・非上場株式・所得税・法人税・民法等の要素に加え、ご遺族の想いが複雑に絡む事象であるため、講じることのできる策も豊富に存在しております。
本講義ではその対策ごとのポイントや、税務調査を受ける事を防ぐために、気を付けてヒアリングすべきポイントをおまとめ頂きました。
非常に濃い内容だったので、少々理解が追い付かなくなることもあったものの、レジュメも一覧表やフローチャート等を用いて非常に網羅的にまとめられておられ、お客様の抱えるお悩みごとに、どの様な策を講じることができるのかを俯瞰できるものとなっておりました。
このレジュメをアレンジして、自己の理解、またはお客様への提案資料に利用して参ります。
M様
今回は、納税資金対策と最近における相続税の税務調査のポイントについての講義を受けました。
税務調査を受けない為には、調査官の立場に立って問題点を抑え、指摘されやすい項目を検討しておくことが大切だと学び、また、納税者の立場に立って問題点を解決し財産を評価する、そして、疎明資料を添付することが大事だと学びました。
お客様との間で不明な点が生まれないように、しっかりとコミュニケーションをとることが重要だと感じました。
O様
今回の講義では、税務署が相続税申告書の内容でどのようなところを重点的にチェックしているのかということが具体的にわかりました。
また、近年の相続税の税務調査はどのようなことを行っているのか、過去の事例と共にいくつか説明してくださったので、相続人と協力して丁寧、確実な情報を集めていくことがとても大切であることを改めて実感しました。
税務調査で認められなかったケースも紹介してくださったので、対策方法を学ぶことができました。
F様
今回は、相続税対策の一つとして重要な納税資金対策について学びました。
税務署が相続税申告書のどのような点を重点的にチェックしているかなど、税務調査が入らないためのポイントを具体的に教えていただきました。
税務調査が入らないための対策も重要ですが、調査が入ることになってしまった場合に臨機応変に対応することも大事だという話が印象的でした。
お客様は税務調査をされることが決まった際は動揺し、申告までに培ってきた信頼関係が壊れてしまうと、万全な対策ができなくなってしまうため、お客様と連携しあえるように日頃から信頼されることを心がけるように努めます。
T様
遺言や建物の法人化、贈与など今までの復習のような内容が多く、知識を持ち、聞くことでより深く理解することができました。
不動産収入の物件を節税のために法人設立するという話はよく聞くのですが、年齢が高齢であったり、利回り、他の所得の関係で個人で所有している方が有利な場合もあることに驚きました。
また、税務調査について、対象にされやすい申告内容や調査内容についても聞くことができました。
税務調査対象にならない申告書等の作成が重要だと感じました。
相続マイスター講座13期 第10講座の感想
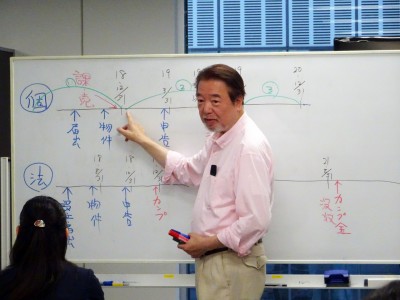
また、還付を受けてもその後の還付金を没収されてしまう「調整計算」という規定の適用を受けないための対応をとる必要があるので、調整計算がどういうものなのかしっかりと把握し、対応するべきだと思いました。
適切な申告をするために事前にとるべき対策を学び今後の実務において活かせるようにしていきたいと思いました。 S様

そのためにも、三年間の課税売上をコントロールして、変動率・変動差が適用にならないようにする必要があります。
また、簡易課税制度を受けている法人は消費税が低くなる代わりに還付金を受け取ることができないメリットがあります。どちらの方が利益になるかを考えたうえで取捨選択しなければなりません。
平成31年には消費税率が8%から10%に変わり、還付金も増えるため、知っておきたい内容だと思いました。 H様
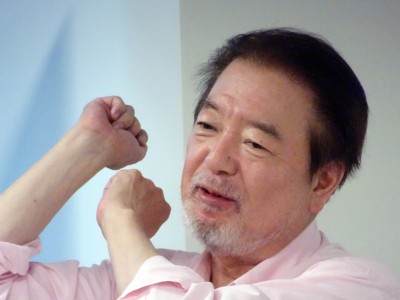
法人の場合は、国内において対価を得て行った営業行為であればすべて消費税の課税対象になる事から、金地金の売買でも営業行為と見なされ、その金地金を使った今回の消費税還付方法は合法的で有効なスキームだと感じました。
また、金融機関からの融資金額も法人への貸し付けの方が大きく出来るという買い手側にも有利な事情があります。
今後お客様を担当する際、個人のお客様へは法人化も視野に入れた提案を心掛けたいです。 I様
消費税還付が年々厳しくなっており、「調整計算」による消費税の没収をされないためには家賃収入を上回る課税収入が必要であることを学びました。不動産投資家が課税収入をそこまで得るのは容易ではないため、金の売買で課税収入を作るということもやっているそうですが、外国で金を買い付けて日本国内に密輸して販売し、消費税8%を得るという違法行為をする人たちもいることを知りました。
現段階では消費税還付は可能ですが、これまでの改正を見ていると、いずれその方法も使えなくなってくるのではないかと思いました。
S様
これまで消費税については、簿記や税の勉強を通して学んだ初歩的な知識しかありませんでしたが、今回の講義で「消費税還付」を主とした内容を学びました。消費税還付については、例え税理士であっても失敗を恐れて還付申告しないことがあるというお話を聞いて、やはり、「知識は力なり」であると強く再確認しました。
職場では、消費税は、相続税などに比べて大きく触れる機会は少なく、我々の最も身近に存在している税であるので、レジュメを主として消費税の知識を培い、活用できる機会に備えておきたいです。特に、消費税還付については、お客様にアドバイス等する際に役立つと思うので、基本的内容を押さえておきたいです。
M様
今回は消費税還付についての講義でした。消費税は複雑で頻繁に改正されることが多く、内容を十分に理解していない税理士が多い為、損害賠償を請求されることが多いそうです。信頼を損ねないためにも、改正される度に新しい制度をしっかり理解し、知識、経験を増やしていくことが非常に大切であると今回の講義で思いました。
消費税還付を受けてもその後の還付金を没収されてしまう調整計算という規定があります。調整計算を受けない為にも、4段階の対応をミスなく対応すべきだと感じました。
M様
AIの躍進により会計士や弁護士等の仕事がとって変わってしまうという話しが昨今話題となっていますが、厳密にはそうではなく、会計士に関しては監査業務や経理関係の仕事はAIに取って代わるかもしれません。
しかし、会計士の仕事はそれだけではなく、コンサルティングや税務調査対応等の税務判断は現状人にしかできない業務になるので、今後会計士は徐々にそちらの業務にシフトしていくと考えられます。
ただ、会計事務所の職員の仕事はAIで事足りてしまうので何らかの対策が必要です。消費税の還付はお客様獲得の為には最適な商品となるので、相続税だけではなく他の税法に関しても知識の幅を広げる必要があると思いました。
M様
今回は、消費税還付の概況と、消費税還付による集客力を学べた回でした。消費税還付は、近年数回に渡って改正があり、その複雑さから手掛ける税理士は少ないといいます。
相続税とどのような関連があるのかという点において、今回の講師の田中先生は次のように仰っていました。「消費税還付は、損害賠償に発展することも少なくなく、それを恐れてやらない税理士が多い。しかしながら、私たちはできるという事実がお客さんを集めることにつながり、この信頼があれば相続税の申告が他に流れることはまあ無い。消費税還付は、契約の入口として大きなインパクトがある。」と、お客さんを集める方法として理にかなっていると感じました。
消費税還付を受けるには、前提として消費税申告をすることが必要です。そのため、消費税申告をしていない者については、「消費税課税事業者選択届出」を提出し、消費税申告をする旨を届け出なければなりません。
この届出を税理士が出し忘れ、損害賠償へ発展するケースが多いと田中先生は仰っていました。
消費税に限らず、期限には細心の注意を払って業務にあたりたいと思います。
O様
消費税は頻繁に改正されることが多く、内容を十分に理解していないと損害賠償を請求されてしまい、信頼を損ねるため、改正される度に新しい制度を理解していくことが非常に大切であると改めて今回の講義で思いました。
また、今回の講義では消費税還付金を受けるまでの流れを学ぶことができ、調整計算などに注意し適正な還付を受けることができるように流れをしっかりと掴んでいけるように理解したいです。4段階をミスなく確実に計算することを徹底していこうと思います。
I様
前半は田中先生のマーケティング方法などのお話、後半はレジュメに沿って消費税還付を受けるまでの流れなどの講義でした。お客様をどのように獲得していくか、消費税還付を行い信頼を得てから月次や相続などの依頼に繋げる手法は弊社と異なっており、強みにしているところも違いますが、お客様のためにという思いは変わらないと思うので、そういった部分も今回の研修で学べてよかったです。
還付を受けるには、事前に消費税課税事業者選択届出書を提出しなければならないので、還付を受けるには将来を見越して計画を立てておく必要があり、担当者は以上のことも意識しながら進めておかなければなりません。
内勤として計画性を持ち、常に広く周りを見て仕事をしていきたいです。
I様
不動産を所有している方が個人として確定申告をする場合と、法人を設立して確定申告をする場合では、法人を設立して確定申告をした方がよいことを事例を交えてお話頂きました。
一般的に法人を設立するとなると煩雑なのだろうかとお客様に嫌厭されてしまうことがあるように思われます。実際に先生の講義を聴く前は私もそうかと思っていましたが、個人事業主でも届け出を出す必要があるならば、もはや法人を設立して節税効果を得た方がよいなと感じました。
今回の講義によって、ランドマークの法人設立試算、法人活用試算の仕組みをより理解することができました。
T様
会計業界での在り方・身の立て方と消費税還付の方法・注意点を学ぶ内容でした。
前半では会計業界での成功のポイント、今後の業界の展望について、田中講師の実体験を混ぜて学びました。
後半で学んだ消費税還付は、きわめてその効果が大きい反面、税務当局・立法サイドからの対策を受けやすく、注意が必要であるというものでした。危険性が大きい一方で、ポイントを十分に抑えることで確実な還付を受けられるという内容が大変印象的でした。今後、さらに学んで十分に活用できるよう取り組んでいきたいと思います。
H様
消費税は損害賠償を請求される件数が一番多い税金であること、また、税制改正があったことから、税理士でさえも失敗を恐れて還付申告をしないという話を伺いましたが、還付を受けるまでの流れや対策をしっかりと学ぶことで、今後の業務に活かしていきたいです。
また、還付を受けてもその後の還付金を没収されてしまう調整計算という規定があるため、調整計算についてもしっかりと把握し、対応すべきだと感じました。
T様
相続税など相続に関する講座が多かった中で、消費税還付のお話はなかなか聞くことのできない話でした。
消費税還付は難しく申告する人も少ないそうで、お客様に提案するには知識を持ち合わせることが必須だと感じました。
調整計算に引っかかると還付金が募集されることもあるので、調整計算に適用されないために家賃収入以上の課税売上を作る、免税事業者や簡易課税制度を利用する方法があるそうです。
消費税還付は馴染みが薄かったので、グラフ等あれば理解しやすくなると感じました。
相続マイスター講座13期 第11講座の感想

審査請求と法定訴訟の違いですが、前者が国税不服審判所で手続きがされ行政的な判断で画一的な面があるのに対し、後者は大半が3人の裁判官による合議制をとっているため意見をぶつけさせて、審査請求では判断できないような法律の解釈を問う案件が多いとのことでした。
訴訟で更正となった案件もあるので、経済的に余裕のある人は訴訟に持っていけるかもしれませんが、経済面だけでなく労力や公開されることの精神的負担もかなり大きいというところで、始めから漏れのない申告をすべきだと改めて思いました。 M様

また、コストや時間を考えると取消訴訟まで発展するよりも、「再調査」や「審査請求」での審理手続きの方が納税者としての負担も少なく、取り組みやすい事が分かりました。
その中でも「審査請求」については、第三者的機関により独立した判断を受けられ、約1年以内に裁決が出るという決着の早さがあります。
さらに、原処分庁も取消裁決に対しては訴訟提起できない行政機関の最終判断となるので、納税者にとっては長期化するリスクを減らせられます。
とは言え、いずれの手続き方法も納税者にとって不利になるケースもあるので、過去の先例も踏まえた上での情報提供がお客様へ必要になると感じました。 I様

どちらを選択するかは不服申立者の判断ですが、これらを考慮して選ぶ必要があります。
また、証拠の質や量、先例があるかなども考えるべきであると思います。
税務訴訟の動向については、H25の通則法改正やH28の行審法の改正によって税務訴訟と審査請求にそれぞれ影響がありました。後者の行審法の改正は審査請求にもう少し影響を及ぼすのではないかと思いました。
税務訴訟の最新動向と審査請求書の実務ということで、お話を聞くことができました。審判所の話や、内部の話を聞くことができ、実務とすごくつながる内容だと思いました。
また、スキームを使いどっちの選択の方が正しいのかも学ぶことができました。特に裁判例のお話が、私的には面白い内容だと感じました。今回の講座の内容を踏まえて、これからの業務に活かしていきたいと思います。
I様
税務訴訟は関わることのない領域だと思いますが、知識の幅を広げ、最新の動向を知る良い機会でした。
納税者が納得できるか、できていないかがまずポイントとなり、争うべきかどうかの判断は専門家が基準を提供しなければいけないとのことでした。とても重い判断だと感じてしまいました。
一方、審査請求は費用がかからない、手続きが非公開、決着が早いなどのメリットもあり、件数は増加の傾向にあるとのことでしたので、税務訴訟よりは少し身近な審査請求の基礎レベルの知識は身に着けておいて損はないと感じました。
S様
税務訴訟や審査請求について学びました。
その中で印象に残っている内容の一つに「専門家は、納税者が修正申告で決着することに納得できない場合、その納税者に代わって、争うべきか否かの判断ができるようにならなければならない」というものがありました。そのためには、税務訴訟の概要や動向について理解しておく必要があります。
再調査の請求や審査請求、取消訴訟などといった不服申立制度のメリット、デメリットについて理解し、適切な判断ができるよう、知識を蓄えていきたいです。
M様
税務訴訟と審査請求について判例を交えながらのお話でした。
修正申告での解決が費用もかからず、手続きが非公開で決着が早いなど行いやすい反面、税務訴訟になってしまうと費用も弁護士も期間も必要となってくるので、修正申告などを行う際は、とても慎重に判断して行わなければならないことが分かりました。
また、判例があると勝ちやすいので、よく調査してから行うことが大切だということが分かりました。
税務調査はないに越したことはないですが、いざ起きたときのことを考えて知識をつけておきたいです。
M様
税務調査に関する講義でした。特に、修正申告、監査請求、税務訴訟について詳しくお話ししていただきました。
修正申告や監査請求は費用も弁護士も不要のため比較的行いやすいですが、税務訴訟になると費用も弁護士も期間も必要となってくるため、行うかどうかは慎重に判断しなければいけないことが分かりました。
税務訴訟の場合は、先例の判断が覆ることが滅多にないため、先例をよく調査して勝てると判断できれば有効ということでした。
税務調査は、時々朝礼発表で聞きますが、弊所は少ない方なのかなと思います。また、先例をよく調査することは、朝礼発表での事例にも通ずるところがあると思うので、覚えておこうと思うことはメモしていきたいなと思いました。
K様
税務訴訟の動向、不服申立制度の特徴、審査請求の実務面に関する講義でした。
近年の判例や、動向を踏まえ、それぞれのメリット・デメリットを比較しながらお教えいただき、審判所にお勤めのご経験のあった石井先生ならではのご見解を伺うことができました。
しかしながら、私には前提となる知識が不足しておりましたので、講義内容を講義中に消化することができませんでした。
内容を理解するまではいかずとも、まずは基礎的な用語の理解は必要最低限求められると反省しております。
次回以降、レジュメを一読したうえで基礎知識を付けたうえで講義に臨もうと考えております。
W様
内容としては、税務の訴訟の実態を事例等交えながら説明するものでした。
日々業務をしていて、税務調査という言葉をよく耳にしますが、税務調査の殆どが修正申告で決着がついていることは知りませんでした。国税不服審判所の人はどこで採用されているのか前から気になっていましたが、国税で採用された人と民間の人で構成されていることを知れて勉強になりました。
取消訴訟のデメリットとして挙げられていた、弁論と判決が公開されてしまう点において、原告側保護の観点からやや問題があるように感じました(日本国憲法の知る権利との兼ね合いもあって判断は難しいですが)。
また、裁判所の違いとして挙げられていた、審判所は自ら調査することが可能ということも初耳でした。
S様
税務調査のほとんどが修正申告で決着をつけることが多いため、修正申告で処理されていることを学びました。
しかし、更正不可なので修正という可能性がある場合、税法の解釈について先例がない場合、事実の認定が間違っている場合、納税者が心情的に納得ができない場合については、修正申告で処理すべきではないので注意する必要があるということも学びました。なんでもかんでも争うべきではないとは思いますが、争うべき案件もあると思うので、そういった場合に対処できるようになるために税務訴訟についても、今後学んで理解できるようにならなければいけないと思いました。
T様
税務争訟についてのお話でした。税務争訟はあまり馴染みがないと思っていましたが、税務調査の修正申告など朝礼でも聞くお話でした。修正申告等は簡単に行えるのに対し、税務争訟は弁護士を雇う費用が掛かってしまうなど難しいものだと思いました。
資産税関係の判決・判例も紹介していただき、実際に関わった石井先生のお話を聞くことができて良かったです。
税務調査が少ない弊社ですが、知識をつけて業務に生かしていきたいと思いました。
O様
今回の講義ではレジュメに再調査の請求の発生状況や処理状況、審査請求の発生状況などをグラフ化されていて、とても分かりやすかったです。そのため、最近ではどのような案件が見られているのか分析しやすかったです。
納税者が争うべきかどうか迷っているときの判断基準を提供できるように、税務訴訟の概要や動向について理解してアドバイスできるようにしたいと思いました。
また、再調査の流れを覚えて、お客様を不安にさせないように十分な準備をしようと思います。
T様
税務訴訟は身近なものではなかったので、全く知識がありませんでした。
しかし、修正申告、監査請求、税務調査など項目ごとに詳しく教えて頂いたのでとても参考になりました。修正申告より税務訴訟になってしまうと費用が高くなり、期間も長くなってしまうことからお客様の負担が大きくなると感じました。
税務調査は当事務所では少ないとの事でしたが、もし、担当のお客様がなった場合は対処できるよう事前に学習していきたいです。今後は、なぜ税務訴訟になったのか、なぜ勝訴・敗訴になったのか、様々な事例を調べていきたいと思います。
相続マイスター講座13期 第12講座の感想

田中先生が用途地域の建築物の用途制限の覚え方についておもしろくお話してくださいましたが、土地や建物についての知識が必要不可欠であることを再認識しました。 M様

その中でも畑を宅地に含める事例はとても参考になりました。地目が畑になっている場合でも、自家消費のための家庭菜園程度の利用の場合、庭の一部としてみなし、宅地と合算して評価額を下げる方法です。
実際にそういったケースで畑を利用されているお客様もいると思うので、今後の提案の中に組み入れたいと思います。 I様

広大地評価から規模格差補正へと移行するにあたって減額率が下がった反面、その適用要件が明確化され、同時に拡大したことでその利用の機会が大きく増えるものであり、大変に重要であると感じました。
また、規模格差補正へと切り替わったとはいえ、更正の請求の可能性がある以上、広大地評価に対する理解も同時に為す必要があるということを改めて認識致しました。
今後、両評価の特徴・要件を十分に理解して、実務において活用できるよう取り組んでいきたいと思います。 T様
広大地と規模格差補正について学びました。
広大地評価では曖昧であった評価が、地積規模の大きな宅地の評価により、より具体的になりました。このことにより、この土地は規模格差補正が使える、この土地は規模格差補正が使えない、といったことが明確になりました。
広大地評価について弊社の長所であったところが少し薄れてしまったところもありますが、その分明確になったことで、お客様に具体的に説明できることにより、よりご納得いただけるようになると感じました。
自分自身がお客様に提案するときにはこのこともしっかりと把握して、お客様目線にたって説明していくよう心掛けていきます。
A様
地積規模の大きな宅地や広大地は、実務上で関わることが多く、とてもいいお話を聞くことができました。
他には、農地転用や評価単位のお話も聞くことができ、知識や経験の浅い私にはまた理解を深めることのできる内容でした。
宅建の内容や覚え方などを含め、実務で役に立つ事ばかりだったので、復習を重ねていき、実務や勉強に活かしていきたいと思います。
I様
朝礼の各先生方の見解でお世話になっている、ひかわの杜かんていの田中先生の講義でしたので、大変興味がありました。
講義内容は、広大地評価改定の歴史をフローチャートも合わせて振り返り、市街化区域、市街化調整区域の相違点、用途地域についての説明と用途制限一覧表の覚え方等でした。広大地評価は過去三回改正されているとのことで、複雑に変化しているように思っておりましたが、フローチャートと合わせて考えると大変分かりやすく改正前の不備の多さに驚きました。
どれも日々仕事をしていく中で大変重要となってくるものなので、大変勉強になりました。
I様
広大地の歴史を細かく丁寧にご教授いただき、理解が深まりました。
朝礼などで「広大地」という単語を耳にしていたので何となく理解しているつもりでしたが、今回の講座でよく分かりました。
初心者向けの説明で分かりやすく、お客様に説明するのにとても参考になりました。
一体評価の仕組みもいまいち掴めていませんでしたが、現況を重点に土地全体の状況を観察して定めるものなのだと理解しました。
I様
都市計画区域と一概にいっても、その中で市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分かれていて、地域によって農林漁業用の建物の建築や、一定規模以上の計画的開発以外は許可されていなかったりして難しく感じました。
用途地域内の用途制限についておもしろい覚え方を教えていただき、これなら覚えられそうでした。
広大地評価の変遷も興味深く思いました。特に平成6年から平成16年では結構変わったなと思いました。
M様
広大地補正と規模格差補正についての講義でした。どちらもほとんど同じことを指しますが、過去の改正によって名称が違うとのことでした。
平成16年から適用の広大地補正の場合は、土地の価格を路線価×面積×広大地補正率で算定します。規模格差補正は平成30年から適用のもので、路線価×面積×規模格差補正×画地補正で算定します。どちらも適用には要件がありますが、規模格差補正の方が要件を満たしているかの判断がしやすいとのことでした。広大地補正は更正の請求の場合にまだ使う可能性があるとのことだったので、規模格差補正とともに覚えておきたいと思いました。
潰れ地についても理解できたので、朝礼発表で広大地や規模格差が出てきた場合は注意深く聞きたいと思いました。
M様
広大地評価についてのお話で、分かりやすい講義でした。広大地の評価が下がる一因は、広大地を開発業者が買い、潰れ地があるまま土地をバラ売りする為ということを学びました。路線価差し替えを業務で行う際に、市街化や市街化調整区域等の言葉をよく耳にしていました。今回の講義で市街化調整区域などの違いを知ることができたので、今後はしっかりと理解しながら業務にあたることができると感じました。用途地域の建築物の用途制限の覚え方についておもしろくお話してくださいました。
S様
用途地域や容積率、建ぺい率など土地ファイルを作成したときに目にしたことのある単語が出てきて、今までよく分からないまま実務を進めていましたが、少しずつ理解できるようになった気がします。
普段実務を行う中で目にはしていても、どういった意味を持つものなのか、というところまでは理解できていないので、しっかり理解できるように勉強すればより作業を効率よく進めることができるのではないかと思いました。
また、評価単位において、どこまでが「宅地」でどこからが「畑」なのか、という判断基準も示されていて、今後活かせるようにしていきたいと思いました。
O様
広大地評価で単価が下がる理由が大きい土地は開発業者が買い、バラ売りとして他の人に売却しているためと、潰れ地が発生する可能性があるためということが分かりました。
市街化調整区域は10年以内に市街化を進めるところであるので、一定規模の計画的開発以外は許されないことが分かりました。
用途地域内に建てられるものと建てられないものの覚え方をいくつか教えてくださり、面白かったです。
K様
地積規模の大きな宅地については、現在配偶者贈与にて検討している事もあり、とても参考になりました。
他には農地転用を説明して頂き、相続時に農業委員会へ農地転用をなぜ聞くのかまで理解することができました。
今回学んだ内容は宅建の勉強をしていた時の内容と被るところもあり、復習もかねて講義を受けましたが、用途地域など自分では理解をしているつもりだった部分も完全に理解はできていないという事が分かりました。
今回の講義は、実務で役に立つ事ばかりだったので復習を重ねていきたいです。
A様
広大地評価につき改正の歴史を知ることができたのは大変有意義でした。
平成6年以降の有効宅地化率を出すのがどんなに難しかったか、各自治体により基準が違って困ってしまう評価方法を税法で決めるのだなという現実を知るのも興味深かったですが、平成16年以降の基準が悩ましかったこと、それらを考慮して平成30年以降の基準の明確化は、14年もかかってやっと改正されるという当局側の試行錯誤の努力の感心というか遅いというか複雑な気も致します。
都市計画法の用途地域名と路線価の地域名と両方がごっちゃに現在の判定のフローチャートに入っていると教えていただき、確かにそれが自分の混乱の原因だったなと思うと、理解できて大変ありがたかったです。
田中先生が次はもっと高いレベルの話をしますといわれていたので、次回の相続大学でのことだと思います。
ぜひまた田中先生のお話を聞かせていただきたく存じます。本日は実に受講できて有意義でした。
相続マイスター講座12期 第1講座の感想

現行の広大地と、税制改正のメリット・デメリットの説明もあり、とても分かり易いと思いました。
相続税を安くする手段として、「広大地をつくり出す」という方法があるのは知らなかったです。
また、レジュメが見やすかったので、初めて聞く用語も複数ありましたが、理解しやすかったです。 B様

現行の制度と改正後の制度を比較し、何がどう変わるか、変わることによるメリット・デメリットは何なのかということに対する説明がとても分かり易く理解しやすい内容でした。
特に生産緑地の2022年問題により発生する影響がどの程度のものなのかというのは興味深かったです。 N様

今後の税制改正について多く学べたことはとても良かったですし、なにより実務に近い説明も多く、今後のためになるものだったと感じました。
自分自身は少し内容についていけてない部分もあり、学ぶべきことが大変多いことも実感しました。
実務を行う際に是非参考にしていきたいです。 T様
相続マイスター講座12期 第2講座の感想

節税をするよりも、納税猶予からの免除のパターンの方が、最終的に納める税金が少なくて済むということを初めて知りました。
また、講義が面白く、ゴロ合わせによりその場で覚えることが出来ました。
条文を漫画で覚える本を是非出版していただきたいなと思いました。 S様

大変複雑な内容で混乱していたが、具体的な数値計算や図解があったので、理解をする上で非常に助かりました。
ただ、今回の講座は入口の入口ということだったので実務を行う為にはもっと深い理解が必要だと思いました。
原則は原則にすぎず、状況に応じた柔軟な対応が必要だと思いました。 B様

納税猶予という税金を大幅に軽減できる制度を知ることができ、とても役立てることができそうです。
非公開株式の譲渡は難しく、理解するのが大変でしたが、所々にユーモアのあるトークが交え楽しかったです。 K様
相続マイスター講座12期 第3講座の感想

事業承継に対する経営者の方の悩みや、その悩みに対する提案や対策について知ることができました。
また、コンサルティング業務において報酬は顧客・競合・主観という3つの視点から設定されていることも知り、とても勉強になりました。
会社法の知識はとても重要な知識だと思うので、しっかり学んでいきたいと思いました。 E様

事業承継という資産家の相続問題と切り離すことのできない問題について、そのあり方、現状、それに対してすべきこと求められること等のイメージを持つことができるように思います。
会社法は苦手な分野でしたが、本日の講義でその実務の中での重要性を改めて認識したことで、今後の勉強のモチベーションの向上にもつながりました。
よく復習して、きちんと頭にいれて使いこなせるようにしていきたいと思います。 A様

会社法についてはあまり意識したことはありませんでしたが、相続案件など、関わってくることは多くあることを実感しました。
コンサルティング業務をするとすれば、税務のみならず様々な角度からみる知識が必要であるとも感じました。
内容に関しましては、株式について実例も含まれており、とても興味深かったです。 K様
相続マイスター講座12期 第4講座の感想

消費税還付の場合、届け出を前もって出したり、税額控除計算で有利になるように方法を教えるなどしますが、それをするかしないかでは税額のケタも変わってきてしまうということを学びました。
後から数字を調整することはもちろんできないので事前に対策をすることが重要という点で、相続税と通じる部分がありました。
度重なる税制改正で何が変わったのか、新たにどのような対策が必要になったのかが分かり易かったです。
消費税に対する知識がもっとあれば、今回の講義の理解はより深まったと感じたので、概要はきっちり抑えられるよう勉強します。 T様

レジュメを読み上げるのではなく、聞き手に語り掛けるような口調だったので、内容が頭に入ってきやすかったです。
消費税還付のためにいくつか手段はあるものの、あくまで「合法的」に行うことが大切だということを改めて感じました。 M様

無視してしまうにはあまりにも大きなものであることを知り、今後自分でも十分に活用できる様にしていきたいと思いました。
また、十分に活用していくためには自身が知識を持つだけでなく、顧問先と連絡を密にすることが大切だということも知りました。
今後これらをきちんと意識して取り組んでいきたいと思います。 S様
相続マイスター講座12期 第5講座の感想

これからも色々な事にアンテナを張って、お客様の経営者人生のお手伝いができるような仕事をして行きたいと思いました。この度はありがとうございました。
また次回も楽しみにしております。 K様

日経新聞でM&Aという言葉をよく目にしますが、株式譲渡と事業承継の2種類が存在することは知らなかったです。
今後新聞記事でM&Aという言葉を目にしたときはどちらの種類なのかに注目して読んでみようと思います。 S様

利益で生み出していて経営状況が良好にも関わらず、後継者不足でそのままやっていけないという問題が近年、本格的に深刻しているとういことで、節税の分野でも案件が増えていく分野だと感じました。
知識はもちろんのこと、5年後・10年後の顧客を考えた提案をする姿勢を勉強させていただきました。 M様
相続マイスター講座12期 第6講座の感想

特にいわゆる新広大地の評価についてとても分かりやすく解説頂き、判定しやすくなった事が分かり安心しました。
これからの5年間は新旧の広大地評価を理解しておかなければ対応できないことも理解出来ました。
明日からすぐ実務に活かすことが出来そうです。ありがとうございました。
T様

基礎的なところから大変分かり易く学ぶことができました。
また、現行の制度について、平成30年4月から実務に入る自分にはあまり関係のないものという意識を持っていましたが、今回の講義でそれが間違えであったことに気付かされました。
今後今回学んだことを活かしていけるようにしていきたいと思います。 K様

また、ジョークを交えながらの講義であったため、3つ目の講義だったが退屈せずに受けられました。
「広大地評価」という言葉をよく耳にしていたが、意味や大変有意義であったと思います。
「若手の人がいるから」と気遣って細かく説明をしてくださったので理解が高まりました。
今後実務を行う上で活かしていく知識の基礎を構築できたように思います。 S様
相続マイスター講座12期 第7講座の感想

成年後見制度とそれを補う家族信託と考えていましたが、そうではなく、家族信託がありその補完として成年後見制度があると考えた方が良いことが分かり、お客様にもそのように説明しようと思いました。
認知症だけでなく、2次3次相続にも有効で資産管理を求められるお客様にも提案して、将来の相続案件にも繋がる、実務的にも重要な内容だと思いました。
今後とも是非先生のお話を伺えたら幸いです。この度はありがとうございました。S様

よく「成年後見制度」という言葉は耳にしていましたが、親族が横領してしまうことが多かったり、本人が認知症になってしまうと財産が固定されてしまう等、不都合が多いものとは知りませんでした。
今後、高齢者の割合が増加し、認知症を発症する可能性のある人が増加することを考えると、家族信託を積極的にお客様に勧めた方がいいなと思いました。
また、お客様に自信を持ってお勧めするためにも、家族信託についてより理解を深める必要があると感じました。N様

お客様がもっている資産を、たとえ認知症になったとしても有効活用することができるというメリットが信託の強みであると理解しました。
成年後見制度の不自由さを知って、お客様の資産・家族の状況に応じて対策を組み合わせることが重要だと感じました。
家族関係が良好であまりモメない場合は、生前贈与、遺言、当事者の意向を踏まえてベストな提案をするためにも幅広い知識を身につけていきたいです。T様
相続マイスター講座12期 第8講座の感想

家族信託ではなく一般社団法人を活用することで、受託者の心配をすることがなくなることも良く理解できました。
お客様の資産管理や事業承継の際にもご提案できたらと思いました。この度はありがとうございました。
また次回も楽しみにしております。K様

「信託」という言葉自体はよく聞きますが、個々人の複雑な状況に対して応用して対応可能だとは思っていなかったです。
相続や贈与は、個々人の感情が複雑に絡むので、将来的に信託を存分に活用できるよう理解を深める必要を感じました。I様

会社の代表が後見人に株を全て渡し、その後見人が代表より早く亡くなった場合、株の権利を分割する大切さを痛感しました。
議決権分離型信託や受益権分離型信託などのスキームを大手メガ信託がカバーしきれないお客様に提案する事ができれば、多くのお客様のお役に立てると思うため、信託について深く勉強していきたいと感じました。A様
相続マイスター講座12期 第9講座の感想

特に、いわゆる新広大地の評価についてとても分かりやすく解説頂き、とても判定しやすくなった事が分かり安心しました。
これからの5年間は新旧の広大地評価を理解しておかなければ対応できないことも理解出来ました。
明日からすぐ実務に活かすことが出来そうです。
ありがとうございました。S様

特に、相続発生後の流れと、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いの記載が知識のない身としては助かりました。
レジュメの字も大きく、カラフルで見やすかったです。
本講義を通して、相続税の税務調査が来ないためには、入念なチェックが必要であることを再認識しました。T様

マニュアル通りにいく事例というのはほとんどないと思いますので、そのような状況においても適切な方法を見出すためにはお客様との信頼関係も大切だと思いました。 K様
相続マイスター講座12期 第10講座の感想

遺言や養子縁組の組み合わせによって結果が全然違うものになってくるのが面白いなと感じました。
遺産をあげたい人にちゃんと渡すためには、意志があるうち、文字が書けるうちに、確実に有効となるように整えて遺言を残すことが大変重要だとよく分かりました。 K様

相続でお困りのお客様に対し、悩みがどれだけあるのか、その悩みがどのようなものなのかを丁寧にお聞きすることが大切で最重要だと考えます。
そのために、聞く側も豊富な知識が必要とされるはずなので、今回の講義は、実際のお客様のリアルな悩みを聞けて大変満足しました。ありがとうございました。 S様

遺言と養子縁組が絡み合っているとき、双方の意思が一致している場合はなんの問題もなく、相続に関することも丸く収まるのだと思いますが、事例にあったように、双方の意思が一致していないと複雑な問題に発展してしまうのだなと思いました。
相続に関することは、被相続人も相続人も判断能力がしっかりしているときに早めの意志を明確にしておくことが改めて大切なことだと学びました。 T様
相続マイスター講座12期 第11講座の感想

価格の付つけ方に関しては直接お客様に説明することはない内容ですが、基本的な知識として必要なことであると感じました。
広大地のお話は、再確認することができてよかったです。
下﨑先生の、実務家ならではの制度に対してのご意見のお話が面白かったです。 S様

土地の評価ポイントについて、レジュメに簡潔に記載されていたので、理解がしやすかったです。
また、相続税路線価は、日本だけで他の国にはないとの説明があったが他国でもあると思っていたので意外でした。 O様

価格についてお客様に聞かれることもあるため為になりました。
今回学んだ基準をどの様に用いていくかということを常に意識しながら取り組んでいきたいと思います。
より効果的な活用をしていくことができるように、日々学んでいこうと思います。 M様
相続マイスター講座12期 第12講座の感想

特に最近改正のあった居住用宅地の二世帯住宅の取り扱いについて、条文上での「家屋」と「建物」の違いが明確になりました。
ありがとうございました。 T様

民法を経験した経験があるので、今回の講義内容は面白く感じました。
また、かみ砕いた表現に変えての説明があったので、理解を深めることができました。 Y様

基本は何よりもまず条文の正しい解釈であり、決してそこを疎かにすべきではないというあり方は、税務の仕事上、絶対に外してはならないもので改めて意識しました。
この姿勢を忘れずに業務に取り組んでいこうと思います。 O様
相続マイスター講座11期 第1講座の感想

本日の講座を受けたことにより、広大地の減額の仕方等をしっかりと身に付けることができました。
また、要点をしっかりとおさえて、講義をして頂いていましたので、もの凄く分かりやすく、講座自体が楽しいものに感じ、時間が過ぎるのが早く驚きました。
講師である清田先生のセミナーは良いという話を聞きますが、その理由についても改めて理解できる場でもありました。
沢山のことを吸収できる時間になりました。
次回も参加したいと思っております。本日はありがとうございました。 B様

所内研修の際にも広大地のチェックがありますが、どのような土地が広大地として考えられるのかを知ることができました。
これからも土地評価を行っていくので、どのような土地が適用されそうかを考えながら取り組んでいこうと思います。 T様

相続税申告の中の土地評価の役割が明確にわかって良かった。
評価減を検討し、当初から適用するか更正の請求をするのかどうやって考えたらよいのか少しばかりだが、わかった。
また、土地の評価減がどのような理由でどれだけの割合かわかりやすかった。
事例を用いた話が多く実務に大きく役立てることができると感じた。 N様
相続マイスター講座11期 第2講座の感想

税理士試験に出ないような実務でよくある疑問点を学ぶことができ、とてもためになりました。
原則が建前になっていたりほとんどの税が所得後で計算するのに対し、同族株主に該当するかどうかは贈与直前で判定することになっていたり、ケースバイケースで奥が深いなと思いました。 O様

話し方が面白くて聞きやすかったです。財産を動かす方法として、譲渡、贈与、相続があり、贈与と相続は対価なしなので、財産が減るから後でもめることが分かりました。 M様

牧口先生の講座は今回で二回目ですが、前回同様とても分かり易い説明で何もわからないわたしでも理解できるような講義で、勉強になりました。 B様
相続マイスター講座11期 第3講座の感想

シンプルな商品なので、様々な事情を持つ個々のお客様に最適なものを提案する為には相当な保険の知識が必要だと感じました。
具体的な数字や実際にある保険の商品を使って説明してくださったのでとても分かりやすかったです。 S様

保険のプロが話す保険の話は分かりやすく、理解しなければと思いました。
相続対策のための保険以外にも役割として事業承継、納税資金など様々なものがあり、接客をする上でお客様に合う保険がどんなものか考える必要があると思います。
農協や銀行につなぐようにどう話を進めるかも自分で考えたり、マニュアル、諸先輩方のやり方を見て学び、ベストな提案をすすめていこうと思いました。 K様

まず、生命保険の基本的な知識を学ぶことができたので、相続税に関わってくる保険について今まで漠然としていたものが具体的にイメージできるようになった。
さらに、知識をつけてお客様に自信をもって提案できるようにしていきたい。
その後は実務にどう活用するかという話で内容をすべて理解することはできなかったが、保険の活用方法を自分で考える足掛かりにすることができたので今後学びを深めていきたい。 B様
相続マイスター講座11期 第4講座の感想

家族間での分割について実際に問題に発展してしまった事例を取り上げて、1つ1つ細かく説明して下さったので、民法の知識が不十分でも理解することができました。
失敗事例も紹介して下さったので、今後の実務にすぐにでも活かすことができそうだと思いました。 N様

特に近年養子縁組制度が増加しており、それに伴い協議、調停、審判といった形で「争族」としてこじれる場合が増加していることも分かりました。
「相続は事業承継のひとつである」と講師のお言葉にもあるように、相続開始前に十分な対策が必要であると痛感しました。
講義では複数の判例を通して実務上の対応方法について知識を得ることが出来ました。 O様

相続で争っているケースにはまだ直面したことはないが、争いを防ぐ1つの方法として遺言は有効な手段であることが改めて分かった。
当事務所では相続の争い自体に介入することはないが、遺言作成する際には必要な知識ばかりだった。
とても興味がある分野だったので、面白かった。
先生のお話しもとても分かりやすかった。 T様
相続マイスター講座11期 第5講座の感想

事業承継戦略と課題について、大きく分けて4つのパターンがあり、後継者がいて業績が良いと株価が高くなっている可能性があるので、株式の移転の際に贈与税(相続税)に注意する必要があると分かりました。
好条件なのに注意しなければならない事がたくさんありそうなので、もしお客様に提案する際は、しっかり理解して聞いてもらうようにしたいと思いました。 E様

事業承継と一口に言っても業種や後継者の有無により対処が大きく異なるため、まずは対象となる関与先の特徴を見極める事が重要であると感じました。
また事業承継は企業の将来像を見据えて長期的な関与が必要となるケースが多く、財務・法務・人事等の多岐に渡り綿密な計画の下に実行することが必要であると感じました。 K様

株式の移転で、持株会社を設立する場合、オーナーが自分の会社で自分の株式を譲渡する場合には、相続回避になるケースがあるので、注意喚起された。
事業承継の目的で、事業承継者の息子には持株会社に株式を移転することがベターである。
株式移転を考えるとき、まず第一に納税猶予を考えることが重要である。 A様
相続マイスター講座11期 第6講座の感想

また、法令改正とは別途、「宅地」と「土地」の定義や評価方法については案件ごとに大きく異なり、また評価者により解釈が異なりうることも再確認することができました。
小規模宅地特例の原則として、特別措置であるため申告期限内の提出が必須であるため、迅速な処理が必要であると痛感しました。 U様

小規模宅地の特例と一言で言っても、法律、施行令、施行規則など、複数で構成されているのは初めて知りました。
また、二世帯住宅について、当初は完全分離型二世帯住宅にも適用できることになった点のお話では、法律を支える施行令や施行規則の重要性を分かりやすく伝えて頂きました。 S様

相続税申告において小規模宅地の特例は活用していたが、前提等は良く知らなかったので、今回の講義で条文から知ることができ、より理解を深めることができた。
特に条文を知ることで厳密に判断することができるようになったと考えられる。
今後、申告時には自信を持ってお客様に提示することができると思う。 H様
相続マイスター講座11期 第7講座の感想

税制改正についての講義で、特定の1つに絞ったものではなく、改正の内容を一通り説明して頂きました。
その中でも、広大地に関するものと生産緑地に関するものを詳しく説明して頂きました。
実務に関わる重要なことなので、通達の内容等細かく説明して頂き良かったです。知識のもれがないようにして、業務に臨みたいです。 A様

H29年度税制改正の説明と今仲税理士が現場でどのような提案をしているかを聞くことができました。
税制改正については自身でも勉強しましたし、所内でも講義がありましたが、現場でのビジネスチャンスを教えていただけたのでとても参考になりました。
実践できることが多かったためすぐに実務に反映させていきます。 S様

条文に交えての解説で、特に広大地の改正についてはH30年からの評価方法について詳細にお話し頂けたので良かったです。
改正により、普通住宅地区と普通併用のみしか広大地が適用されないという点で、区画計画図の要否に影響が出てくると思われますので、注意していきたいと思いました。 T様
相続マイスター講座11期 第8講座の感想

税務調査が行われた場合に、修正申告をするべきか、更正かという判断をどうするべきかを場合別に学びました。
現状、私自身がこのような判断をすることはありませんが、所内研修の際にでも、本日教えていただいた知識を活かせるとよいと思います。 T様

税務訴訟や審査請求自体の件数は少ないですが、以前に審査請求を行った際に、今回の講義であったようなメリットがありましたので、更正の請求等で税務署から決定通知が届いた場合でも出すだけ出しても良いかと思いました。 O様
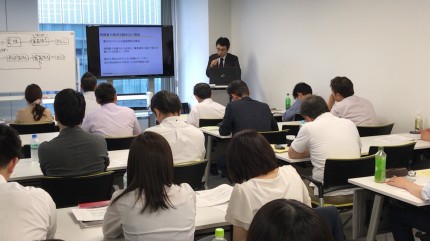
税務訴訟について今までよく知らなかったが、今回の講座ですこしばかり知ることができました。
いざという時に自分で考えられるようにしておきたいです。
特に最近の動向について聞くことができ、今後は増える可能性があるということなのでしっかりアンテナを張って情報収集をしておこうと思います。 M様
相続マイスター講座11期 第9講座の感想

家族信託について、研修が増えてきているが、実務的な内容の講義でしたので一番分かりやすく感じました。
特に、契約書や通帳、謄本などの例が出ていて、イメージがしやすくお客様の説明にも有効活用できそうだと思いました。 K様

民事信託についてお話をいただきました。
民事信託の問題点や最近の動向を知るところから始まり、実例も交えての講義でしたので、実際にどう使われているのかが分かり易く、大変興味深かったです。
社内研修でも信託をテーマとした研修があったので、そこで得た知識に加えて信託を使いたいというお客様のニーズに応えていけるように活かしていきたいです。 O様

家族信託が後見制度の不備をカバーするものであり、契約者の作り方次第で様々な活用ができることを学びました。
最近、話題になることが多いテーマなので、お客様から質問されることも多いと思います。
しっかり勉強していきたいです。 T様
相続マイスター講座11期 第10講座の感想

消費税の還付は、だんだん条件が厳しくなっており、税理士としても、慎重にやらなければならないと思います。
消費税の知識と還付のスキームをしっかり理解すれば、他の税理士に差がつけられる分野だと思うので、しっかり身に付けたいです。 B様

消費税還付については近年複数回の改正がなされており改正によって消費税還付の要件が大きく異なる点について学習しました。
届出書提出のタイミングが変更されたため提出時期を誤るとお客様が還付を受けることができなくなるため書類提出の時期や必要な書類について改正の都度確認することの必要性を痛感しました。
関与先においては不動産管理業に従事されている方が多く、課税及び非課税売上の双方を計上するケースが多いためそれぞれの税務上の特性を理解した上で業務にあたります。 Y様

どのような税制改正が行われ現在に至ったのかということやこれからの消費税還付は法人所有が有利とはどういうことなのかといったことを教えていただきました。
不動産は個人ではなく法人所有するのが有利であると言うことでした。
今後、消費税について業務で扱うことがあると思いますので、今回教えていただいたことを活かせるようがんばります。 E様
相続マイスター講座11期 第11講座の感想

平成30年1月1日以後 相続税対策として、利用をしている例 具体的に説明をしていただき判りやすかった。
主な国税庁質疑応答事例 具体的な事例で、再度勉強になりました。 S様

相続税税務調査対策の講義と言うことで自分の今行っている業務のために必要なテーマでありました。
調査に入らないためにクリアにしていなければならない点や実際の現在の調査件数なども知ることができ、より学んでいかなければならないことを実感しました。 A様

相続税申告においてどのようなことが間違いやすいか指摘されやすいかを知っておくことで、より良い提案ができると感じましたので、本講義で学んだことを実務に生かしていきたいです。 T様
相続マイスター講座11期 第12講座の感想

第12講座では相続税の納税方法について学ばせていただきました。
相続税の税額控除の方法ばかりに気をとられておりましたが、二次相続や納税方法を考えるべきことがたくさんあり相続税の難しさを改めて実感しました。
今後のお客様の生活の事や無理な納税方法になっていないか考えるため、相続の知識を深め、最善をつくしたいです。 T様

今までは財産の評価方法や税額の計算方法を学んできました。
業務をしている時では土地の評価や税額を気にしていました。
しかし講義を受講して、納税資金についても考えていかなければならないことに気づきました。
また一次相続で二次相続を考慮した遺産分割や二次相続までの対策など客様のその後の人生を考えた対策を学べました。
今後はお客様のその後の人生を考えた仕事ができるよう精進していきます。 Y様

生命保険金のメリットは資産総額から法定相続人×500万円を非課税に出来るというだけではなく、分割の対象外であることから納税資金を確保できるという点は目から鱗でした。 K様
相続マイスター講座10期 第1講座の感想

又、それにともない「小規模宅地等の特例」適用要件緩和、があり、よく理解できました。農地の生産緑地のメリット(固定資産税が下る、相続税が大幅に下がる、500㎡以上の規模が必要)がよく理解できました。又、33年問題で生産緑地の見直しがあるということがわかりました。
農地の納税猶予は1日でも遅れると認められないという点は厳しすぎると思います。暦年贈与の3つの注意点には具体的でわかりやすくよく理解できました。
①印鑑が違う、預金口座に振り込むこと、
②毎年時期・金額を変えること(きまぐれ贈与)、
③贈与契約書を結ぶこと→これは税務署の対抗要件になる。
非常にわかりやすくよく理解できました。
(目指すべき相続・事業承継対策、事例に見る都市農家地主相続の実態、最新税制事情) A様

後半の相続対策については、養子縁組や生前対策など聞いたことはありましたが、内容はよく分かっていなかったので、しくみ等を学ぶことができて良かったです。
これから実務で自分自身がやることのイメージをつかむことができたので、この講座を足がかりにしてもっと制度の理解を深めて、仕事に活かしたいと思います。 T様

これから仕事で納税猶予を検討する機会もあるだろうから、報告をしっかりとしスピードを意識して処理をすすめていきたい。相続対策メニューのように、チェックをして淡々と処理を進めていくことでミスの低下やスピードの向上につながると思う。
相続税申告後についても対策や準備をしている所ところがお客様への不安を軽減することにつながると思いました。 I様
相続マイスター講座10期 第2講座の感想

牧口先生の教え方のうまさが際立っている。
ダジャレ、お金をみせる、モノマネ等、一方的に講義するだけではないところは、私たちがお客様とコミュニケーションをとる上で必要なところなのではないか(相手に合わせたコミュニケーション)レジュメに関して、内容は非常に難しいところではあるが、図を使いイメージすることができた。
事業承継の方法とは一般社団法人に譲渡することを聞いたがお客様にとって良い選択をするために暗記よりも理解を深めていきたいと思いました。
まだ非上場株式に関する評価に触れたことはありませんが、先生が執筆された本を読み、理解を深めていきたいです。
E様

大学で相続法を学びましたが、それは個人のことだけで会社の相続は今日初めて聞かせていただきました。
譲渡が一番安定をしていることや一般社団(財団)法人を作り、そこへ譲渡をすると相続税がかからないこと、ただし「みなし譲渡」といって、1/2より安く行うと時価とみなす等、様々な条件があるということを学びました。
信託では私が考えていたことと違いがあることに気づき、勉強していかないと、と思います。
A様

未上場株式の評価は財産評価通達により原則的な取り扱い総則により具体的な取り扱いは178から189~7に規定されています。
事業承継の方法には、①親族への承継、②従業員への承継、③M&A(事業譲渡等)、④一般社団法人がありデメリットを事業計画に合わせて検討することが重要であることが理解できました。
具体的な方法として、①一般社団法人(一般社団法人は持分がないので相続税がかからない点)、②持株会社の設立(100%事業承継者がもてば事業承継が完了すること)、③信託を利用し有効な事業承継を行うこと、以上、実務的に今後仕事に役立つ内容でした。
B様
相続マイスター講座10期 第3講座の感想

税理士業務をするにあたっての心がまえに共感することが多く、大変満足することができた。
その心がまえになったいきさつを事例になぞらえて説明して下さったことで共感しやすかった。
レジュメに詳しい事例がたくさん載っているため、実務をする際のチェックの役に立つので、活用してみようと思った。
様々な体験談から、当事務所で行っていることにどんな意味があるのかが分かり、とてもためになった。来年の新人にも必ず聞かせたほうが良いと思った。
D様

税務調査に立会いなどをテレビで特集しているのを観たことがあるのですが、いきなり税務官と納税者がぶつかり合うというイメージだったので、実地調査に至るまでに長いプロセスがあるのを初めて知りました。
また、納税者が預貯金の管理を撤廃したり税理士が丁寧に申告書を作成・精査することで、調査を省略できるということは、私たちの向き合い方でお客様の運命を変えてしまうのだなと自覚する良い機会となりました。
M様

税務調査がこないように資料(税務署がほしそうな資料)を段ボール3箱渡したというエピソードにおどろきを感じました。
税務調査で申告漏れを指摘される財産について、私はタンス預金、配偶者に収入がないのに口座に多額の残高があることなどは知っていましたが、有価証券、不表現財産の割合が高いことは新たな情報でした。
妹尾先生は、実際の税務調査の経験を軸にPDCAサイクルをしっかり回り、日々己をみがいていらっしゃる。私も日常の業務で問題を発見し、解決していきたいです。
N様
相続マイスター講座10期 第4講座の感想

はじめて税務訴訟手続きについて講義を聞き、大変勉強になりました。
税務訴訟の最新の動向をふまえて聞くことができ、今後に生かせる内容でした。
講義の中で最も印象に残ったのは、税務訴訟は本当に必要なのかというところです。
納税者と国税の見解の相違で妥協できないケースが増えてきているとのことなので、税務訴訟についての知識はしっかり勉強しておかなければならないと思いました。
今日だけの講義で得た知識にせず、定期的にレジュメを見直し、税務訴訟手続きと実務の流れを勉強しようと思います。
N様

また、弁論期日では口頭主義といいつつも書面が必要であること、そして10分程度で終えてしまうのにも驚きました。
私たちが働く上で、訴訟にならないように、納税者と税務署の双方に納得してもらえるような申告ができるように、精進していきます。
O様

税務訴訟について、そもそもどういうもので、どういった流れか、最新の動向等が主な内容でした。
これまで「税務訴訟」という言葉しか知りませんでした。
どこか他人事のような気がしていましたが、この先自分の担当のお客様たちが関わる可能性があるのなら、しっかり勉強して対応できるようにしなければと思いました。
言葉は知っているが、関わる頻度は低いものに関しては放っておいてしまうことがあるので、基本的な部分や背景、財産評価基本通達は時間つくって目を通します。
そんな基本の大切さを改めて感じた講座でした。
T様
相続マイスター講座10期 第5講座の感想

今後、譲渡所得の案件で地主のお客様から空き家対策でアパートなどの貸家を売りたいとご相談を受けた際に本日の講義の話を仕事に活かしていきたいと思います。
U様

空家対策や広大地の評価、タワーマンションやリフォームなど資産税に関する現代の問題点についてお話を頂きました。
そもそもの根本的な制度の理解がまだ深まっていないため、講義の内容を理解するためには更なる勉強が必要だと思いました。
タワーマンションの評価については年末の税制改正大網で話題になるであろうポイントだというお話だったので、注目してみようと思います。
B様

特に小規模宅地の特例の改正については、興味深くきくことができました。
また、名義預金と名義株のお話が興味深かったです。
よく贈与は110万まで控除があるので生前贈与をして税金対策をするということがあります。
しかし、管理運用を贈与された側がきちんと行わないと名義預金とみなされて全く対策にならないということにもなるので、実際に提案をする際には注意が必要だと改めて思いました。
O様
相続マイスター講座10期 第6講座の感想

租税特別措置法、財産評価基本通達、民法等、様々な法令が出てきたため、少し困惑しましたが、勉強になりました。
細かな注意書きや例えの話しもある資料で、内容は難しかったですが、聞きやすく分かりやすかったです。
時間の都合で割愛された部分もあったので、見返して学習しておきたいと思いました。
K様

説明責任をしっかりと果たすこと、要件の確認を疎かにしないことの重要性を実感しました。
「建物」と「家屋」の違いなど少しの言葉の違いで同じように思えても定義が違う言葉の意味を正しく理解していきたいです。
細かい違いを知ることができ、とても勉強になりました。
A様

言葉の言い回しが難しく、普通に読んだだけではしっかりと理解して使うところまでできませんが、今回のお話をうかがって少し読み方を学ぶことができたと思います。
親族を例にどこまでが親族なのか具体的に説明していただいて、普段何気なく使っている言葉もしっかり定義を核にすると自分の解釈と異なることも多く、難しいと感じると同時に興味深かったです。
H様
相続マイスター講座10期 第7講座の感想

小さな会社の事業承継の大切さを学ぶことができました。
小さな会社といえど、日本の約26%を担っています。
小規模事業者の会社は大手とは違い、明日生き残ることができるか、否かの状況でやっています。
そんな小規模事業者の会社でも事業承継したいという意思があります。
そのため、生前の対策がとても大切だということになります。
私の家も生前の対策ができなかったため、大変だったと思います。
そのため、今後働いていく中でかかわっていく可能性もあるので、今日学んだことを活かしていけたらと思います。
K様

事例に基づいて、まず事業承継はどのようなステップで、どんなことに注意しながらやっているのか、そこに遺言や保険の活用、今後認知症の発生、相続の発生を見すえてどんな対策やアドバイスをすることができるか学びました。
月次、相続のお客様対応時に活かせるように勉強します。
N様

小さな会社(有限会社)の事業承継については、半数以上の割合で経営者が60歳以上であること、相談相手の33.3%が税理士・会計士であること、銀行には融資の関係で本音は言えないため税理士に相談することになります。
税理士は記帳代行、申告書作成だけではなく、経営コンサルタントとして経営者の各種の相談に乗らなければなりません。
また、中小企業で株価評価を行っている企業は3~4%であるということで年に1回の決算法人税申告の時点では、少なくとも株価評価をして、説明する必要があると思います。
後見人の制度もいろいろ問題があると思いました。
現在は急速に「民事信託」が普及しており、特に不動産信託が注目されています。
「民事信託」とは、「家族信託」とも呼ばれ、信託銀行が関与するものは「商事信託」と呼ばれ、「信託法」は平成18年に大改正され徐々に使われるようになってきています。
「自益信託」の場合は、贈与税等の税金の問題は生じません。
これからは、民事信託の活用が重要だと思いました。
A様
相続マイスター講座10期 第8講座の感想

相続が争族になるその原因、遺言の活用と注意点、養子縁組の活用と注意点を具体的な事例で良く理解できました。遺言の活用と養子縁組の活用が争族予防になると思います。
「相続」とは、財産を譲る側から譲られる側(相)への円満な想いの橋渡し(続)であり、「互いに譲れない想い」のギャップが「争族」の原因となり、実質的公平の欠如が原因であると思います。公平な相続とは、形式的な相続(均等)は必ずしも実質的に公平とはいえない相続で、実質的公平確保のため、寄与分制度があります。
寄与分については譲られる側で協議をし、法律では「特別な寄与」を要求しています。はっきりいって「認められにくく、もめやすい」ことからです。
解決策としては、譲る側が寄与分相当を生前に決め、生前に自らの意思で譲れない思いを表明するのがいいと思います。
特に税務は遺産争族に関することはできず、遺言、遺産分割書に基づき相続税申告書を作成するのですが、相続対策としては、重要な関心事であると思います。
K様

しかしながら会社に入社し、争いの話はまだ聞いたことがない。
今日の講義はとてもドロドロした相続人同士の争いの話でドキドキしながら聞くことができた。
7講座の内容とリンクしていて、大変理解が深められた。
はやめの遺言や養子縁組が必要不可欠であり、それを怠ったために理想の相続ができないといったことはあふれている。準備をしっかりしなければならない。 Y様

遺言の作成、養子縁組の活用による遺留分対策がとても参考になった。多くの事例をお聞き出来大変勉強になりました。
ありがとうございました。
O様
相続マイスター講座10期 第9講座の感想

具体的に講義して頂き、よく理解できました。
広大地の基礎(財産評価基本通達第24条第4項)と広大地の科学=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積で求められること。
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条(定義)第12項に規定する開発行為を行うと、その場合に~原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。
広大地評価フローチャートにより評基通24-4の「広大地」に該当するか否か判定するのは大変参考になりました。
道路の基礎として、建築基本方第42条(道路の定義)1項、幅員4m硫黄の公道建築基準法43条(敷地等と道路との関係1項本文に建築物の敷地は道路に2m以上接し無ければならない。
以上のように具体的に基礎から採血例まで具体的に事例を説明して頂き、実務に役立つと思います。
M様

高低差の10%減については駐車場を作っている場合には、否認される可能性が高い。
42条1号、5号の違いは、開発規模の違いである。
3号道路はバスケット条項であり、要注意。
理由付けを確認する必要がある。
以上のことを実務に活かしてまいりたいと思います。
E様

また、道路についての基礎のお話しがとても良かったです。
実務で都市計画情報など取得することは多いのですが、詳しく調べたことがなく、またあまりにも基本的なことだと思うので、なかなか聞き難かったので、専門家の知恵を教えて頂けて良かったと思います。
土地評価について、もっと勉強したいです。
S様
相続マイスター講座10期 第10講座の感想

消費税の大原則、課税売上で預かった消費税課税仕入で支払った消費税を引いた金額が還付されるという基礎を押さえることができました。
そこから改正の流れを背景に現在の消費税還付の為の仕組みを勉強することができました。
消費税の還付を受ける上でポイントになるのは、いかに課税売上を上げるかという点でしたが、課税売上を上げる方法として、
①金地金の売買(有価証券は不可)、
②サブリース契約におけるオーナーと不動産会社間の契約において、「住居以外の目的で使ってはいけない」旨の文言の削除(契約書面作成において文言を入れない)
などの方法があることを知り、②の方法については、お客様に提案できそうだなと思いました。

消費税法の改正について順を追って説明頂き、現行制度における還付スキームについて学びました。
現行制度は今のところ消費税率が10%に増税される平成31年10月1日までは還付スキームが使えるので、この期間までに実際にお客様より消費税還付のご相談を頂いた時に処理することができるよう本日頂いた資料を読み返して勉強します。

消費税法の勉強をした際に「住居用として貸した物件を事務所として利用されていた場合、実態ではなく、貸した側の示した住居用として扱い、その家賃収入は非課税売上げとする。」と学びましたが、その際あいまいだと感じたことがあります。
そして、そのあいまいさを上手く利用し、還付金の返還を免れられるというのはまさに目からウロコでした。
ゆっくりと消費税計算の大原則からお話していただけたので、非常に分かりやすかったです。
相続マイスター講座10期 第11講座の感想

家族関係が複雑になると、いろいろな問題がでてきます。
認知症の被相続人の遺言、相続の問題等、相続税の申告についても重要なことです。
やはり法定後見人ということではなく、生前から任意後見人契約を結び、相続対策を元気なうちから行い、相続税申告に結びつけるということが重要だと思います。
法定後見人ということになると被相続人の財産の保全という点から、なかなか相続対策も重要な契約はできないという点があります。
①成年後見制度とは
②成年後見と任意後見の仕組み
③任意後見と死後事務
④成年後見に関する動向
を分けて事例を含めて説明を受けよく理解できました。
司法書士の立場からの法的説明ですが、税理士の立場での後見制度を理解することが重要であると思います。
実務には遺言書の作成、相続対策等に税理士が任意後見契約を結び、財産管理をすることが重要だとわかりました。

成年後見人制度の方が信託を用いるよりも値段が安くすむので、進めていくことが多くなると思います。
また任意後見人制度と遺言を先に進めておけば不足の事態にそなえることができると分かりましたのでお客様に勧めていきます。
担当先で成年後見人制度を利用しているところが2件あるので、もっと勉強をして実務に活かして行きたいと思います。

ただ後見人をつけると、本人は判断能力がないということで様々制限をうけることになります。
相続の際にも制約を受けることがでてくるので、もし、実際の仕事の案件等ででてきた時には注意しないといけないと感じました。最近では民事信託との合わせ技で、財産の横領等を防ぐ手法も多いとうかがったので、自分も調べてみたいと思いました。
相続マイスター講座10期 第12講座の感想

今回の税制改正で広大地評価の計算式に変更がでてくるという話や最近の広大地判定の考え方として基本に三層開発基準というものがあること開発行為には原則6m道路が必要だが、実務的には4m幅の道路でも広大地評価が認められている(道路幅の狭い道に接道している敷地は実際に業者が買い取る金額は時価の半値程度であることを考慮して課税庁も認めざるを得ない所がある。)という話が聞けてとれも勉強になりました。
そして、タワーマンションの評価、高低差、純山林の評価減のポイント等、当事務所でもこれから土地チェックの機会が増えていくので、今回の講義で学んだことをしっかり復習し、今後の仕事に役立てていきます。

広大地をはじめ、高低差の評価や山林の評価など、実務でよくある土地の評価について事例を用いてお話をいただきました。
航空写真や図面など、評価に使う資料を見せていただきながらでしたので、とても分かりやすかったです。
土地の評価は、今後仕事で扱う内容であると思うので、この講義を基礎として知識を深めていきたいと思います。

広大地や高低差にはあいまいな基準が多く、適用できるかどうかが画一化されておらず、土地の周辺の様子や地形によりケースバイケースである難しい制度だと感じました。
公図を見るだけでは分からないことも多く、対象地周辺の写真を見たり、直接現地に赴いて調査することが大切だと学べる良い機会を頂きました。
相続マイスター講座9期 第1講座の感想
都市農家と地主の最新税制事情
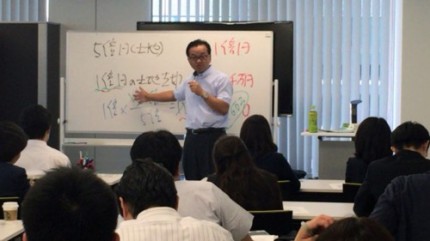
とても面白く受講することができました。
又、今後この業界は「考える力のある事務所」しか生き残って行くことができないのだろうなと強く感じました。
T様

また、消費税においてはインボイス制度やマイナンバー制度の導入など様々な新しい仕組みについて、それぞれの良い点、悪い点など多面的な視点で学ぶことができました。
Y様
また、結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税措置で、教育資金の一括贈与非課税措置との制度設計の違いが分かりやすく、理解できました。
他方で、農地の納税猶予の通常の場所、三大都市圏における制度の違いについて不勉強な点が見つかりましたので改めて勉強の必要を感じました。
B様
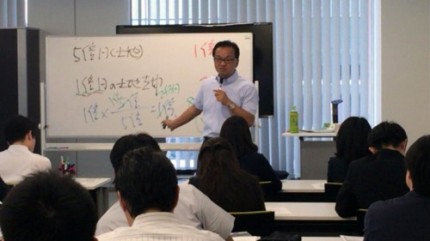

相続マイスター講座9期 第2講座の感想
弁護士が語る「「争族」解決のツボ

全ての相続人が納得し、最終的に円満に分割するためには、相続人、被相続人が前もって準備をしておくことが重要なのだと再認識しました。
分割の際にトラブルを最小限に抑えるためには効力の強い公正証書遺言を活用することも、一つの方法であることも理解でき、今後の仕事に応用をして行こうと感じました。
A様

普段あまり身近で起きてないような話ばかりでした。
やはり相続というものは、もめてしまうととてもドロドロした世界ですし、弁護士の先生も大変だなと改めて感じました。
遺留分についての考え方も参考になりました。
また、業務問題についても税理士ができる分野、弁護士が行う分野など線引きにも配慮してトラブルにならないよう意識する必要があると感じました。
K様
大切なこととして、公正証書遺言と養子縁組をしっかり覚えておき、これからの実務に役立てて行こうと思いました。
相続発生の際は起こり得る可能性のあるものとして、人事ではなく身近なものと捉えていくべきだと実感しました。
T様


相続マイスター講座9期 第3講座の感想

一般社団法人を活用した相続スキームをもっと勉強してみたいと思いました。

節税スキームで、一般社団法人が出てきたのは意外でした。
ただ、勉強不足なので良く分かりませんが一般の会社と違ってそんなに簡単に設立することができるのか、何かしばりは無いのか、会社が無くなったときに財産はどこに帰属するのか(おそらく国だと思いますが)もう少し詳しく講義の内容を聞きたかったです。
S様
聞く側に対し、興味を持たせるようにメリハリがあり、話し方に関しましてとても参考になりました。
業務を進める上で、一般社団法人に関わることがないのですが、これからは増えてくるだろうと感じました。
新しいジャンルの知識ですがしっかりと学んでいきたいと思います。
B様


相続マイスター講座9期 第4講座の感想
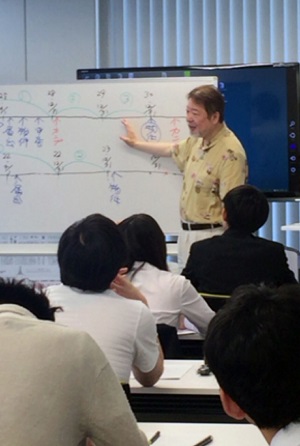
普段行っている業務の中で、あまり消費税について詳しく勉強する機会がなかったので、講義を聞くことができてよかったです。
講義を聞く中で1番おどろいた事は、普段自分も業務の中でエントリを打つ際に不動産収入は課税・非課税で分けて入力していましたが、消費税の還付について考えると不動産業者に物件をサブリースした際に居住用であるという書面をかわしていなければ、課税として計上でき、消費税の還付額を増やすことができるという事です。
消費税の還付額を増やす方法については特に考えたことはありませんでしたが、通算課税売上を増加させることによることで届出や申告をする時期はありませんが、消費税の還付をすることができると分かりました。
今回の講座で教わった事を日頃の業務に活かせるようにしていきたいです。
A様

中古物件を個人で購入すべきか法人で購入すべきか、太陽光発電などの減価償却資産の節税効果、修繕費積立用の保険商品の活用など、周辺知識でも大変有益なものを多く聞かせていただいたので今後の活動に活かしていきます。
消費税については知識があまりなかったのですが、今回消費税の還付スキームの返遷を聞いてとても参考になりました。
現行の税法では課税売上を3年間計上し続けるというところがポイントで、「サブリースの契約方法」でその計上が可能になるという所は実際に使えるのではないかと思いました。
根拠を見たいので早速通達確認しようと思います。
M様

消費税還付は二度も税制改正があり、特に今年の改正に関して詳細な解説がありました。
今回は届出を出してから二年間待つ必要がなくなりましたが、還付申告年を含め三年間の課税売上の推移に注意する必要があるそうです。
一年目に課税売上が100%で、三年間合計の課税売上が極端に下がれば、調整計算が入り、還付金を返済する必要があるそうです。ゆえに課税売上を増やしていく必要がありますが、どのようにして増やしていくかを提案するかは大変だと思います。
H様
相続マイスター講座9期 第5講座の感想

日頃、当事務所の代表から聞いてはいましたが、当事務所では税務調査がほとんど入らないということは知っていました。
その税務調査がはいらないようにするためには普段自分が行っている預金不明点をあらいだす事であったり、書面添付をしっかり行う等、ひょうご税理士法人様と同じようなクオリティの高い業務を行っているのだと再認識をいたしました。
税務調査に入る案件があると実績を傷つけるとともに、お客様の信頼をなくしてしまう原因にもなってしまいます。
調査があったとしても修正申告をされないような資料づくりを心がけながら、今後も業務を行っていきたいです。
E様

相続税申告において気を付けるべき点として、申告書の添付資料を作成すること、申告書を作成するに至った過程をしっかりと示すことが重要であると仰っていました。
税務調査が入ると80%の割合で追徴課税がなされるというデータがあり、税務調査ははいるとほぼ追徴課税されるということに驚きました。
添付資料の重要性、使途不明な出入金、宙に浮いてしまっているようなお金を放置しないことの重要性も再確認できました。
I様

これまでは預金不明点などぼんやりとしたイメージしか持っていませんでしたが、調査官が注目している所を知ることで何が大切でどうすべきかを考えるよい機会でした。
また、納税者目線にも立ち、相続処理をしていく点で不明な財産を明確にして申告をする等、調査にひっかからない申告をしていくことの大切も学ぶことができました。
このような調査官目線、納税者目線に立ち業務が行えるようこころがけていきたいです。
O様
相続マイスター講座9期 第6講座の感想

今回の講義では事業承継について詳しく学ぶことができました。
弊社でも事業承継をすすめる事はしているとの事は知っていましたが、事業承継とはどのようなやり方があるのか等の内容についてはほとんど知りませんでした。
講義では事例をもとに詳しく内容を説明していただく事で、後継者がいない時には会社を2つにして借入金や株主を2つに分ける方法、逆に後継者が複数いるため会社をホールディング化し、1つの会社をそれぞれ分けることで事業をさらに展開していくことができることがわかりました。
弊社でも事業承継については、お客様におすすめをしている商品の1つです。
今回の講義で詳しく内容を聞くことができ、知識を高める事ができたので、今お客様に提案できるようにさらに知識をつけていきたいです。
T様

今回の講座で、株式交換により費用をかけない(株式のみによる再編)及び期間もかけない(債権者保護手続きが不要)という手法を学ぶことができ、これによって株式の含み益の控除や連結納税による親会社の欠損金と子会社にした所得を通算することができるなどお客様のメリットを提案できると感じました。
O様

事業承継を通じて、会社組織を再編する方法を講義していただきました。
分割型、分社型、株式交換、持株会社など、普段日常業務できかないワードを丁寧に説明していただき、だいぶ理解することができました。
事業承継は今後仕事として増えていく見込みがありそうなので、様々な事例に合わせてもっともよいスキームを選択できるように、もつと知識をとり入れていきたいと思いました。
H様
相続マイスター講座9期 第7講座の感想

レジュメの財務省主税局資料3「相続税の課税件数割合及び相続税贈与税収の推移」と、4「相続税の課税状況の推移」を見ると、死亡者数は年々増加しているのも関わらず、相続税の課税件数は平成3年をピークに平成16年頃まで減少傾向にあり、それ以降再び上昇していることがわかりました。
ただし近年の上昇は死亡者数が増加し続けていることに起因しており、死亡者数における課税件数の割合でみると、やはり平成年以降は減少傾向にあると教えていただきました。
それに伴い、納税税額も同じ動きをしているため、近年の課税ベースの拡大につながっているのだと感じました。
また、特に目を引いたものとして法定相続人数が昭和58年以降、ずっと減少していることがあります。
少子高齢化の影響なのかわかりませんが、養子縁組等のアドバイスにつながる傾向であると思いました。
K様

大変ご高名な先生だと認識はありましたが、お若い頃から各地の税務署での実績や資産税部門に限らず、様々な分野でのお仕事を積み上げられてこられての結果なのだと思いました。
また、お仕事の内容だけでなく若い頃からの人脈がその後のお仕事にいい影響を与えたというお話も興味深いと感じました。
今年の税制改正のお話もありましたが、もう少し詳しく聞けたらよかったと思います。
M様

最近の問題意識を強く持つことの重要性を再認識できました。
特に今年から始まった空き家対策の3,000万控除について1億円問題の場合は不適用になる際に、共有の場合は共有割合における譲渡対価を基準とするのか否かについて、どう結論を出すべきかしっかり考える時間を得ることができました。
さらに潜在需要的にみると、相続税の基礎控除額の引き下げにともない、4.1%程度に課税件数が増えるとのデータだったようですが、東京都だけでみると10%程度あったということで、当初の想定よりも申告需要が増えるであろうと感じ、それをどう掘り起こしていくべきかを再考できる機会になりました。
E様
相続マイスター講座9期 第8講座の感想

今回の講義を聞いて事業承継を行いたい企業はどのくらいあり、実際小さな会社が事業承継を行っていく場合はどのような問題があるのか等、事業承継について詳しく知ることができました。
小さな企業で事業承継を行う場合の事例(実際にトリニティ様で扱った案件)を出していただくことでどのようなやり方で行っていけばいいのかがよく分かりました。
事例でもあったように自分で立ちあげた会社に対して事業承継を行う場合、自分が生きている間にすべての権利を移転してしまうのは、少し難しいと感じると同時に、遺言によっても事業承継を行うことができることを知りました。
また、事例を聞いている中で、事業承継を行う事で、相続との関わりもでてくることが分かりました。
今回の講義で事業承継を行うにあたっての基本的な知識を得ることができました。
この知識は今後自分が仕事をしていく中でも活用できる知識だと思うので活かしていくようにしたいです。
E様

事業承継について。
会社の株式が0のとき、さっさと贈与して事業承継をした方がいい。
しかし社長としては全ての発言権を奪うのは同意を得られにくいので、種類株式を発行したりするような方法があると伺った。
司法書士は登記、設立などの法務上の仕事をサポートするだけだと思ったが、個人のライフプランまで考えて提案すると知り、驚きました。
M様

生命保険金は相続発生時において保険給付金という考え方から、原則遺留分の対象とならないとの事なので、これは相続税コンサルにおいて保険商品の提案をする上でメリットとなるポイント説明に使えると思いました。
黄金株というものについての説明とその黄金株を活用した事業承継についての話は大変勉強になりました。
創業者より後継者へ普通株式を全て贈与し、黄金株1株のみ創業者へ残し、株主総会での決議の重要事項についての発言権をのこしておくことでスムーズに承継を行う方法もある。
U様
相続マイスター講座9期 第9講座の感想

今回は信託の仕組みから課税庁の判断、一般社団法人を設立することでオーナーから後継者への株式の相続移転をスムーズに行うポイント等をお話し頂きました。
その中で小林先生が力を入れてお話されていた「受益権分離型信託」は、株式を信託し、配当をもらう人を「収益受益者」とし、元本をもらう人を「元本受益者」とすることで、設立時の株式評価額で10年間配当をもらえない部分を考慮した評価額で移転することができ、贈与額を大きく減らすことができるという大変興味深いお話でした。
このスキームを実際のコンサルに役立てていけたらもっと提案の幅も広がると思いました。 K様

信託については他の講義においても何度かお話がでており、非常にニーズが高まっていると感じました。
小林先生の本講座では一般社団法人を活用した相続スキームを紹介してくださいましたが、課税関係やリスクについて細かくお話してくださったため、とても勉強になりました。
受益権と指図兼を分けることができるということが知れてよかったです。 U様

そのうえで自社株の相続時の対策において受益者と議決権(行使の)指図権者を分離する方法や受益権自体を収益受益権と元本受益権に分離する方法などで、委託者の意図を汲みとった移転ができることを学べました。
煩雑な手続きが必要な遺言の代わりに信託を活用できることも知ることができ、そのような義務の発生はあるものの今後の業務に活かせるのではと感じました。 A様
相続マイスター講座9期 第10講座の感想

「広大地」の基礎から説明していただき良く理解できた。
財産評価通達24条4項により、広大地の評価の基礎から(趣旨をしっかり把握する)建築基準法の道路に面してない土地には建物を建てられない点、開発行為を行うために道路の調整が必要であることには、広大地の調整が必要であることが理解できた。
又、適用要件があいまいであることから、税務局との間で争いがあり、国税不服審判所の裁決から最新の適用基準が示され、説明をされ、良く理解できた。
特に平成27年9月2日の採決で①「著しく地積が広大」②評価対象地は500㎡以下の394.16㎡、③路地状開発が道路入り開発かについての事例説明はわかりやすく良かった。
やはり広大地の評価は、主々な要件を個別土地に適用に総合的に判断するべきで、通達どおりにはいかないということが理解できた。
I様

国税不服審判所に国税側の機関であるが、民間人と国税側の人間合わせて3名で話し合って裁決している。
最後に貸家建付地の土地の評価単位の考え方についても分かりやすく説明して下さり、本当に勉強になりました。
なかでも市道と一指定道路(私道で持分が無いケース)に面した土地が広大地補正の適用を受けられるかどうかの判断はとても勉強になりました。
E様

広大地の実務に馴染みが薄かった私にも分かりやすい講義で、広大地評価を検討できる土地はどのようなものなのか、実際に行う土地評価でどのように適用されるのか等、事例をまじえながら詳しく学ばせていただきました。
また広大地評価をするにあたり、接している道路の種類(私道・公道)で評価がかわってくる等、位置指定道路についても詳しく教えていただきました。
現在、業務の中でも多くの土地に広大地評価を検討しています。業務を行っていく上で今回の講義の内容を活かしていけるよう努力していきたいです。
O様
相続マイスター講座9期 第11講座の感想

小規模宅地等の特例が事例と条文からわかりやすく解説していただいて非常に役に立ちました。
相続税の話は財務省の主税局、執行は国税庁との説明からはじまり、「措法69の4第1項と3項」の定義関係の詳細表は役に立つと思う。
(入学試験)と(卒業試験)が良かった。
25年以前と26年以後では、二世帯住宅と老人ホーム入居時の死亡の場合の通達について、詳細表説明及び事例の解説により、明確になった。
又、「相続」の実務について相続税法では、民法の借用概念であり、民法725番「親族の範囲」を参考とすることで、事例を含め説明が良かった。
特に先生のことばで「税務署がダメだといって終わってはいけない、それに反論していくのがプロだ」ということばに感銘を受けました。
T様

小規模宅地の特例の活用ということでしたが、思った以上に法律の話が濃く、自分の勉強不足を感じました。
勉強する際は字面ばかりを並べるのではなく、図などを用いてわかりやすいようにまとめたいと思いました。
今回は事例を用いることはなかったのですが、法律の難しい言葉を一つ一つていねいに解説して下さり、そういった面からも勉強してみたいと思いました。
O様

我々の業務上の基礎となる条文上の文言を細かく丁寧に条文に照らしてご説明いただき、普段ついついおろそかになりつつある条文にもどる重要性を教わった気がします。
今回の講義で、普段よく使う小規模宅地の特例で見落としがちな点(親族の定義を正確に把握することで適用の可否が変わるなど)に気づくことができ、大変勉強になりました。
A様
相続マイスター講座9期 第12講座の感想

土地評価は土地評価の常識で評価するということばに感銘を受けました。
「公的評価の問題点」で競売価格が時価の40~60%とは驚きました。
相続でもめると、地価か競売を提案しますが、円満な相続解決が重要だと思います。
相続人同士にもそれが利益となるでしょう。
裁決例の説明で高低差の裁決は大変参考になりました。
国税庁のタックスアンサーでしか参考資料がないとは驚きです。
法律等で規定するべきと思いました。
E様

路線価の標準地の鑑定評価書が開示されていることは知りませんでした。
今度から検索して参考にできると思います。
開発行為とは主として、建築物の建築するに当たり、土地の区画、形、質の変更を行うものをいう。
そして、三要素として区画、形、質のいずれかを伴うものをいう。
開発の定義が明確となり論点がぶれにくくなりました。
K様

土地の公的価格の基礎を学ぶことができました。特に地価公示価格がベースになること、それを基に相続税路線価が80%、固定資産税路線価が70%になるなど基礎知識の取得ができました。
また、遺産分割協議において、話し合いが土地についてまとまらない場合は競売価格(地価公示価格の40%~60%)という安い価格により分割されてしまうという原則論があるとのことで、協議がまとまらない場合に、この知識を活かすことができそうだと思いました。
M様
相続マイスター講座8期 第1講座の感想
オーナー経営者の視点で考える事業承継対策

事業承継対策についての制度や具体的な内容及び事例について、
大変わかりやすい講義でした。
業績好調企業の対策と業績不調企業の対策の違い等、
実践的な話も聞けたことが収穫でした。
普段聞くことが出来ない内容でもあったジャンルをお話し頂き、
事業承継対策に関する周辺理解が深まりました。
I様

事業承継については仕事柄若干の知識がありましたが、
復習とともに新たな知識も得ることが出来ました。
特に農地等の納税猶予や生産緑地に関する話は、
経験の浅い分野でしたので、
豊富な案件を手がけている清田先生の話を聞くことができ、
とても興味深く勉強になりました。大変良かったです。
M様事業承継は、今世の中でも大きな問題点になっているテーマであります。
その中で、詳しい解説からレジュメまで事業承継対策に関する知識を増やすきっかけになりました。
経営承継円滑化法や事業承継税制、民法の特例など幅広い知識と教養が必要なのだと痛感しました。
今回の講義を実務に活かすために、今後も自己研鑽に励みたいと思います。
Y様

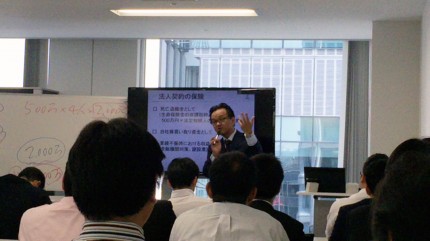
相続マイスター講座8期 第2講座の感想
相続税をめぐる最近の情勢等について

実際の裁判事例、税務調査で指摘されやすい事例を
具体的な事例を交えながら挙げられ、大変参考になりました。
休憩時間に非上場会社の自社株の買取価額についての質問もさせていただき、
アドバイスをいただけました。
完全に受講料以上の価値を持ち帰ることが出来そうです。
I様

課税する側の考え方が垣間見えて勉強になりました。
税制改正大綱や小規模宅地の話など、
「ここだけの話」が面白く、
流石庄司先生だと感じました。
M様
会計業界にて大変権威ある庄司先生のお話を聞くことができ
勉強になりました。
以前から一度庄司先生の講演を聞きたいと思っていました。
特に相続税、贈与税の基礎から各判例にいたるまで、
詳細にご説明頂きましたので、今後の実務に役立てて行きたいと思います。
Y様

相続マイスター講座8期 第3講座の感想
最近の事例から読み解く広大地評価の理論と活用のポイント

広大地評価について、初級、中級、上級とかみ砕いて
ご説明してくださり仕組みが良く分かりました。
案件として扱ったことがなく、大規模工業用地に該当するか
どうかの判断など知らなかったことも多くありました。
事務所に戻って再度テキストを復習しようと思います。
Y様
広大地評価が難しいことに変わりはないのですが、
講義の内容が初級から入ってくださったので考え方を
整理することができ助かりました。
実務に活かせるポイントを具体的な事案に絡めて
お話くださり大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。
M様
路線価の仕組みや路地上開発判定など知らなかった知識が聞けて、
勉強になりました。
不動産鑑定士の土地の評価の考え方なども知ることが出来たので良かったです。
普段は相続についてのテーマは同業者の視点からしか見ることが出来ませんでしたが、
鑑定士の先生の講義だけでなく、今後の講義では弁護士、司法書士先生の話など
異業種の先生による講義がいまから楽しみです。
T様


相続マイスター講座8期 第4講座の感想
保険のプロも見落としがちな生命保険の相続・贈与のポイント

講義の全体的な流れとして、簡単な保険商品の説明から、最新の相続税・贈与税対策のための保険商品のお話をうかがうことが出来ました。
生命保険については税金対策のため様々なスキームが語られているように思いますが、本日の講演は初めて聞くようなお話も多くあり、参考になりました。
生命保険契約に関する権利は、契約者の変更があった時点で、贈与税が課税されるものと思っていましたが、実際には解約返戻金を受け取った時点で贈与になるということには驚きました。また、その「みなし贈与」を作った、個人間の財産の移転のスキームについては、実際に運用できそうなもので、これもまた勉強になりました。
O様

以前、大学で保険についての授業を履修していたことと、先生が難しいと思った所も「ようは~」と身近な事に置き換えて教えてくださったので理解しやすかったです。
また、仕事にどう活かせば良いかという点について、イメージはしにくかったのですが、自分自身の生活に活かすという点で、料金や利率を母が気にしながら保険業者の方と話していたのは視野が狭すぎたなと今回の話を聞いて思いました。
また、保険にはリスクがあるとずっと思っていましたが、使い方によって大きなメリットがあるという事を学びました。
相続が発生する前の節税対策に保険を活用するメリットが良くわかった講義でした。ありがとうございました。
K様

保険商品の種類や機能性の点から保険商品を使った相続スキームの話がありまして保険商品の自分が持っていたイメージを変わった気がしました。
今後も今回の話が自身の仕事に生かせていければと思いました。
その一方で自身の生活においても役に立ちそうな話で、今後必要になることもありそうだと感じました。
T様
相続マイスター講座8期 第5講座の感想
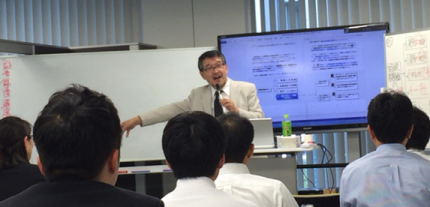
事業承継において一般社団法人がどのような節税効果を持っているのか、また一方でどのようなリスクがあるのかをお話いただいた点は興味深かったです。
牧口先生のお話の内容も話し方も引き込まれるものがあり、また機会があったらご講演を拝聴してみたいと思いました。
N様

ただ、基本的な知識を持っていなかったので、きちんと理解できなかった部分があって悔しかったです。
講義自体はユニークでとても楽しく、また知識を持っていない私でも少し理解できた部分があった事、先生の教え方がとてもわかりやすかったのだなと理解しています。
ぜひまた機会があれば先生の講義を今度はある程度知識をつけた状態で聞ければと思います。ありがとうございました。
K様
さらに制度上の話をしつつ、具体的例を混じえていて実務的な色彩が強い印象を受けました。
そのため非常にわかりやすい話の内容だと感じました。しかし業務に必ずしも直結するわけではないですが、事業承継の1つのスキームとして考えた場合、知っておくと大変有益なものになりそうです。
いずれにしても初めて聞くテーマの講義の内容ですので、もっと理解を深められるように努めたいです。
Y様
相続マイスター講座8期 第6講座の感想

不動産業界で働いていらっしゃったということもあり、不動産と税金を絡めたお話が面白かったです。
二時間の中で多くのスキームについてお話して頂けましたが、少し消化不良の部分もあり、そこはさらに勉強が必要だと思いました。
K様

法人化のメリットや具体的な手続き、法人化を勧めた方がよい場合とそうでない場合の住み分けなどは大変理解が深まりました。
具体的な事例のお話も多く、実務でどのように法人化が活用されているのか知るよい機会となりました。
M様

講義の中では法人化のメリットとデメリットが説明されていました。さらにどのような法人を設立すべきか、その法人の種類について話があり、興味深いものでした。
講師が不動産実務の経験が大変豊富な事もあり、不動産を活用して節税スキーム作りに関して大変精通してました。そのため多くの例示が紹介され、大変よくわかりました。
今回の講義は理論的な話より、実務的な話が多い印象でした。今回の話をもとに制度の理解へも役に立てていきたいと思います。
W様
相続マイスター講座8期 第7講座の感想

レジュメの量もとても2時間ではおさまりきれない程のものでしたが、1つ1つ丁寧に説明している様子で落ち着いている方だなという印象を受けました。
内容も私にとってとても難しいものだと感じましたが、これからの業務に活かすことができるよう理解を深めたいと思いました。
I様

特に、贈与について知らない自分自身にとって、贈与の基本的な意味や効果について、詳細に説明があり、大変有意義なもので、勉強になりました。
また、実務面の話においては、納税対策の方法や当局の税務調査の視点など、今後実務に携わった際に役に立つものになるはずだと感じました。
今回の講義をきっかけに、生前贈与について今回のレジュメ等を見返したり、様々なケースを通じて理解を深めることに努めていきたいと思います。 Y様
贈与税について大変詳しくお話頂いたので、どのように生前贈与を行っていけばよいのかが、非常によく分かりました。
夫婦間や親子間などで贈与を行う場合、どのような財産をどのような手続きを踏んで贈与すればよいか、など具体的な事例を挙げて頂きながらの説明だったので、イメージを持ち易かったです。
レジュメも非常に内容の濃いものだったので、講義内容をよく復習して実務に活かしたいと思います。 S様
相続マイスター講座8期 第8講座の感想

講義中に質問を受ける事に関しても、自分が分かりにくい部分に関してや、このような件ではどうなるのかなど、講義の中で疑問に思った事も質問する時間があってよかったです。
H様

その中でも特に信託を構築する際、柔軟性がある点が面白く感じました。議決権指図権者をスキームお中に含めたり、自益者信託や他益者信託があるスキームなど、様々なスキームの形があって、クライアントの要求次第で多様なスキーム構築が可能です。
今後相続の形としてもっと身近なものになっていくのではないかと感じさせられました。今回の講義をきっかけにいろいろなケースを知ることで、理解を深めていきたいです。
R様
今回の講義では「信託」の基礎を明確かつシンプルに教えていただいて理解が深まりました。
特に受益権分離型信託の説明では、信託受益権を元本受益権として収益受益権に分け、割引現在価値の考え方を用い評価する、ということがよく分かりました。
それ以外にも信託を活用した相続対策の実例が多く提示されており、非常に興味深い講義でした。
F様
相続マイスター講座8期 第9講座の感想

今回の講義では、信託法の基礎的な部分がそこに付随する背景などについて説明があり大変わかりやすく面白いものでした。
特に信託の基礎的な話を法律の専門家が説明することで今までにはない違ったアプローチから理解をすることができました。
その一方で実務的な話は非常に難しく感じました。もっと理論的な部分の理解を深めて、実務面のスキームなどについて理解できるようにしたいです。今後税務の面からだけではなく、法的な面からの講義も聞いてみたいと感じました。
A様

弁護士さんならではの条文番号を含めた法文の提示や、判例の有無の解説が随所にあり、大変勉強になりました。
「信託とは何か」という基本からしっかり説明しながらの講義だったという点も良かったです。
Y様
相続税対策として、信託を活用できる範囲が広い一方で、法律的に必要な要素や前提、適切な手続きを理解した上で、信託を活用しなければならないと感じました。
T様
相続マイスター講座8期 第10講座の感想
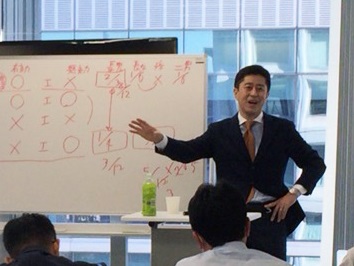
T様

N様

S様
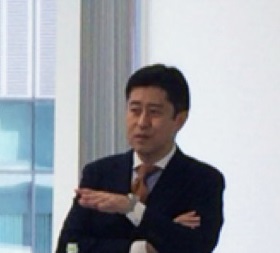
W様
相続マイスター講座8期 第11講座の感想
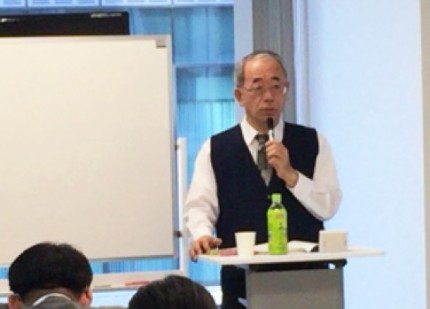
Y様

T様

K様
相続マイスター講座8期 第12講座の感想
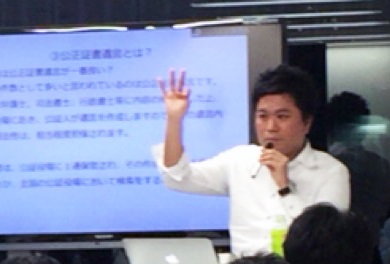
I様

M様

T様

そのような状況で生前にやるべきことがあるにもかかわらず、自らがやることは難しくなっています。そこで司法書士のような専門家が後見人になったら身元保証を行うことでサポートすることが求められています。社会情勢上やむを得ないことでありますが、非常に考えさせられる内容でした。
O様